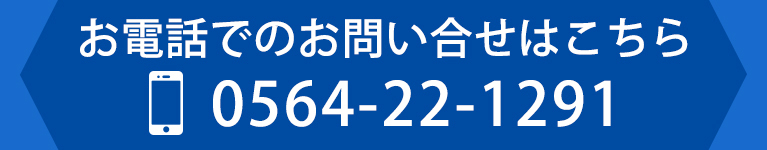クリニック案内
アクセス
- 電車
名鉄名古屋本線 東岡崎駅より徒歩5分
| 医院名 |
|---|
| 医療法人 桐渕眼科 |
| 院長 |
| 桐渕 惠嗣 |
| 住所 |
| 〒444-0043 愛知県岡崎市唐沢町1丁目30番地 |
| 診療科目 |
| 眼科 |
| 電話番号 |
| 0564-22-1291 |
| FAX番号 |
| 0564-22-0151 |
| 連絡方法 |
| お電話・FAXでお問い合せ下さい。 |
ブログ
今年も宜しくお願いします! 午ジャケット特集 その1
令和8年もこのブログを通じて皆様と音楽のお話をさせて頂きたく思います。本年もよろしくお願いいたします。
さて、今年の干支は午~うまですので、馬ジャケットを飾ってみます。
馬は人間にとって馴染みが深く、特に西洋では大変親しみ深い動物のようでして、馬をモチーフとしたジャケットの多いことおおいこと!
とても一回では紹介しきれないので、今回はパート1という事にします・・・。
先ずは玄関先です。
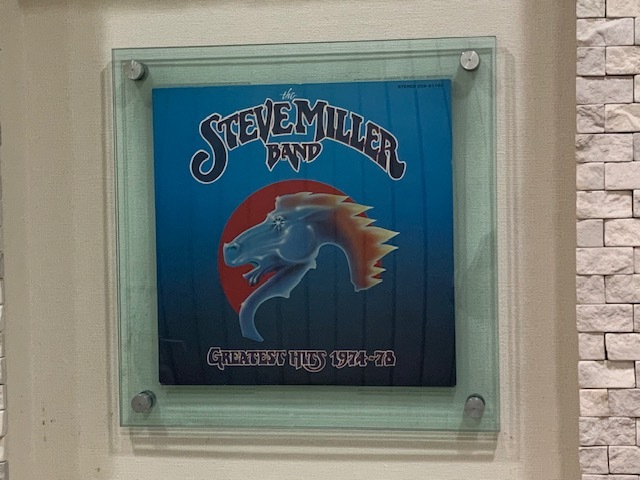
1978年発売のSteve Miller Bandの「Greatest Hits」です。当時も今も寡作なミラーさんですが、1973年の「Joker」、1976年の「Fly like an Eagle」、1977年の「Book of dreams」までは割とコンスタントに質の高いアルバムを発表してましたよね!
当時の所属レーベル、キャピトルはかなり儲けさせて貰った筈です・・・。(デビューから1972年までのジリ貧?状態を補って余りある位!?)
あまりにヒットした為キャピトルは1974年から1978年までのたった3枚のアルバムから選曲したベスト盤まで出しちゃってますね。
私は「フライライクアンイーグル」の浮遊感、トリップ感(あぶないあぶない・・・)が好きで好きで溜まりません・・・・。たまにDJするときは大抵かけてますね!
なんてことないベスト盤ですが、彼らの代名詞的なアイコン、馬がデン!とジャケットに描かれてますので、このジャケットを飾ってみました・・・。
お次はこの2枚です!

この2枚は、疾走する馬~ギャロップ、とでもいうのかな?を表現したものにしました。
先ずはドウービーのこれです。
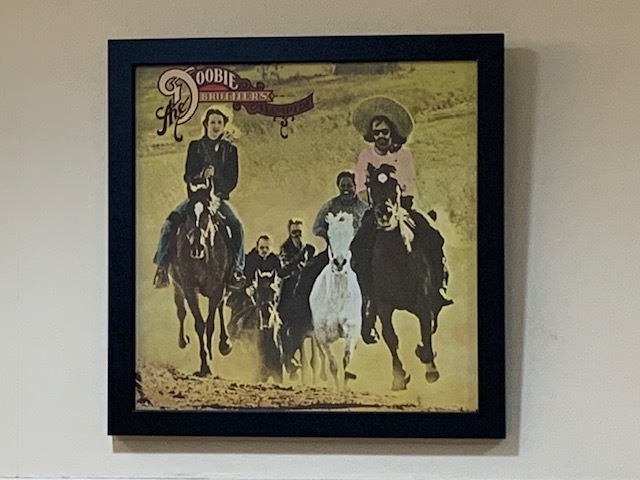
Doobie Brothersがまだ豪放だった時代、トムジョンストン期最期の傑作、1975年の「Stampede」です。
スタンピードとは、動物の群れが興奮して一斉に同じ方向へ走り出すこと、らしいですが、メンバーが跨った馬たちの雄叫びや疾走音が聞こえてきそうですね・・・。
これ、合成なのかもわかりませんが、裏ジャケットでは、怖くて乗れなかったのか、写真撮影日程が合わなかったのか、ジェフバクスターだけ普通のスナップですが、他のメンバーたちは颯爽と馬を乗りこなしていますね!
この後からマイケルマクドナルドが加入し、徐々に作風が変わって洗練されていくんですが、私的には実はそっちの路線の方が好みでして、案外最期の「One step closer」がヘビロテだったりします・・・。
そしてこれです!
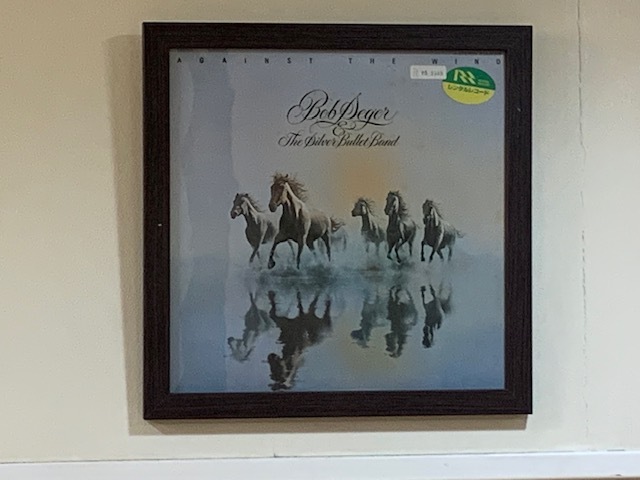
1980年発表のBob Seger & The silver bullet bandの傑作、Against the wind~奔馬の如く です!
このアルバムはあの時代のアメリカンロックの素晴らしさを体現していますね。
まず、風に逆らって進む、というタイトルが最高なんですが、曲も哀愁ある旋律が、まさにアメリカの田舎へ通ずる寂れたインターステートを走っているような気がするんですよね。目を閉じると乾いた土の匂いまで漂ってくるような感も致します。
この当時のボブシーガーは「Nine Tonight」というサザンの桑田さんも思わずカバーした物凄いライヴアルバムを出してますし、ブルーススプリングスティーンと並んで、アメリカンロックのキングだったと思います・・・。
いつの日か、ボスみたいにボーナストラック満載の再発盤が出てくるといいなあ・・・。
という訳で馬ジャケットはまだまだありますんで、次回に乞うご期待を!
今月の壁レコードはベタにクリスマス特集で!
12月ともなれば寒いのは当たり前とはいうものの、ここ最近は朝晩はかなりしばれますね~!
こんな思いをするならまだ灼熱の夏の方がいい、とは思うのですが、夏は夏で凍てつく真冬が恋しい、なんて言ってたのを思い出し苦笑する今日この頃です。
さて、これを書いているのは12月8日でして、ジョンレノンの命日なんですが、今年はジャケットではなくて絵画で追悼しようと思いますので、壁レコードはベタなクリスマスレコードでいかせていただきます・・・。
まずは玄関先です。

1987年10月に発売された、オムニバスアルバム、「A Very special Christmas」です。
印象的なキースへリングのイラストが最高なんですが、中身も今では信じられない位の人気アーティストがこれでもかと金太郎飴状態で飛び出してくる、まさにあの時代の雰囲気が漂ってくるアルバムです。
プロデューサーのJimmy Iovineの辣腕なんでしょうが、盟友?Stevie NicksやBruce Springsteenは分るんですが、当時の英米のトップアーティストを良くこんなに集められたなあ、と感服します。 70年代ならこういう役はRichard Perryあたりがしそうなんですけどね・・・。
でもやはりクリスマスソングはどんなアーティストも気合が入ってますね。全曲素晴らしいパフォーマンスで一切手抜きがありません・・・。さすがキリスト教国家です。
お次は待合室です。

先ずはほのぼのとした雪だるまが可愛い、「ベンチャーズインクリスマス」です!
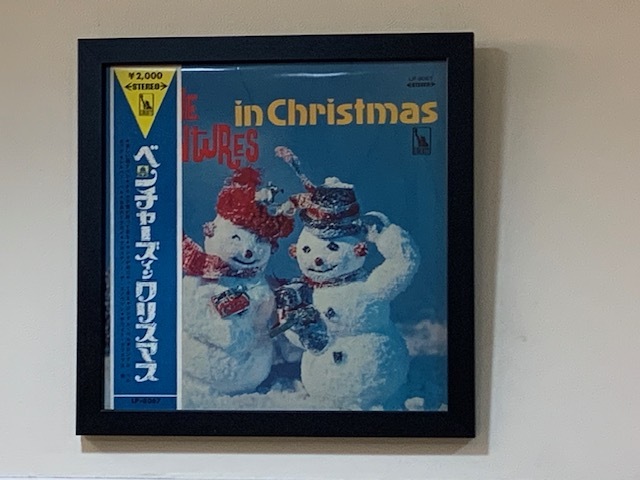
1965年にリリースされた19作目(すごい!)にして初のクリスマスアルバム、だそうです。
私はVenturesに関しては門外漢にて、完全にジャケットで選んでおりますので、細かなキャプションは省かせて頂きます・・・。

1986年にリリースされた村松邦男さんの「Christmas present」です。
村松氏はあのシュガーベイブのオリジナルメンバーでして、その筋の方々には絶大な人気を誇っていますよね。
このレコードもあの伝説のレコードショップ、パイドパイパーハウスの自主レーベル、Believe in magicから出されています。
私がこれをチョイスしたのは、いかにも80年代の東京を象徴するイラストレーター、スージー甘金さんのイラストが気に入っているからです。
スージーさんの手掛けたジャケットで最高傑作は、あの桑田バンドの名ライブアルバム、「Rock Concert」ですよね!
軽音の武田先輩のヘビーローテーションで、いやになるほど聴かされたものです・・・。
皆さま、よいクリスマスをお過ごしください!
今月の壁レコード ~ 車って怖いですね~ The Cars特集
今月の壁レコード ~ 車って怖いですね~ The Cars特集
11月になり、流石に肌寒くなって参りました、ついこの間まで恨めしく思っていた御日様が恋しく感じられますね。
さて、長らく皆様にご迷惑をお掛けしておりました医院の工事がやっと終了しました!
思い起こせば5月23日午前11時頃、外来も一番混んでる慌ただしい時、突然バリバリバリ!ガッシャ―ン!!と物凄い音が炸裂しました!
すわ、空襲か?と思ったくらいでした。
慌てて待合室を見に行ってみると、車が風除室に突っ込んできており、ガラスが粉々に粉砕し破片が散乱していました・・・。
車の突っ込み事故でした・・・。不幸中の幸い、というか奇跡的に運転手を始め患者さん、スタッフも皆怪我もなく無事だったのは日頃の行いが少しだけ良かったからかもしれません・・・。
しかし、問題はそこからでした。かなり広範囲に外壁が凹み、樹木も倒壊し、ガラスもバリバリ、ブラインドカーテンもヨレヨレ・・・という訳で部品作成、工事に半年の期間を要しました・・・。
日頃便利に使っている車ですが、使い方を誤ると恐ろしい凶器と化します!
皆さんもホント、お気をつけてくださいね!
という訳で今月はアメリカはボストン出身の知的ロックバンド、カーズを特集します

1979年発表のセカンドアルバム、「CandyーO」です。
このアルベルトバルガスの艶めかしいイラストが最高なんですが、やはり医院の入り口に飾るのは倫理的に宜しくない、との判断にて取りやめにしました。代わりにはサードアルバムのこれを飾ります。

1980年発表の問題作?サードアルバムの「Panorama」です。
御多分に漏れず私もこのアルバムはあまり聴かないですね~。ヒットシングル「たっちゃんゴー」はまあまあ好きですが・・・。
私的には彼らの最高傑作は4枚目の「Shake it up」だと思っています。
リアルタイムで貸しレコード屋さんでアメリカ盤を借りて良い音で聴いたからかもしれませんが、A面はホントよく聴きましたね~。
ジャケットは今回は飾りませんが、シェイカーを振っているオネーちゃんは、ドラマーのDavid Robinsonの彼女らしいです。
次は待合室の上段の2枚です。

センセーショナルなファーストアルバムと円熟味を増した一番のヒットアルバム「heartbeat city」です。
やはり女性をあしらったジャケットは彼ら(Rick Ocasek?いや、Benjamin Orr?)の好みなんかな?

1978年発表のファーストアルバムです。
いつも言ってますが、ファーストアルバムは締め切りが無いので、どんだけでも作曲や構想に時間はかけられるはず(お金はかけられないので、スタジオはあまり抑えられないが・・・)ですので、彼らの場合もかなり完成度が高いですね。
プロデューサーもクイーンで一世を風靡したあのRoy Thomas Bakerだしね・・・。
やはりカーズ!といったら殆どの方が脳内再生するのはデビューヒット「Just what I needed」だと思います。
タイトなリズムにグレッグホークスのヘナヘナしたキーボードが絡んでくる感じが最高です!
彼らのいいとこは解散まで不動のメンバーだった事で、5人それぞれのキャラが立ってましたね~。
個人的にはぎっちょのギタリスト、Elliot Eastonの変態的痙攣ギターが好きでしたね!!

1984年発表の最も商業的に成功した5枚目、「heartbeat city」です。
これは私、高校1年の春に今は亡き岡崎のレコード屋、「サウンドイン大衆堂」で発売日に買いまして狂ったように聴いてました!
番組名は失念しましたが、今野雄二氏総合司会のMTV的な洋楽TV番組で、大々的にプッシュされていたのを思い出します。
私がこのタイトルを全部小文字で書いたのは意味があって、なんかの雑誌で「今アメリカでは頭文字に小文字を使うのがナウい」と書かれていたからで、実際このアルバムのインナースリーヴの歌詞は全部小文字なんですね~。
曲はもうMTVの申し子的なポップなものが多いのですが、私の一押しは、B面4曲目の「I refuse」です!
ヒットした「you might think」や「magic」、「hello again」は今聴くと時代を感じさせますが、「I refuse」はいつ聴いてもカッコよくて、他の曲とはちと違うんですよね~。
あと、見事全米一位になったベンジャミンオールの名唱、「drive」も涙なしには聴けません・・・。
2000年に膵臓がんで亡くなったときは残念でした。
カーズ、いいバンドでしたね。
今月の壁レコード~映画観ました? レッドゼッペリン特集その2
10月に入っても日中は暑い陽射しが続く日がありますが、朝夕はさすがに涼しくなって参りました・・・。
やはり秋は格別ですね!
巷ではレッドゼッペリンの映画、「ビカミング」が話題沸騰中ですが、私は上映時間が都合つかず、結局見逃してしまいました・・・。
だって岡崎での上映時間は朝9時からの一回だけなんですよ、後半は6時半になりましたが、やはり仕事終わって駆けつけても間に合わないんですよね・・・。
こういう映画こそレイトショーでかけるべきだと思いますがね・・・。
さて、という訳で先月のパープルに続きBritish Hard Rockの雄、Led Zeppelinの二回目の特集です。
先ずは映画の公開記念で急遽リリースされたこのアナログです。

6作目のアルバム、「フィジカルグラフィティ」の挿入曲のライヴヴァージョンを4曲、アナログ化したものですが、A面は1975年のアールズコート、B面は1979年のネブワースという定番音源であり、ちと肩透かしでした。(でもマニアはお布施として買わなくてはいけない・・・)
ジャケットもそのまんまで工夫がないが、まあこんなものでしょうかね?
お次は泣く子も黙るこの2枚です!

多くの人がフェイバリットに挙げる4枚目、通称「フォーシンボルズ」です。
ジミーペイジと恐らくピーターグラントのゴリ押しで、表ジャケットに一切の文字(タイトル、バンド名は勿論、レコード番号さえも!)を載せなかったというレコード会社泣かせのアルバムです。

当時何の情報もなく、イギリスのレコード屋にこのまんま並んだ光景はどんなんだったでしょうかね?
アメリカでは時期により宣伝用のハイプステッカーが貼られたようですし、日本ではしっかりと帯が巻かれ、邦題に勝手に「レッドツェッペリンⅣ」と付けられてしまいましたが、所詮東洋の島国、お咎めは無かったようです。
丁度この後、1971年9月に伝説の初来日を果たし、3時間から4時間超えの凄まじいライヴを繰り広げ、語り草となっています。
幸い、音の良い海賊盤がいくつかあり、圧巻の演奏を追体験できますが、この頃はロバートプラントも高音がちゃんと出ており、ほんと、いい時に来てくれましたよね~。
しかし、この頃の彼等、まだ20代だったと思いますが、ものすごい貫禄でして、とても信じられません。
特にプラントが「天国の階段」でケルト文学に根差した深~い内容の歌詞をこの年でものにしたなんて、その早熟ぶりは凄いです。
曲については、A面の「Black Dog」「Rock'n Roll」はまだこなれてない、というかライヴの方が数段良いですが、「限りなき戦い」「天国の階段」はスタジオテイクが最高峰なんじゃないでしょうか?
後者は彼らの十八番ですので、毎回ライヴの終盤で演奏されますが、なんかセルフコピーという感じで、スタジオ版のイギリスの霧のかかった森に連れていかれそうな抒情性には到底かないません・・・。
大昔、軽音時代に無謀にもカバーしましたが、上手な先輩たちに助けて頂き何とか完奏できましたが、この時は手前味噌ですがかなり良いドラム叩けまして、ひょっとしてボンゾが眠い目をこすりながら草葉の陰から「おらよ、下手糞!」と少しだけ手を貸してくれたのかな、と勝手に思い込んでます。
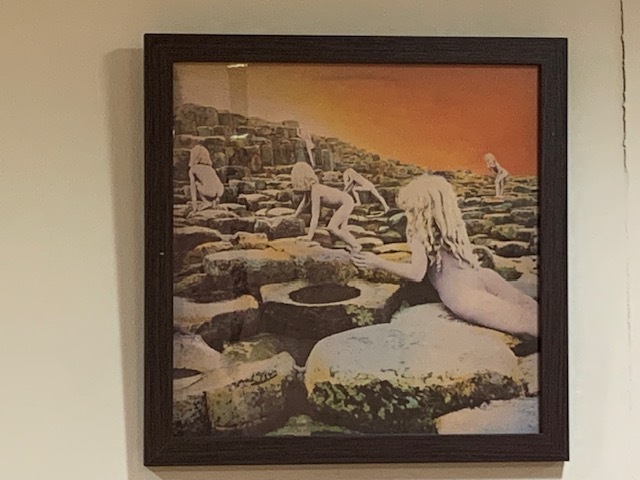
五枚目のアルバム、「Houses of the holy」~「聖なる館」です。
このジャケットのアートワークはあのヒプノシスが手掛けており、先日の映画でもいろいろ種明かしがされてまして非常に興味深かったです。
アイルランドの奇景、ジャイアントコーズウェイでゲイツ姉弟をモデルに撮影したらしいですが、悪天候に悩まされ、結局うまく撮れなかったらしいです。
このジャケットも前回同様文字情報一切なし、で製作されましたが流石に女児のお尻は特にその辺に煩いアメリカではさすがにまずかったようで、日本みたいに帯を巻く、という策を取らざるを得なかったようです。
内容は円熟味溢れる素晴らしいもので、とくに後のライブの定番となる冒頭の「The song remains the same」から「Rain song」の組曲は圧巻でして、後者のメロトロンを駆使した抒情性はいつ聴いても沁みますね・・・。
ジェームスブラウンのパロディー?「クランジ」もボンゾのつんのめりドラムが最高です!
という感じでキリがないのでこの辺でやめておきます。
やはりZeppは最高ですね!
今月の壁レコード ~ Deep Purple 特集
九月に入りましたが、日中はまだまだ暑い日が続きます。
先月宣言した通り、私もついに日傘を購入しまして、陽射しが強い日は恩恵に預かっている次第です。やっぱ日陰はいいですね。
さて、今月の壁レコードは、最近「ライヴインジャパン~デラックスエディション」が話題沸騰中のDeep Purpleを特集してみます。
先ずは玄関先のこれです!
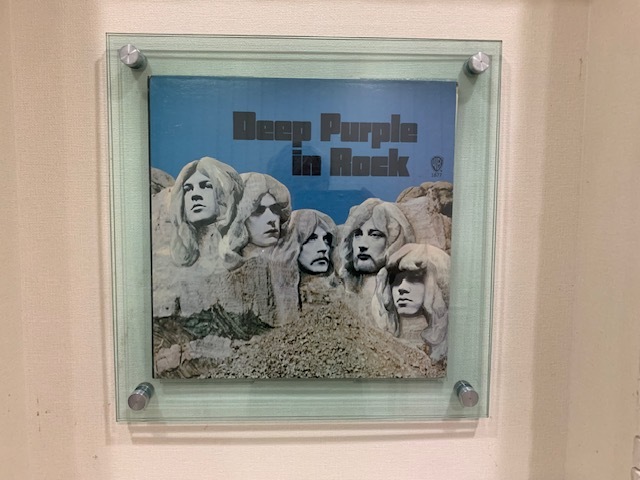
アメリカの有名なラシュモア山をパロったもので、大統領の代わりにメンバーの顔が彫刻されてます。
岩(ロック)の中に刻まれている(イン)、ロックミュージック、というダサカッコいいコンセプトは誰の発案だったんでしょうか?
それまでのジョンロード主導のクラシック~アートロック路線からリッチーブラックモア主導のハードロック路線に舵を切り直した快作で、オープニングの「Speed King」のカッコよさったら無いですね!
「王様」の直訳ロックもこの曲が一番効果的だったんじゃないでしょうか・・・。ほんとに面白かったです。
では待合壁のこの2枚です!

泣く子も黙る「ライヴインジャパン」です!!
今回のボックスもすんごい売れ行きで、国内盤ボックスは即売り切れとなったみたいですね。
私、今回の再発プロジェクトのニュースは割と早くに入手しまして、CD版の装丁がロングボックス形態、というのに憤慨して海外のオフィシャルサイトで10枚組LPレコードボックスも注文してしまいました。
やはり、ボックス物はLPサイズでなくちゃね!!
このアルバムはやはり彼等の真骨頂であるライブ音源、しかも一番美味しい所がギュッと凝縮されている、あまたあるロックのライヴ盤の中でも白眉だと思います。
故にいろんな形態で所持しておりますが、日本盤と海外盤ではタイトル、ジャケットがちと違うんですね・・・。
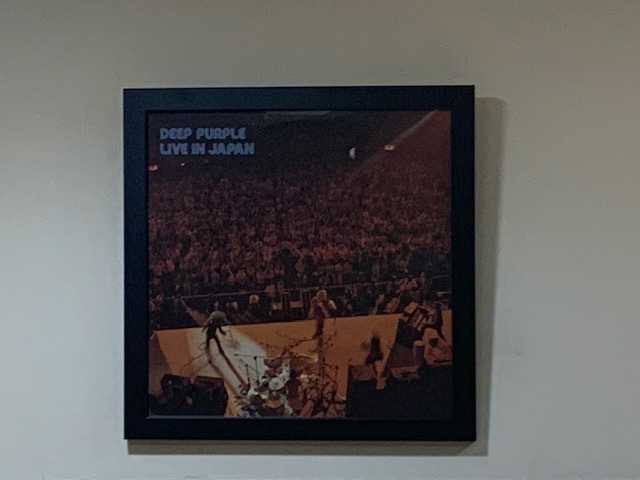
1972年8月15日、16日の大阪公演と17日の東京日本武道館で計3回行われた来日コンサートを編集した日本限定のライヴ盤です。
当時はまだ緩かったのか、日本公演の限定ライヴ盤って結構出てましたよね。
「シカゴライヴインジャパン」とかシルヴァーヘッドのやつなんか、かなりお気に入りです。
これの初回盤のおまけにはステージ写真のネガフィルムがついており、私も持ってます。(さすがに現像はしてないですが・・・。)
やはりオープニングの「Highway Star」が流れてくると興奮しますね!!
続く「Child in Time」も静と動を巧みにコントロールするイアンペイスの細かなスネアロールには唸ります・・・。
日頃はツェッペリンに比べてその世界観がスケール小さいよなあ・・・なんてパープルを揶揄している自分ですが、このあたりの演奏には鳥肌が立ちます。ごめんなさい!!
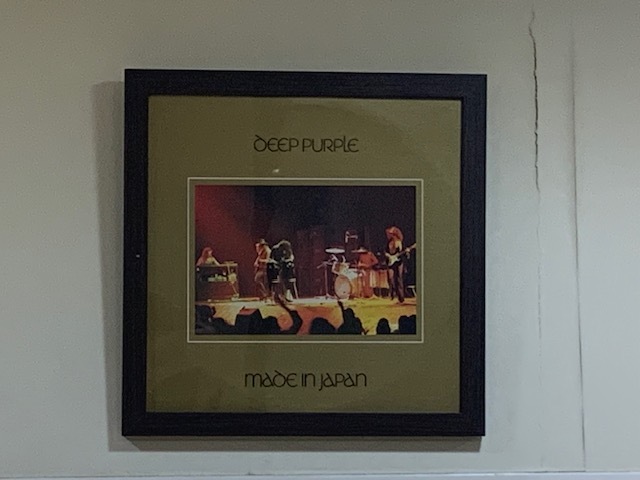
このライヴ盤は日本限定だった為、かなり輸出されたようですが、買えなかった海外のファンから購入希望が殺到した為、タイトルを「Made in Japan」とし、ジャケットを変え1972年12月にイギリスで、1973年4月にアメリカで発売されたようです。
私は英盤、米盤両方持ってますが、これ面白いのは内ジャケットが旭日旗で、もろ東洋趣味なんですよね~。
どうしても欧米から見た日本、というのは旭日旗が使われてしまい、クリエーションがクリームのフェリックスパパラルディと共演したレコードもその手のデザインになってしまってました・・・。
話は変わりますが、彼等いや、ハードロックの代名詞的な役割となっている「Smoke on the water」なんですが、私どうもこの曲が苦手でして・・・。
いや、ザッパの肩を持つ訳ではないですが、そんな不幸な(ある意味しょうもない題材)事をロックバンドが唄ってもな~って気がしますし、弾きやすいリフだから、といってオッサン達が集まると、取り敢えずセッションしようか~という流れでゆるゆるで始まる演奏がどうにも容認できないんですよね~・・・・・。(大抵尻切れトンボで回りは吉本新喜劇よろしくずっこける(笑))
今月の壁レコード~オジーオズボーン追悼特集
先月も同じことを言っていますが、ホントに暑い日が続きますね・・・。
41度を超えた地域もあるなんて、ここは日本なのでしょうか?と言いたくなります。
私は男子たるもの、日傘など邪道と思っているのですが、ここ最近の陽射しにはさすがに参りまして、購入を考えている今日この頃です・・・。
さて、今月は7月22日に惜しくも亡くなったOzzy Osbourneさんを特集してみました。
先ずはBlack Sabbathのこちらからです。
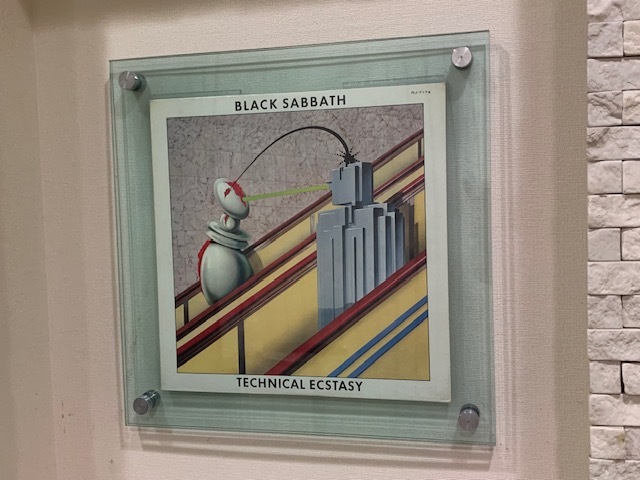
1976年発表の、「Technical Ecstacy」ですが、実はホントはここには「Paranoid」をぶちこみたかったんですが、やはり超名盤ですので、次回?ブラックサバス単独での特集で採用しようと思います。
テクニカルエクスタシーはヒプノシスが手掛けたジャケット、という事で所持していますが、実はまともに聴いた事がないんです・・・。これから聴いてみますね。
調べてみると、オジーはあまりこのレコード制作に乗り気でなかったみたいで、脱退を考え始めたのもこの頃からみたいです・・・。
という訳で、これからはオジーの名作2枚を紹介します。

サバス脱退後の1980年に満を持して発表された名作ファーストソロアルバム、「Blizzard of Ozz」です。
タイトルは「オズの魔法使い~Wizard of Oz」をパロったもので、洒落が効いてますね。

このアルバムはRandy Rhoadsという若き才能を得たオジーのやる気みなぎる傑作だと思います。
彼のヴォーカルは、一般的なメタル系の金切り悶絶シャウトとは一線を画した、個性的な声と歌い方で、ノブさん風に言うと、「クセが強いんじゃあ!」という感じなんですが、そこがまたいいんです。
Crazy Trainなんて最高ですね。
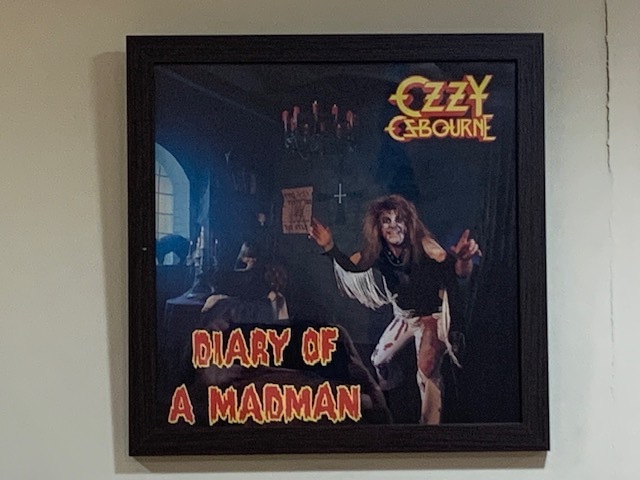
続いて、絶頂期の1981年に発表された「Diary of a madman」です。
このハリウッドホラー映画のポスターのような"お化け文字”を使ったおどろおどろしいデザイン、素晴らしいですね。
この、”お化け文字”を使った同時期のアルバムジャケットとしては、ビリージョエルの「Songs in the attic」なんかが思い浮かびますね。
客から投げられた蝙蝠の死骸を、おもちゃだと勘違いしてステージ上でかじりついて大騒ぎになった事件はこの頃でしたっけ? 彼らしいエピソードとして音楽雑誌で面白おかしく取り上げられていましたが、マジでワクチンとか大変だったみたいです。
ギターヒーローとして人気絶頂を極めたRandy Rhoadsでしたが、このアルバムツアー中に不幸な事故で1982年3月19日に亡くなっています。まだ25歳だったのに残念な死でした。オジーの喪失感は半端なかったみたいですね。
ただその後、日本の血を引くギタリスト、Jake E Leeを擁し、これまた名作「Bark at the moon」を発表していき、日本での人気はすさまじいものとなっていくのです。
大学時代の先輩、Thin Lizzy(このバンドも特集してみたい!)のBlack Roseを教えてくれた水野さんもJeke E Leeは大好きでしたね~。
今月の壁レコード~Brian Wilson追悼特集
毎日容赦ない陽射しが降りそそぐ今日この頃ですが、ほんとキツイですね・・・。
こんな時は涼しいサーフミュージックを!という訳でBeach Boysでいってみたいのですが、そんな能天気な事は言っていられない事態が発生してしまいました・・・。
2025年6月12日、リーダーのBrian Wilsonさんが82歳で亡くなったニュースは世界中の音楽ファンを悲しませました。
という訳で基本的にブライアンのソロっぽいレコードを集めて追悼させていただきたいと思います。
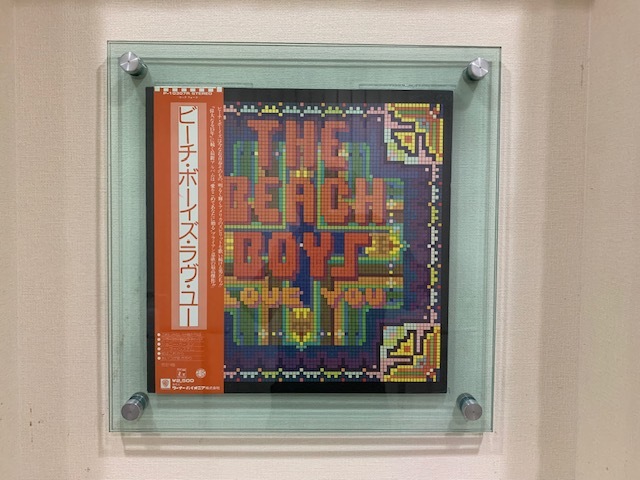
1977年にリリースされた「Love You」です。
これは久々にブライアンが全曲を書き下ろしており、停滞気味だった70年代半ばにしては、彼がかなり?やる気をみせてくれた佳作でして、ほぼほぼブライアンのソロアルバムといっていいと思います・・・。
皆が言及しているように、B面の充実ぶりは素晴らく、2曲目から4曲目の流れは最高ですね。
特に奥方との掛け合いが何とも言えない味を醸し出している4曲目はいつ聴いてもほっこりしてしまいますね・・・。
お次はこの素晴らしい2枚です!

1966年に発表された、ブライアン渾身の世紀の大傑作、「Pet Sounds」です。
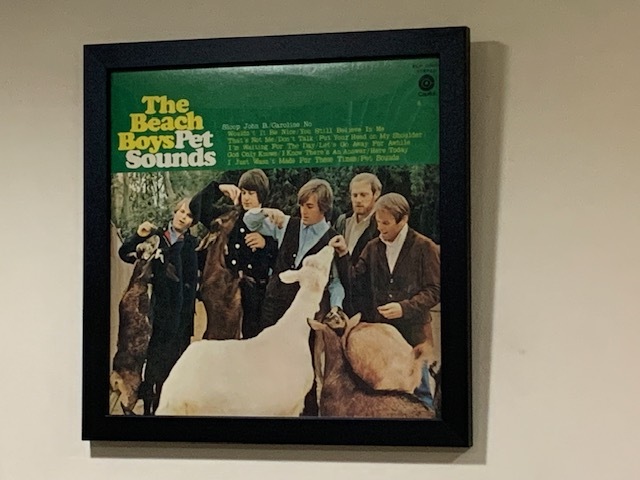
ビートルズの「Rubber Soul」に触発されて作成を決意した、だのどうだの言われてますが、実際のところどうなんですかね?
歌詞の内容もジョンとポールの作風の違いもあり全方位にアンテナを広げているラヴァーソウルに対して、ペットサウンズはほぼブライアン独りの視点で歌詞が書かれていることもあり、非常に内に籠った(そこがいいんですが)内省的な作風であるのが、ちとひっかるんですね・・・。
ブライアンがB面4曲目のタイトルに挙げている様に、このレコードはwasn't made for these timesだっだと思います。
今でこそ大傑作の烙印が押されていますが、私がロックを聴き始めた80年代初頭はペットサウンズなんて誰も評価してなかったような気がします。
そもそもビーチボーイズ自体が過去の懐メロバンド扱いされており、レコードはベスト盤以外は皆廃盤で、探すのに苦労した覚えがあります・・・。
再評価されたのは1988年に世界で初めて日本でCD化され、萩原健太さんあたりがミュージックマガジンで絶賛した頃じゃなかったかな・・・。
私も恥ずかしながらその初CD化で初めてまともに聴きましたが、当時鬱屈した学生生活を送っていた私にとって、ホントに染み渡る音楽でしたね。・・・。毎日聴いてましたね~。
個人的には「That's not me」の後半、転調するところが大好きです・・・。

1967年9月発売となった、自身のレーベル、Brother Recordからの第一弾「Smiley Smile」です。
皆さんご存知の通り、頓挫した大作、「Smile」の縮小代替盤ですが、確かにA面B面一曲目の2大ヒット曲に比べると小品揃いですが、取り敢えずリリースしてくれただけでもうけもん!だったかもしれませんね。
B面一曲目に収められている、彼らの最高傑作(と私は思う)「Good Vibrations」は、前作ペットサウンズ後にブライアンが作り上げたグループとしても最高のチャートアクションを記録した大ヒット曲です。
テルミンの不気味な音色がこの曲の独特さに色を添えています。ジミーペイジもここから影響されたのかな?
A面一曲目の「英雄と悪漢」は様々な曲を寄せ集めた?目まぐるしい、落ち着きのない曲ですが、なかなか面白い曲で私は好きです。
後年、ブライアン抜きのライヴアルバム「In Concert」で苦労して再現しているのが何かいじらしい感じがしました・・・。
リッキーファタールのタイトなドラム、最高です!
看板書き替えました!~ S●● Pistols 特集
先月半ばに国道一号線豊橋方面から見える立て看板を新しく代えて頂きました。
流石に16年も前のものですから、かなり文字に切れ目が走り、何かパンクロックのジャケットみたいなフォントになってしまってました・・。
個人的にはなかなか味があって気に入っていたのですが、不評の声も多く、思い切って直してみました・・・。

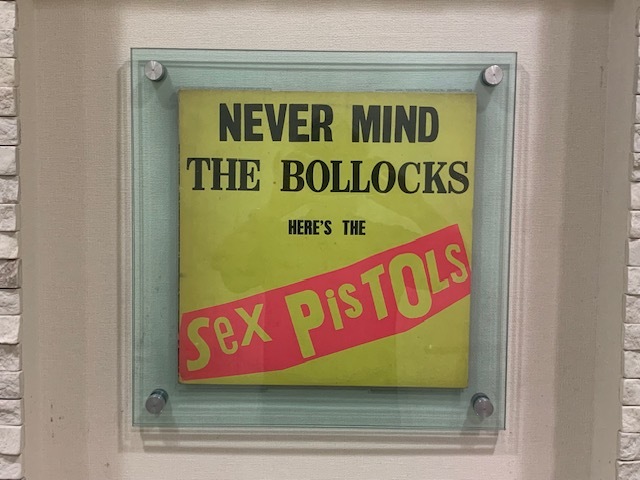
1977年発売後、一大センセーショナルを巻き起こした鮮烈なデビューアルバム、「Never mind the bollocks」です。
流石に医院のブログに「SEX PISTOLS」を連呼する訳にはいきませんので、バンド名にはこれより触れません!
邦題は「勝手にしやがれ」で、多分ジャンポールベルモントの映画より、沢田研二さんの曲に感化されたんかな?
この脅迫文書みたいなおどろおどろしいジャケットをデザインしたのはジェイミーリード氏で、2023年に76歳で亡くなっているようです。
イギリスオリジナル盤のこの鮮やかな蛍光黄色のジャケットは星の数ほどあるロックアルバムのジャケットの中でも白眉だと思います。いや~、素晴らしいデザインですね!

待合室壁の2枚です。
彼らは自然発生的なバンドではなく、マルコムマクラーレンによるプロジェクト的な成り立ちであった訳でして、クリストーマスの周到なプロダクションによる「完璧な」サウンドにより後世に名を遺すパンクバンドとなっていったのですが、その辺の面白さをマルコムの視点で描いた映画、「Great Rock'n Roll Swindle」関連の2枚です。
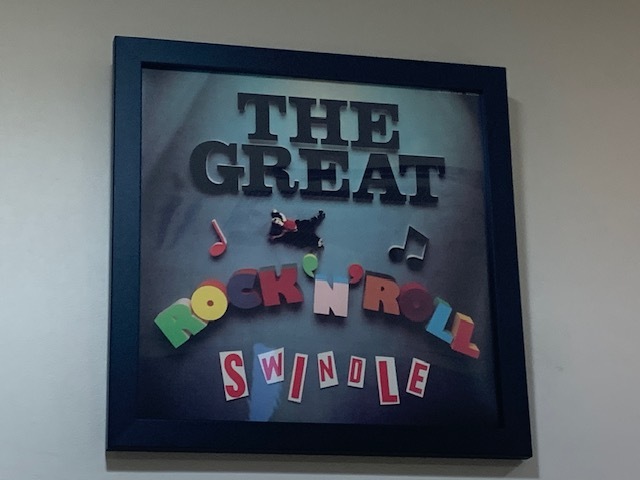
こちらは映画のサントラですが、同じように脅迫文的切り貼り文字で構成されていますが、何となく可愛いくなっております・・・。怖くもなんともありません、逆に狙ってたのかな?

こちらも映画関連のレコードですが、こちらのイラストの方が映画の内容をめちゃ面白く表現しており、破天荒な彼等らしい最高のジャケットですね!
パパラッチ?に吐瀉物を浴びせているポールクック、本人はなんと思ったんでしょうかね?
あと確かにパンクのアイコンとしてのシドヴィシャスはカッコいいとは思いますが、音楽的には何の貢献もしてないので、破滅的な最期という事もありますが、ちと崇められすぎなんじゃないかな?と個人的には思います。
やはりピストルズが凡百のパンクバンドと一線を画してるのは、前任のグレンマトロックの卓越したソングライティングの賜物だと私は思います・・・。
もう少し脚光を浴びてもいいと思いますがね・・・。

という訳で、真面目なフォントの看板に落ち着きました!
パンクバンドからフォークミュージックのグループに変身!みたいな感じですね・・・。
もちろんフォークミュージックを揶揄した訳ではありませんので悪しからず・・・。
今月の壁レコード~サザンオールスターズ特集
四月も半ば近くになり、栄華を誇った桜もさすがに散って、葉桜になりつつあります。
これからまた一年間、唯の樹木に落ちぶれてしまうのえすが、数週間はスターでいられるのですから、桜ってすごい木ですね。
さて、今月は最近新作をリリースして再び脚光を浴びているサザンオールスターズの初期作を特集してみました。
先ず玄関先はこれです。
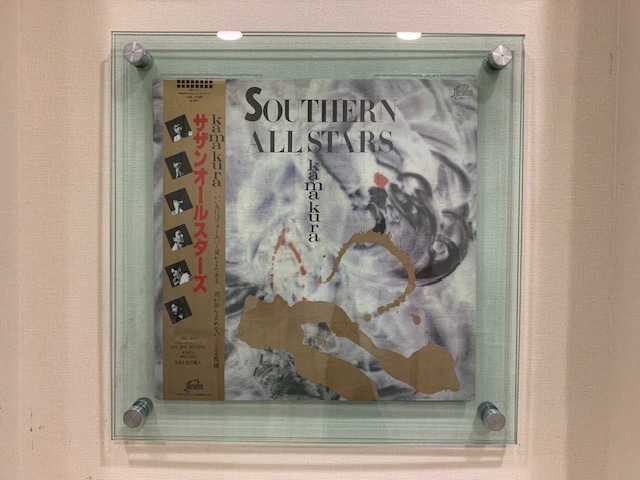
こないだのNHKでの特番で桑田さんが仰っていましたが、心に残っているアルバムは?という質問で、「kamakura」という答えが返ってきた時は意外でしたね~。
私にとっては80年代に出した2枚組、というだけの薄い印象だったので・・・。
これからしっかりと聴いてみなくては・・・。

お次は待合壁の2枚です。
先ずは1981年の「ステレオ太陽族」です。
この頃はまだやんちゃな感じでしたが、なかなか渋い曲もやっておられますね。
私は実はサザンの良いリスナーではなく、ヒット曲以外はあんまり知らないんです・・・大変申し訳ありません。
大学の軽音の先輩方がサザンのフリークでして、「旅姿六人衆」を西日本医学生音楽祭で熱演されたのは大変感動的でした・・・。
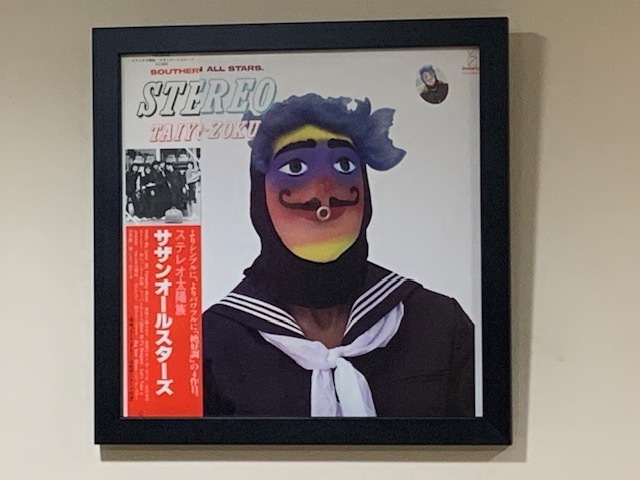
最後は1983年の自主レーベル立ち上げ後初のアルバム、「綺麗」です。
自主レーベル立ち上げ、は成功したアーティストの特権だと思います。
ビートルズのアップル然り、レッドゼッペリンのスワンソング然り、Jefferson Airplaneのグラント然り・・・。
やはり彼らは日本を代表する「Taishita」バンドですね。
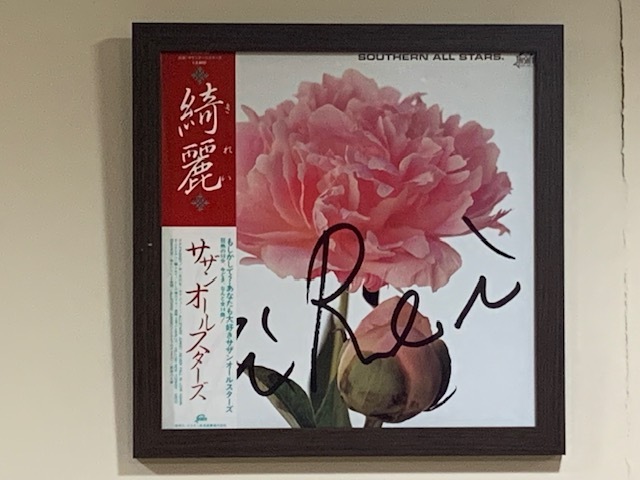
先に書いたように、私はサザンオールスターズについては語る資格はありません・・・。
私はむしろ桑田さんのソロプロジェクトの方が気に入っております。
古くは渋谷エッグマンでの熱狂ライブ、「嘉門雄三&The Victor Wheels」~これは大学時代聴きまくりまして、Otis Clayをここで知りました!(ただ、桑田さんは少し前に発売されたボブシーガーのライブアルバムのヴァージョンで演っておられますが・・・。)
そして80年代半ばのサザン一時休止期に思いっきり好きなことをやりまくった、「Kuwata Band」~これも軽音時代、長野県での合宿に向かう時、先輩の車の中でカセットテープが擦り切れるほど聴かされまくり、大好きなアルバムになりましたね。
あとはAct Against Aids projectで数年に渡って披露された、洋楽の鬼気迫るカヴァー大会!
ジョンレノンの会や、エリッククラプトン(本人曰くエリッククラプトソ!)の会も凄かったですが、なかでも50年代から現代までのロックの歴史を総括した会はドアーズの「Touch Me」を素晴らしいアレンジで唄って頂き、感動しましたね~。
ロックだけではなく、夷撫悶汰(イブモンタ)と名乗り、スタンダードジャズを唄った時も素晴らしかったです。本当に粋で上手で素晴らしいシンガーだと思います。
サザンのファンに袋叩きにされそうですが、これからはジャズやシャンソン、往年のロックスタンダードをライブハウスでガンガン唄っていって頂きたいですね~。
今月の壁レコード~ヒプノシス特集
寒かった冬もようやく落ち着いてはきましたが、日によっては寒い日もあり、まさに三寒四温といったところですね。
先日、音楽好きには話題の映画、「ヒプノシス」を観てきました。
やはり私のようなレコード命の人種にとっては物凄く素晴らしい内容でした!
オープニングからエンドロールまでほぼ瞬き無しで集中した映画を観たのは初めてと言っていいかもしれません・・・。
私はヒプノシスは、ストームソージャーソンがリーダーで、オーブリーパウエルはカメラマン、ジョージハーディーがグラフィックデザイナーだと思っていたのですが、まあ、そんな立ち位置ではありますが、オーブリーパウエル(以降ポー)がこれほどまでに貢献していたなんて映画をみるまでは知りませんでした・・・。
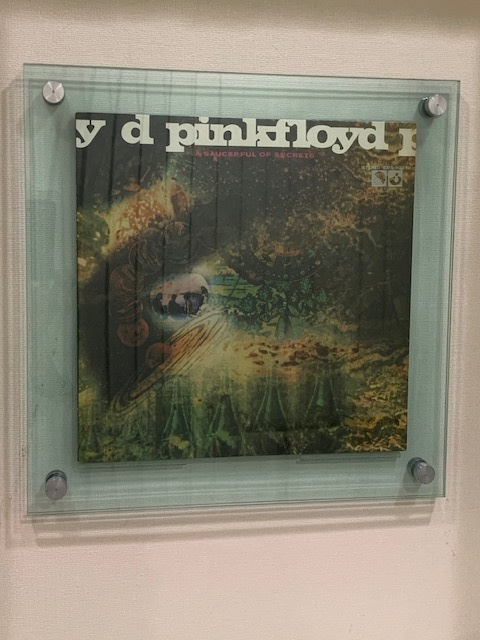
先ず玄関先ですが、これはポーやストームと親交の深かった、ピンクフロイドのセカンドアルバムのジャケットで、これが本格的なメジャーアーティストのジャケットの初仕事だったみたいです。
混沌とした、まさに麻薬で飛んでいるときの脳内映像みたいですね・・・。

待合室の2枚です。この2枚は初期と後期の人海戦術コンセプトの新旧傑作と思います。
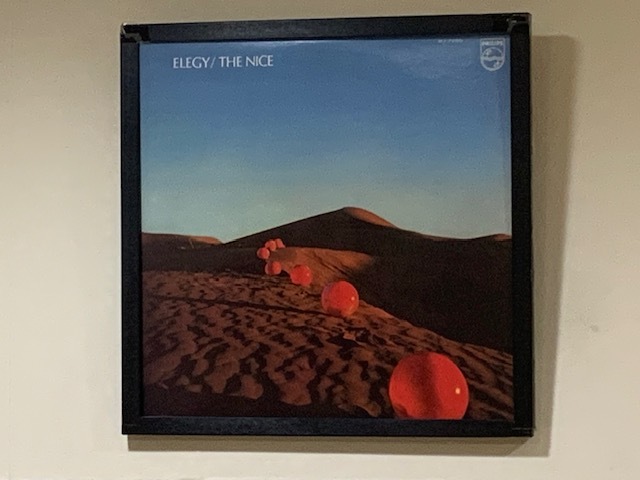
キースエマーソン率いるナイスのラストアルバム、「エレジー」ですが、これ凄いのは本当の砂漠に行って実際にボールを延々と人の手で並べているんですよね・・・。
1970年当時、CGなんて存在してない訳ですから・・・。
気の遠くなる作業を繰り返し繰り返し撮影した彼らの根気には頭が下がります。
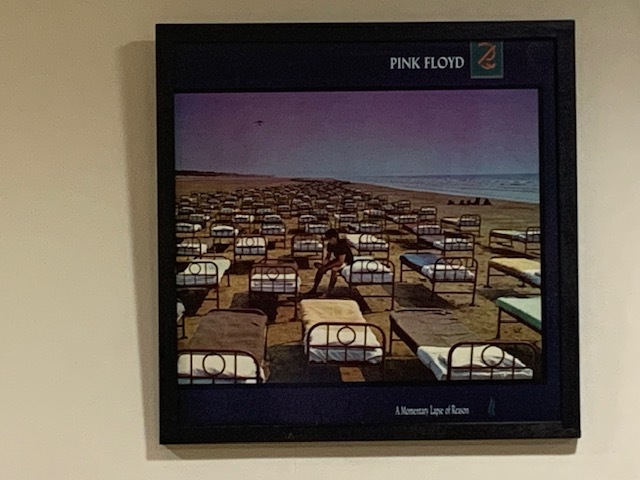
再結成ピンクフロイド~Roger Watersの居ないフロイドを、フロイドと言っていいのか、未だに思いますが、ジャケットにヒプノシスを起用する以上、やはりフロイドなんでしょうね・・・。
これもCGではなく、海岸に実際にベッドを延々と並べて撮影したらしいです・・・。
右端に写っている犬もちゃんと大人しく伏せのポーズを取らせているのは奇跡に近いと思います・・・。
今月の壁レコードも蛇~スネークでいきます
2月となり毎日寒い日々が続きますね~。
今月もスネイク関連レコードでいってみたいと思います。
先ず玄関先ですが、ちょい反則技ですが、スネークマンショーの迷盤?「戦争反対」です!
当時中学生の私にとって激烈刺激的なレコードでした! 未聴の方は是非ともヘッドフォンで(これ大事です)聴いてみてください!
小林克也さん、伊武雅刀さん、桑原茂一さんの三人を中心に数々の才人が集結し、80年代初頭のTokyoでしか成し得なかったエキセントリックなレコードです!

お次はちょいマニアックな蛇レコードです!

アリスクーパーの出世作、「Killer」です。
アリスクーパーはステージでも本物の蛇を使ってましたね・・・。

最後はELPが設立したレーヴェル、Manticore から渋いレコードを発売していたHansonの「Now hear this 」です。
このレコードは凄くファンキーでカッコいいサウンド満載で愛聴盤であります。
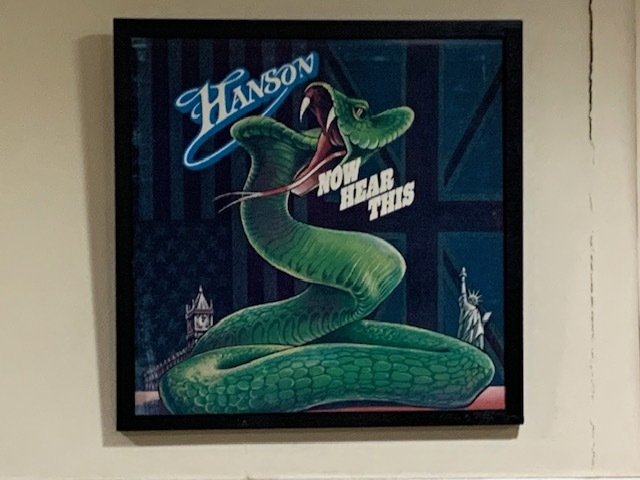
謹賀新年 巳年にて蛇ジャケット特集 (2025/01/10)
明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
恒例の干支ジャケットですが、巳年にて蛇さんでいってみます!
先ずはユーライアヒープのこれです!
Vocalがジョンロートンに変わった後で、個人的にはあまり聴き込んでないのですが、この何とも言えないイラストが妙に引っ掛かりますね・・・。
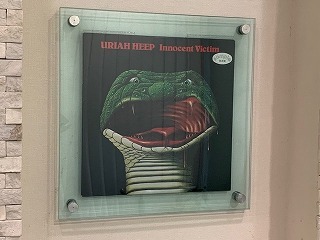
お次はWhitesnakeです。
特にこの2枚はカッコイイです!

これはセカンドアルバム(実質的にはバンドとしてはファーストアルバムなんですが・・・)「トラブル」のアメリカ仕様盤で割と見かけないやつです。
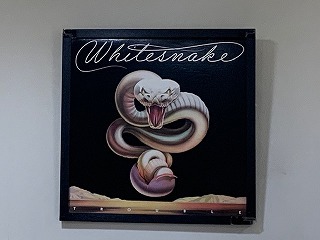
こちらは名曲「Don't break my heart again」を擁する円熟期の名盤「Come and get it」でして、こちらのアメリカ盤は蛇の口の中が修正されていますが、イギリスオリジナル盤はちょっとマズイ仕様になっていますので、医院には飾りませんでした・・・。
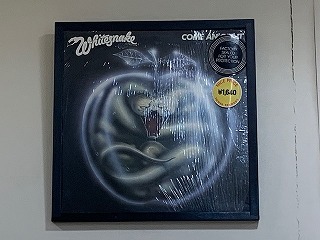
クリスマス仕様! (2024/12/24)
メリークリスマス!という訳でちょこっと入れ替えました。


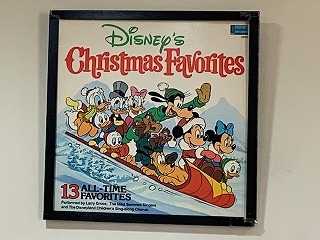
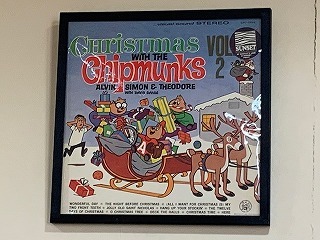
今月の壁レコード~追悼クインシー・ジョーンズ特集 (2024/11/18)
あれだけ暑かった夏が恋しく感じられる程めっきり冬めいて来た今日この頃です...。
今回は先日亡くなったQuincy Jones氏の関連レコードを特集してみました。
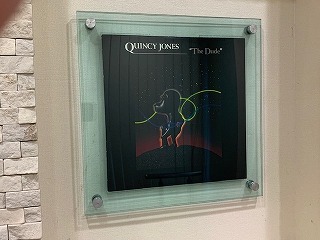
先ずは1980年発表の代表作「The Dude」です。
この頃の御大はお気に入りシンガーのJames Ingram とPatti Austin、ドラムのJohn RobinsonとベースのLouis Johnsonの鉄壁のリズムセクション、鍵盤のGregg Phillinganesを基本として、ギターにSteve Lukatherなど数々の有名セッションミュージシャンを起用して分厚いサウンドを繰り広げています。

お次は御大のproduse作品の中で群を抜いて成功したマイケル・ジャクソンの2枚です。
1979年の「オフザウォール」ですが、やはり2曲目のRock with youでの鉄壁のリズムセクションには惚れ惚れしてしまいます・・・。(特にジョンロビンソンのハイハットワークは鳥肌が立ちます。)
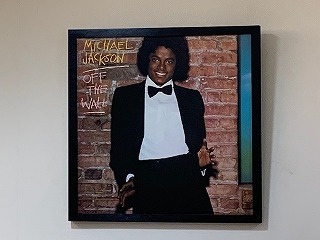
1982年の「スリラー」は社会現象になりましたね。
今聴くと2曲目の「Baby you're mine」が当時のブラコン路線で実は一番カッコいいんですよね~。
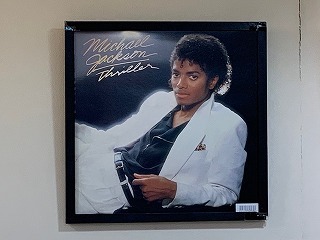
最後は全然関係ないですが、懇意にしている画商さんがパリへ買い付けに行かれて買ってきたJane Birkinさんの若かりし頃の美麗ポートレイトが入荷してきたので、飾ってみました!

今月の壁レコード~ジミヘンドリックス特集 (2024/09/30)
10月真直になり、ようやっと朝晩は過ごし易くなってまいりました今日この頃です。
今月の壁レコードは、9月18日の命日をお迎えになったジミヘンを特集してみます。
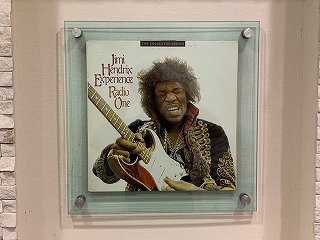

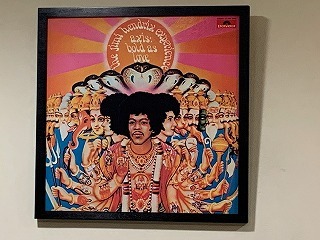
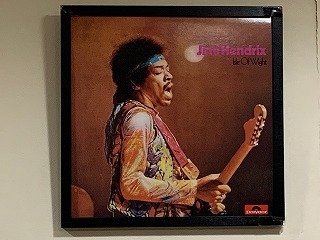
今月の壁レコード~hotter than July という訳でStevie Wonder特集 (2024/07/10)
酷暑の毎日です。七月にしてこんな暑いなんて、八月はどうなちゃうんでしょうか??
という訳で、例年の七月より暑い! Hotter than Julyという感じで、スティーヴィ―ワンダーさんを特集してみます!
彼のレコードの特徴として、曲間が殆ど無く、間髪入れずに次の曲が始まる、というのがありますが、A面の冒頭の1,2曲は素晴らしい流れですよね。
B面のバラッド、「Lately」は美しい曲ですが、後半になるとこれでもか、といった転調の嵐が流石Stevieですね!
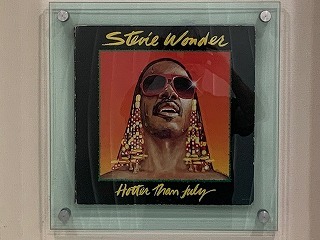
お次は70年代と80年代の代表作2枚です。

1976年に発表された大傑作、「Songs in the key of life」です。
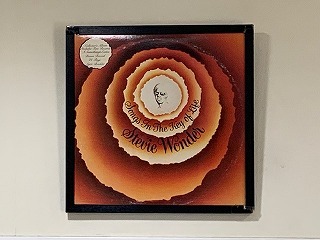
1986年の大ヒット曲、「part time lover」を擁する「In square circle」です。
最近結構聴き直してまして、A面の流れはなかなかいいですね。
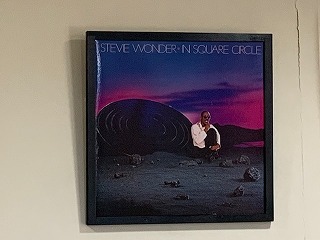
今月の壁レコード~魔力の刻印‼アイアンメイデン特集 (2024/06/06)
本日は令和6年6月6日です。
という訳で、魔力の刻印、アイアンメイデンを特集してみます。
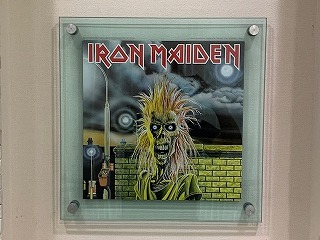
先ずは震撼のファーストアルバムです。
一枚目にしてこの完成度!世界観も既に確立されていて、やはり最高傑作だと思います。
次作、「キラーズ」も名曲「ラスチャイルド」など、さすがのPaul Deano節が聴かれ、凄いアルバムですね!
こちらも飾りたかったんですが、さすがに医院の壁にはそぐわないので、泣く泣く断念しました・・・。


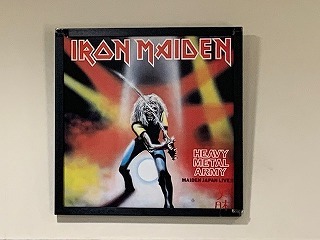
今月の壁レコード Pretenders特集 (2024/05/09)
久々の更新となってしまいましたが、今回はPretendersでいってみます。
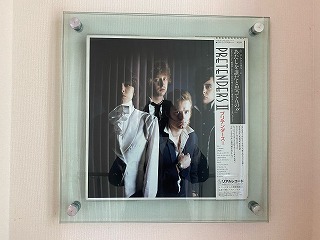

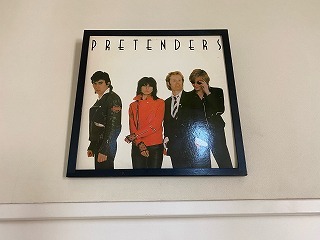
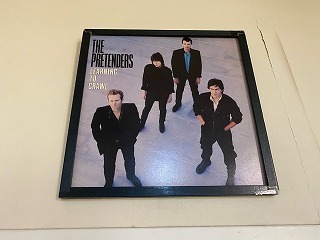
2024年は辰年です!ドラゴンジャケット特集!! (2024/01/19)
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。
今年は辰年、という事でドラゴンの描かれたジャケットを飾ってみました。
先ずはブルースリーの映画「燃えよドラゴン」のサントラです。
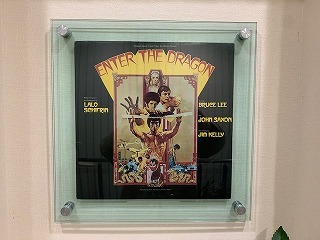

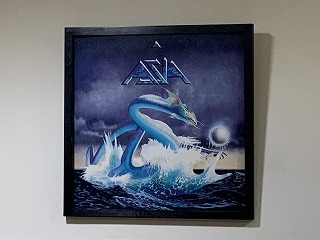
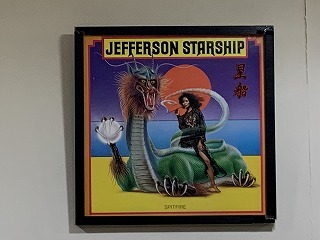
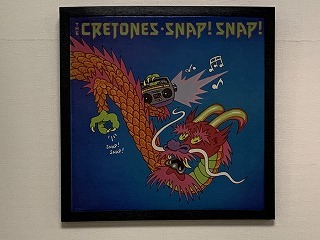
今月の壁レコード モンスター特集 (2023/10/02)
暑かった今年の夏も10月に入り、流石に朝晩はかなり過ごしやすくなってきました。
流石にサーフィンジャケットは無理がありますので、今月はハロウィンっぽくモンスタージャケットでいってみます。
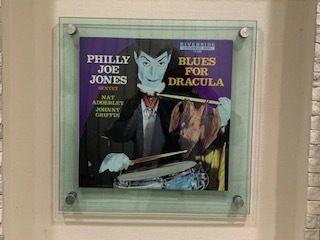
ジャズ界の名ドラマー、Philly Joe Jonesの珍しいリーダー作です。

続きまして中待ち合いの2枚です
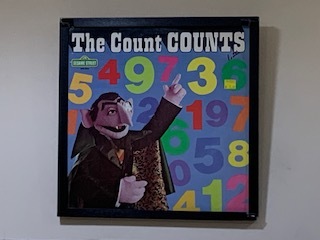

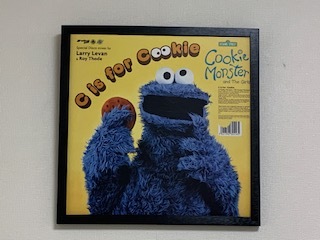
今回の壁レコードはサーフィンジャケットで! (2023/08/31)
なかなか更新できないので、「今回の壁レコード」にしてみます。
今回は夏らしくサーフィンジャケットでいってみます。
今月の壁レコード~EW&F、というか長岡秀星さん特集 (2023/06/26)
久々の更新です・・・なかなかこの作業が出来ない私です。
今回は前からやってみたかった、Earth Wind And Fireの長岡秀星さんのイラスト盤でいってみます。
すなわち、「太陽神」、「黙示録」、「グレイテスト・ヒッツ第一集」、「天空の女神」の黄金期4作です。
ただ、個人的には彼らの最高傑作は「暗黒への挑戦」と続くライブ盤「灼熱の饗宴」だと思ってます...
追悼 YMO特集 (2023/04/04)
うっかりしてて3月のブログを作成するのを忘れてました・・・。
壁レコード自体は更新していたんですが・・・。
実は1月11日に鬼籍に入られた高橋幸宏さんの追悼で、YMOのレコードを飾ってはいたんです。
4月に入ってからは懸念していたゲイリーロッシントンさん追悼でレーナードスキナードでも飾ろうかな・・・と思っていたら、4月2日夜に坂本教授の訃報が飛び込んできました。
という訳でもうしばらくはこのままYMOで行かせてください・・・。
今月後半からは坂本教授のソロで行こうと計画中です。
今月の壁レコードは訃報続きで難しいです・・・。(2023/02/02)
今年に入ってから大物アーティストの訃報が多いと思います。
先ず最初に驚愕したのはJeff Beck氏でして、これは意表をつかれた、という感じでしばらくショックでした・・・。

次の週は高橋幸宏氏、そしてDavid Crosby氏、Tom Verlaine氏、
そして今週は鮎川誠氏まで・・・。
2023年は兎年です、ラビットジャケット特集!(2023/01/30)
2023年も宜しくお願いします。
ここ最近はなかなか更新できませんでして、申し訳ございません。
今年こそは毎月の更新を目指して頑張りたいです。
一月は恒例の干支特集なんですが、兎さんジャケットってなかなか無いんですよね・・・。
先ずは玄関先です。
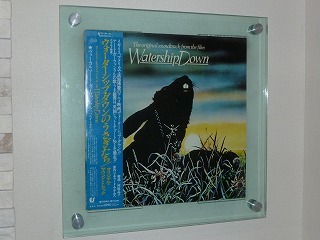
1981年のイギリスのアニメーション映画、「ウォーターシップダウンのうさぎたち」です。
未見にてNHK衛星で放映されないかな?といつも思っております。
お次はこの2枚です。

定番のエリックゲイルとラッシュのプレストです。
2枚とも、兎の大量発生現象が見られます。
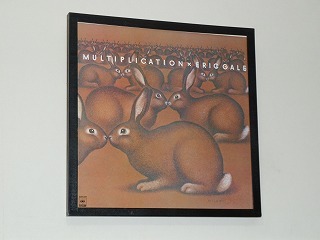
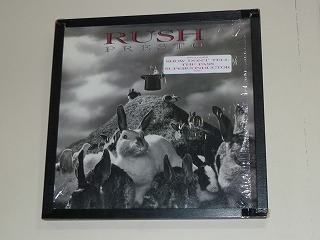
ラッシュのものは当時CDで購入しましたが、年代的にアナログでの入手は結構大変でした・・・。
ラッシュはニールパート氏の逝去により、解散してしまいましたが、本当に素晴らしいバンドでしたね。
今月のレコード Cat Stevens 特集(2022/08/16)
2022年の夏は兎に角暑いですね・・・ここ数年でも最悪の暑さですね。
こう暑いと様々な弊害が出てきますが、私もここ最近全くホームページを更新しておらず、とうとう夏季休暇の掲示も出さずにお盆が明けてしまったのに、本日16日に気づきました!
こんな事では皆様にご迷惑がかかりますので、今後は一生懸命になるべく更新するように心掛けます。
今回のジャケットは前回の猫繋がりで、Cat Stevensを特集してみました。
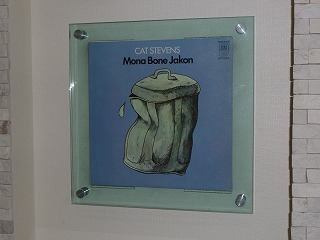

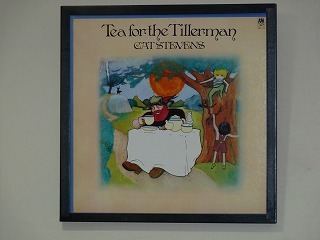
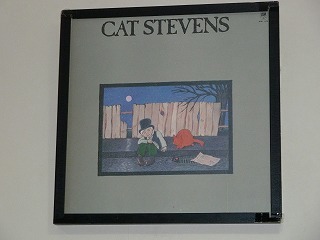
宜しくお願い致します。
猫ジャケット!(2022/02/28)
だんだん春の気配がして参りました。
先日、2月22日は2022年、という事もあり、「スーパー猫の日」でして、猫好きの私としては大変愉しい一日でございました…。
という訳で、先月の虎から猫へソフトチェンジしてみました。
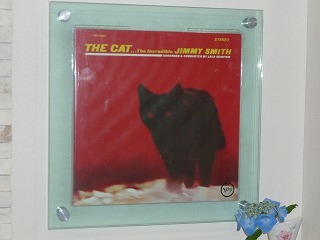

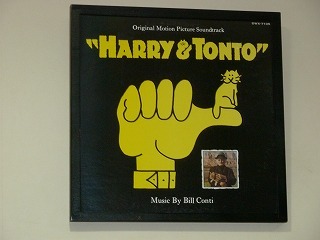


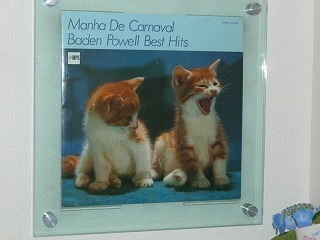

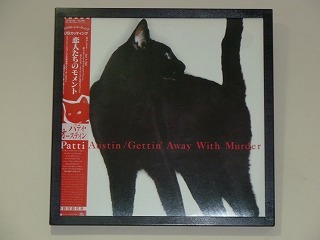
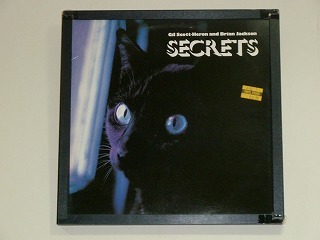

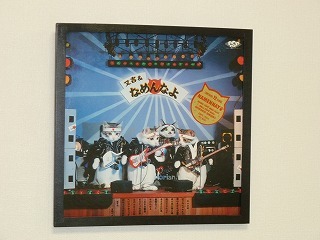

2022年は寅年です。タイガージャケット特集(2022/01/24)
皆様、2022年も宜しくお願い致します。
最近、ほんとにブログを更新できずにおります。
根っからのアナログ人間にはなかなか腰が重い作業なんです・・・。
という訳で、一月も終わりに近づいてやっとのことで更新致します。
毎年一発目は干支の動物ジャケットを飾っておりますが、トラジャケは意外と多いんですねえ…。
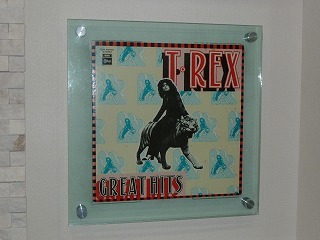

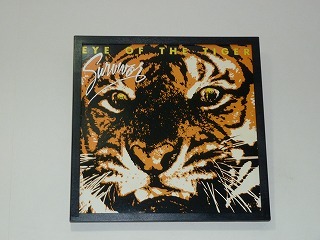
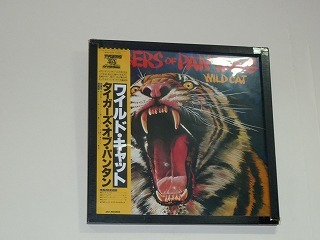
秋らしく…ジョニミッチェル特集(2021/11/01)
暑かった夏も去り、急に秋めいてきました。
実は10月から壁レコはカナダの生んだ才媛、ジョニミッチェル女史を特集していたんですが、例によってなかなかブログに揚げられませんでした。
よって、月を跨いでしまいました事をお詫びします。
九月ですが、サーフィンジャケットで!(2021/09/12)
九月ですが、まだまだ暑くじめじめした日が多いですね。
こんな憂鬱な時は、カラッとサーフィンジャケットでいってみましょう。
先ずはこれなんかどうでしょうか?

ミッキーマウスがビッグウエーブを果敢に攻めているエグイ構図がカッコいいですね!
そしてやはりサーフィンジャケットといえばこれです。

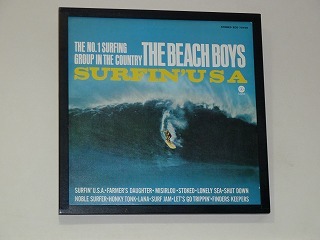
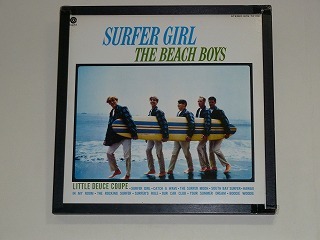

僕の学生時代の1980年代後半位から、やたらペットサウンズが持て囃されるようになり、ビーチボーイズといえばブライアンウィルソンの持つナイーヴなイメージが先行するようになった感がありますが、やはり初期の破天荒ないかにもアメリカ!という感じは素晴らしいものがありますね・・・。
久々の更新です、パロディジャケットは如何?(2021/08/24)
本当に久々の更新となってしまいました.
レコード自体はちょこちょこ変えてはいたのですが、なかなかブログにまで手が回りませんでした。
今回はちょっと趣向を変えて、With the Beatlesのパロディージャケットでいってみます。
先ずはこの2枚で・・・

本家本元の、ビートルズのものです。内容については敢えて言及しませんが、私が一番最初に入手したビートルズのUKオリジナル盤、という事もあり、ものすごく好きなアルバムです。特にA面に針を乗せて数秒間で炸裂する「It's won't be long」のジョンの鯔背なvocalにはいつも失禁させられます。オムツしてから臨んだ方がベターです。
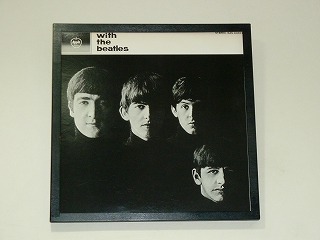
これはジェネシスの12インチ盤ですが、ロゴやフォントなど全てに於いて徹底的にパロってますね~。さすがのセンスです!
敢えて醜悪にデフォルメされたパペットは確か当時のイギリスの人気番組だったような気が・・・。エリザベス女王やチャールズ皇太子もお構いなしにデフォルメされてましたな・・・。(でもダイアナ妃はやらなかったような気が・・・)
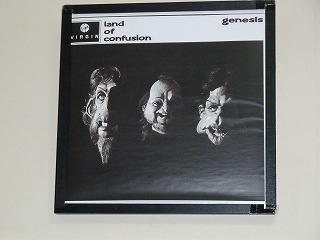
キングクリムゾンのレッドはあまり言及されてませんが、私はこれ、パロってると思うんですがね~。
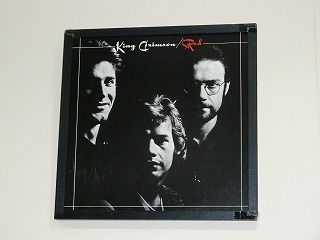
キッスの一作目も、やっぱりパロってますよね・・・。

2021年もよろしくお願いします~丑年という事で、うしジャケット特集(2021/01/11)
2021年も宜しくお願い致します。
なかなか更新できないでおりますが、ジャケット自体は毎月ほぼ変えておりますです。
毎年1月は干支を特集しておりますので、今年は丑年なので牛ジャケットを飾りました。
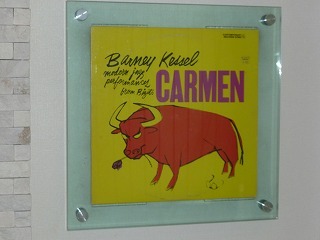

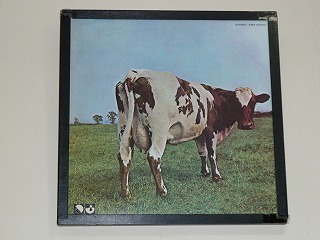
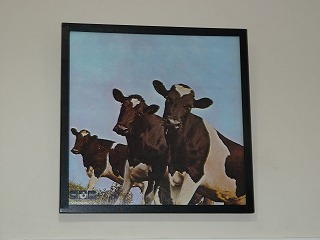
NHKさん有難う、山口百恵特集(2020/10/29)
久々の更新となってしまいました。大変ずぼらで申し訳ございません。
今回は先日NHKで放映された引退コンサートが大評判だった、菩薩、山口百恵さんを特集してみます。
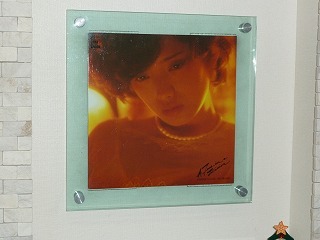

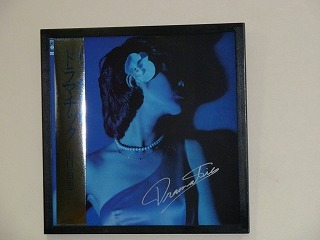

追悼ニールパート氏 ~ RUSH特集(2020/03/31)
ここのところ、本当に更新ペースが落ちており、申し訳ありません。
今回は、惜しくも1月7日にお亡くなりになった、世界一のドラマー(と私は思う)、ニールパート氏を偲んでラッシュを特集します。
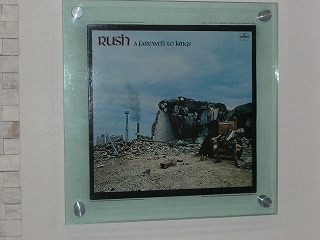

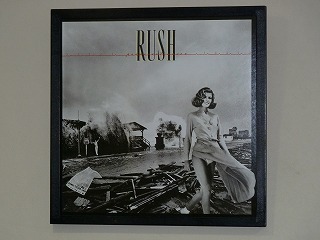
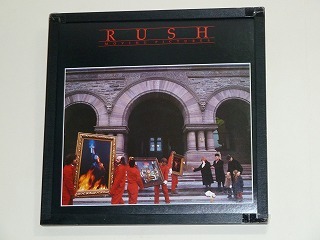
今月の壁レコード ~ 子年という訳でネズミ特集(2020/01/30)
皆様、本年もよろしくお願いいたします。
新年一発目はやはり干支ジャケットで始めさせていただきます。
ネズミさんジャケットです!
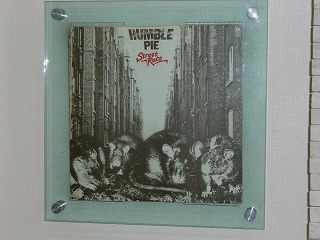

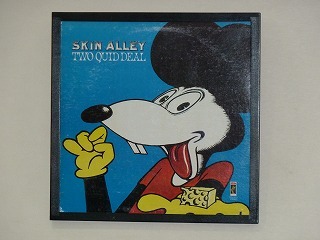
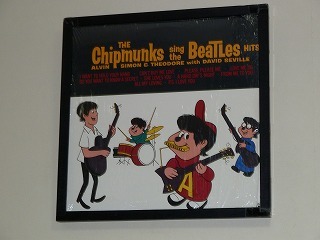
祝デラックスエディション ~ アビーロード特集(2019/11/25)
またまた久々の更新となってしまいました。
今回は充実のデラックスエディションが好評の、ビートルズ大団円、「アビーロード」を特集しました。
やはり、さすがビートルズです。今回は患者さんの食い付きが違いますね~。
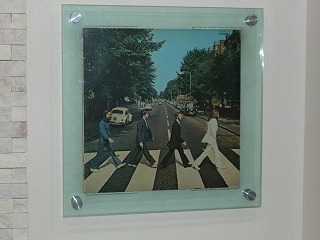

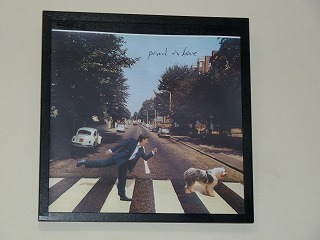
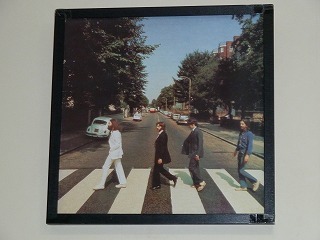
今が旬?久々のエルトンジョン特集(2019/09/03)
大変ご無沙汰です。
とはいっても院内の壁にはちゃんとレコードは飾ってましたよ!
なんか、アナログ人間の私には、ネット関連は苦手なんですよ・・・。
毎日、いや一日に何度もSNS更新される輩みたいに自分大好きっ子ではないですので、しかたありません・・・。
今回は映画も公開された、エルトンジョンを久々に特集してみたいと思います。
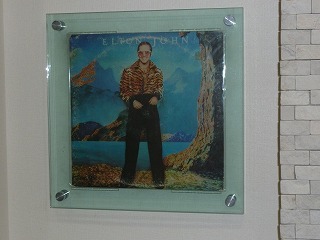

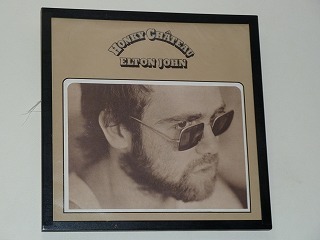
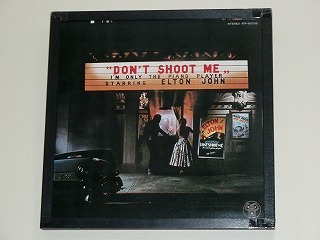
今月の壁レコード ~ プリテンダーズ!(2019/06/30)
久々の更新となってしまいました。
クラプトンがなかなか好評だったこともありますが、なんか最近あまりこれは!と思う企画を思いつかないんですよね・・・。
祝来日!エリッククラプトン特集 ~ 令和にレイラ?(2019/05/05)
今これを書いているのは、既に令和に改元されてからなのですが、当初は違和感バリバリでしたが、慣れてくるとあまり気になりませんね。
やはり、よく考えられた良い元号なのですね。
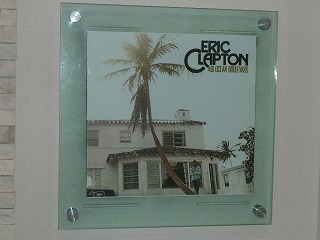

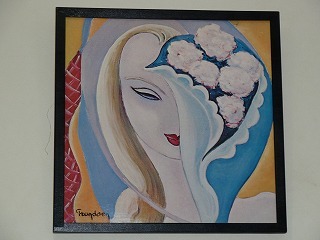
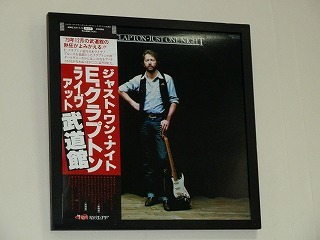
祝来日!リンゴスター特集(2019/03/30)
まだまだ三寒四温といった塩梅ですが、徐々に桜も開花してまいりました。
もうすぐ春ですね~、なんてキャンディーズみたいなフリになってしまいました!
四月は大物の来日が多いみたいですが、今回はこの方を取り上げてみました。
Richard Starkeyリンゴスターさんです!!
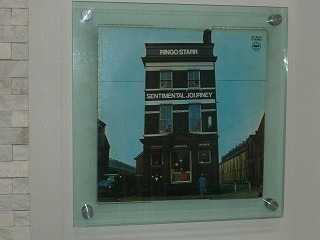


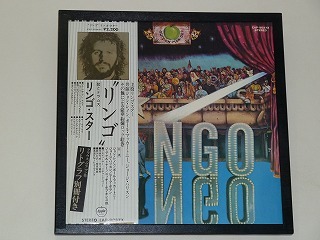
祝来日!イエス特集(2019/03/01)
だんだん春めいてきましたが、花粉の飛散には思いやられます・・・。
さて、今回のジャケットは二月に来日した「イエス」を特集したいと思います。
しかし、ジョンアンダーソンの居ないイエスはやはりイエスではないような気もします・・・。

今月の壁レコード ~ イノシシ?豚さん特集(2019/01/29)
皆様あけましておめでとうございます、と言ってもこれを書いているのは、一月も終わろうか、という時なんですが・・・。
とにかく、今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
今年の干支、イノシシは、あまり西洋では馴染み薄いようで、レコードジャケット探しに苦労しました。
申し訳ありませんが、豚も許容範囲に入れさせてくださいませ。
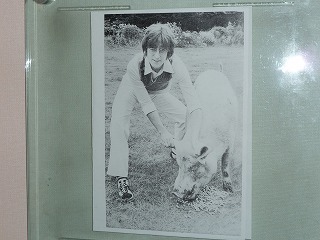

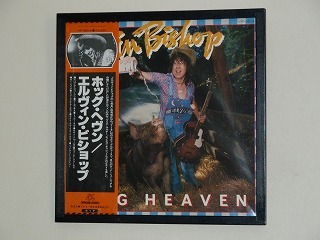
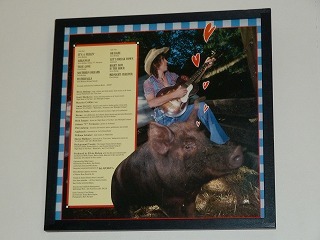
今年もありがとうございました。(2018/12/31)
ご覧になって頂いている皆様、最近殆ど放置状態となっており、申し訳ありません。
院内のジャケットは定期的に交換してはいるんですけどね・・・。
また時間を作って、どーんとアップしたいな、と思っておりますので、どうかたまに覗いてやっては下さいませんでしょうか?
来年はどんな元号になるんでしょうかね?
それでは、良いお年を!!
今が旬?クイーン再特集!(2018/11/30)
だんだん寒くなってまいりました。
さて、何故か大好評のクイーン映画、「ボヘミアンラプソディ」、私も公開2週目の土曜レイトショーを独りでいそいそと観に行きました。
感想はまた後程・・・。
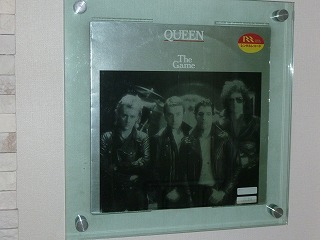

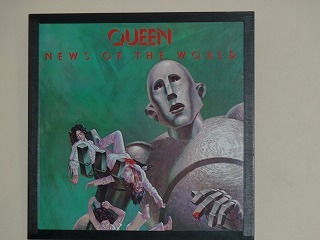
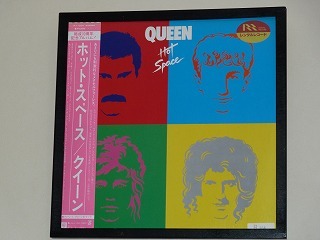
祝来日!ポールマッカートニー特集(2018/10/31)
あんなに暑かったのに、やはり秋は来るんですね、日本は四季のある良い国ですねえ~。
さて、今月の壁レコードは、またまた来日されるポール様に合わせてみました。
アメリカンニューシネマ特集(2018/09/29)
雨ばかりの九月でした。ここは倫敦か?と独りツッコミしてしまう程でしたわ・・・。
さて、前回飾ったミュージカル映画のサウンドトラックジャケットはかなり好評でして、やはり映画は娯楽の王様ですね。
私も学生時代はいっぱしの映画小僧でして、「スクリーン」や「ロードショウ」は勿論、「キネマ旬報」などもカッコつけて読んでいたクチです。
今回は、昔夢中になった映画のなかから、所謂アメリカンニューシネマの傑作をご紹介したいと思います。
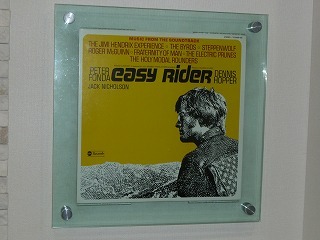

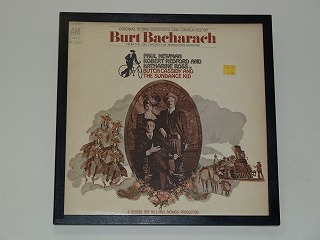
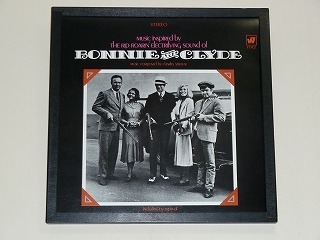
ミュージカル映画特集(2018/08/31)
久しぶりの更新になってしまいました。
八月はお盆休みもあって、何だかあっという間に過ぎてしまった感があります。
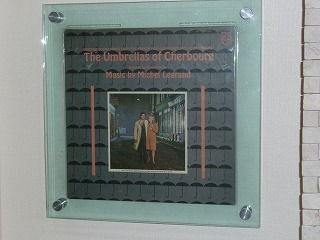

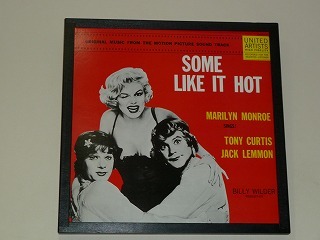
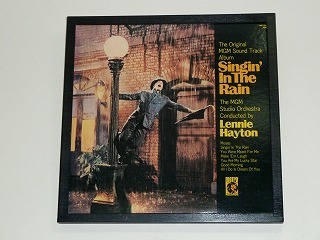
今月の壁レコード ~ 半分青い?侍ジャパン?ブルー特集(2018/06/29)
梅雨のせいで、湿気に悩まされる今日この頃です。
さて、NHK朝ドラ、「半分青い」、最近は減ってきましたが、岐阜弁が出てくるとドキッとしてしまいます。三河弁とちっと似とるんだわね。
あの松雪泰子さんが、「あんた、何言っとるう!」なんて言った日には胸がキュン!としてしまいます。
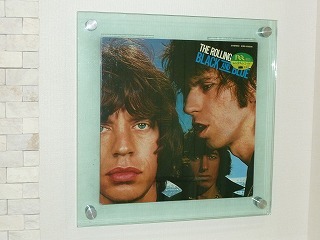

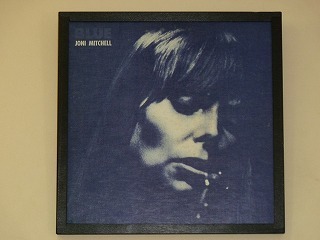
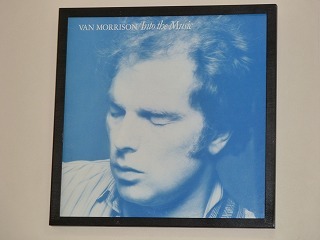
今月の壁レコード ~ オードリーヘップバーン特集(2018/05/30)
梅雨は湿気が嫌いな私にとって地獄の日々です。
何でこうジメジメしてんですかね~。
さて、こないだ出入りの画商さんが、院内掲示の絵の交換に来てくださいました。(レンタルなんです)
割と私の好みを覚えててくださって、なかなか良いものを持ってきて頂けるんです・・・。
今回は、一番大きい絵として、オードリーヘップバーンさんの恐らく「ティファニーで朝食を」でのシーンを描いた、洒落た絵を持ってきて頂きました。
確か中国系の作家さんの作品だそうです。確かにやや東洋調のヘップバーンさんです・・・。
という訳で、今回はヘップバーンさんが主演した名作のサウンドトラックレコードを、ビジュアル的に選んでみました。
私は彼女の魅力は大作とか、超人気俳優とのお相手、という有名な作品よりも、「いつも二人で」みたいな、小品の方がパーソナリティに合っているように思います・・・。
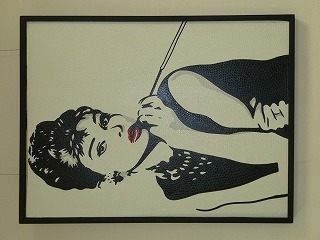
今月の壁レコード ~ 猫ジャケット特集!(2018/04/28)
久々の更新となってしまいました。
最近、時の過ぎるのがやけに早くて、気付いたらこんなに間隔が空いてしまいました・・・。
Time Flies・・・
さて、犬ジャケットが続いたものですから、世間の皆さんは私が犬派だと思ってらっしゃるんじゃないでしょうか?
勿論、犬も好きですが、どちらかと言えば、私は猫派なんですね・・・。
実際、家では2匹飼っております。名前は「ちびた」と「クロちゃん」です。
では、今回は猫ジャケットでいってみます。
猫はジャケット映えがするのか、犬よりも登場する回数が多いような気がします。
なんせ、猫の登場するジャケットだけ集めた本が、第二集も出版されてる位ですので・・・。
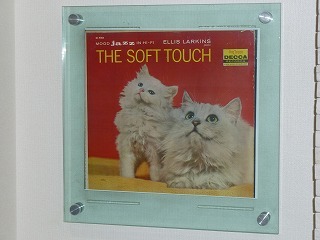

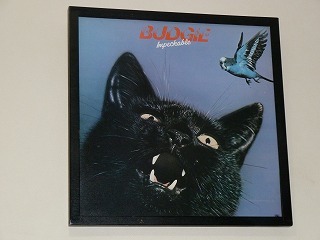
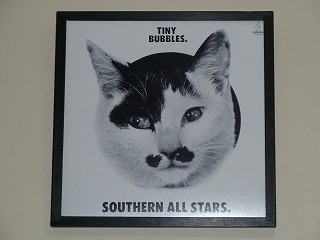
今月の壁レコード ~ 犬特集 その2(2018/02/28)
なかなか更新できなくて申し訳ありません・・・。
つい、オリンピックに夢中になっていたので・・・・・。
しかし、羽生選手は異次元の人ですよね、あの状況で2連覇ですか・・・。
皆さん言われてますが、ひょっとしたらどこか違う星(惑星ヴェガかなんか)から来た方なんでは・・・。
また、カーリング女子も脚光を浴びましたね、「モグモグタイム」や「そだねー」など、流行語を生みました。
やはり、ルックスがいいとマスコミは食いつきますね~。でも、実力も伴っていたからこそ、なんでしょうが・・・。
さて、今回も干支に因んで、犬ジャケット、その2をお送りします。


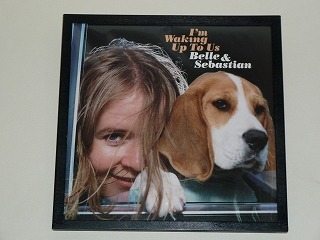

今月の壁レコード ~ 戌年にちなんで犬特集(2018/01/30)
すっかりご無沙汰してしまいました。
皆様、今年も宜しくお願い申し上げます。
ここのところ、なんだかんだで忙しく、ブログの更新が滞っております。
やはり歳なんでしょうか?私も今年で50歳になります。
さて、一月は恒例の干支シリーズなので、今年は戌年なので、犬ジャケットで特集してみました。
犬はやはり身近な存在ですので、沢山ありまして、選ぶのに一苦労しました・・・。
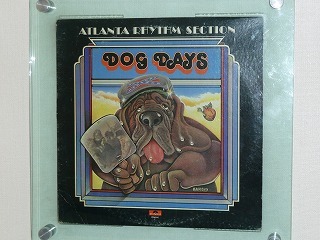

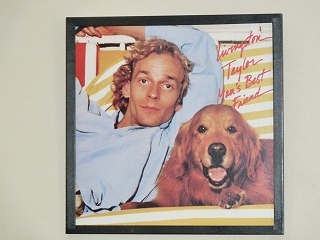
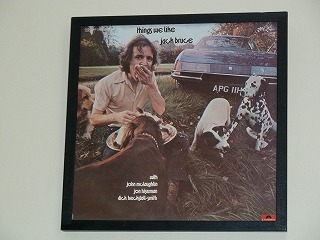
今月の壁レコード ~ ケイトブッシュ特集(2017/11/30)
とうとう年度末も近づいてまいりました。
なんだか、年を取るたびに時間の経過が早く感じられます。
ついこないだまで暑い暑い、と言ってたような気がするんですが、もう明日で師走なんですねえ・・・。
さて、今回の壁レコードは、大英帝国の歌姫、ケイトブッシュを特集してみます。
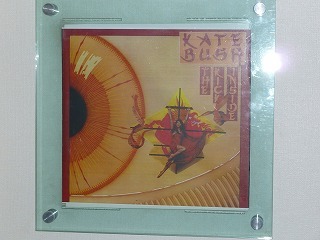


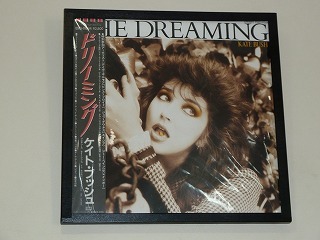
今月の壁レコード ~ 追悼トムペティ特集(2017/10/29)
もう秋なんですが、今年はホント、雨が多くて嫌になってしまいますね・・・。
今月のトップニュースは、何と言っても、トムペティ氏の突然の死去でしたね・・・。
10月3日、その日の白内障手術執刀を終えて、遅めの昼食を摂りながら何気なしにテレビを見てたら、「アメリカの歌手、トムペティさんが亡くなりました。」
と、唐突に女子アナが言ったんです。
私は驚いて口にしていた御飯をまき散らしてしまいました・・・。
多分、80年代ならともかく、現代の日本でトムペティの訃報を聞いて驚愕する方はそう多くはないでしょう・・・。
1986年にボブディランと組んで来日したなんて言っても、ピンと来ない方が多いんじゃないでしょうか?
(しかし、あのライブは女房を質に入れてでも?行っておけば良かったなあ・・・。当時高校生でしたが・・・・)
彼はLA周辺のクラブサーキットで注目され始めたようですが、もともとの出身はフロリダ州ゲインズビル市でして、私が留学していたフロリダ大学のある町なんです。
という訳で、非常にシンパシーを(勝手に)寄せていたミュージシャンだったのです・・・。
先ずは玄関先です。
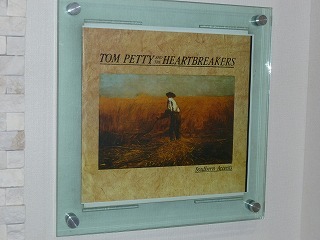
そして待合壁です。

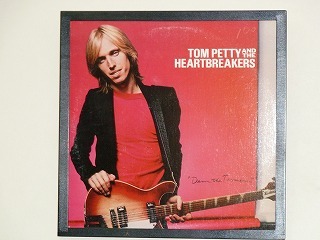
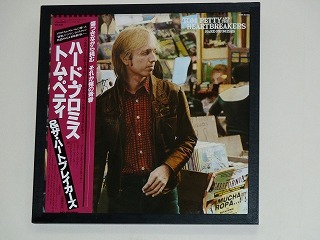

残念無念!ドナルドフェイゲン来日中止&ウォルターベッカー死去(2017/09/29)
朝晩はかなり涼しくなってきた今日この頃です。
一年で最も過ごしやすい季節ですよね~。
さて、先月のブログで、「祝来日!」なんて調子に乗ってましたが、盟友、Walter Beckerが亡くなった事のショックなのか・・・
Donald Fagenの来日が中止となってしまいました・・・・。残念ですが、仕方ありませんね・・・。
今月も、ベッカーさん追悼の意味で、Steely Danを特集します。
先月ではフェイゲンとベッカーの職人ユニットになってからのダン、即ち「エイジャ」以降の、洗練されたアルバムをご紹介しました。
今回は、まだまだロックバンド然としていた頃のダンを特集します。
先ずは玄関先です。
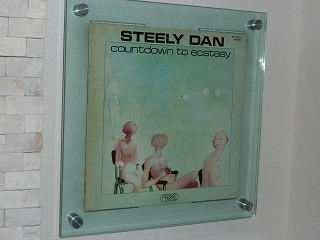
続いて待合壁です。

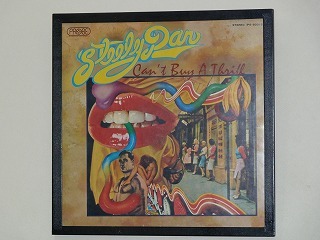
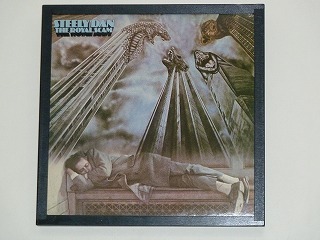

今月の壁レコード ~ 祝来日!ドナルドフェイゲン特集(2017/08/28)
残暑厳しい中、皆様如何お過ごしでしょうか?
さて、先月のサージェントペパーズは思いのほか好評でして、なかなか交換するタイミングが図れませんでして、こんな遅い更新となってしまいました。
大変申し訳ございません。
今回は、9月に久々に来日する、ドナルドフェイゲン~スティーリーダンの諸作を特集してみます。
先ずは玄関先なんですが、やはりSteely Dan の最高傑作、「Aja」でいきましょう。
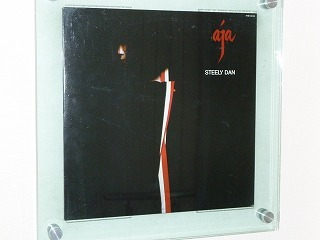
お次は、待合壁です。

1980年発表の、個人的には一番良く聴く、これです・・・。
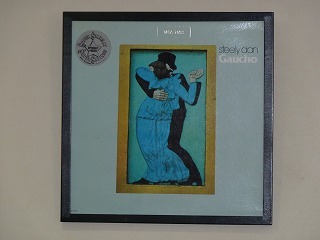
そしてそして・・・・フェイゲン自身の最高傑作、「ナイトフライ」です。
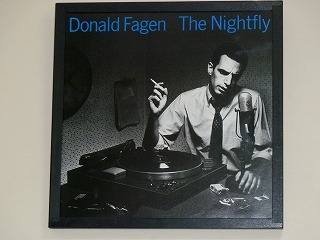
今月の壁レコード ~ ひよっこ効果?サージェントペパーズ特集!(2017/07/11)
蒸し暑い日が続いております。一年で最もキツイ季節です・・・。
加えて当院の前後2か所で、大規模な解体、改修工事が毎日延々行われており、騒音で不快感この上ない毎日です・・・。
早く終わって欲しい・・・切に願います。
さて、今回はNHK連続ドラマ「ひよっこ」で、大騒ぎになっているビートルズ来日騒動に触発された事もあり、最近リマスター化された、評価の高いこのアルバムを特集します!
「Sergent Peppers lonely hearts club band」です!
しかし、天下のNHKで、「ムネオさん」みたいなハチャメチャなキャラが暴れまわるのは、見てて痛快ですね。
ムネオさん、武道館の中にいかせてあげたかった・・・・。
先ずは玄関先です、と行きたいのですが、事情で今回は一番最後に・・・・・・。
最初は待合壁からまいりましょう・・・・。

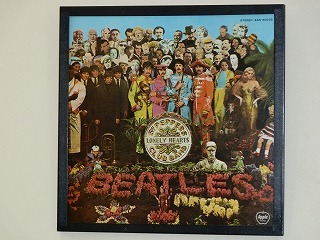
ビートルズ中期の代表作、「サージェントペパーズロンリーハーツクラブバンド」でございます。
内容はちと過大評価されてるんじゃ?と思いますが、ジャケットは一大芸術作品!彼らのジャケットアートワークの中ではダントツに素晴らしいと思います。
それまで、こんなにジャケット制作に金と時間と(権利関係をクリアにする)手間暇をかけたレコードは無かったと思いますし、ひょっとしたら今に至るまで、唯一無二なんではないでしょうか??
という訳で、古今東西様々なパロディジャケットが発表されました・・・。
中でも、最も有名なのが、ライバル?バンド、ローリングストーンズのこれまた最近デラックス版が発売された、これです・・・。
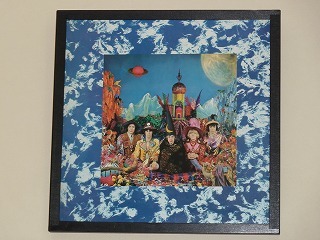
確かに、ジャケットは真似てはいますが、スケールが小さすぎますね・・・。まあ、オリジナル盤は3D写真を使って、角度により表情が違って見える、というのはアイディアですが・・・・・。
そして、一番の問題作が、フランクザッパ&マザーズのこれでしょうな・・・・。
玄関先に飾ったこれです・・・。
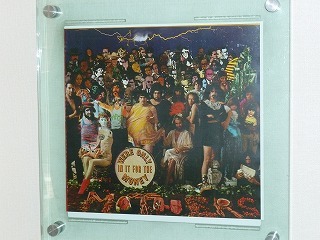
これは、カラーコピーなんです。勿論、アメリカヴァ―ヴのオリジナル盤は持ってるんですが、これ、あまりの写真のハチャメチャさに恐れをなしたヴァ―ヴ側(多分クリードテイラー?)が表と裏の見開きをチェンジしてしまったんです。
そういう訳で、通常の表ジャケットが、ビートルズ版では内側にデザインされてる、「鮮やかな黄色をバックにしたLSD?でイッチャッてる4人のお顔」のパロディである、うす汚いマザーズの面々なんですよ・・・・。
今月の壁レコード ~ 追悼グレッグオールマン特集(2017/06/26)
梅雨入り、という年間で最も憂鬱な時期になってまいりました。
雨はお出掛けする時は最悪ですが、夜寝ている時にしとどに屋根を叩きつけている雨音はいとをかし・・・ですね。
さて、今月は惜しくも5月28日に亡くなった、グレッグオールマンを特集してみました。
ここで皆様にお詫びです。
本来なら、グレッグオールマン特集として、玄関先には「イートアピーチ」、待合には「レイドバック」と、「嵐」を飾るつもりでした・・・。
しかし、どこかにいってしまったのか、レコードが見当たらないんです・・・。確かにどこかにあるはずなんですが・・・。
そういう訳で、グレッグさんの追悼は、もう少し先にさせて頂きます。
今月の壁レコード ~ 追悼Jガイルズバンド特集(2017/05/29)
五月なのに、かなり暑い日が続いております・・・。こんな時期にこんなに暑くては夏になったらどうなっちゃうのか・・・・。
さて、今月は先日亡くなった、いぶし銀のギタリスト、J Geils氏を偲んで渋いアメリカンバンド、J Geils Bandを特集してみます。
J.ガイルズ、と言っても果たしてどの位の方がご存知なのか、見当もつきませんが、訃報が中日新聞に出たのにはちょっとビックリしました。
恐らく、アメリカのメディアがかなり大きく取り上げていたことに関連してるんでしょうね・・・・。
それ位、アメリカでは人気あったバンドでした。
日本では、あの「堕ちた天使~Centerfold」の大ヒットで知られた訳して、大抵の洋楽好きの脳裏に刻まれているあのフレーズですが、その他の曲まで知っている方にはあまりお目にかかりません・・・・。
アルバムを遡って聴いていくと、あの曲はキーボードのセスジャストマンの嗜好性でして、バンドとしては不本意なヒットだった、という事が良くわかります・・・・。
何しろ彼らはそんじょそこらの黒人バンドが裸足で逃げ出す程「真っ黒い」ブルース/R&Bバンドだったのですから・・・・。
先ずは玄関先です。
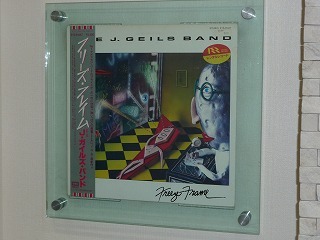

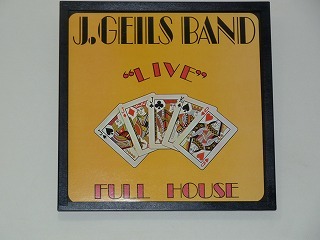
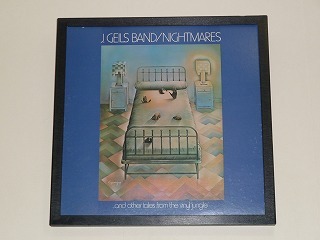
今月の壁レコード ~ 祝来日!Doobie Brothers特集(2017/04/24)
寒かった今年の冬もやっと終わり、春らしくなってまいりました。
皆様、如何お過ごしでしょうか?
今回は、久々の来日目前の、アメリカンロックの雄、ドゥービーブラザーズを特集してみます。
よく、トムジョンストン色の強い、豪快ないかにもアメリカン!といったスカッとしたイメージの前期、
途中加入のマイケルマクドナルド色の強い、洗練されたAORっぽい後期、と括られてますね・・・。
ただ、現在はトムジョンストンが復帰してからの再結成期の方が、数え年数的には一番長くなっちゃいまして、
何となく「懐メロ」バンド臭くなってしまっているのは残念です。
先ずは玄関先です。
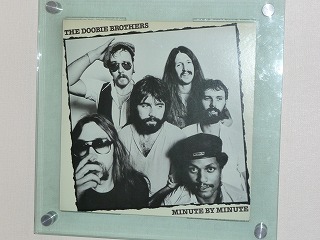

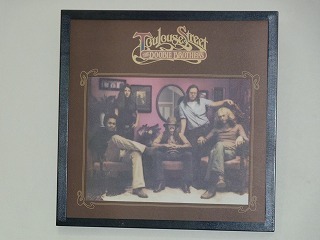
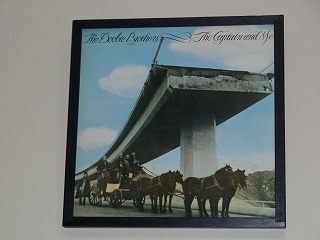
今月の壁レコード ~ 来日大盛況!!ジャーニー特集 その2(2017/03/23)
すっかり春めいてまいりました今日この頃です。
私も多くの皆様と同じように、花粉症で苦しい毎日です。
ある程度はお薬が効きますが、やはり完全に症状を止める事は難しいですね。
さて、今月の壁レコードですが、先月好評だった、Kelly/Mouse画伯のスペーシーなイラストで迫ってみました。
この二人のイラストレイターは、サンフランシスコやバークリーといった、所謂ベイエリアを中心に活動していたアーティストでして、ジャーニーの一連の作品の他にも、これまたシスコの大御所バンド、グレイトフルデッドのジャケットなんかも描いております。
今回は、前回より遡って、まだグレッグローリーが幅をきかせている時代の3枚をご紹介します。
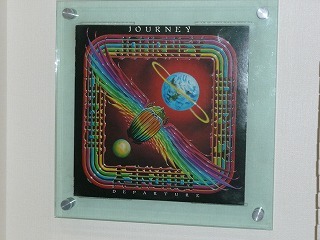

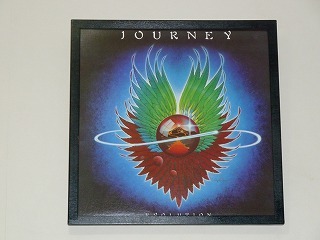
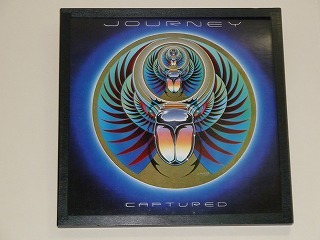
今月の壁レコード ~ 祝来日!ジャーニー特集(2017/02/20)
皆様如何お過ごしでしょうか?
遅々として進まないこのブログですが、医院の壁ジャケットはしっかり更新していますので、ご安心を・・・。
さて、今月は大好評のうちにジャパンツアーを終えた、アメリカンハードロックの雄、ジャーニーを特集してみました!
私がロックを本腰入れて聴き始めた1981年頃は、アメリカンハードロックの全盛期でして、TOTO、フォリナー、スティクス、カンサス、REOスピードワゴン・・・などなどカッコいいバンドが沢山がんばっていました。
中でも、最も成功したのはジャーニーではないでしょうか?
特に、若干サンタナの影を引きずっていたグレッグローリーが脱退し、ポップな側面を持ったジョナサンケインが加入した後は、最高傑作、「エスケイプ」で名実ともにナンバー1アメリカンロックバンドの地位を固めました。
エスケイプは当時、他のクラスの音楽通の八木君にレコードを貸してもらって、奮発してTDKのOD46にダビングして、テープがワカメになるまで聴きまくりましたね・・・・。
まずは玄関先です。
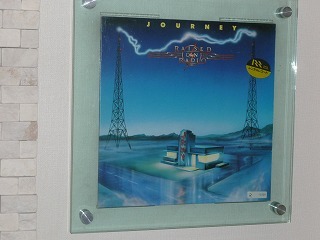

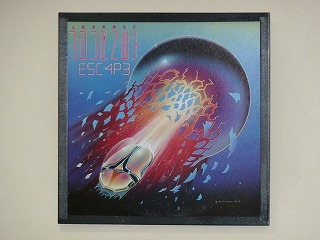
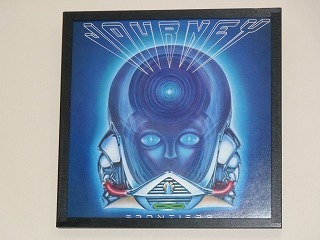
今年も宜しくお願い申し上げます ~ にわとりジャケット特集!(2017/01/23)
平成29年 今年も宜しくお願い申し上げます!!
今年は酉年、という事で恒例の干支ジャケット特集は、勿論にわとりで行ってみたいと思います。
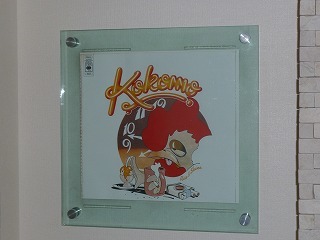

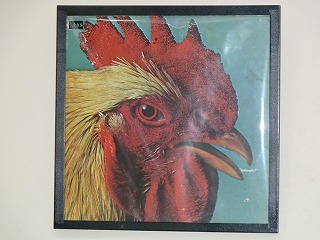
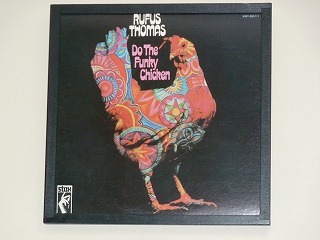
今年もありがとうございました(2016/12/30)
寒い日々が続いておりますが、皆様、如何お過ごしでしょうか?
ここ最近、多忙にてブログ更新もままならず、(少数の)楽しみにして頂いていらっしゃる皆様に申し訳なく思っています。
今年も一年間、有難うございました。
来年も宜しくお願い申し上げます。
今月の壁レコード ~ 癒しのグッドミュージック!キャロルキング特集(2016/11/22)
秋本番、11月は個人的にも大好きな月で、過ごしやすい毎日を送らせて頂いています。
毎年言ってますが、この季節だからこそ、より良く心に染みてくる音楽ってありますよね!
要は、ハートウォーミングな、暖かい、ホロリと来る、グッドミュージックの事なんです・・・。
今月はその第一人者?素晴らしいソングライターであり、ワン&オンリーな暖かい歌声の持ち主、キャロルキングさんを特集しました。
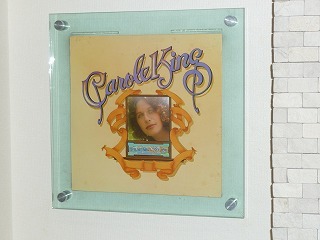

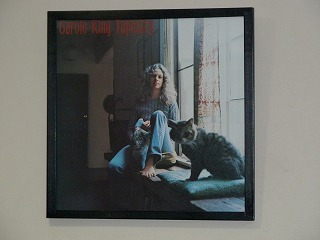
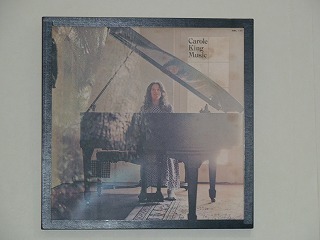
今月の壁レコード ~ 祝来日!!Queen特集 その1(2016/10/20)
いよいよ秋らしくなってきた今日この頃、皆様如何お過ごしでしょうか?
今回は予想外?の好評だった、クイーン+アダムランバートの来日を祝して、クイーンを特集してみました。
前回の来日は、何とポールロジャースをヴォーカルに据えた驚きの形態でしたが、名古屋ドームにも来てくれたので、いそいそと観に行き、大変感動させて頂きました。
意外とロジャースのクイーンナンバーも味があり、楽しめました。
今回は、残念ながら名古屋はすっ飛ばされました(いわゆる名古屋とばし!)ので、行けませんでした。
悔しいので、「ふん、何じゃ、アダムなんちゃらなんて・・・どうせ海賊みたいな衣装着て調子こいてるんやろ・・・(アダム違いですう・・・・)」と、まさにイソップの「すっぱい葡萄」理念で、自分を慰めていました・・・。
恐る恐るネットで情報入手すると、結構好評だったようで、臍をかむ思いをしました・・・。やはり、無理してでも行けばよかったなあ・・・・・。
という訳で、今回はクイーンの特集をしてみます。キャリアのあるバンドですので、第1回として初期~中期の3枚を選んでみました。
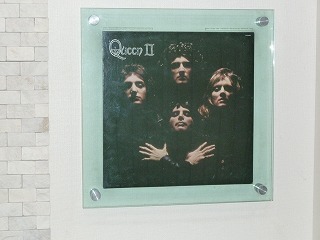

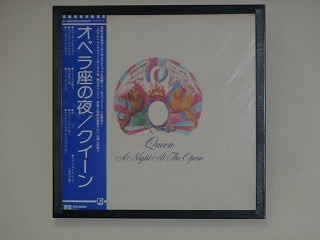
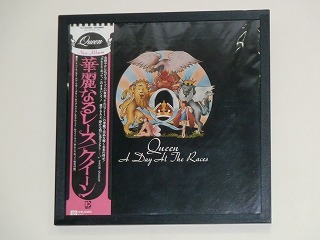
今月の壁レコード ~ 五輪良かったですね・・・金銀銅ジャケット特集(2016/09/27)
やっと、秋らしくなってきたか?と思いきや、例年になく台風野郎が大挙押し寄せ、雨ばかりの9月ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
ちと時期を逸した感がありますが、リオオリンピック、良かったですよね~!
普段野球とテニス以外のスポーツはあまり見ないのですが、やはりどんな競技でも、一流の方々は凡人の目を引き付けてしまうだけのパワーをお持ちですね。
という訳で、今回のジャケットは、金、銀、銅、をイメージして選んでみました。
まずは黄金ジャケットといえば、これです。
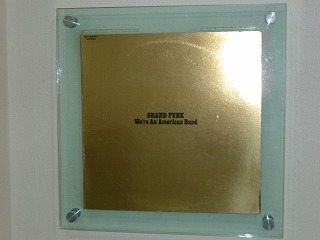
Grand Funkの1973年リリースの「we're an American Band」です。
驚異の暴走機関車、であったグループ名、Grand Funk Railroadから、もう俺たちゃ線路なんか要らないんだぜ!ってな感じで、レイルロードを外し、当時プロデューサーとしても名を挙げていた、トッドラングレンと創り上げた最高傑作です。
キャピトルさん、かなり金をかけていたんですね・・・。初回ジャケットは何とキンキラキンのピッカピカ!おまけにレコード盤も流石に金ではないが、濃いイエローワックスで、カスタムレーヴェル、といった大判振る舞いでした。
それにならい、国内盤もビートルズで大儲けした?東芝さんだった事も幸いしてか、同じような仕様に加え、日本独自の重厚なブックレット、ジャンボポスター、ステッカー・・・とこれまた豪華なものでした。
もちろん、ファーストプレスのみですが、当時良く売れたようで、中古市場にはよく出てきます。しかも、バーゲンコーナーに・・・・・・。
私は中2の時に、当時栄にしか無かった、バナナレコードさんで再発の安いやつを買ったんですが、すんごく気に入り、良く聴いたものです。
ブックレットの小林克也さんのライナーが妙に好きで、流石スネークマン、文章も洒脱だわい・・・と感心しながらむさぼり読んでいたものです。メルサッチャーのベースの事を、「ゴンゲン様!」と呼ぶ件は最高です!!
表題曲は、マークファーナーではなく、ドラムのドンブリューワーのペンに依るもので、彼のドスの効いたダミ声がいい味を出しており、堂々全米ナンバーワンになりましたね。
私はこの曲をどうしても演りたくて、大学の軽音楽部の仲間にお願いして、西日本医学音楽祭のステージで採り上げさせて頂きました・・・。イントロのカウベルのフレーズは今でも叩けます・・・・。
お次は銀と銅です!

図らずもまたGFRになってしまいましたが、銀メダルといったらこれしかありません!!
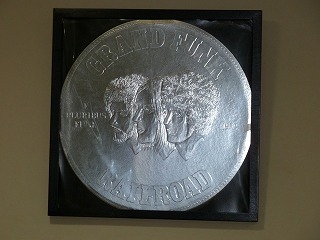
これもかなり予算が必要なジャケットですが、当時全米で最も客を呼べるバンド、だった彼等のアルバムだから、キャピトルさんとしても、「お好きなように.....」ってな感じだったんでしょうね・・・・。
そして、銅ですが、これは悩みに悩みました・・・・。
どうせなら同じGFRで揃えたかったんですが、やはり無理があり、思いつきませんでした・・・・。
そもそも「銅」をモチーフとしたジャケットがないんです・・・。という訳で「銅像」ならいいんじゃ?と思って選んだのがこれです・・・・。
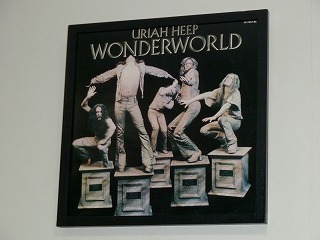
ユーライアヒープの1974年発表の「Wonderworld」です。邦題は「夢幻劇」で、こちらの方が秀逸ですかね・・・。
今月の壁レコード ~ ロバートパーマー特集(2016/08/28)
残暑お見舞い申し上げます・・・・・。
台風の影響で、蒸し暑さも加わり、尋常でない暑さと不快感です・・・。
今年の暑さには、東南アジアの方も驚くそうですね・・・・。
さて、今月のレコードですが、2か月続いたリトルフィート繋がりですが、今回もフィートと関連が深い、ソウルフルな渋いシンガー、ロバートパーマーでいってみます。
先ずは玄関先です。
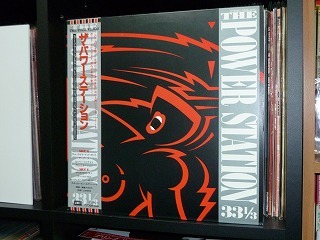
ちょっと禁じ手ですが、私が彼を知るきっかけになったアルバム、1985年に発売された、「Power Station」です。
これは、当時飛ぶ鳥を落とす勢いだった、Duran DuranのベースのJohn Taylor とギターのAndy Taylorが、もっとワイルドでファンキーな演奏をしたくなり、シックの面々の力を借りて結成したプロジェクトでして、ヴォーカルの白羽の矢が立ったのが、Robert Palmerでした。
当時高校生だった私は、まだまだ未熟でして、パーマー氏の事は全く知りませんでしたが、張りのある渋い声にノックダウンされましたねえ。
演奏も、シックのトニートンプソンのドカドカドラム、巧いとは思ってたが、ここまでとは・・・・と皆が驚いた、ジョンとアンディのデュラン組の繰り出すパワフルでファンキーなサウンドも最高でした。
今でもアイフォンに入れていて、良く聴きますが、B面の頭から3曲の流れは最高ですね。
T.Rexの「Get it on」、ジョンテイラーのチョッパーベースがスリリングな、「Go to Zero」、パーマーとアンディが代わる代わるリードヴォーカルを執る、Isley Brothersの名曲、「Harvest for the world」は、あまりのカッコよさに失禁しそうになります・・・。
この後、パーマーは自身の活動が忙しくなったので、ツアーには、何と元シルヴァーヘッド(これまた渋いバンドですが)のマイケルデバレスが参加してましたね。あのライヴエイドにもこの布陣で出演してました!
確かにデバレスもカッコいいんですが、やはりパーマーと較べると分が悪い・・・・。
それからは、ジョンとアンディ達が本家の活動の為、バンドも自然消滅・・・だったのですが、何と1996年頃に2作目を発表しました。
私は当時アメリカに留学中でして、ひょんな事から、彼らのライヴを確かフロリダのオーランドで観ています。
布陣は確かジョンテイラー以外のオリジナルメンバーでして、パーマーさんも結構ま近で観た覚えがあります。
やはりアンディテイラーのギターは良かったなあ・・・・・。
さて、ロバートパーマーのソロアルバムに入ります。

待合壁の2枚ですが、先ずはフィートやアラントウーサン組が大挙参加した名盤です。

1974年発表のファーストソロ、「Sneakin' Sally through the alley」です。
このジャケットの意図がよくわからないんですが、パーマーさんが連れている女性がサリーさんなんでしょうか?
内容はとにかく粋で、A面の3連発は最高です!A面ド頭であのフィートの「sailin' shoes」を演ってるんですが、ローウェルジョージが進言したんでしょうね。
この後、パーマーさんはほぼ毎年一枚新作を発表していくんですが、ジャケットのコンセプトはちょい悪オヤジと女たち・・・てな感じでしょうか?ちと下世話なんですよねえ・・・・。
1978年発表のこれも、そんなジャケットで楽しませてくれます。
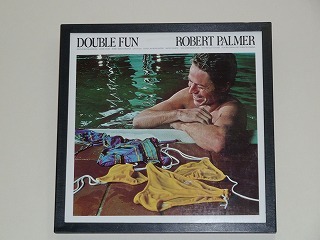
4枚目のソロアルバム、「Double Fun」です。
このアルバムからは、冒頭の「Every kinda people」が全米16位のヒットとなりました。夏に聴くと気持ちいい曲調ですが、これ、作曲はあのフリーのアンディフレーザーなんですね!
ポールロジャース、サイモンカーク達はバッドカンパニーで大成功しましたし、ポールコゾフは悲劇のギタリスト、として称えられているのに比べ、アンディフレーザーはその貢献度に反し、あまりにも過小評価されていると思います。
あの独特のベースが無ければ、フリーがあんなに評価される事は無かったのではないでしょうか・・・・・。
いつかフリーについても書いてみたいです・・・・・・
今月の壁レコード ~ ネオンパーク特集(2016/07/26)
いやあ、暑いですねえ・・・。
寒いのも嫌ですが、暑苦しいのはもっと堪えますよね・・・。
寒ければ、服を重ね着すれば何とかなりますが、暑いのは裸になるしかありませんから・・・。
さて、先月のリトルフィート特集はかなりのインパクトがあったようでして、多くの方から問い合わせ?がありました。
中でも凄かったのは、「せんせー、ネオンパークの絵がお好きなんですか?」と声をかけてくださった女性の方でした。
いやあ、リトルフィートをご存知だけでも稀有なのに、ネオンパークの事までご存知とは・・・。
「今度はあのザッパのやつもお願いします!」なんて言われてしまいました・・・。
という訳で、今回もネオンパーク画伯の素晴らしい傑作イラストを飾ってみました。
先ずは玄関先です。
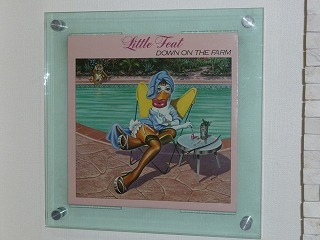
1979年に発表された、ローウェルの居た、オリジナルフィートとしてのラストスタジオアルバム、「Down on the farm」です。
ネオンパークお気に入りの、妖艶なアヒル(ガチョウ?)がプールサイドで寛いでいます。実にいかしたイラストですよね。
私は再結成フィートは一応聴きましたが、やはりローウェルの居ないフィートは認めたくない、というか、別物のバンドとしか思えないんですよね・・・。
確かに、演奏面では、ポールバレールとビルペインがいれば、何となくフィートの香りはしますが、やはりローウェルのヴォーカルがなくちゃねえ・・・・・。
このアルバムがアメリカで出た時は、既にローウェルは脱退した後で、遅れて発売された日本盤の帯には、「ローウェルジョージ追悼」の文字が見られますから、本当に「急死」だったんでしょうね・・・・。
もともと最後のアルバムにするつもりは無かったのでしょうから、内容も割と散漫でして、評論家サン達の評価も芳しくありません・・・・・。
けれど、個人的にはローウェルのヴォーカルがたっぷり堪能できることから、昔からの愛聴盤であります!
A面トップの表題曲は、ポールパレールのペンになるものでして、当然彼がヴォーカルを執っています。彼はこのフレーズ「Down on the farm」が好きみたいで、前作、「Time loves a hero」のB面一曲目の「Old folks boogie」でも、そのフレーズが聞かれます。
最初の、カギを開けて農場に入っていく描写でカエルに怒っているのは、ポールなんでしょうか??
さて、A面2曲目の「6 feet of snow」からB面2曲目の「Second hand news」までは、フィートらしい粘り気のある演奏は聴けませんが、ローウェルの素晴らしい歌唱が目白押しです!
特にA面最後の「Be one now」は、ローウェルのその後の運命を知っているだけに、涙なしには聴けません・・・・・。
このアルバムがもうちょっと評価される事を切に願います・・・・。
続いて待合の2枚です。

先ずは、フィート脱退後にすかざす発表された、ローウェルジョージのソロアルバム、「Thanks, I'll eat it here」邦題は、「特別料理」!!
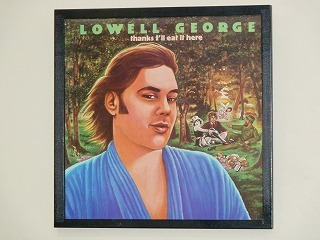
東洋風に描かれた、一見お相撲さん!?風の貫録たっぷりのローウェルの後ろには、マネの「草上の昼食」のパロディが見られます。描かれているのは、キューバのカストロ、ボブディラン、映画「嘆きの天使」でのマレーネディードリッヒ!!という何の脈絡もない3人ですが、ネオン画伯はどんな意図があったんでしょうか?
このアルバムも、やはり世間的な評価は低いのですが、冒頭の昨年惜しくも亡くなったアラントウーサン作の「あの娘に何をさせたいの」を始めとした、ローウェルのヴォーカルを前面に出した内容が結構好きで、良く聴いたものです・・・・。
そして、ちょっとクレイジーな、このジャケットです。
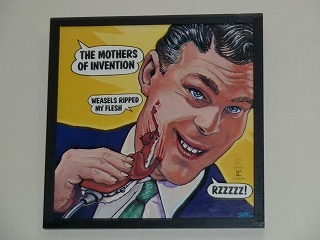
ローウェルが昔お世話になった、フランクザッパ御大が1970年に発表した「Weasels ripped my flesh」です。邦題は大ヒット!「いたち野郎」です!
ネオンパークは恐らく、ザッパから詳しく指示されてこんなイカレタ絵を描いたんでしょう・・・・・。あまりにも変態じみています。ザッパなら納得ですが、(これ位可愛いもんです・・・)粋なネオンパーク画伯が自分からこんなの描くとは思えません・・・・。
しかし、邦題の「いたち野郎」も、秀逸です。ザフーの「ボリスのくも野郎」といい勝負ですよね・・・。
内容は・・・・・実はあまり聴きこんでないいんです・・・・すみません。後に息子のドゥイージルが「My guitar wants to kill your mama」をカッコよくカバーしてましたね・・・・・。
ザッパは大学時代かなり入れ込んでたんですが、ロック色を増した1973年の「Overnight Sensation」から後ばかりで、それ以前は「Hot Rats」以外は苦手なんです・・・・・。軟弱で申し訳ありません・・・・・。
今月の壁レコード ~ Little Feet特集(2016/06/27)
6月は梅雨!という訳で、毎日湿気との戦いであります。
暑いなら暑いでもいいですが、ジメジメした日本の梅雨時はうんざりですね。
という訳で、今回はカラッとしたアメリカンロックを、と思ったのですが、何となく粘り気のあるリトルフィートにしてみました。
たまたま、ネットで今回取り上げている、「ウエイティングフォーコロンブス」のジャケットの考察がされているサイトを読みまして、ピンときたんです。
あと、前々から、ネオンパークのイラストは飾ってみたかったんですよね。
先ずは玄関先です。
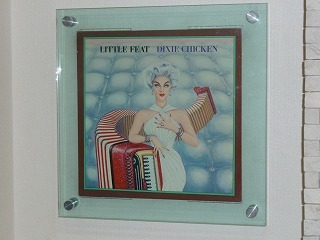
1973年発表の一大転機?となった傑作、「Dixie Chicken」です。まあ、一般的に「リトルフィート」といったら、大抵の方はこのジャケットを連想するんじゃないでしょうか?それくらい評判となったアルバムです。
ジャケットは、マリリンモンローとマレーネディードリッヒを合わせたような、ちと凄味のある?妖艶な女性が蛇みたいなアコーディオンに取り囲まれている構図でして、意図している所はよく分かりませんが、頽廃したハリウッドを皮肉っているのでしょうか?
1、2作目までは、ザッパ関連を匂わすような、何ともいえない、フリーキーで奇想天外なロックを生み出していた彼等が、ベースのメンバーチェンジ(この事は重要だと思うので、後に考察します。)を経て、全く?ノリの違うバンドに生まれ変わりました。
その粘りのある、ファンキーでいて、重たいという唯一無比なサウンドを生み出す原動力となったのは、やはりベースのケニーグラッドニーと、ギターのポールバレアー(と発音するのかな?)の二人でしょうな・・・・。
表題作のビルペインの転がるようなニューオーリンズピアノ、惚れ惚れするローウェルジョージの唄とスライドは絶品ですが、これに先の二人の納豆のような?粘りが加わると、怖いものなしになりますね・・・・。
リッチ―ヘイワードのドラムなんですが、この人は本質的にはタイトなんだと思います。何せ、80年代中頃にはロバートプラントのソロでも叩いていた位ですから・・・・。確か、90年代には、クラプトンのツアーバンドもやってなかったっけ?
そんな彼も、ケニーグラッドニーのベースと、サムクレイトンのパーカッションが加わり、やや腰の入ったドラムを叩くようになりましたよね。でも、決して後ノリにはならないところが、やはり白人ですよねえ~、というか、そこがフィートたる所以ですかね?
そして壁の2枚です。

1972年に発表された、2作目の「Sailin' Shoes」です。
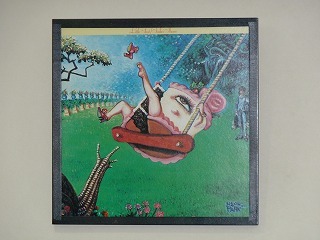
ケーキ少女?がブランコに興じており、弾みで靴が脱げてかっとんでいます。まさに、「セイリン シューズ」ですね。実は歌詞をよく理解してないんですが、これって、結構猥雑な内容なんでしょうかね?ケーキって、スラングであまり良い意味で使われないような・・・。
内容は、先に申したように、なんかザッパに通じるような、混沌としたアングラな感じで、決して一般的なカリフォルニアの明るいイメージではないです。
私も、最初に聴いた時は、ウン????といった感じでしたね。
ローウェルの最高作の一つ、「Willin'」も、サラッとあっさり唄われていますが、やはり、オリジナルだけあって、貫録がありますなあ・・・。リンダロンシュタットのヴァージョンも良いですが、やはり毒が抜けてますね・・・。
そして、これです。
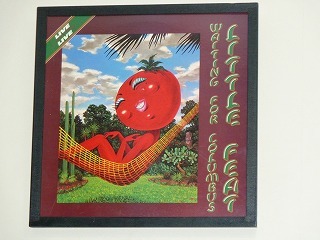
1977年に発表された、2枚組ライヴアルバム、「Waiting for Columbus」です。
昔、何故トマトがコロンブスを待っているのかピンと来なかったんですが、あるサイトを見ていて、氷解しました。
元来、トマトはアメリカ大陸にあったのです。スペインのコロンブスが、1492年に新大陸を発見して以来、多くのスペインを始めとした欧州人たちが去来し、トマトをヨーロッパへ持ち帰り、そこから爆発的に広がっていったとの事です。
トマトは、イタリア料理でよく使われるので、イタリア産のイメージがあったんですがねえ・・・。
という訳で、ネオンパーク画伯は、こういうイラストを描いたようです。
内容ですが、ライヴバンドとして名高い彼等ですから、悪い訳がありません・・・という事で、彼らのリリースしたアルバムの中では最高の売上を記録したようです。
個人的には、映像で楽しみたいので、同じ1977年にドイツの「ロックパラスト」に出演した時のヴィデオテープは、擦り切れるまで?よく見たものです。
今月の壁レコード ~ プリンス特集(2016/05/29)
皆様、如何お過ごしでしょうか?
5月とは思えない程、暑い日々が続きます。なんでも、インドでは50度近く記録した地域もあるそうです。
想像を絶する気象ですね。地球はどんどん壊れていってるのでしょうか・・・・。
さて、また巨星が一つ堕ちてしまいました・・・・・。
まさか、あのプリンスがこんなに早く逝ってしまうとは・・・・・・。
私は訃報を、出入りの業者さんから聞きまして、あまりのショックに椅子から転げ落ちました・・・。
では、駆け足で医院に掲示したジャケットをアップします。
玄関先の1枚です。

個人的には、一番カッコいいと思う、1982年の傑作「1999」の12インチシングルです。また、12インチだと音がいいんですよね。
ライヴ仕立てのヴィデオクリップも、当時ワクワクしながら観ていました。
次は、あの「パープルレイン」でしょうが、内容はいいんですが、ちょっと、何となく下世話なジャケットなんで、今回はパスしました。
壁の2枚です。

先ずは、1981年のまだファンク臭がプンプン漂ってる、痛快な「Controversy」です。邦題は、「戦慄の貴公子」でして、なかなか言い得て妙ですな。
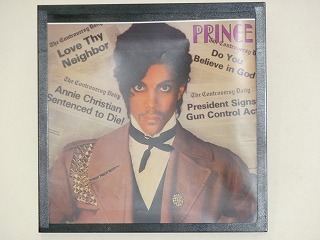
80年代を象徴する、エレクトリックファンクが全編で弾けてますが、A面最後の変態チックなバラッド、「Do me baby」は、メリーサモーガンのカヴァーもいいですが、やはり本家の猥雑さには敵いません・・・。
そしてもう一枚です。
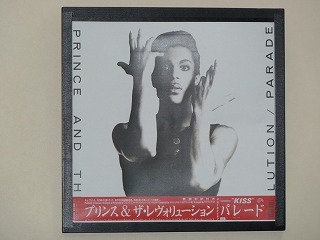
絶頂期という事で、ちょっとお洒落な映画でも作ってみるか・・・てなコンセプトで1986年に作られた?駄作とこき下ろされた映画「Under the cherry moon」のサントラ的意味合いを持つ、異色アルバム、「Parade」です。
でも、私このアルバム、発表当時は結構聴きこんでて、特にA面は、今でも頭の中で完全再生可能です!?
2曲目の「New Position」なんか、最高ですがな・・・。
もちろん、B面の全米№1となったシングル、「Kiss」のファルセットもゾクゾクしますね・・・。
今月の壁レコード ~ キースエマーソン氏追悼・・・EL&P特集(2016/04/19)
あれほど栄華を誇った桜もあっさりと散ってしまいました・・・。
諸行無常であります・・・。
熊本を始めとする九州各地での震災の被災者の方々に心からお見舞い申し上げます。
個人的には、20年前アメリカ留学中に大変親しくさせて頂いた熊本大学病院の医師ご夫妻が被災されたので、気が気ではありません・・・。
後に何とかメールでの安否確認ができましたので、ほっとしました。
今月の特集は先頃、不本意な形で生涯を閉じられた、シンセサイザ―の第一人者?キースエマーソン氏です!
今でこそ、再評価?されて「プログレ四天王」なんて、言われてますが、ちょっと前までは、かの「レコードコレクター」誌をして「(プログレッシブロックの特集は)ELPだけはやる気ないです!」などと言わしめるほど、バカにされていたもんです。
確かに、クリムゾンやイエス、フロイドらの世界観と較べると、ELPのそれはやや稚拙な感じも致しますが、その「わかりやすさ」がウケて、70年代前半の彼らの人気は凄まじかったようです。
ミュージックライフ誌のバックナンバーを読むと、人気投票ではレッドゼッペリンを抑えて一位になってた時期もあるんですから・・・・・。
その証拠に、中古盤屋さんの投げ売りレコードコーナーではタルカスや展覧会はかなりの頻度で遭遇しますので、当時相当売れたんではないでしょうか?
今回はそんな彼らの名盤を3枚、取り上げてみました。
先ずは玄関先です。
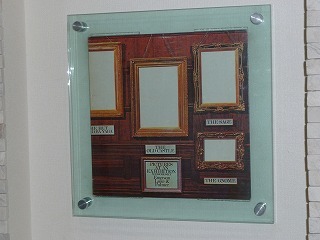
ムソルグスキー作曲、ラヴェル編曲の、クラシックの組曲を大胆にロック的要素を盛り付けアレンジしたもので、当時、アイランドレーヴェルからは廉価盤でリリースされてますので、純粋にはオリジナルアルバムとはカウントしないんでしょうが、
同じような経緯のキングクリムゾンの「アースバウンド」と違って、こちらは世界中で大ヒットしましたね。まあ、音源も演奏内容も雲泥の差ではありますが・・・・・。
グレッグレイクの付けた歌詞はなかなかのもので、流石、痩せてる時の彼は素晴らしいですねえ・・・・・。
お次はこの2枚です。

個人的には最高傑作と思う、セカンドアルバム、「Tarkus」です。
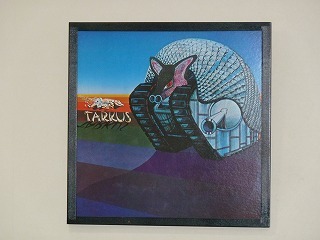
この、チープなヘタウマ?イラストが頭から離れませんが、内ジャケットの絵本?がこれまたいい味なんですよねえ・・・・・。
火山の噴火から突然変異して誕生した、何故か戦車とアルマジロが合体した、キース曰く(ロクデナシの)怪獣、タルカスですが、無慈悲で冷酷なその眼と両手の大砲で、数々の敵を撃ち殺していきます・・・・。
怖いもの無しの彼が最後に出会ったのが、後にELPが設立したレーヴェル名にもなった、存在感抜群の顔は人間、体はライオン?、尻尾は蠍、といった、日本の妖怪、鵺みたいな怪獣、マンティコアです。
タルカスとマンティコアは互角の戦いを繰り広げるんですが、最後に、何とマンティコアの繰り出した蠍尻尾攻撃で、タルカスは目を切り裂かれてしまうのです!!(またこのアップの絵がこ・わ・い・・・・。)
眼科医の私からみても、「そりゃないぜよ!」的な反則技ですから、一般の皆様からすると、恐怖で目を覆いたくなる事でしょう・・・・。
眼を切り裂かれたタルカスは、可哀そうに、川に流れていきます・・・・。その後の顛末はどうなったんでしょうか??まあ、あえてとどめを刺さなかったマンティコアを称えて?レーヴェルデザインに採用した位だから、続編も構想にはあったのかもしれません・・・。
さあ、素晴らしかったA面に隠れて、あまり評価されてない感のあるB面ですが、実は個人的にはこちらの方がお気に入りで、良く聴くのです・・・・。
B面一曲目の「ジェレミーベンダー」は、何ともいえないキースの弾くヘンテコ?な味のあるキーボードと、飄々としたグレッグレイクの唄が素晴らしく、何か時代を超越した雰囲気の佳曲でして、大好きな曲です。
次の「ビッチェズクリスタル」も、先ず曲名だけでもカッコいいですが、突っ走るカールパーマーのドラムに先導されて暴れるキースのキーボードには痺れますね・・・・。
また、最後のハチャメチャな「Are you ready Eddie?」は、エンジニアで後にプロデューサーとしても大成する、Eddie kramerの事を唄ったんでしょうが、こういう所、すきだなあ・・・・・。
そして、もう一枚はこれです。
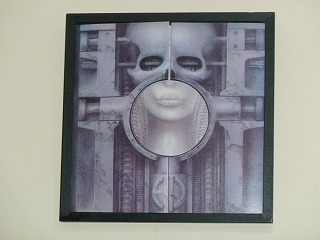
SF映画、「エイリアン」のデザインで御馴染みの、ギーガー画伯のデザインがおどろおどろしい、1974年発表の「Brain salad surgery」です。邦題は何と、「恐怖の頭脳改革」!!
私はいつもこの邦題を聞くにつけ、漫画「東大一直線」の一コマを思い出します・・・。
確か、主人公、東大通(とうだいとおる)が、親友の多分田吾作(たわけたごさく)の脳をネズミの脳と入れ替える!?というとんでもない手術をするシーンでして、東大の発するセリフは「ただちに外科手術が行われた、にぎにぎしく・・・」ですので、ちと違いますが、まさしく「恐怖の頭脳改革!!」
内容は、もう彼等でしか成し得ない世界観で満ち溢れてまして、聴く方もかなりのパワーが要ります。特に両面に渡って繰り広げられる中期の最高傑作と言われる、「悪の経典」は何かこう、凄すぎて一気に聴き続けると眩暈を起こしそうです・・・。
今月の壁レコード ~ 追悼デヴィッドボウイ氏 その3(2016/03/24)
だんだん春めいて参りました今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか?
今年に入って、往年のロック、ソウルスターの訃報が止まりません・・・。
実は今月は、グレンフライ氏の追悼を予定していたんですが、生憎傑作ソロ、「No fun aloud」がどこかに行って見つからず・・・。
取りあえず、前回飾りきれなかったボウイ氏の他のレコードで間に合わせていたんです。
そうこうしているうちに、モーリスホワイト氏、ジョージマーティン氏、キースエマーソン氏・・・と連鎖反応?的に訃報があいつぎ、驚いています。
先の4人のスター達も、これから取り上げさせて頂きたいと思っております・・・。
玄関先は、以前も掲示しましたが、やはり彼を象徴する一枚と思いまして、再度登場のこれです。
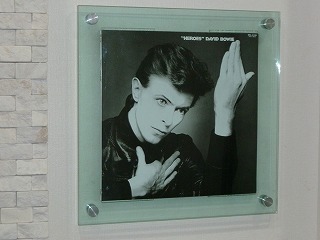
鋤田正義氏の素晴らしい写真に打ちのめされます。
数ある追悼本でも、やはりこの時の別ショットを採用した、ミュージックマガジン社のものが、一番ヴィジュアル的には優れてましたよね・・・。
そして待合壁の2枚です。

前回、飾れなかった2枚をどうぞ。
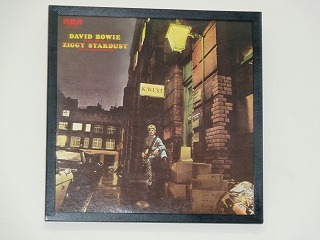
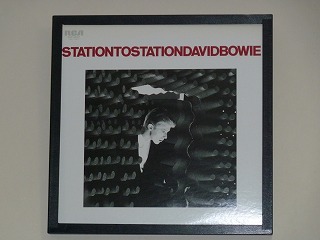
やはり、この2枚は音楽的には全く別物ですよね。しかし、その差はたったの4年です。
恐るべし変容・・・まさにカメレオンマンですね・・・。
ビートルズもたった8年であの深み(Love me doからLet it be・・・・)に到達したのは、何か神がかっていますよね。
優れたミュージシャンには、我々凡人とは違った時空が流れているんでしょうねえ・・・・・。
今月の壁レコード ~ 追悼、デヴィッドボウイ特集 その2(2016/02/15)
寒暖差激しい今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか?
先日のデヴィッドボウイ氏の突然の訃報には本当に驚かされましたよね。
その前の週に、久々に気合入った新作が発表されたばかりでしたので、NHKのニュースで知った時は、腰を抜かしました・・・。
私は、ボウイ氏もかなりのファンでして、レコードはいろいろ集めておりました。
という訳で、今月の壁レコードは、「院長のひとこと」で予告した通り、二回目のデヴィッドボウイ特集でいってみますね。
前回の特集は一番好きな「ベルリン三部作」でしたので、今回は、割とベタな選択でいってみたいと思います。
先ずは、最も美しい?時期のポートレイトが素敵な、ベストアルバム、「Changes one」です。
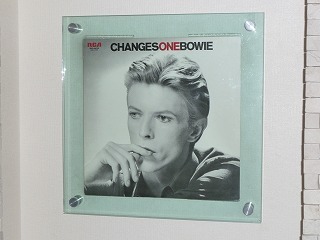
まあ、当然ベスト盤なので、全曲素晴らしいです。言う事なし・・・。やはり初期の二大傑作、「スペースオディティ」、「チェンジス」はホントに良い曲ですね。
世間では、ボウイ氏のイメージは、ジギーの頃のグラムスタイルか、レッツダンスの頃の金髪スーツの2択なのが、今回の訃報でよ~く分かりましたが、私個人的には、ボウイといって想像するのは、オールバックで固めたこの写真の雰囲気なんですねえ。
待合室壁の2枚です。

先ずは、ビジュアル的には白眉のこのアルバムです。
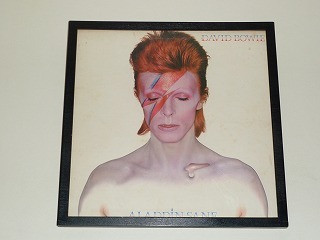
1973年発表の、「アラジンセイン」です。確か、タイトルの意味は、「A lad insane」の駄洒落?だったような気がします・・・。
兎に角、前作「Ziggy Stardust」が大成功を収めた後に出されたアルバムなので、ノリに乗ってる様が垣間見れます。
個人的には、ジギーよりもへヴィ―ローテーションのアルバムです。マイクガーソンのアバンギャルドなピアノが素晴らしいタイトル曲もいいですが、凄いのはローリングストーンズのカヴァー、「夜をぶっとばせ」です。
カッコよさは完全にミックジャガーを凌いでます!(と言ったら、ストーンズファンに怒られそうですが・・・・)
そして間髪入れずに始まるこれまた名曲、「ジーンジニ―」!!あまりの格好よさに「クーッ、たまらん!」フレーズが出てしまいます・・・。(中山さん、ごめんなさい)
そして、訃報を伝えるニュースのBGMに最も使われた、1983年のビッグヒット、「Let's Dance」です。
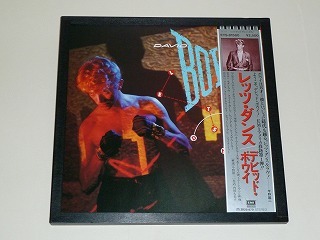
このアルバムは、何度も言うようですが、「ナイルロジャース印のアルバム」ですよね。
ドラムに起用したシックのトニートンプソンの叩き方、音像処理があまりに個性的なんで、(私は好きですが)賛否両論分かれるアルバムだと思います。(オマーハキムも叩いてはいますが・・・・)
実際、当時の音楽雑誌には、あまりの変貌ぶりに皆ズッコケてましたもんね。「売れ線狙い」「日和った」「これは売れるよボウイ様」などと、揶揄されていましたね。
私は1981年から洋楽聴き始めたので、リアルタイムで聴いたボウイ氏の曲は、クイーンと共演した「アンダープレッシャー」が最初でした。(これは名曲です。)
なので、「レッツダンス」はそれほど抵抗なく楽しめた記憶がありますね。
しかし、タイトル曲のヴィデオに、スティーヴィーレイヴォーンを何故登場させなかったのでしょうか?映像では自分がギター持ってるんで、私の友人は、「デビッドボウイ、むちゃギター巧いやん!」と思いっきり勘違いしてましたがね。
なんて、偉そうな事言ってますが、当時は私も知らなくて、「ほだらー、何でもできるんよ、ボウイは・・・。」などど、知ったかぶりっこでしたね。
謹賀新年 ~ 申(猿)ジャケット特集(2016/01/16)
皆様、明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
今年は申年、実は私、年男でございまして、今年は例年以上に気合いが入っております。
皆様方のお役に立てるよう、微力ながら頑張らせて頂きます。
という訳で、今月のジャケットは猿もので統一致しました。
先ずは玄関先です。
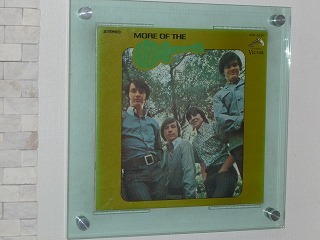
1967年発表の、モンキーズのセカンドアルバム「More of the Monkees」です。
ニールダイヤモンド!がペンを執った「I'm a Believer」は、何と全米シングルチャートを7週間も独占したそうです。確かに、物凄く魅力的なメロディーですよね。
モンキーズといえば、「Daydream Believer」と相場が決まっているような感じですが、個人的にはこっちの方がワクワク感があって大好きです。
モンキーズは今でこそ単なるアイドルグループで括られていますが、そもそもは英国のビートルズに対抗すべく、アメリカショービズ界が叡智を結集(はちと大袈裟ですかね)し、満を持して送り出したグループだったんですよね。
ただ、やはりオーディションで選ばれた4人なので、純粋に音楽だけ取ってみると、ビートルズとは雲泥の差がありますねえ・・・。演技はモンキーズの方に軍配が挙がりますが・・・・。
お次は待合の2枚です。

この2枚はダイレクトに選んでみました。
先ずはトーキングヘッズのラストアルバム、「Naked」です。
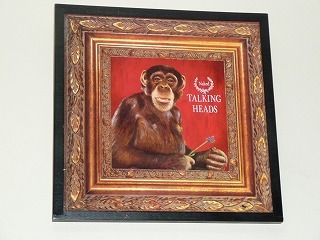
Talking Headsはかなり好きなバンドでして、初期のNYパンク~ニューウェーヴ時代は勿論、80年代前半のファンク~アフリカンビート時代も大好きで、良く聴いたものです。
デヴィッドバーンの非凡さばかりが持ち上げられますが、リズム隊の夫婦、クリスフランツとティナウェイマウスたちの叩きだす人力ビートは最高です。特にクリスのシンプルなドラミングには影響されました。
今野雄二さん風に言うと、「トーキングヘッヅ」ですが、彼等も機会があれば取り上げて行きたいと思ってます。
そしてもう一枚。
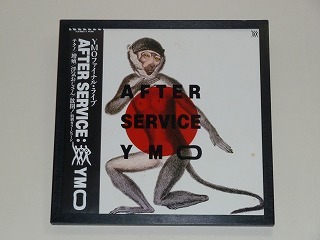
日本の誇るスーパーバンド、YMOの第一次?散開ツアーを収めたレコードです。
YMOは私の中学時代、異常に人気がありまして、イケてる男子たちは皆、KORGやYAMAHAのシンセサイザ―を学校に持ってきて演奏してましたねえ・・・・。
私は当時はまだドラムを始めておりませんでしたので、専らリスニング専門で、「増殖」のスネークマンショーのコントを聴いて大笑いしていたクチです・・・・・。
今年も有難うございました(2015/12/29)
今、これを書いているのは12月29日なんです。
今年もお世話になりました。また来年もよろしくお願い申し上げます。
という訳で、帳尻合わせ?にジャケット画像をアップさせて頂きます。
もう過ぎ去ってしまいましたが、クリスマスの3枚を選ばせて頂きました。
あっ!勿論壁には飾りましたよ!


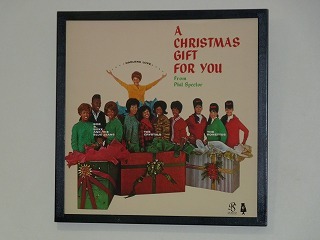
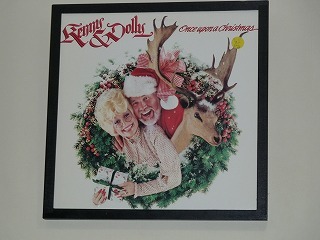
以上、アットホームなクリスマスをイメージしてみました!
来年も宜しくお願いします。
今月の壁レコード ~ キースジャレット特集(2015/11/30)
いよいよ寒くなってまいりました。
皆様、風邪やインフルエンザにご注意ください!
今月は、久々にジャズで行こうかと思います。
この寒い季節にぴったりなECMから出されている、キースジャレットのリリカルなピアノをご紹介しましょう!
先ずは、1985年発表のゲイリーピーコック、ジャックディジョネット達との鉄壁ライヴアルバム、「Standard Live~ 星影のステラ」です。
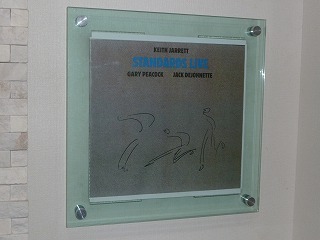
彼らの奏でるスタンダードは、他のトリオが「甘さ」で勝負しているのに対し、「辛さ」?というか、ピリリとエスプリを効かせているような、硬派な演奏が醍醐味です。
続いて、この2枚です!

先ずは彼の最高傑作ではないが、人気度は№1の、「ケルンコンサート」です。
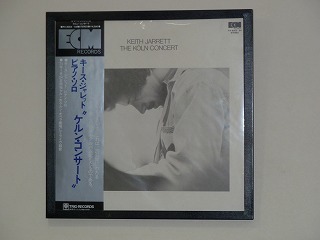
大学の軽音楽部の佐藤先輩が、何気にかけてくれて、ズビッと心に刺さってきましたねえ・・・。今思うと、ドイツオリジナル盤だったような・・・・さすがオシャレな佐藤先輩でした・・・・。
完全即興のピアノソロ、というと何か冗長なイメージがあり、実際前作の3枚組の「ソロコンサート」では、正直真剣に聴き通すのはちと辛い部分がありました・・・。
しかし、これは違います。何か、起承転結がはっきりしていて、全面通して聴いても(なかなかそんな長時間は取れませんが・・・)、結構スンナリ聴けてしまうんです。
特に、アンコールのD面の小品は、ロマンチックなメロディーがと・ま・ら・な・い!素晴らしい演奏です。
この楽譜を手に入れたのですが、難しすぎて全然弾けませんでした・・・・。
そしてもう一枚です・・・。

北欧の香りのする、まさにこの季節にピッタリな名作、「My Song」です。
この哀愁味溢れる旋律、故中山康樹風にいうなら、「ク~っ、堪らん!」です。しかし、中山氏のいかにも大阪人的な、あちこちに笑いを練りこんだ洒脱な文章、本当に好きでした。ご冥福をお祈りします。
今月の壁レコード ~ ロッドステュワート特集(2015/10/31)
流石に11月近くになりますと肌寒くなってまいります。
ついこないだまで半袖ケーシーで診察していたのですが、今週から白衣も羽織るようになりました・・・。
こないだ、いきつけの中古レコード屋さんでRod StewartのNight On The Townのイギリス盤をゲットしまして、嬉しくて何度も聞いてますが、素晴らしいんですよ!
という訳で、今月の壁レコードは彼の特集でいこうと思います。
先ずはその、「Night on the town」です。
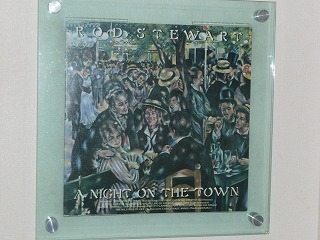
1976年に発表された名盤ですが、ジャケットの絵は、あのルノワールの「ムーラン・ドゥ・ラ・ギャレット」の精巧なパロディでして、学生時代、ヨーロッパ放浪中、パリ滞在時にオルセー美術館で本物を見た時、脳裏に浮かんできたのは「今夜決めよう」のイントロでした。
その「Tonight the night ~ 今夜決めよう」ですが、シングルカットされ、全米№1に輝いています。凄くロマンティックな曲なんですが、当時の恋人、べべヴエルの色っぽい語りを挿入したエンディングはちとやり過ぎな感も致します。
歌詞をそのまま映像化した、下世話なPVも今見るとこれはこれで粋だなあ・・・・・。べべヴエルはそれまではトッドラングレンとお付き合いしてたんじゃなかったっけ?なかなか有名なグルーピーさんだったようです。
このアルバムはA面が本当に素晴らしく、今の季節にピッタリなんです。
2曲目はこれまたもの哀しい内容の曲で、キャットスティーヴンスのカヴァー、「First cut is the deepest ~ さびしき丘」です。
これはかつてフラれた彼女に心身を深く傷付けられた男が、復縁を迫り、「もし君が再び僕を愛する事になれば、その傷は幸運に変わるのだ。しかし君はかつて僕を傷付けた事を後悔し、苦しむ事になるのさ」という意味と解釈してますが、メンドクサイ男ですな。
3曲目もなかなかいい感じの曲ですが、A面ラストの「Killing of Georgie」は軽快なパート1、悲壮感漂わせ熱唱するパート2、共に出色の出来です。
何でもゲイの友人の死を唄ったノンフィクションだそうで、まだ当時はタブーだった「ゲイ」を堂々とテーマにしたという事で、評価されているようです。
あのVillage Peopleが出てきたのはもう少し後なんですかね?しかし、彼らの作る曲は内容は兎も角、物凄くキャッチ―なメロディですよね・・・。西城秀樹もピンクレディーもいいとこ取りしてズルい!!などと当時は全く思いませんでしたよ。
B面は最後の「Trade Wind」以外はパッとしない(失礼!)ので、あまり触れませんが、盟友ロンウッドも同時期に採り上げた「Big Bayou」を唄っているんですが、残念ながらロンの方に軍配が挙がりますね・・・・。
そして待合壁の2枚です。

この2枚はイギリス時代、アメリカ時代それぞれの最高傑作だと思います。
先ずは、イギリス時代の傑作アルバム、「Every picture tells a story」です。
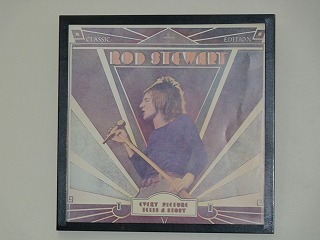
1971年発表の3枚目のソロアルバムでして、「マギーメイ」の大ヒットを生んだアルバムで有名ですが、典型的ブリティッシュハードなタイトル曲や、抒情性のあるトラッドっぽい、いかにもイギリス的な曲も収録されているバランス良いアルバムです。
この頃は並行してフェイセス(このバンドもまた特集してみたいです)でもリードヴォーカリストとして活動しており、八面六臂の大活躍振りでした。
1974年まではそういうスタイルで忙しくしていたロッドが、ギターのロンウッドがローリングストーンズに加入する為に、完全にバンドを解散する事になったので、ロッドはソロだけでやっていく決意を固め、アメリカ移住の為に大西洋を渡るのでした。
そして出たのが、この大傑作アルバムです。
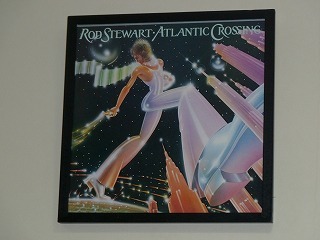
まさに、「All antic Crossing」です。ジャケットの印象的なアールデコ調イラストはあのKOSHのデザインでして、その通り、ロンドンからニューヨークへ大西洋を一跨ぎしている様子がユーモラスに描かれています。
まあ、私はこのアルバムを何度聴いたか分かりません・・・。
A面のファーストサイドは一曲目の余裕いっぱいのミディアムナンバー、「Three time looser」と2曲目のJesse Ed Davisの乾いたギターソロが最高な、「Allright for an hour」が最高です。
B面は唄のうまさを生かしたスローサイドで、全曲が素晴らしい!一曲目の「もう話したくない」はオリジナルのDanny Whittenの、2曲目の「It's not the spotlight」はオリジナルのBarry Goldbergのヴァージョンをそれぞれ完全に凌いでおり、このアルバムのベストトラックです。
Isley Brothresの名曲、「This old heart of mine」も流麗なバックの演奏及び女性コーラスも際立って、本家顔負けの名唱を聴かせてくれます。
そして、一般的にはこのアルバムで一番人気の「セイリング」ですが、私的には、オリジナルのサザーランドブラザーズのテイクの方が、いかにも荒海に出ていく勇ましい感じがして好きです。
アレンジのせいもありますが、ちとロッドの歌い方も女々しい感じがするんですよねえ・・・。(女性蔑視、との声も聞こえてきました・・・。申し訳ありません、あくまで言葉のあやですので、お許しを・・・)
今月の壁レコード ~ 山下達郎さん特集(2015/09/30)
一年で最も過ごしやすい気候になってまいりました今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか?
今回はSugar Babe時代に発表した傑作アルバム「Songs」40周年で一際脚光を浴びている山下達郎さんの特集です。
先ずはその「Songs」です。

ジャケットのこの絵についてですが、大変不勉強にてどういう意図があるのか分かりませんが、何か70年代っぽい香りが漂ってきますね・・・。
私は恥ずかしながら「Downtown」はEPOさんで知ったクチでして、偉そうなことは言えませんので、(達郎ファンはマニアックなので下手な事は書けません)このアルバムの批評などできません・・・。
よって、「感想文」程度と割り切ってお読みください・・・。
これまでの印象は、達郎さん以外は、大貫さんも含めて、大変失礼な言い方ですが、そこはかとなくアマチュアっぽい素朴感がありました・・・。いい意味で70年代初期っぽい、あの感じがしたんです・・・うまく言えないけれど・・・・。
しかし、今回音が良くなったこともありますが、改めて聞いてみますと、やはり皆さん、プロフェッショナルでしたねえ・・・。いやはや、思い込みというのは恐ろしいものです・・・・。
お次は待合壁の2枚です。

まずは1978年の大傑作ライヴアルバム!「It's a poppin' time」です!
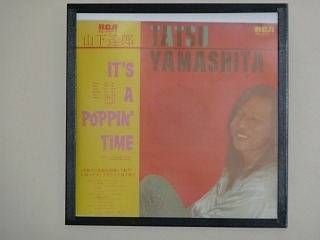
私のこのアルバムとの出会いは、大学1年の時でした。所属していた軽音楽部のギターの先輩が、「このアルバムにいろんなパターンの曲が入ってるから、参考にしなよ・・・。」みたいな事を仰って、このCDを貸してくれたんです。
一曲目の「Space Crush」はスタジオワークでの曲で、前座みたいな感じですが、ポンタさんのドラム一発から始まる2曲目の「Rain Queen ~ 雨の女王」から最後の「Circus Town」の大団円まで、この世のものとも思えない(ちと言い過ぎか)、素晴らしいライヴが楽しめます。
ホントに、録音したカセットテープが文字通り、擦り切れるまで車やウォークマンで聴きまくったものです。
全員が凄腕ミュージシャンにて、非の打ちどころの無い、素晴らしいグル―ヴを放ち続けており、当日この会場(六本木ピットイン)に居合わせた観客は、それこそ(ドラッグ無しでも)極上のトリップ感覚を味わっていたことでしょうね・・・。羨ましい・・・・・。
本当に今考えると、恐ろしく豪華なメンツでして、ポンタさんのドラムは勿論ですが、YMO結成前夜でセッションミュージシャンとして引っ張りだこだった坂本龍一さんの鍵盤さばきには惚れ惚れしてしまいます。ARPオデッセイ、フェンダーローズ、スタインウェイピアノ・・・・と様々なキーボードを駆使して、素晴らしいソロ、バッキングを聴かせてくれます。
特に素晴らしいのが、「Solid Slider」で、中間部で坂本さんのローズだけになり、そこからポンタさんのドラムが被さって二人で凄まじいグルーヴが弾ける所は何度聴きこんでも鳥肌が立ってきます・・・・。
ピットインという場所柄、ジャズに根差した成熟した演奏が聴かれるのは、ベースの岡沢章さん、サックスの土岐英史さん、ギターの松木恒秀さんらのいぶし銀の演奏からなんでしょうね・・・。
コーラスに何と、吉田美奈子さんも名を連ねているのは何気に凄い!
ここでポンタさんのドラミングについて、書かせて頂きます。
私個人的には、日本で一番グルービーなドラマーではないかと思います。とにかく、ノリが半端なく気持ちいいし、小気味良いロール回しや高速タム回しを交えた、粋なフィルインは大変勉強させて頂きました・・・。
また、ちょっとした小節のキメや、シンバルのアクセントなど、とにかく無駄がないんですよね・・・・。リズムキープとして黙々同じフレーズを叩く、という事が皆無なんです・・・・・・。
同じようなメンツで、これまた同じピットインで録音された、渡辺香津美さんがリーダーのユニット、「KYLYN」でのライヴでも、ポンタさんのドラムは素晴らしいですよね・・・。パーカッションのペッカーさんと共に、これまた凄まじいリズム波状攻撃を仕掛けてきます!
このアルバム、「キリンライヴ」についても、いつかこのブログで取り上げたいですねえ・・・・。
そして、もう一枚です。
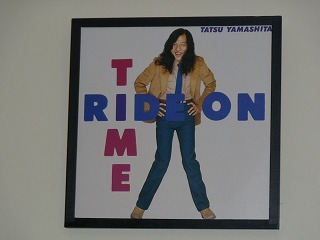
1980年発表の大ヒットアルバム、「Ride on Time」です。
私は当時、小学6年生でしたが、リアルタイムでシングル盤を岡崎の有名レコード店「サウンドイン大衆堂」で購入しました!!子供ながらに中間部の土岐さんのサックソロと伊藤さんのバキバキベースを夢中になって聴いてました・・・・。
このアルバムから、ドラムが青山純さん(早すぎる死が本当に悼まれます)、ベースが伊藤広規さんの鉄壁のリズムセクションが全面参加することになり、彼のサウンドがタイトで隙のないモノに変わっていくんですよね・・・・。勿論格好いいんですが、何かカッチリしすぎて計算されたものになってしまっている感じがします。
ある意味、マンネリ化する前兆だったのかもしれません・・・・・。(あまり適当な事書くと、達郎マニアに殴られそうですのでこの辺で・・・・・。)
でも、何だかんだ言って、伊藤さんのあのベースが無いと、物足りないんでしょうねえ・・・・。最近は行ってませんが、達郎さんのライヴは本人よりも伊藤さんのベースを観てる方が長いんですから・・・・・・。(ご同輩も多いんじゃないでしょうか?)
今月の壁レコード ~ 80年代のビリージョエル特集(2015/08/31)
皆様、お元気でしょうか?
ここの所、激しい雨が続いていまして、割と朝晩は過ごしやすくなってきましたが、まだまだ日中は暑いですね。
今月のレコードジャケットは、久々にBilly Joelでいってみたいと思います。
実は、彼の特集はこれで2回目になりますが、1回目はかなり前でして、このブログがまだ始まっておりませんでしたので、記録がありません。
確か、定番の「Stranger」、「52nd Street」、「Songs in the attic」の3枚だったと思います。
今回は、80年代以降にスポットを当ててみました。
先ずは玄関先です。
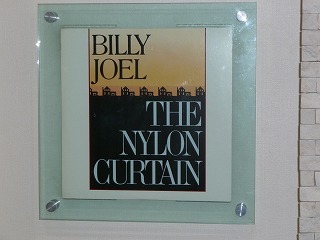
1982年秋発表の「The Nylon Curtain」です。私にとってリアルタイムで聴き始めた最初の彼のアルバムです。
このデザイン性に溢れたジャケット、秀逸ですね。アート作品としても通用しますね。
何となく、暗さを感じさせるデザインですが、内容を如実に物語っています。
次にご紹介しますが、前作「グラスハウス」で、ちょっとはっちゃけすぎ?た反動か、はたまたオートバイ事故で入院を余儀なくされて病院のベッドの上で内省的になったのか?このアルバムは非常にシリアスです。
特にA面はその傾向が強く、明るい曲が全くありません・・・。2曲目の「ローラ」なんて、重厚すぎて、こちらもそれなりの気合いが必要です・・・。(でも良い曲でして、個人的には白眉です。)
当時良く言われてたのは、このアルバムはジョンレノン的だ、という事です。
恐らく、社会性を帯びた歌詞がそう感じさせたんでしょうが、それはあくまでもソロになってからの側面であり、彼の本質はビートルズ時代に炸裂していたシニカルな面にあると私は思っています。
あまりに、「イマジン」のイメージだけで、聖人君子的祭り上げられ方をされているのを見ると、「いやいや、彼はもっと人間臭いひとだったと思うよ・・・」と独り言を呟いてしまいます・・・・。
続いて待合壁の2枚です。

1980年の大ヒットアルバム、「Glass Houses」です。
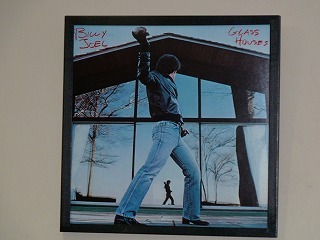
「Stranger」「Just the way you are」、「Honesty」などでついた「ニューヨークの吟遊詩人」的なイメージをぶち壊せ!的な気概で作り上げた、ロックンロール主体のアルバムです。
ジャケットのコンセプトは、皮ジャンを着た、いかにも「ワル」ぶったビリーがガラスの家の前で今にも石を投げる所なんですが、A面冒頭に針を落とすと、「グワッシャーン!!」とガラスの割れた音が聞こえてきます。
続いて、御機嫌なロックンロール「You mey be right」が始まるとこなんざ、いつ聞いてもゾクゾクしますねえ。
しかし、そんな気概を見せたビリーの思惑に反して、日本のソニーさんは邦題「ガラスのニューヨーク」、「孤独のマンハッタン」など、全然内容と関係ないのに、「紐育」から切り離せなかったんですよねえ・・・。
ビリーさん、この事知ってたんですかねえ・・・・・。(ビリーさんで思い出しましたが、ビートルズのイエローサブマリンの中間、潜水艦内のエフェクトっぽい所で、空耳で「気をつけてビリーさん!」と聞こえる所があるのご存じですか?)
そして、最近個人的にはヘビーローテーションになっている、1983年の大傑作アルバム「Innocent Man」です。
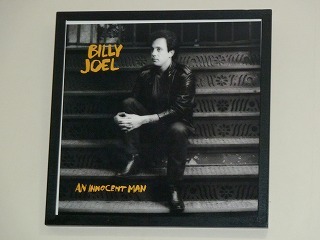
前作、「ナイロンカーテン」が、内容はともかく、セールス的には今一つだったこともあり、恐らくコロンビアレコードからせっつかれたんでしょうね・・・・・。すぐさまこんな小気味よいオールディ―ズ好きが泣いて喜ぶ?大ポップアルバムを出してくれました!
まあ、とにかく前作で吹っ切れたのか、はたまた新しい恋人、クリスティー嬢とのアツアツぶりがそうさせたのか、どこを聴いても(ほぼ)素晴らしい、金太郎飴のような極上の作品に仕上がっております。
「ほぼ」と書いたのは、一曲だけしょうもない(失礼!)曲があるからでして、それが恋人を唄った「君はクリスティー」であるところが、その後の顛末を考えると、何とも皮肉なんですが・・・・・。
このアルバムは全曲レヴューでいかせて頂きます。先ずはレイチャールズを彷彿とさせるイキの良い冒頭の「Easy Money」で軽くジャブをかまされます。荘厳で気高いタイトル曲「An Inoccent man」、一人アカペラでDion&Belmontsみたいな素晴らしいハーモニーを聴かせる「Longest Time」、ベートーベンの「悲愴ソナタ」を引用した美しい「This Night」
そして最初のシングルカットで彼にとって2枚目のナンバー1ヒットとなった、軽快な「Tell her about it」邦題の「あの娘にアタック」は、まあ意味はそうなんですが、なんかイモですよね・・・・・。(イモは死語か!?)
レコードを引っくり返して、B面にしましょう。
冒頭の多分Four Seasonsを意識したと思われる名曲「Uptown Girl」は2枚目のシングルカットで、第3位にまで登りました。この曲、我々日本人には、空耳「オッチャンがーる」で有名ですよね・・・。
次の「Caress Talk」もなかなかの佳曲で、いかにも「グローインアップ」や「アメリカングラフィティ」みたいな、青春映画で流れていそうな感じです。
ちょっと浮いてる?「Christie Lee」はすっ飛ばしても構いません!!??
4曲目の「Leave a tender moment alone」は、名手トゥーツシールマンスの哀愁のハーモニカが冴える、泣ける名曲です。邦題「夜空のモーメント」は秀逸!!
そして、最後の曲「keeping the faith」も、この名盤のしんがりに相応しい、素晴らしくノリの良い曲です。
こんなに素晴らしいアルバムなのに、アルバムチャートでは全米4位が最高だったなんて、当時のアメリカ音楽界はどんだけハイレヴェルだったんでしょうかねえ・・・・。
記憶では同時期にヒットしてたのは、83年の夏だから、ポリスのシンクロニシティーとか、フラッシュダンスのサントラだったような・・・・・。あと、スリラーのロングセラー状態か・・・・・・。
ならしょうがないかもしれませんねえ・・・・・。
若者向きのオサレな曲やラップやサンプリングがチャート上位を占める昨今のビルボードチャートとは対極の「楽曲の良さ」で勝負できていた?昔の音楽業界は良かったですねえ・・・。
今月の壁レコード ~ フリートウッドマックの歌姫たち(2015/07/31)
毎日猛暑!であります。
今日はここ岡崎でも37度を記録したようで、日中外出した時は頭がクラクラしましたね。
体温以上の気温はまさに「熱波」であり、尋常ではありませんでした。
まあ、多治見の方からすれば、「何言ってやがんでえ。」ってなもんでしょうが、免疫の少ない我々には堪えます。
さて、今月は前回の続編として、フリートウッドマックの2人の歌姫、Stevie NicksとChristine McVieのソロアルバムを特集してみます。
まずは前回で特集しきれなかった、グループとしての一枚です。
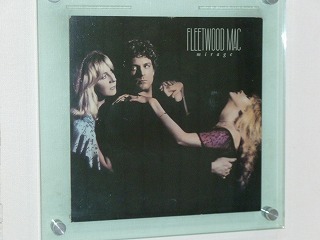
1982年の全米№1に輝いた「Mirage」です。このアルバムは中学2年の秋にリアルタイムで聴きました。ヒット曲「Hold me」と「Gypsy」が目立ちますが、他の曲も彼等らしく粒ぞろいです。
「Hold Me」は印象的なヴィデオクリップが忘れられませんが、リンジーとクリスティーンのユニゾンヴォーカルが力強くていつ聞いてもほれぼれしてしまいます。
「Gypsy」も、Stevieの小悪魔的魅力全開のヴィデオクリップが最高でしたし、曲自体も彼女のお気に入りのようで、ライヴでもかなりリキ入れて歌ってましたね・・・。(後述しますが、アメリカ留学時代の1997年に再結成ライヴをオーランドで観ました!)
しかし、Stevieはこの年は夏に2枚目のソロアルバム、「Wild Heart」もリリースし、「Standback」の大ヒットを生んでいるんですよね・・・・・。かなり旺盛な創作意欲ですねえ。
そして、院内待合壁の2枚です。
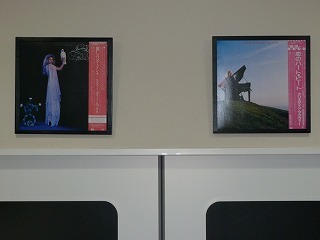
1981年に発表された、ファーストソロアルバム、「Bella Donna」です。
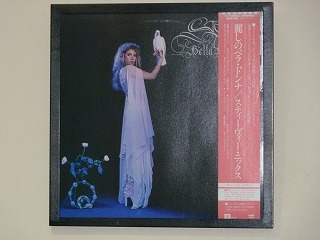
グループとしての活動が停滞している時に満を持して作られただけあり、楽曲、参加メンバーともに文句なしの出来です。
とにかくゲストが凄くて、ツインヴォーカルを決めるTom Petty 、流石のハーモニーを聴かせるDon Henleyは別格ですが、Waddy Wachtelらのタイトなバッキングも素晴らしいです。
このアルバムは彼女の魅力全開で、ライヴの定番曲ばかりで素晴らしい内容です。
この後もコンスタントにソロアルバムを発表し続けますが、個人的には1986年の3作目、「Rock a little」が一番好きですね。高校時代、通学時のウォークマンではヘビーローテーションでしたよ!!
そして、もう一枚は姉御、Christine McVieのマック参加後は初の?ソロアルバムです。
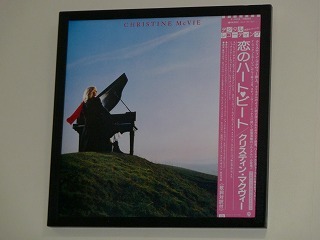
このアルバムをほぼ全編網羅したヴィデオクリップ集があり、昔見た覚えがあるのですが、またStevieとは違った「大人の女」的な魅力があり、画面に釘付けされてしまいましたね・・・・・。
先述のように、私はアメリカ留学時代の1997年に、当時久しぶりにリンジーバッキンガムが復帰して、話題になっていたマックの再結成ライヴを観に行きました。
やはりStevie Nicksの人気は絶大でしたし、一番大物感がありましたが、びっくりしたのはリンジーが女性、(特に中年おばちゃん!)達の絶大なる喝采を浴びてましたねえ・・・・・。
クリスティンもなかなかの存在感でしたし、意外にもリーダー、ミックフリートウッドが芸達者な所を見せてくれ、例のアフリカンドラムソロから金玉クラッカー?まで楽しませてくれました。
ピント来ない方に説明しますと、金玉クラッカーとは、前回特集した「噂」のジャケットに写ってる、ミックの股間にぶら下がっている「アレ」の事ですよ・・・・。
今月の壁レコード ~ フリートウッドマック特集(2015/06/29)
梅雨といえば梅雨で、雨も多いんですが、何となく今年はじとじとさを感じない梅雨ですよね。
まあ、湿気嫌いの紙媒体コレクターの私としては、大いに助かります。
先日、ひょんな所から、Fleetwood macの大ヒットアルバム、「Rumours」のマルチチャンネル盤を聴いたんですが、素晴らしい音空間に圧倒されました。
「こんな音、声が入ってたんだ・・・」とよく聴きこんだアルバムだけに、新しい感動に感激致しました。やはり、マルチチャンネル盤は凄い!
という訳で、最近よく彼らのアルバムを(マルチではありませんが)聞き直しております。
フリートウッドマックのバンド名は、ドラムでリーダーの、Mick FleetwoodとベースのJohn McVieの名前から取っていると思います。
この二人のリズムセクションに、各時代に様々な才能あるミュージシャンが去来して、沢山のアルバムを発表し、離合集散を繰り返している、ロック界でも稀有なバンドです。
最初は、Peter Green、Jeremy Spencerの二大ギタリストを擁する、渋ーいブルーズバンドでした。チッキンシャック、サボイブラウンと並び称され、「三大ブリティッシュブルーズバンド」なんて呼ばれたものです。
この頃も大好きで、特に、本場シカゴに出向いて、アメリカのブルーズマンと嬉々としてセッションした音源は大好物でして、よく聴いてます。
70年代に入ると、ダニーカーワン、クリスティンパーフェクト(後にマクフィー)、ボブウェルチらが頑張ってセールス面は低調でしたが、何とかバンドは存続していったのであります。
しかし、さほど売れもしない(失礼!)のに、ほぼ毎年一作ペースでアルバムを制作させてあげたワーナーさんは本当に太っ腹でしたよね。
後の大ヒットでお釣りが来るくらい充分に儲かったとは思いますが、先見の明があったのでしょうねえ・・・・・、いやはや南友・・・。
1974年の「Heroes are hard to find」を最後に、それまで屋台骨を支えていたBob Welchが脱退してしまい、残された3人はまさにタイトルのような心境だったと思いますが、ここで彗星の如くヒーロー&ヒロインが現れます。
Lindsey BuckinghamとStevie Nicksです。
1973年にデュオアルバムをリリースしたものの、鳴かず飛ばずだった二人が、ミックフリートウッドに見いだされ、とんとん拍子にバンドに加入する事になったのです。当初はギター&ヴォーカルの補強として、リンジーだけを希望したそうです。
しかし、当時は恋人だったスティーヴィーとの「パッケージ契約」でないと首を縦に振らなかったそうです。結果としては大吉になりました。
それからの彼等の活躍は少々後回しにさせて頂いて、先ずは玄関先の画像です。
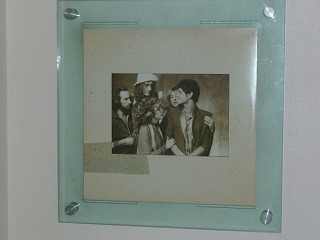
1980年の2枚組アルバム「Tusk」のインナーに使用された、ノーマンシ―フ撮影のグッとくる素晴らしい写真です。
ノーマンの撮る写真はすぐ彼だと分かる独特のセンスがありますが、いつも思うのは被写体をその気にさせるのが巧みだな、という事です。
この写真なんぞ、バンド内の各人の立ち位置が見事に表れてますよね。華のあるリンジーを二人の名花が取り巻き、リーダーのミックが見守り、マイペースのジョンが遠巻きに見ている・・・・。
タスクは「牙」という邦題ですが、大ヒットした前作「噂」の後に難産の末に出したとは思えない程、肩の力の抜けた作品集となっていて、リアルタイムで聴いた方は肩透かしを食らった事でしょうね・・・。
個人的には好きな作品ですが、これは2枚組にする必然性は全くなかったとは思います。
これはプロデュ―スも兼ねたリンジーのソロアルバムに、スティーヴィーとクリスティ-ンがゲストで参加したようなイメージだからです。
ただ、流石に当時のナンバー1バンドの一つですから、所々に光るものはありまして、聴くたびに新たな発見のある、スルメのような味わい深いアルバムではあります。
それでは待合壁の2枚です。

統一感のある2枚でして、デザイン的にも優れていますね。しかし、昔からミックフリートウッドは出たがりの自意識過剰男?でして、この2枚はスタイリッシュなイメージでキメてますが、初期の全裸や女装ジャケットはおぞましかったですよねえ・・・。
先ずは出世作、1975年の黄金メンバーでの一作目、その名も「Fleetwood Mac」です。
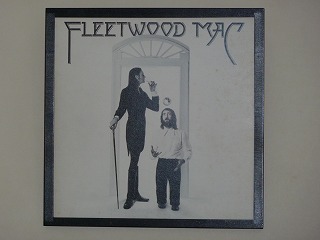
セルフタイトルにしたのは、新しいバンドとしての気負いなんでしょうかね。1975年7月にリリースされた当初はあまり売れなかったようですが、新加入の二人にライヴパフォーマンスがジワジワと人気を集め、あれよあれよとチャートを登り出し、遂には念願の全米チャート1位を獲得するんです。
発売から一年以上かけてナンバー1になるのは、余程の事です。本当に魅力的なステージだったんでしょうね。
このアルバムからは、冒頭のリンジーらしさの光るジャンプナンバー、「Monday Morning」、Stevieの代名詞となった「Rhianon」が光ってますよね。
そしてそして、モンスターアルバム、「噂」です。
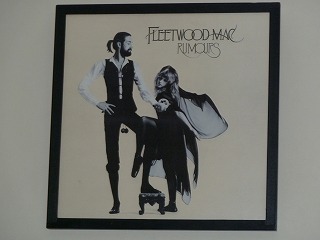
1977年の全米チャートで、合計31週間も首位に君臨した大ヒットアルバムですが、マイケルジャクソンの「スリラー」が出るまでは最高記録だったんじゃないでしょうか?
しかし、内容的には「ふつうの」ロックアルバムでして、マイケルさんのようなクインシージョーンズ一派総結集!といった、いかにも金のかかったアルバムではないんですよね・・・・・。
ただ、流石に3人のソングライターを擁するだけあり、駄作が無く、聴いていてストレスが全く感じられないのは凄いことです。
いろいろ本を読みますと、この時期は、リンジーとスティーヴィー、ジョンとクリスティーンの二組のカップルは別れの危機に直面していたそうですが、そんな逆境がバネになったのか、各人それぞれキャリアを代表する傑作を生み出しているのは感服致します。
しかし、Stevie Nicksの「Dreams」はいつ聴いても素晴らしい!
今月の壁レコード ~ オリヴィアニュートンジョン特集(2015/05/28)
5月下旬だというのに、30度を超える日々が続いております。
この時期にこんな暑さでは、夏本番が思いやられます・・・・。
さて、少し前に「イルカ追い込み漁」の是非を巡って、世界と日本で議論が白熱してましたね。
門外漢にて、コメントは避けさせて頂きますが、頭に浮かんだのは、オリヴィアさんはどう思ってんのかな・・・という事でした。
実は4月後半からコンサートの為に来日してたんですが、くしくもポールマッカートニーと被ってしまい、殆どマスコミ報道されませんでしたよね・・・。
という訳で、我々昭和世代には永遠のアイドルだった、元祖歌姫、Olivia Newton Johnを特集してみました。
1970年代から1980年代前半にかけて、洋楽マニアのアイドルといえば、やはり彼女が筆頭でした。もちろん、デビーハリーやパティスミス、ランナウェイズ、パットベネター、などなどいきのいいロックねえちゃんは沢山いました。
ただ、老若男女誰もが好感を抱く、何というか純粋培養で育った良家の御嬢さん、という清純さが感じられたのは彼女以外には考えられませんでした。
それでは玄関先です。
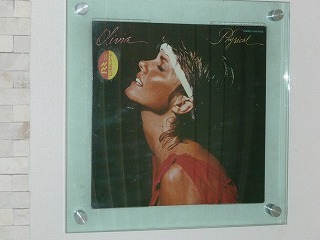
1981年発表のターニングポイント?となったアダルト路線アルバム「Physical」です。
それまでのロングヘアーをバッサリ切って、スポーティーな「健康的な」アダルト路線に華麗にイメージチェンジ!
当時は賛否両論だったような気がしますが、まさに80年代っぽくてやはり正解でしたよね。
アルバムとほぼ同時に発売された、同名タイトルのプロモーションビデオ集も良かったですよね・・・・。
もの凄く魅力的でして、中学生にはドキドキものでした・・・・・。
芝居仕立てのPVより、ライヴハウス?でのギグものに惹かれましたね・・・・。口パクにて実際のミュージシャンではないと思いますが、皆さんいい感じでして、特にシカゴのJames Pankowみたいなキーボードのバンマスのオッサン、いい味だしてます。
大ヒットした表題曲の「Physical」ですが、これ、メロディーは凄くキャッチ―ですが、唄の内容は物凄く下世話なんですよねえ・・・・・。
そういう唄を、数年前から映画などでややシフトチェンジしてはいましたが、あのオリヴィアが歌うんですから、そりゃあ、ヒットする訳です。
そして院内壁です。
ここからは彼女の別の側面、映画にスポットを当てていこうと思います。

まずは1978年のミュージカル青春映画、「グリース」です。
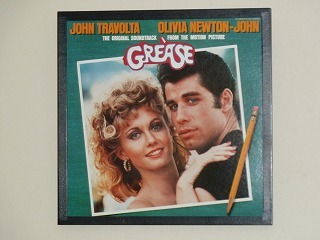
ジョントラボルタと初共演した、大ヒット映画ですが、こないだ久々に見返しましたが、やはりあの歳で高校生の設定はかなり無理がありましたよね・・・・。
後半、オリヴィアが突然ガラが悪くなるとこ、いい子ちゃんが無理に粋がっているみたいで可愛かったです。
そして、興行的にはともかく、音楽的には最高だった、1980年の「ザナドゥ」です。
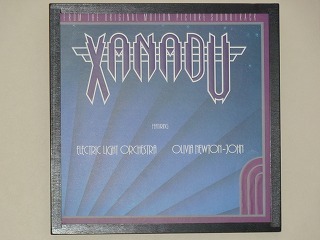
往年のミュージカルを意識した、アールデコ調の懐古趣味的なジャケットですが、多分あのKoshのデザインではないかと思いますが、デザインのクレジットが無いんですよね・・・・。
映画も久々に見返しましたが、やはり凡作(失礼!)ですよねえ。
オリヴィアだけでは弱い、と思ったんでしょうね。あのミュージカルの大御所、ジーンケリー御大を担ぎ出していますが、あまり大した効果が感じられませんし、何よりオリヴィアの相手役(マイケルベック)が没個性にて、どうしようもない・・・・・。
救いはチャーミングで、なかなか達者な踊りを披露する主役オリヴィアのカリスマ性でしょうね・・・。
そういう訳で、映画は大コケ、ELOのリーダー、ジェフリンも当時、「音楽は素晴らしかったが、映画は最悪」とインタヴューで答えていた気がします・・・。
やはり彼女は「歌手」なんですよね。その後は暫く映画出なかったですよね。1985年にジョントラボルタと久々に組んで、「Twist of fate」を撮りましたが、評判は芳しくなかったと記憶してます・・・。
ただ、やはりサントラは佳曲揃いで素晴らしいです。
オリヴィアサイドは全米№1を獲った「Magic」や、師匠?クリフリチャードとのデュエット、「Suddenly」が、ELOサイドでは、「I'm alive」、「All over the world」が抜きんでています。
そして、メインテーマとして何度も劇中流れる、素晴らしい傑作、タイトルトラックの「Xanadu」は、ELOの演奏、コーラスにオリヴィアのリードヴォーカル、という夢の?コラボレーションが聴かれます。
この曲、ジェフリンとしても最高傑作の一つなんじゃないでしょうか?
後に本人のヴォーカルで再録してますが、やはりこの曲に関しては、オリヴィアの方に軍配が挙がります。
まあ、ELOは素晴らしい曲が沢山あるし、例の円盤のコンセプトで面白いジャケットが沢山ありますので、いずれ単独で取り上げたいと思っています。
ネットで情報集めてみますと、今回の来日公演、なかなか好評だったようですね。
10年近く前に、名古屋公演を前から2番目で観たのを未だに覚えてますが、衰えない美貌と声にはビックリしましたね・・・・。
画像なんぞ出回らないものでしょうか・・・・。
今月の壁レコード ~ バッドカンパニー特集(2015/04/23)
美しかった桜もあっという間に散ってしまい、初夏の様相を呈してきました。
しかし、桜は本当に潔いですよね。
持て囃されるのは、ほんの数週間・・・。あとは翌年春までは「ただの木」として過ごすのですよねえ・・・。
さて、4月の壁レコードは未発表曲満載のデラックスエディションが好評の、Bad Companyを特集してみました。
Free解散後、ポールロジャースとサイモンカークは、元モットザフープルのミックラルフス、元キングクリムゾンのボズバレルとバンドを結成します。
各人が素晴らしいキャリアの持ち主で、イギリスを代表する名バンドの出身だった事から、世間では「スーパーグループ」扱いされましたが、本人達はそれほど気負いは無かったようです。
バンド名の「Bad Company」は決して「ブラック企業」ではなく、「悪友」と書くとちょっとあれですが、要は「気の置けない仲間」的なイメージなんでしょうね。
それでは玄関先から・・・

1974年に発表された彼らのファーストアルバム、「Bad Company」です。
何でもないようで、計算されたデザインは流石、ヒプノシスですね。
このアルバムは中学の時(1982年)レイコウ堂(レンタルレコード屋さん)で借りました。東芝盤の黄色の帯付でした。今思うと、岡崎の片田舎の貸しレコード屋にしてはなかなか渋めの品揃えでしたね。
とにかく、このアルバムはA面が素晴らしい!サイモンカークのカウントで始まる冒頭の「Can't get enough」でもうノックアウトされますが、続く「Rock Steady」のカッコいい事!!
この2曲は大学の軽音楽部で嫌がるメンバーを拝み倒して?コピーさせて頂きました。幸いにして?音源は残ってませんが、今聞いたら赤面ものでしょうね・・・・・。
そして3曲目に哀愁味のある佳曲、「Ready for love」が控えております。
この曲はミックラルフスが前バンド、モットザフープル時代に既に発表したものですが、やはりあのグループはイアンハンターの作品中心に動いてますので、ミックは扱われ方には多いに不満があったとか・・・。
確かに、イアンハンターよりもポールロジャースの粘り気のあるこぶし回しの方がマッチしてますよね・・・。豪快さばかり取沙汰されるサイモンカークのドラムですが、こういう曲では意外に繊細なんですよね・・・。
そして4曲目はポールロジャースの唄の巧さが光る、ソウルフルなバラッド、「Don't let me down」です。彼はあまたあるブリティッシュロックヴォーカリストの中でも、トップクラスの喉と表現力を備えていると思います。
ロッドスチュワート、ヴァンモリスン、スティーヴマリオット、スティーヴウインウッド、フランキーミラー、ジェスローデン・・・・・・などなど私のお気に入りのヴォーカリスト達と遜色ない歌声を聴かせてくれます。
B面も勿論いい曲ありますよ!冒頭の彼らのアンセムともいうべき、「Bad Company」は、意外と達者なポールロジャースのピアノも堪能できます。サイモンカークとボズバレルのつんのめるようなキメもカッコいいです。
3曲目の「Movin'on」も軽快で彼等らしい曲です。
彼らの醍醐味は、ブリティッシュ然とした佇まいから想像できない程、アメリカンロック的な曲を演奏する所にあると思いますが、まだこのファーストアルバムではイギリス臭さがかろうじて残ってますよね。
お次は待合壁です。

翌1975年に出されたセカンドアルバム、「Straight Shooter」です。
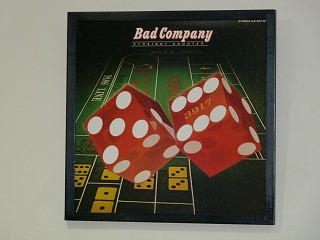
カジノのダイスをデザインしたカッコいいジャケットは勿論ヒプノシスですが、ジャケットよりもインナーの写真の方が面白いですよね。
このバンドがアメリカで人気を博した理由の一つに、メンバーのルックスの良さも挙げられるんじゃないでしょうか?
サイモンカークなんて、なかなか色男ですよね。
全体的に、アメリカンロック的なおおらかな曲調が多いんですが、特に「Shooting Star」は大好きですねえ。
数年前の来日公演でも、ロジャーズと一緒にサビを唄いましたよ~。
そして、今回はデラックス化されませんでしたが、ブリティッシュロック魂を取り戻した快作、3枚目の「Run with the pack」です。
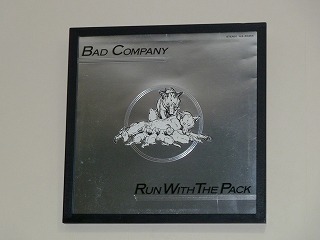
この絵って、何なんですかね?オオカミに育てられた少年を意味してるのだと思いますが、果たして彼らの真意は・・・・・・?
今月の壁レコード ~ ブルーススプリングスティーン特集(2015/03/23)
3月も後半にて、春めいてきましたが、本日23日は真冬のような寒波がおしよせ、寒かったです。
まさに「三寒四温」ですね。
さて、今月の壁レコードは、前から特集してみたかったBruce Springsteenでいってみます。
昨年、気合いの入ったリマスターボックスが出まして、即アマゾンで購入したものの、暫く未聴のままでした。
ここ最近、無性に聴きたくなり、一枚目からガンガン聴きまくりましたが、いやあ、やはり素晴らしいですね。
また、皆さん指摘されている事ですが、今回のリマスターは音がすこぶる良いです!
特に、初期の2枚と、そろそろボックスが噂されている「The River」は新たな命を吹き込まれたかのように、輝いています。
それでは玄関先です。
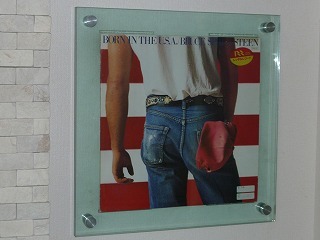
1984年発表の大ヒットアルバム、「Born in the USA」です。
今回、3枚アルバムを選ぶにあたって、2枚(待合室壁の2枚)は直ぐに決まりましたが、あと1枚は非常に悩みました・・・。
順当にいけば、「闇に吠える街」なんでしょうが、確かにダークネスツアーは最高なんですが、あまりに凄いライヴ音源を聴きすぎた為に?何かスタジオ作は物足りないんですよね。
内容的には、ブレイク前の昂揚感の感じられるセカンド作なんですが、やや冴えない髭面の大アップ(リヴァ―の精悍な顔つきとは大違い!)でちと医院にはそぐわない・・・・・。
という訳で、ベタすぎますがこれになりました。
このアルバムは高校当時、耳たこになる位聴きまくりましたので、抵抗感あったんですが、改めて聴いてみたら、やはり凄いアルバムでした。
アルバムは当然全米№1を独走したんですが、凄いのはシングルカットを何と7曲!も切り、しかも全てトップ10入り!という過剰人気ぶりでした。
しかし、最高位は「Dancing in the dark」の2位(4週連続!惜しい・・・)という所がボスらしい・・・・。
確かに、最初のシングル3枚・・・「Dancing in the dark」、「Cover me」、「Born in the USA」はシングルに相応しいナンバーですが、あとの4曲はLP収録曲、というレヴェルでして決して名曲!という訳ではないと思います。
とにかく稼げるうちに稼いだれ!ってなコロンビアレコードの思惑が手に取るように分かりますが、コレクターとしてはアイテムが多いことは嬉しいといえば嬉しいのですが・・・。
この後、1985年に出したライヴアルバムボックスは、シカゴも驚く何と5枚組!!それでも確かチャートの首位に立ったんですから、この時期の人気は凄まじかったですよねえ・・・。
このボックス、日本盤は7500円もしましたが、ボス狂の友人、牧君は発売日に買ってたなあ・・・・
続いては壁の2枚です。

やはり、ボス(Springsteenの愛称)といえば、この2枚でしょう・・・・。
先ずは出世作にして、ロック界を代表する名盤、1975年発表の「Born to run ~ 明日なき暴走」です。
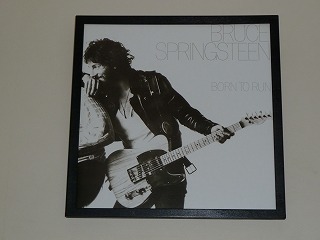
この、ボスがサックスのビッグマン~クラレンスクリモンスの肩にもたれてニヤけてる構図が最高ですね。
このフォトセッションで撮られた有名な写真に、ボスがテレキャスのネックに紐で繋いだスニーカーをひっかけてるものがあるんですが、あれもいつ見ても胸にグッとくるものがあります・・・。分かる方は分かってくださると思います・・・。
まあ、このアルバムはホント、神がかり的な出来栄えですね。ロックの神が降臨したのでしょうか・・・・。全ての曲が素晴らしいです。
冒頭の「Thunder Road」、哀愁あるボスのハーモニカからバンマス、ロイビタンのテンポ良いピアノが聞こえてきたら、もう他事はできません!全身全霊をかけてスピーカー(ヘッドフォン)に耳を傾けるしかありません!!
何てワクワクする曲なんでしょう・・・。歌詞の内容も素晴らしいものがあり、フィナーレまで息もつかせぬ展開に、フェードアウトが恨めしくなります・・・。
でも大丈夫、次の「Tenth avenue freeze out ~ 凍てついた10番街」も、負けず劣らずの名曲なんですから・・・・・・
ブレッカー兄弟やデヴィッドサンボーンらのシャープなホーンセクションの勇ましいリフに、これまた御機嫌なロイビタンの弾むピアノが乗っかって、非常にソウルフルな演奏ですが、これに絡むボスのヴォーカルが、これまたいかしてるんです!
まさに、「ガッツだぜ!」てな感じでして、トータス松本さんがカヴァーしたら、案外ハマるんじゃないかな?(余談ですが、トータス松本さんのサムクックのカヴァーアルバムは、ジャケットも含め最高でしたがな・・・・。)
3番の歌詞で、「big man joined the band・・・」ていうと、クラレンスがサックスをブオ~と鳴らすとこはライヴでも定番ですが、カッコいいですねえ、鳥肌立ってきます。
しかし、この曲に関しては、ライヴよりもこのスタジオヴァージョンの方が数段カッコいいと、個人的には思います。
やはり、サックス一本ではあのリフの厚みが出ないんですよね、仕方ありませんが・・・。
冒頭2曲の素晴らしさの余韻に浸っている暇なく始まる、疾走感溢れる「Night」に続いて、よく自伝のタイトルなんかに使われる、壮大な「Backstreets」でA面が終わります。
これだけでも、精神的には満足感満ち溢れているんですが、レコードをひっくり返してB面に針を落としましょう・・・。
B面一曲目は、タイトルトラックにしてSpringsteenの代名詞と言える超名曲、「Born to run ~ 明日なき暴走」です。
しかし、「走る為に生まれた」を「明日なき暴走」とつけた当時のCBSソニーのディレクターのセンスは最高です!素晴らしい感性の持ち主ですよ。
この曲に関しては、もう私があれこれ下手な講釈垂れるより、まず聴いて頂きたいです。何から何まで完璧な出来です!
よくぞこんな曲が書け、演奏でき、唄えたものです。1975年という時代がそうさせたんでしょうか?1974年でも1976年でもいけないような、そんな気がします。理由はうまくいえませんが・・・・・・。
リズミックな「She's the one」に続いて、ランディブレッカーの哀愁味溢れるトランペットが素晴らしい、「Meeting across the river」が始まります。
ロイビタンのジャジーなピアノは相変わらず素晴らしいですが、ベースはいつものギャリ―タレントではなく、ジャズ界の大物、リチャードデイヴィスが担当しております。
私はこの曲を聴くと、いつも夜のハドソン河のたもとで、ぽつんと膝を抱えて座っている自分の姿が浮かんできます。
行ったことありませんが・・・・・。
ニューヨークの闇、(ボスは故郷ニュージャージーから見たニューヨーク、というイメージで作ったのかしら?)を感じさせる渋い作品です。
さあ、そしてラストに控えしは、映画みたいな壮大なスケールで描かれる「Jungleland」です。
いつもこの曲を聴き終わると、あまりのスケールに来る日も来る日も同じような生活をしている自分が嫌になり、どこかへ逃避行したくなる、恐ろしい?曲です。
アルバム全編通して、やはりロイビタンのピアノが光ります。マックスワインバーグの、細身からは予想できないパワフルなドラムも最高です。もちろん古くからの盟友、ギャリ―タレントのベースや、圧倒的な存在感のビッグマン、クラレンスも凄い!
そして、これまた素晴らしい2枚組アルバム、1980年発表の「The River」です。
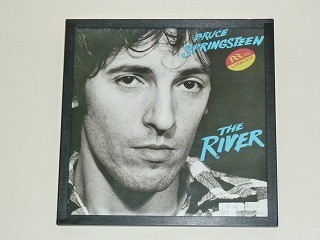
見てください、この精悍な顔付を・・・・。昔のハリウッドホラー映画なんかでよく使われた「お化け文字」のレタリングに負けない存在感です。
このアルバムは私がロックを聴き始めた1981年では、彼の「最新アルバム」でしたので、ほぼリアルタイムで聴いた事になります。
2枚組という事でかなりのヴォリュームがあります。確かに一枚目の方が質が高いのでシングルアルバムにしても良かったかもしれませんが、Led ZeppelinのPhisical Graffitiと同じで、「一枚にまとめるにはマテリアルが多すぎる、かと言ってボツにするのも惜しい・・・」
という感じだったんでしょうね。ただ、ボスはそういう曲がやたら多く、数多いスタジオアウトテイク集が存在してますね。
A面ド頭の「Ties that bind」はダークネスツアーでも披露されていた曲ですが、ここでのアレンジは最高です!12弦ギター?の音がキラキラしてます。
次のパーティー会場で歌われているような楽しげな「Sherry Darling」に続いて、硬派な「Jackson Cage」、畳み掛けるような「Two Hearts」、この4連続パンチにノックアウトされます!
B面一発目はこのアルバムで最も有名なヒット曲、「Hungry Heart」ですが、この曲は特にフィルスペクターの影を感じますね。
E Street Bandの厚みあるサウンドに、フロー&エディの変態チックなハイトーンコーラスが絡むと、正に「ウォールオブサウンド」ですね!
続く「Out in the street」はスプリングスティーン節というか、いかにも彼らしい曲調でして、ライヴでも人気の高い曲です。
そして、「Crush on you」、「You can look(better not touch)」のロックンロール2連続はかなりぶっ飛びます!
カッコいいの一言です。
特に後者は、アメリカ留学時代の私が常に心がけていたスローガン?でして、要は、金髪美人を見かけても、決して調子にのって手を出さない!という事でして、分かる方は分かって頂けると思うんです。
亜米利加に留学する若者は多いですが、東洋人女性は白人男性にモテますが、その逆は稀です。私も淡い幻想を抱いて乗り込みましたが、玉砕いたしまして身に染みて感じました・・・・・。
時代背景は違いますが、マッサンは凄いですよねえ。
さ、阿呆な話はこれ位にして、次にいきます。
B面最後はアルバムトラックにして、キャリアを代表する名曲、「The River」です。
もの悲しいハーモニカから始まり、ボスの淡々とした唄が次第に熱を帯びてバックの演奏と共に盛り上がっていく所は鳥肌が立ちます。
歌詞もとっても深いものがあります。デヴュー当初は第二のボブディラン、なんてキャッチフレーズだったんですよね。
素晴らしい一枚目に比べて、二枚目はちょっと散漫なイメージがあり、キーとなる曲がないように感じます。
歌詞がダイレクトに入ってくると大分違うんでしょうが、ミドルテンポのじっくり聞かせる曲が多くて、正直キャデラックランチ以外あまり印象に残らないんですよね・・・・・。マニアの方、失礼。
先日、とある所から、このアルバム(The River)の当初リリース予定だったが、諸事情で頓挫した一枚ものの音源を入手しましたが、う~ん、確かにすんなりシングルアルバムで出した方が良かったかも・・・と思わせる内容でした。
「院長のひとこと」を更新しました(2015/03/16)
今年は終戦70年なんですね。
おそらくこれからいろんな特集番組が組まれる事でしょうが、3月10日の東京大空襲については、知る限りでは殆ど素通りだったような気がします。
たった一晩で一国の首都が無差別に爆撃され、10万人以上もの非戦闘員が殺戮されたケースは世界史でも稀だと思います。
そんな悲惨な出来事も、時代の流れなのか、風化しつつあるようです。
しかし、それではいかん!と思います。
戦争に至ったどうしようもない国家事情はあったかもしれませんし、生き物は他を駆逐する本能がありますから、全く戦争が無くなる事はないでしょう。
軍人たちの戦闘は致し方ないものがあるかもしれません。
けれども、悲惨な状況に陥るのは、いつも非戦闘員である女性や子供たちなんですよね。
「院長のひとこと」にも書きましたが、早乙女勝元氏の「猫は生きている」という絵本を全ての子供は読むべきだと思います。
そうすれば、成長し、例え軍人になったとしても、民間人を爆撃するなどといった愚行は犯さない筈だと、強く信じたいです。
今月の壁レコード ~ トラフィック特集(2015/02/12)
毎日寒いですね!私は寒いのが苦手でして、この時期は憂鬱です。
ウインタースポーツもからっきしダメでして、恥ずかしながらスキーもスケートもろくに滑れません。
こういう寒い時には、イギリスのトラッド音楽なんかハマりますよね。
凍てつくスコットランドなんかの大平原が目に浮かんできます。
という訳で、久々にトラフィックの「ジョンバーレイコーンマストダイ」を聴いてみたら、改めてトラフィックの凄さを再認識しました。
やはりイギリスを代表するバンドですよね!
Steve WinwoodとDave Masonという、大物二人を輩出したバンドとして有名ですが、いぶし銀のJim Capaldiもお忘れなく!
先ずは玄関先です。
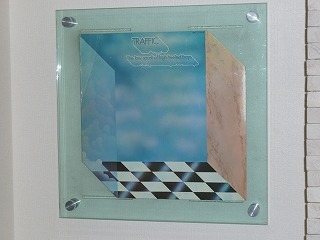
1971年発表の第二期トラフィックの個人的には一番好きなアルバム、「The low spark of the high-heeled boys」です。
私がこのアルバムを聴いたのは、ウインウッドが生涯最高?の(チャート上の)成功を収めていた1986年でした。
当時、飛ぶ鳥をも落とす勢いだったナイルロジャースのおかげで?初のヒットチャート№1ソング、「Higher Love」をものにしたSteve Winwoodですが、彼の凄い所は、全てをナイルに任せなかった所です。
全体のプロデュ―スは大物、ラスタイトルマンに任せたのが、流石何十年もショービズの先端で生きてきた彼ならではの慧眼であります。
先のヒット曲「ハイヤーラヴ」は、今聞くと流石にアレンジが時代を感じさせ、ウインウッドである必然性は無いように感じます。要は「ナイルロジャース印」の86年のヒット曲、でしかありません。
しかし、ラスタイトルマンが手掛けたナンバーは今でも鑑賞に堪えるんです。(エラソーにすみません・・・。)
当時高3でしたが、登下校時のウォ-クマンではへヴィーローテーションでして、当然彼の他のアルバムに興味が出てきます。
必然的にトラフィックに行き着く訳ですが、当時殆ど廃盤状態でして、中古レコード屋をハシゴして、やっと見つけたのが奇抜な変形ジャケットの本盤でした。
このアルバムは当時は「ダラダラしていて、レイドバックの悪い見本」みたいな低評価されてたみたいですが、いやいや、ジムゴードンとリックグレッチのリズム隊は熱いですよ~!
グレッチはBlind Faithからの付き合いでしょうが、ゴードンの合流はちょっと意外です。クラプトン繋がりなのか、デイヴメイスン繋がりなのか分かりませんが、相変わらず素晴らしいドラム叩いてます。
タイトル曲は確かに長すぎるというか、冗長な部分もありますが、ジムゴードンのドラムで救われます。後にマッスルショールズの名ドラマー、ロジャーホーキンスもライヴで叩いてますが、何か物足りないんですよね。
やはりジムゴードンは性格はともかく、(実はかなり凶暴で、クラプトンとの大喧嘩は有名な話ですし、後に殺人事件を起こし、確か未だに服役中)ドラムに関しては天下一品です。私のフェイバリットドラマーの一人です。
あと、大好きな曲が2つあります。
先ずは、ジムキャパルデイの才能が開花した、「Light up or leave me alone」です。邦題は「なんとかしてくれ、さもなきゃほっといてくれ」と、直訳ですが、何ともカッコ悪いものです。
これは意外に甲高いジムのヴォーカル、なかなかファンキーなリックグレッチのベース、貫録のゴードンのドラム、鋭角的なウィンウッドのギターソロが最高なナンバーでして、数年前、軽音楽部のOB会でカヴァーしました!
もう一曲は抒情性高い、如何にも彼等らしい佳曲、「Many a mile to freedam」です。
これは、ウインウッドの憂いのあるヴォーカル、クリスウッドの幻想的なフルートが素晴らしい出来でして、まさにトラフィックでしか作りえない音ですね。
やはり、トラフィックの肝はクリスウッドの管楽器であった事は、クリス死後に再結成された「第3期」トラフィックの音が全く個性的でなかった事に集約されています。
お次は待合室壁です。

先ずは第一期トラフィックの名盤、1968年発表の「Traffic」です。Dave Masonが眠そうな目をしてる写真を選んだのはアイランドレコード社長、クリスブラックウェルの意地悪なんですかねえ。
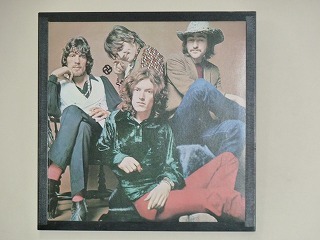
このアルバムではウインウッドとメイスンはほぼ対等な力関係の様ですね。ロック名曲100選にも必ず取り上げられる、「Feelin' Alright」など、メイスンの貢献度はかなりのものがあります。
このアルバムは殆ど捨て曲が無く、ロックファンならグイグイ引き込まれてしまう名盤です。
このアルバムのイギリスオリジナルのモノ盤が欲しいんですが、高くて手が出ない・・・というより、特殊ジャケットの為か、美品がまず市場に出てきませんね・・・・・・。
そして、最後にウインウッドのキャリア上、最も重要な作品(と私は思います)である超名盤!「John Barleycorn must die」です。
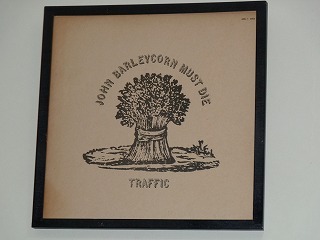
これはかなり売れたようで、中古盤市場には良く出てきます。
これこそ、ブリティッシュロックを代表する超名盤です。A面冒頭のインスト「Glad」から次の「Freedom Rider」へ繋がる所なんざあ、何度聴いても背筋がゾクゾクしますね。
謹賀新年 今月の壁レコード ~ 羊特集!(2015/01/13)
遅くなりましたが、皆様明けましておめでとうございます。
本年もこれまで通りよろしくお願い申し上げます。
今年は未年、という訳で「ひつじ」ジャケットを、と思っていろいろ思案しましたが、なかなか無いんですよね。
まず、誰もが挙げるのは、ポール&リンダマッカートニーの「ラム」ですが、その他はなかなか浮かびません。
ネットで検索してみますと、10CCのルックヒア!なんてありますが、私このアルバム、昔売り払ってしまったんです。
他に、後にフォリナーで名を馳せるルーグラムのいた「Black Sheep」なんてバンドもありましたが、残念ながら、ジャケットに羊は出てこないんです・・・。
あと、ピンクフロイドの「アニマルズ」に、「sheep」という曲がありますが、ジャケットはあのバターシ―発電所ですしねえ・・・。
ニュージーランド、という点から、Split Endzなんて手もありましたが、ちょっと通すぎる・・・。
という訳で、困った時のポール様・・・・という訳で3枚ともポールマッカートニー関連にしちゃいました。
先ずは玄関先です。
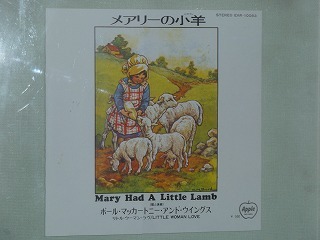
ビートルズ解散後の1972年に発表されたシングルで、「メアリーの子羊」です。
この前のシングルが、「アイルランドに平和を」という、ジョンを意識したのか、珍しく政治的な歌詞で放送禁止になってしまいました。
その反動か、この曲は幼稚園で歌われるような童謡調になっております。
凄いのは、こんな(失礼!)曲でも当時のイギリスのシングルチャートで9位になっているんですね。やはり大物です。
ポールって本当に何でも屋さんでして、「ヘルタースケルター」みたいなへヴィな曲も書けば、「ハニーパイ」みたいなヴォ―ドヴィル調の懐古的な曲も得意だし、今回のようなメルヘンチックな童謡もさらっと書き上げます。
やはり「ス・ゴ・イ・ネ!」(コンサートでよくこういうんですよ・・・・。)
続いて待合室壁です。

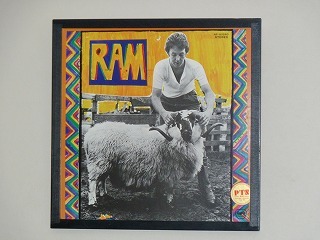
1971年発表の妻君リンダさんとの連名アルバム、「ラム」です。リリース当時はあまり良い評価されなかったようですが、流石にチャートでは首位を2週獲ってます。
確かに、ゴッタ煮的要素が強く、良く言われてる事ですが、自らのプロデュースでは詰めが甘いんですよね。
良い曲もあるんだから、George Martinにお願いすれば良かったのに・・・とも思います。
羊の角を掴んでいるジャケット写真は後にジョンレノンが「イマジン」のアルバムのおまけカードで、悪意を持ってパロディにしました。(豚を捕まえてニヤニヤしてる図)
おまけに収録曲「How do you sleep?」では、強烈にポールをこきおろしており、聴くのが辛い・・・・・。
因みに、タイトルの意味は、ポールの目があまりにギョロ目なので、「そんなにデカくちゃ寝る時にしっかり閉じないだろ、そんなんで眠れるのかい?」という、いかにも意地悪ジョンが言いそうなフレーズですね。
あと、リンダさんについて書きたいと思いますが、まだまだこのアルバム辺りでは彼女の音楽的な貢献というのは感じられませんね。まあ、ポールに対する精神的な支柱、という貢献度は計り知れないものがあったと思います。
もともとはプロのカメラウーマン(性差別的表現に当たるならば、カメラマン)だったリンダさん、当初は裏方稼業らしく、どちらかというとサバサバした姉さん女房的なイメージだったんですが、ショービズのライトが当たる側に回ってからはどんどん洗練され、美人になっていきますよね。
昨年のポールの病気ドタキャン騒ぎも、リンダさんが生きてれば手綱をしっかり握ってあそこまで酷くならなかったんじゃあないかしら?なんて考えたくなります。
そして最後は、「ラム」のアルバムをオーケストラで再現した名盤「スリリントン」です。
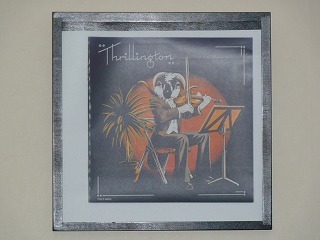
このアルバムはなかなかレアで、オークションでもかなりの値がついておりますので、私は再発CDでしか持っておりません。よって、拡大コピーを飾りました。お許しください・・・。
今月の壁レコード ~ クリスマス特集(2014/12/18)
うかうかしているうちに師走も半ばを過ぎてしまいました。
本日は特に寒く、ここ岡崎でも降雪があり、日本中に大寒波が到来してる現状を痛感させられます。
さて、12月はどうしてもこうなってしまいますが、時期的に外せないので例年の如く、クリスマスアルバムを並べてみました。
先ずは玄関先です。
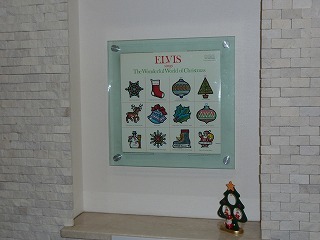
エルビスプレスリーのいくつかあるクリスマスアルバムの一つです。
「Elvis sings the wonderful world of christmas」です。
1971年にリリースされた、ナッシュビルにて録音された作品です。
ジャケットが可愛らしいので、子供さんにうけるかな?と思って飾りましたが、
本当は1957年の絶頂期に発売された「Elvis Christmas Album」の方を愛聴しております。
その「エルヴィスクリスマスアルバム」ですが、初めて聴いたのは、1985年にリリースされた国内盤でした。
この時の再発盤はアメリカで発売されたグリーンカラーレコードを直輸入して解説兼帯を付けたものでしたが、この時の萩原健太さんのライナーは最高でした!
これまでに沢山のライナーを読んできましたが、内容といい、洒脱な文章といい、非の打ちどころの無い素晴らしいライナーでした。
今でも、時折無性に読み返したくなる名ライナーです。
知らない方の為に、あらすじを記します。
曰く、氏が東京は水道橋のとある中古レコード店(トニイレコードか?)にふらっと立ち寄った所、このレコードのアメリカ盤オリジナルを発見したそうな。
これはめっけもん!と色めきたったものの、オリジナルだけに値段は法外、状態はイマイチ・・・。
どうしようかな?と葛藤しながらおもむろにジャケットを裏返すと・・・・。
エルヴィスのにこやかなポートレイトの肩のあたりに、「To Debby with love」と落書き?があったそうな。
大体、この手の落書きはジャケットの価値を著しく下げるので、普通は敬遠するのですが、ロマンチストな健太さんは違います。
「これはアメリカのとある田舎町で、少年がガールフレンドのデビーちゃんへ贈ったプレゼントに違いない。
そんな初々しいパピーラヴの象徴だった筈のレコードなのに、無情にも中古屋へ売り飛ばされてしまい、紆余曲折を経て、
何の因果か東京の中古屋で俺に買われるのを待っていた!」
という訳で氏はそのレコードを抱きかかえながらレジに向かうのであります。
何枚か万札が飛んで行ったそうです。まあ、キズ多く、ジャケ不良なので、いいとこ2~3万かとは思いますが、確かにこのレコードは見ないですねえ。
長々とすみません。
お次は待合壁です。

まずは1987年発売の、キースへリングのアートワークが印象的なオムニバスアルバム
「The very special christmas」です。
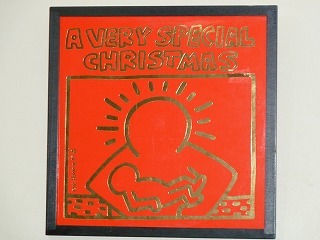
このアルバムは当時の人気アーティストが一曲ずつクリスマスソングを披露するもので、素晴らしい内容です。
大物ばかりですが、特にWhitney Houston, Bruce Springsteen, Stevie Nicks Chrissie Hynde(Pretenders)の唄は最高です。
因みに、私はキースへリング大好きでして、現在医院の内部にも彼の作品を飾っていますよ。

この雑然感が最高ですよね。
そしてもう一枚はこれです。
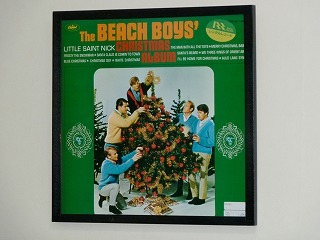
1964年の全盛期に発売された、「Beach Boys Christmas Album」です。
やはり、こういうクリスマスソングって教会で賛美歌として歌われる事が多いので、彼らの素晴らしいハーモニーで聴くと、ハマりますね。
冒頭の「Little Saint nick」はノリの良い佳曲ですが、現在ではクリスマススタンダードになってるんですね、すごいな。
今月の壁レコード ~ 追悼ジャックブルース特集(2014/11/06)
11月になりました。しかし、季節外れの台風の話が天気予報で出てくるなど、まだそれほど肌寒くはないですね。
やはり、秋はこれくらいでいいですね。一年で最も快適な季節だと思います。
さて、今月の壁レコードは、先日お亡くなりになった、Jack Bruceさんに因んで、クリームの名盤を飾ってみました。
Jack Bruce氏は今年の10月25日、71歳で死去されました。
ここんところ、目立ったニュースはあまり聞かれず、9年前のクリーム再結成ライヴで久々に存在感を示した程度でしたよね。
彼は長いキャリアを持った名ベーシストであり、名ヴォ―カリストでしたが、やはり最も輝いていたのは、Cream時代だったと思います。
クリームはエリッククラプトン、ジャックブルース、ジンジャーベイカーという優れた3人のミュージシャンが集まったスーパーグループの走りでした。
純粋なオリジナルアルバムとしては、たった3枚しか残していませんが、挨拶回りみたいな一枚目はともかく、2枚目、3枚目はロック史に残る名盤です。
先ずは玄関先です。
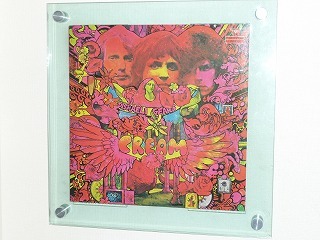
1967年発表の傑作セカンドアルバム、「Disraeli Gears」です。
原題は、何でも誰かが自転車の変則ギアーの事を言い間違え、その言葉の語感が面白くてつけた、みたいな事が雑誌に書いてありました。
当然、我々日本人には何のこっちゃ?という訳で、邦題は見たまんま、「カラフルクリーム」でした。
このアルバム、壁に飾ってあるのは当然、安い国内盤の中古ですので、なんかゴチャゴチャしてますが、
イギリスオリジナル盤は色も写真も超鮮明で、おまけにラミネートされてますので、全然雰囲気が違って見えます。
このレコードに限った話ではありませんが、やはりオリジナル盤はジャケットの質、レコードの音も全然違います。
まあ、オークションのおかげで昔ほど探すのに苦労しなくなりましたが、やはりそこそこの値段はしますが、ジャズやクラシックに比べればまだロックのレコードは安いほうです・・・・。
内容は、私はこのレコードはジャックブルースの良さが存分に出ていると思います。
まだクラプトンは唄に自信が持ててない時期なので、余計にジャックの朗々たる逞しい歌声に魅了されます。
クラプトンの十八番になってしまった感のある、名曲「Sunshine of your love」は勿論ですが、クラプトンのワウワウギター炸裂の「英雄ユリシーズ」、桑田圭祐さんも嬉々としてカヴァーしていた、軽快な「スウラバー」、サイケ調な名曲「ストレンジブルー」、クラプトンが一生懸命?歌う「苦しみの世界」など、良い曲ばかりです。
また、A面の最後は、ジンジャーベイカー作、唄の何とも気怠い「Blue Condition」、B面の最後は3人のおふざけアカペラ「Mother's Lament」でニンマリさせる所は、やはり辣腕プロデューサー、フェリックス パパラルディのセンスでしょうねえ。
後に、クリームスタイルのハードロックトリオ、「マウンテン」を結成するフェリックスですが、後に日本のロックバンド、「クリエイション」と関係を深めた事で、我が国のロックファンには非常に馴染みの深い方ですよね。
そして中待合の2枚です。

純粋なオリジナルとしては最後となった(Goodbye Creamは微妙な所ですが、やはり解散後のアルバムですよね・・・)3枚目のアルバム、「Wheels of fire」です。
これは一枚目はスタジオ録音の新作、二枚目はフィルモアでのライヴ録音の二枚組でリリースされましたが、当時、二枚組では売れぬと判断した?日本グラモフォン社は、銀と金のジャケットに分けてバラ売りしたんですよ!
今となっては貴重なその二枚を飾ってみました。
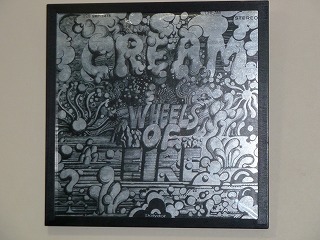
まずは正規での銀色にて発売された一枚目の方です。
これはジャックブルースとフェリックスパパラルディの二人の才能がまさにスパークした芸術作品であります。
クラプトンもギタープレイでは素晴らしいところを見せ付けますが、ヴォーカルは殆ど目立ちません。そんなところも解散の引き金になったんでしょうね。
一般的には、ライヴで三人それぞれがエゴの塊となり、殴り合いの喧嘩のような凄まじい演奏に疲れ果てたから・・・と言われてますが・・・。
さて、冒頭の「White Room」は、作詞家ピートブラウンと共に作り上げた、ジャックブルースの最高傑作だと思います。
ワウワウを利かせたクラプトンのギターも最高ですが、やはりこの曲の肝はジャックの朗々たる歌声でしょうね。
だから、クラプトンが自分のライヴの定番で取り上げるのはまあ、ギタープレイの面からはいいのですが、リードヴォーカルを執るのはなんか違和感ありましたね。途中高音をネイサンイーストに任せるのも何だかなあ・・・。
私的にはA面二曲目の渋いブルース、「Sitting on top of the world」がこれまたジャックのヴォーカルが素晴らしくて大好きです。ここまではブルースロック的な側面ですが、ここからがちょっと凄いんです。
三曲目の「Passing the time」から四曲目の「As you said」にかけての流れは、何だか危ないクスリの匂いが漂ってきて、うっかりしてるとどこぞの世界に連れて行かれそうで怖いですね。
昔、中学生の時はあまりの怖さに特に四曲目は泣きながら聴いていました・・・。(嘘です)
B面はどちらかというとブルースっぽい側面が強調され、これまたジャックの名曲「Politician」「Deseeted cities of the heart」はカッコいいですね。
また、ブルーズの名曲、「Born under a bad sign」を演ってるのは、多分クラプトンのアイディアでしょうが、この時期にしか書けない曲があったのでしょうから、何のヒネリのない淡々とした演奏する位なら、オリジナルを入れて欲しかったですね。
さあ、そして誰もが認めるクラプトンの神がかったプレイが片面で聴ける、「金盤~ライヴサイド」です。
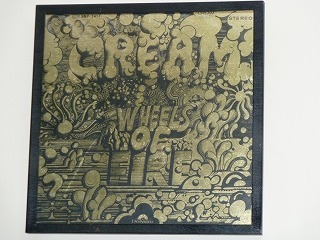
冒頭のRobert Johnsonのカヴァー、「Crossroads」では、クラプトンの独壇場でして、ヴォーカルも彼が執り、ものの本によれば「完璧」なギタープレイを繰り広げています。
確かに、二回あるギターソロはそれぞれとんでもなく素晴らしく、ギターを弾けない私でもエアーギターをついしてしまう程、情念的なプレイです。
勿論、ジャックブルースのブンブンベースも凄いし、ジンジャーベイカーも軽めですが、なかなかシャープなドラムを聴かせてくれます。
今月の壁レコード ~ CSN(&Y)特集(2014/09/30)
もう10月、というのに朝晩はともかく、昼間は暑い日が続きますね。
御嶽山の噴火があったり、異常気象も多い昨今ですが、自然が牙を剥くと人間なんて如何に弱い存在なのか、と改めて思い知らされます。
さて、今回の壁ジャケットは、あの幻の1974年再結成ツアーの正規リリースが(マニアの間では?)大好評のアメリカを代表するグループ、CSN(&Y)を特集してみました。
まずは玄関先です。

1974年発売のベストアルバム、「So Far」です。味のあるイラストは彼等とは縁深い、Joni Mitchel女史の手によるものです。
このアルバムは先ほど触れた1974年の再結成ツアー後、ニューアルバム作成に取り掛かるも、頓挫してしまったお詫び?に発売されたものですが、当時の人気を象徴するかの如く、チャートの一位に上り詰めています。
確かに、このアルバムはジャケット、選曲、曲順に相当気合いが入って作られており、入門者はこれ1枚で大丈夫ですね・・・。因みに私もここから入ったクチです。
中学生の時、当時岡崎にあった「モンキーパンチ」という、輸入盤ばっかり、何と海賊盤までも置いてあった恐るべし?貸しレコード屋でアメリカ盤をレンタルしてマクセルのUD46にせっせとダビングしたものです。
話題がそれますが、この「モンキーパンチ」は、多分どこかの輸入盤屋さんの在庫をそっくりレンタルへ転化したんでしょうね。今思うと、すんごくマニアックな貸しレコード屋さんでした。
(借りる時は店のカウンターで、一枚一枚検盤をして、キズの有無を申請する!という七面倒くさいやり方でしたが、あれでレコードの扱い方を覚えた気がします。)
「レイコウ堂」とか「フカツ」みたいなチェーン店では絶対に置いてないような、Doorsの「13」とか、CCRの「1970」という編集盤や、ザバンドの「南十字星」やボブディランの「プラネットウェイヴス」のアメリカ盤、はたまたZEPPELINやStonesの膨大なブートレッグ!!
当時、中学生がブートレッグなんて知る由もないので、「何か変なジャケットだなあ、曲は知ってるけど、これって誰かが勝手に作った編集盤なんじゃないかな?」なんて思い、手が伸びませんでした。
流石に中学校3年になると、そのへんの事が分かってきて、一番ジャケットがまともだった「Bonzo's last ever gig in Berlin 1980」という海賊盤を借りてみましたが、モコモコした音にびっくりし、「騙された!」と憤慨し、二度とブートは借りませんでした。
今思うと、もっと沢山借りておけばよかったなあ、と後悔しきりです。
最初に「デストロイヤー」とか借りてれば、人生変わったかもしれませんね・・・・・。*注釈「デストロイヤー」とは、Led Zeppelinの1977年米オハイオ州クリーヴランドでの演奏を収めた海賊盤で、演奏内容はともかく、音はオフィシャル級であり、定番中の定番であります!
その名店、「モンキーパンチ」ですが、あまり国内盤新譜を入れてくれなかったものですから、ついつい他のチェーン店を利用するようになってしまい、気付いたらつぶれてました・・・・。
あの在庫、どうしたんだろう?ジャケットに直にシールを貼って、キズの有無を書き込んでいくので、多分中古屋には売れないですよねえ・・・・。おそらく殆どが廃棄されたんでしょう・・・。残念です。
長々と同世代の岡崎市民以外にはどうでもいい話、申し訳ありませんでした。
さて、ジャケットを描いたジョニミッチェル女史ですが、彼女は、もともとはDavid Crosbyのガールフレンドだったんですよ。何度となく他のメンバーと顔を合わせるうちに、一番ハンサムなGraham Nashと付き合うようになっていくんですよね。
その蜜月を歌ったのが、「デジャヴ」に収められた「Our House~僕たちの家」なんですねえ。クロスビーはどんな思いでコーラスを付けたんでしょう・・・・?
ただ、そんな下世話な勘繰りは当人たちには全く見当外れのようで、どうもミュージシャンの恋愛概念というのは我々凡人には窺い知れないものがあります。
あまり一人の異性に執着しない割には、激しい恋愛の唄を情念込めて歌うんですよねえ・・・・・。よくわかりません!!
気を取り直しまして、院内にまいりましょう。

CSN(&Y)としては、まずはこの2枚です。
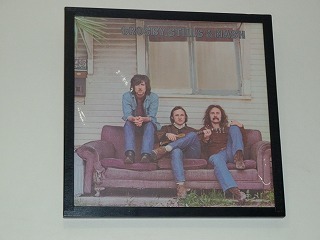
1969年のデヴューアルバム、「Crosby、 Stills & Nash」です。
今更ながらですが、説明しますと、元バーズのDavid Crosby、元バッファロースプリングフィールドのStephan Stills、元ホリーズのGraham Nashの3人が集まったシンガーソングライターの集合体です。
当時は「スーパーグループ」と持て囃され、ものすごい人気だったそうです。
ただ、このアルバムはそんな期待感を持って気合い入れて聴くと、肩透かしを食らわされる程、リラックスして作られていますね。
冒頭の「組曲:青い目のジュディ」は代表曲とも言える名曲でして、3人三様のヴォーカルが複雑でいて、決して乱れぬ美しいハーモニーを形成し、夢心地のような時間を作り出しています。
続くグラハムナッシュらしさ満載の「マラケッシュ行き急行」はソフトボッサ的な展開がオシャレですね。クラブ世代にも人気だとか・・・・。(クラブのイントネーションはラですよ!念のため)
そして、もう一枚。
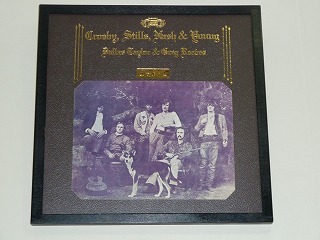
これぞ60年代アメリカンロックの最高峰、CSNの3人に、ニールヤングが加わった、CSN&Yの超名盤!「デジャヴ」です。
当然の事ながら、チャートの一位を独走。収録されている曲も個々のキャリアを通じてもベスト!ではないかという名曲が満載です。
特にA面は、恐ろしい程の完成度の高さでして、B面2曲目のグラハムナッシュの最高傑作(と私は思う)、「僕達の家」までは弛緩する事が全くありません。(B面3曲目からあとは、やや完成度が落ちるのが残念です。)
ニールヤングが加わった事で、ライヴァルのStillsも本気出したのか、唄、ギターともに神がかってますよね。
この二人のギターバトルはライヴでは凄かったようで、のちに出したライヴアルバム「4 way street」でも、「サザンマン」なんかで鳥肌の立つ名演を繰り広げてますね。
グラハムナッシュは彼らしい、ジェントルな2曲の傑作、「Teach your children」「Our House」をものにし、デヴィッドクロスビーも緊張感漂う2曲、「Almost Cut my hair」、タイトルトラックの「Deja Vu」をものにしてます。
このアルバムは私はアメリカオリジナル、イギリスオリジナル、日本初盤、とかなりコレクションしてます。やはりアメリカ初版は写真の精度がダントツで、ジャケットの作りも豪華金の型押しで頬ずりしたくなりますね。
今月の壁レコード ~ ビートルズ「A Hard Days Night」特集!(2014/08/29)
暑かった8月も終わってしまいますね。
今月の壁レコードですが、「院長のひとこと」で予告した通り、先日ブルーレイで新装発売されたBeatlesの初主演映画「A Hard Days Night」を特集してみました。
8月15日夜に一回だけ映画館でリバイバル上映がありまして、いそいそと独りで出かけて参りました。満員かな?と思ってましたが、5~6割程度の入りで丁度良かったです。
同じような境遇(家族を誘っても断られ、映画館に行く程の熱狂的なファンの知り合いも捕まらない・・・)とみえるオッサンの一人客が殆どでした。
映画の話は後程たっぷり・・・という訳でまずは玄関先です。
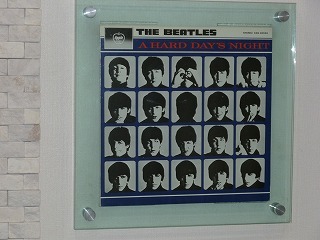
1964年発表のサードアルバム「A Hard Days Night」です。
ビートルズについては下手な事は書けませんので、私感、という事でお読み頂ければ幸いです。
このアルバムは初期の最高傑作だと思います。全てオリジナル曲で固めた最初のアルバムだし、特にジョンレノンの最もいい部分が炸裂していますよね。
ビートルズのオリジナル曲はジョージ、リンゴの単発以外は、確かインストの「Flying」を除いてはみんな「Lennon/McCartney」のクレジットですよね。
確かに極初期は対等に共作してたんでしょうが、やはり聴きこむと、これはどちらがメインの曲かが分かってきますよね。
後期になると、クレジットは形だけで、てんで勝手バラバラに作ってますけどねえ・・・・・。版権の問題なんでしょうが・・・・・。
多分、完全ポール主体なのは「And I Love Her」、「Can't buy me love」、「Things we said today」の3曲でしょうね。
美しい、それでいて彼等でしか成し得ない凝った曲展開の「If I fell」、「I'll be back」はジョン、ポールが対等に作ったのではないでしょうか。
後はジョンの独壇場でしょうね。ヴォーカルをジョージが執る「I'm happy just to dance with you」もどう聴いてもジョンの作風ですよね。
印象的なギターのコード音で始まるタイトル曲なんぞ、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いが充満してますね。一音として無駄が無い・・・・・。冒頭の「dog」と「log」で韻を踏むとこが洒落てますねえ。
2曲目の「I should have known better」はジョンレノン節炸裂の、個人的にはアルバム中のベストトラックです。何でこんな素敵な曲が書けるんでしょうか・・・・?
という風に、一曲ずつレヴューしていくと、えらいことになってしまいますので、ちょこちょこコメントさせて頂く事にしますね。
6曲目の「Tell me why」も威勢の良いジョンのヴォーカルが素晴らしい曲ですが、この曲は昔良く上の子供を連れて行った、名古屋の熱田プールの休憩時間にかかってまして、選曲のセンスにニンマリしてました。
A面ラストの「Can't buy me love」は、昔通好みのUKバンド、「Squeeze」の(確か)’92年名古屋公演のアンコールでグレンティルブルックがノリノリで歌ってたシーンが目に浮かんできます。いやあ、あのライヴは最高でした。
B面一曲目の「Any time at all」はサザンの桑田さんの変名バンド、「嘉門雄三&Victor Wheels」の白熱のライヴアルバムでの演奏を思い出します。中古盤屋さんでは割と見かけるので、結構売れたに違いありません。
是非とも完全版(小林克也さん以外の変なMCは要らん!)でCD化して頂きたいです。
10曲めの「Things we said today」はこのアルバムでのポールの最高作でしょうね。この曲を生で聴けなかったのが今年上半期の心残りです。
11曲目の「When I get home」と次の「You can't do that」は地味な曲ではありますが、これぞジョンレノン!といった鯔背な歌い方はファンにはたまらない曲です。
そしてそして、しんがりの「I'll be back」ですが、この曲はあまり有名ではありませんが、完成度としてはアルバム中一番の傑作だと思います。
冒頭からジョンとポールのハモリが美しすぎます!途中ジョンだけになるとこもなんか男の哀愁を感じさせますし、ブリッジに至ってはよくこんな展開考えつくなあ、と只々彼らの才能に感服してしまいます。
本当に素晴らしい曲ですが、シングルにもならずにポツンとアルバムに埋もれて?います。彼等にはこんな曲だらけです。「赤盤」「青盤」だけでは彼等の本質は解りませんよ!
な~んて、エラそうにすみません。
ではお次はこちらです。

まずは当時の国内盤ですが、ジャケットが差し替えられてるんですよ。
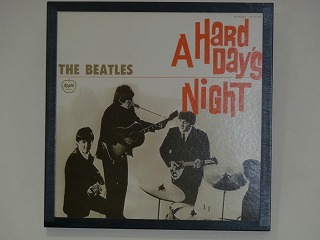
これは先々月号の「レコードコレクターズ」誌にありましたが、当時の東芝レコードの担当ディレクターだった高嶋氏のアイディアだったようですね。
因みに、美人毒舌?ヴァイオリニスト、高嶋ちさ子さん(実は結構好きなんです)のお父さんでもあります。
そして、最後は映画のレーザーディスクです。
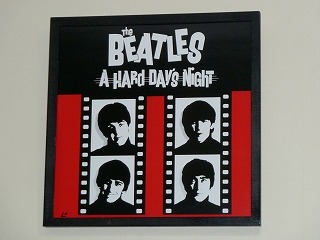
実は私、この映画を全編通して観たのは今回が初めてでした・・・・・自他ともに認めるビートルズマニアのくせに、とんでもないですよね。
演奏シーンは何度かあるんですが・・・・・。
今回は映画館でしたので、集中して彼等の演技にも見入ることができました。
感想ですが、やはりこの頃はまだ「遠慮」しているなあ、という感じでした。本来はロックンローラーで豪快な彼等が「アイドル」を演じさせられている、という感じです。
他の3人のセリフが「言わされてる」感が強い中(特にジョージ)、ジョンだけは、立て板に水、というかいつもこんなんだろうな、という感じのウイットに富んだセリフ回しが流石です。
やはり、初期ビートルズはジョンレノンあってのバンドでしたねえ。
4人がホテルから抜け出して地元のクラブ?で発散するシーンなんかは、はしゃぎ踊るジョージとリンゴと、女性を侍らせ酒をあおるジョンとポールの対比が面白かったです。
まさに力関係を表しているようです。
終始気になったのは、リンゴの酷い?扱われ様です。
彼は身長173センチでして、178センチの他の3人と比べて確かに見劣りしますが、「チビ」はないと思います。しかし、イギリス人的にはそうなんでしょうね。
事あるごとに「チビ、チビ」と言われて可哀そうでした。
あと、「デカ鼻」です。
確かに、デフォルメされると例外なく鼻がダンゴッ鼻ででかく描かれてますが、The Whoの Pete Townshendや、女優のBarbra Streisandなんかに比べれば全然問題ないんじゃあ・・・。
ただ、先の二人の鼻が鼻筋の通り過ぎた、シェイプとしてのでかさであるのに対し、リンゴのそれは団子っ鼻で固まりとしてデカい、という点で大きく異なります。
その辺りがツッコまれてしまうのかも知れません。
本人も十分自覚して?おり、街中で一般人に小馬鹿にされてもメゲるどころか、全くスルーしてるのが映画とはいえ凄いですねえ。
そんな本国での扱われように、高嶋さんも影響されたのか、「This Boy~リンゴのテーマ」のシングル盤では「こいつ」扱いですからねえ・・・・・・。酷いもんです。
今月の壁レコード ~ Led Zeppelin特集その1(2014/07/31)
いよいよ夏本番!といった感じで、毎日うだるような暑さです。
屋外で作業されている皆様、熱中症にご注意くださいね。
さて、今月はどうせ暑いのなら、”熱い”ハードロックは如何?という訳で、前々から特集してみたかったLed Zeppelinでいってみます。
最近、最初の1枚から3枚のアルバムが、ジミーペイジ監修の下に、デラックスエディションで再発売され、ちょっとしたZeppブームでしたよね。
私も勿論買いましたが、本屋に行っても、音楽コーナーに彼らの特集本が沢山出ていて、嬉しくなりました。
それではまず玄関先から・・・
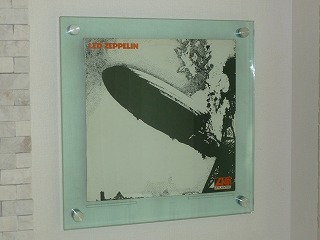
記念すべきファーストアルバムです。
これのイギリスオリジナル盤は「ターコイズブルー」のレタリングにて、マトリックスの修正のない「完全」オリジナルは高すぎて手がでません。というか、まず店頭には出てこないでしょうね。オークションでたまに見かける位です。
これはセカンドプレスにて、日本盤と同じオレンジのレタリングのものです。
内容は、その後のアルバム群と比べると、やはりまだまだ完成度が低い感じがしますが、それは後追いの感想であって、リリース当時は、かなりの衝撃度だったでしょうね。
既に、ジミーペイジとジョンポールジョーンズはセッションマンとして、かなり有名だったですし、そもそもジミーが参加していた後期ヤードバーズが発展解散して出来たバンドですから、ポッと出の新人バンドではないんです。
どうしても、「Good Times Bad Times」、「Communication Breakdown」ばかり聴いてしまいますが、他の曲も、勿論悪くはありません・・・・・
でも、「You shook me」は、Jeff Beck Groupの演っている方がカッコいいし、「Dazed and confused」はライヴでの凄さを知ってるだけに、やはり物足りないです。
まあ、彼等の真骨頂は調子に乗れば4時間も5時間も演った?というライヴに表れてますので、初期のスタジオ盤は、「俺たち、こんな感じの曲演ってま~す!」っていう「メニュー表」のようなものなんですけどね・・・・・。
続いて待合の2枚です。

先ずは初の全米チャートナンバー1を獲得した、個人的には一番好きなアルバム「Led Zeppelin2」です。
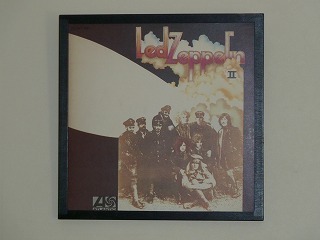
これは星の数ほどあるロックアルバムの中でも、ロックの本質を体現しているという点では、ナンバー1と言えるのではないでしょうか?
うまく言えませんが、評論家並に音楽を聴いてきたと自負できる私の中でも、このアルバムは別格です。
初めて聴いたのは、中学2年の夏休みでして、当時ロックの名盤選の本に載っているアルバムを片っ端からレンタルレコードで借りてきては、テープに落として聴きこんでいたんですよ。
ビートルズはほぼ制覇して、次に触手の伸びた大物ロックグループが彼等でして、その中でも一番評価の高かったセカンドアルバムを聴いてみたんです。
何か、ハンマーで殴られたみたいに感性を揺さぶられましたね。それからしばらくは一日中バカみたいに聴いてましたね。
当時、ツアーに明け暮れていた彼等ですので、じっくり腰を据えてレコーディングなんて到底無理なので、あちこちのスタジオで録音したマテリアルを、ジミーペイジやエディクレーマーが巧みに編集したんでしょうね。
でも、流石ノリに乗っている若き彼等ですね、素晴らしい統一感に溢れてます。
これぞハードロック!というカッコいい曲、演奏が次から次へと飛び出してきますが、やはり白眉は「Whole Lotta Love」、「What is and what should never be」、「Lemon Song」と続くA面の3連発でしょうね。
特に、「レモンソング」のめくるめく展開!ボンゾのドラムも絶好調です。素晴らしいです・・・。
ボンゾといえば、こないだ外来で、若い如何にもロック好きそうな青年が、ジョンボーナムのプリントされたTシャツを着てたんで、我慢できずに診察して病状説明した後で、「Tシャツかっこいいね!」とツッコミ入れてしまいました。
その青年も「よくぞ突っ込んでくれました!」みたいな嬉しそうな顔だったので良かったですが、次の日に来たストーンズのべろマークのTシャツを着たおばちゃん(!!)に突っ込んだら、無反応でがっかりしました・・・。
ストーンズのべろマークは有名過ぎるので、ファンでなくても着てる人多いですよねえ。チャーリーワッツのドラム粋だねえ、なんて言っても通じないんでしょうが、せめてミックやキース位は知ってから着て欲しいです、マジで。
話が逸れました。
ここでマニアックな話を少々・・・。
このアルバムのイギリス初期のプレスではB面2曲目の「Living Loving maid」が、何故か「Living Loving Wreck」になっているんですよ!
どうもDeep Purpleが少し前に「Loving Wreck」という曲を出してたから間違えた、という説が正しいようですが、結構この時代のロックアルバムのクレジットはいい加減な事が多いですよね。
その辺も我々コレクター泣かせなんですが、やはり集めがいがあります。
そしてもう一枚!
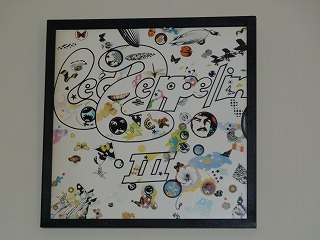
これまた全米アルバムチャート1位を獲得した3枚目、「Led Zeppelin3」です。
ジャケット表面はくるくる回してのぞき穴からいろんな模様や写真が見えるという、凝ってるというか、バカバカしいというか、兎に角、金をかけたジャケットです。この辺りから彼らはジャケットに凝るようになっていくんですね。
Zeppelinの4人の中では誰が一番好き?といった論争?はあまり聞きません・・・。やはり圧倒的にジミーが人気なんでしょうからねえ・・・。パーシ―(ロバートプラントの愛称)は、解散後評価を下げましたから・・・。ビートルズならジョンやポール、ジョージは結構分かれると思うんです。(リンゴさん失礼!)
私はゼップの中では断然ボンゾですね。(因みにビートルズでは昔はジョージ派でしたが、最近はやはりポールが一番好きになりました・・・。)
という訳で、円盤はボンゾの顔が見える所で止めてあります・・・。
Sonny Rollins特集(2014/06/26)
梅雨入りしてるのに、なかなか雨が降りませんが、毎日除湿機に溜まる水の量が半端ありません!
この時期はレコードの保管に悩みます。
さて、今月のレコードジャケットは、久々にジャズでいきます。
こないだ、某レコード店に後で紹介する、泣く子も黙る「サキコロ」オリジナル盤が入荷しました。
まだ値付けされてなくて、店のステレオでかけられていましたが、めちゃくちゃいい音でした!
家に帰って所持してる安い国内再発盤を聴いてみましたが、全然音が違いました・・・。
とはいっても、腐っても名盤!やはり素晴らしい演奏でして久々に聞き惚れました。
という訳で、今月の壁レコードはソニーロリンズで行ってみます。
まず玄関先は、これしかないでしょ!の名盤「サキソフォンコロッサス」です。
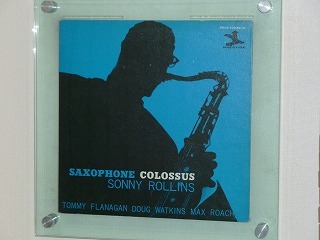
1956年に発表された、彼の代表作であるばかりでなく、モダンジャズを代表する超名盤でございます。
主役のロリンズの豪放ながら温かみのあるテナーサックス、サポート陣も名手トミーフラナガンの味わい深いピアノ、的確なダグワトキンスのベース、
そして鯔背で鋭いスティックワークが流石のマックスローチのドラム・・・う~ん、名演です。
曲も悪くないと思うんですが、このアルバム、マニアには評判悪いんですよね。
寺島靖国氏のエッセイで、「サキコロの完全オリジナル盤を25万円で買った紳士」の話が出てくるものがありますが、「愚行」とこきおろされてました。
料理、酒の薀蓄漫画で大儲け?のラズウェル細木先生の初期の作品で、主人公ラズウェルがサキコロを初めて買うとき、恥ずかしくて「聴きつぶしちゃって3枚目だよ」なんて台詞を吐くシーンがありましたね。
確かに、ジャズをシニカルに考え、暗い(照明が、という意味です)ジャズ喫茶で腕組みして瞑想に耽ったり、唸ったりする人種には、このあまりにも分かりやすいアルバムは敬遠されてしまうかもしれません。
60年代のジャズ喫茶は反体制運動家たちのメッカで、資本論などを読みふけったマルクスかぶれなんかが夜な夜な集まっていた、という話を聞きます。
そういう時にかかって欲しいのは、やはりインパルス後期のコルトレーンや、激しいフリージャズであって、「セントトーマス」や「モリタ―ト」ではありませんね・・・・・。
ただ、2曲目のバラッド「You don't know what love is」は割と感傷的な演奏なので、苦手な方はまずここから聴いてみては如何でしょうか?
お次はこの2枚です。

なかなか面白い構図だと自負しております。
まずはロリンズのブルーノートでの第2作目です。
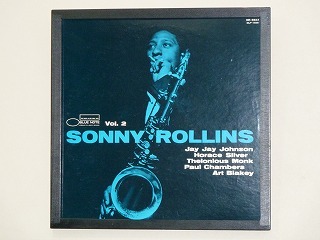
これは1957年のアルバムですが、サイドメンが素晴らしく、まあブルーノートらしいといえばそうなんですが・・・。
ドラムはアートブレーキ―、ベースはポールチェンバース、ピアノはホレスシルヴァーとセロニアスモンク、トロンボーンにJJジョンソン・・・と凄い布陣です。
当然、この時代しか出せない音がレコード盤から飛び出してきます。
安い国内中古盤でもこんなんだから、オリジナル盤なら悩殺モノの爆音が聴けるんでしょうねえ・・・・・。お値段も凄いんでしょうが・・・・・。
そして、見事なパロディジャケットを作ったジョージャクソンさんに拍手です!
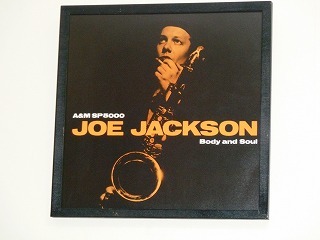
イギリスのシニカルというか、一筋縄ではいかない天才ミュージシャン、Joe Jacksonの1984年発表の「Body and Soul」です。
まあ、見事な出来栄えですよね。古今東西、いろいろなパロディジャケットがあり、それだけ集めた本も何冊も持ってますが、これは最高峰の一枚です!
ただ、内容はジャズばっかりではないんですよねえ・・・。
個人的には彼の最高傑作は1981年に発表された「Jumpin' Jive」だと思います。
これは1940年代に一世を風靡したルイジョーダン、キャブキャロウェイなどの「Jive music」を再現したものです。
まだジャズが盛んになる前の時代、こんな「チンピラ」な音楽が「ヒップ」な人たちの間では流行ってたんですねえ。
所謂「スクエア」な方々が眉を顰めるようなね・・・・・。
全曲楽しく、カッコよくて粋なんですが、特に好きなのはA面3曲めの「Is you Is or Is you ain't my baby」です。
中学の英語教師が聞いたら、赤点つけそうな文法ですが、「これが粋な話し言葉ってえもんよ!」てな感じなんでしょうか・・・・・。
あの名ミュージカル、「ポーギーとベス」でも、「You is my woman」なんて曲があったような気がします。
この曲、確か「トムとジェリー」でも、トムが可愛い娘ちゃんを口説く時に、ウッドベースを弾き弾き、ダミ声で熱唱してましたねえ。
祝来日!TOTO & BOSTON特集(2014/05/29)
まだ5月後半だというのに、30度以上の地域もあるようで、今年の夏はかなり辛そうです。
皆様体調管理をしっかりなさってください。
さて、今回のレコードジャケットは先頃来日し、大好評だったTOTOと、これまた数十年ぶりに来日するBOSTONを特集してみました。
まずは玄関先です。
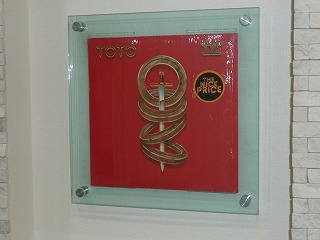
TOTOの1982年発表の4作目、「Ⅳ」です。
リリース当時、私は中2でして、このアルバムを貸しレコード屋で借りてマクセルのUDテープに落とし、それこそテープが擦り切れるまで聴いたものです。
「ロザーナ」がヒューマンリーグの「愛の残り火」(勿論名曲ですが・・・。)に阻まれ、なかなかビルボードチャートの一位になれませんで、ヤキモキしながら「アメリカントップ40」を聴いてたら、とうとうヒューマンリーグが下位にダウンしたので、
「やった!今週はトトが一位だ!!」と思ったら、赤丸急上昇してきたSteve Miller Bandの「アブラカダブラ」にスルッと持って行かれた時の悔しさは今でも忘れられません。
その後、「アフリカ」で念願の一位をさらっと獲得しましたがね・・・。
私はこのアルバムはちょっとTOTOにしては出来過ぎな感が昔からあります。
勿論、全員がスタジオミュージシャンなので、演奏が巧いのは当たり前ですが、何というか、それまでの彼らの魅力でもあった「はっちゃけぶり」が皆無なんですよね。
2曲目の「Make Believe」なんて、素晴らしすぎますが、あまりにもアダルト過ぎてトトじゃないみたいです。
セカンドアルバム「Hydra」のB面一曲目「All us boys」の「俺たちゃ音楽死ぬほど好きだもんね!」的なノリノリのはじけた演奏が彼らの真骨頂だと思います。
日頃スタジオで譜面通りかそれに近いアレンジで初見で演奏させられ、巧くなくちゃ当たり前、なおかつリスナーを唸らせるソロを盛り込んでね!というプロデューサーの無茶振りをこなしていくうちに溜まったフラストレーションを発散させる為のバンドだった筈ですから・・・。
1980年の初来日のライブ音源を聴くと、若さもありますが、全員すさまじくノリノリのプレイをしており、ブッ飛びます。
特にジェフポーカロのオカズ満載ながら決して乱れぬドラミングは凄いです。
そういう意味では、最もトトらしいアルバムは「Hydra」と「Turn Back」なんでしょうね。
個人的には最高傑作はデヴュー作「TOTO」なんですが、これはそれまで温めてきた曲を時間をかけた最高のアレンジでじっくり演奏してますから、出来が良いのは当たり前なんですね。
お次はBOSTONです。

MIT(マサチューセッツ工科大学)出身のエリートで天才ミュージシャンのTom Shulzの結成したバンド、BOSTONの2枚です。
まずは新人バンドながら破格の成功をもたらした1976年のデヴューアルバムです。
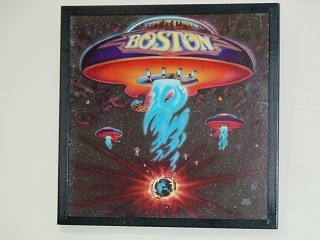
やはりデヴューアルバムというのは、ストックしてきた楽曲を周到なプロダクションで完成させられる(締切がない!)ので、御多分に漏れず、このアルバムも完成度は高いですね。
しかし、A面冒頭の「More than a feeling」は、邦題こそ「宇宙の彼方に」ですが、内容は実に素敵なラヴソングなんですね。
トムシュルツの曲の特徴としては、昂揚感のあるギターリフが挙げられますが、この曲などギターキッズがこぞってコピーしたくなるようなフレーズ満載ですよね。
バンドとしてツアーもする為に、一応バンド形態ですが、殆どの楽器はトムが担当してるんではないでしょうか?
ジミーペイジと並んで、ギター多重録音の鬼なんでしょうね。
そして、大ヒットの余波をかって(エピックに急かされて?)早くも1978年に出されたセカンド、「Don't look back」です。
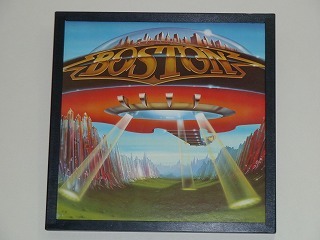
今考えると、たった2年で次のアルバムを出したのは驚異的ですがそれは「ボストン」の尺度での話で、当時は年に一枚は当たり前、の世界でしたからねえ。
結局その後三枚目のアルバムが発表されたのは、実に8年後の1986年でした。
まあ、それだけかけただけに、佳曲が揃ってはいますが・・・。
さて、「ドントルックバック」ですが、これは冒頭のタイトル曲は最高傑作ではないでしょうか!
私は落ち込んだ時や人生に疲れた時の「カンフル剤」ならぬ「カンフル曲」として愛聴しております。
まあ、「振り返るな!」というポジティブなメッセージもさることながら、これまたギターキッズが泣いて喜ぶカッコいいリフにノックダウンされます。
この曲のプロモーションヴィデオはライヴ仕立てにて、メンバーの雄姿も垣間見れます。
このバンドはリーダー、トムシュルツとヴォーカルの惜しくも他界したブラッドデルプの二人が肝だと思いますが、もう一人のギタリスト、Barryさんもカッコいいし、
ちと変わった風貌(失礼!)のリズムセクションの二人もなかなか魅力的です。
ドラマーはシブハッシャンという名前と風貌から、イスラム、アラブ系の方と見受けられますが、なかなかタイトなドラミングですね。
さて、数十年ぶりの来日、加えて名古屋は初めてみたいですね。
さすがに、ライヴ会場まで足を運ぶつもりは今のところありませんが、映像が出たら見てみたいですね。
祝来日!Jeff Beck特集(2014/04/24)
もうじきゴールデンウイークだというのに、まだ花粉の飛散に悩まされている私です。
同様の方も多いんじゃないでしょうか?
先月のブログで、今春は大物の来日ラッシュ!という話をさせて頂きましたが、Deep Purpleが抜けておりました。
私は本家は見たことがありませんが、分家のWhitesnakeは数年前に前から5番目の席で観ました。
ヘビメタファンはノリが凄くて、殆どの歌詞を暗記してるし、コール&レスポンスではしっかり答えてましたね。
ミュージシャン冥利に尽きるでしょうね、ああいうライヴだと・・・。
さてさて、今月の壁レコードですが、来日も気付いたらもう終わってた、という感じですが、個人的にはロック界最高のギター弾きと思います、ジェフベックを特集してみました。
まずは玄関先です。
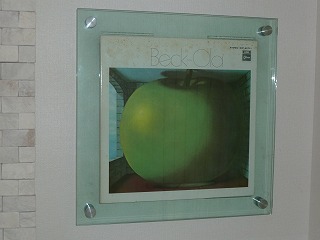
第一期Jeff Beck Groupの1969年発表のセカンドアルバム「Beck Ola」です。
マグリットの有名なリンゴの絵をジャケットに使用したのは誰のアイディアなんでしょう?
ジェフ自身とは思えないです・・・。(違ってたらスミマセン)
とにかくこのバンドは今考えると凄いメンツでして、ヴォーカルはRod Stewart、ベースはRon Wood、キーボードはNicky Hopkins、ドラムはTony Numanなんですよ。
まあ、当時は普通にプレイしてたんでしょうが、今ならスーパーグループですねえ。
冒頭の「All Shook Up」のカッコいいこと!!ロックの理想の形がここにあります。
続く「Spanish Boots」も破壊力抜群のハードロックチューンです。
ただ、ハードロック一辺倒ではなく、3曲目なんぞはニッキーホプキンスをフューチャーしたピアノ曲がしんみりと流れます。
昔は違和感を覚えながら聴いてましたが、これはやはり「恋は水色」を嬉々として?カヴァーしてしまうジェフのセンスなんでしょうね。
では待合室壁です。

まずは1975年発表のギターインストアルバムの金字塔!「Blow By Blow」です。
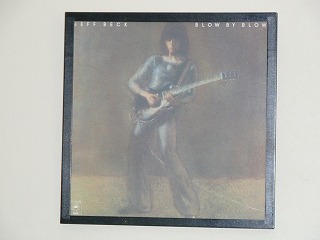
邦題「ギター殺人者の凱旋」はエピック社の宣伝コピーの直訳なんですよね。なかなか言いえて妙なんじゃないでしょうか?
今月号の「レコードコレクター」誌にいろいろ興味深い分析がなされているので、興味のある方は是非読んでください。
特にGeorge Martinがプロデュ―スする事になった経緯については、なるほど、と思いましたね。
レコーディングメンバーも最高で、多彩なマックスミドルトンのキーボード、ファンキーなフィルチェンのベース、特にリチャードベイリーの変幻自在のドラミングには舌を巻きます。
ジェフのギターも、ソロは勿論ですが、細かいカッティングやオブリガードにも素晴らしい冴えを見せていますね。
私はこのアルバム、イギリスオリジナル、アメリカ初盤、日本盤初回帯付と持ってますが、今回の再発CDも勿論買っちゃいました。
何といっても、これまで血眼になって探してたマルチチャンネル仕様を再現してくれたのが嬉しいですね。
そしてもう一枚はやはりこれでしょう。
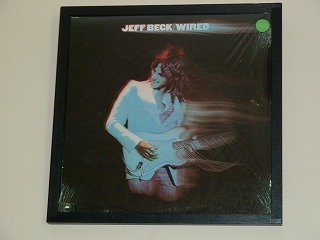
翌1976年に発表したこれまた同系統のギターインストアルバム、「Wired」です。
前作がインストアルバムとしては異例の大ヒット(全米4位!)を記録したのに気を良くしたのか、これまた異例のハイペースで作り上げた硬派のギターアルバムです。
確かにカッコよさは前作以上かもしれません。A面冒頭の「Red Boots」の出だし、「ッシャー、ッシャー、ッシャー・・・」とナラダマイケルウオルデンの歯切れの良いシンバルが聞こえた時点でノックアウトされます。
続けて展開される悩殺モノのギターリフ!カッコいいですねえ。でも、徐々に何か自己主張の強い音が被ってきます・・・・。ヤンハマーのシンセです!
私が何となくこのアルバムに感じる「やりすぎ感」は、ヤンハマーの出しゃばり(失礼!)にあると思ってます。
曲によってはドラムまでこなしてしまうマルチな才能には脱帽ですが、彼のせいでジェフにしか出せない空気感が希薄になってしまい、何かバカテク・フュージョンアルバムみたいになっちゃいましたよね。
勿論、チャーリーミンガスの名曲「Goodbye pork pie hat」の名演など、ジェフ自身のプレイは相変わらず冴えわたってますが・・・・・。
この後、スタンリークラークと組んでツアーしたり、時代の流れもあり、クロスオーヴァー、フュージョン化していくんですよね。
現在も、どちらかといえばギターインスト路線の音楽を展開している様ですが、きまぐれでもいいから、ロッドスチュワートと再会して、唄ものロックアルバムでも出して欲しいなあ、と思うのは私だけでしょうか?
今月の壁レコード・・・祝来日!ローリングストーンズ特集~Decca years(2014/03/17)
寒暖の差は激しいものの、暖かい日も多くなってきた今日この頃、皆さま如何お過ごしでしょうか?
今年の2月~4月は洋楽好きには堪らない日々が続きます。
超大物アーティストの来日がこんなに固まってくることはここ数年無かったですよね。
先ず、終わってしまいましたが、2月後半のエリッククラプトン、同じく2月後半から3月頭のローリングストーンズ、これから3月後半からのボブディラン、ジェフべック、ビーチボーイズと、凄いラインナップですね。
私はどれも行きませんが、ビーチボーイズ以外は昔観に行きましたね。べックとディランは各一回、ストーンズはミックジャガーとミックテイラーのそれぞれのソロ公演も合わせれば4回、クラプトンは5~6回は行ってますが、一番思い出に残ってるのは、やはりジョージハリスンとのツアーでしたね。
さて、今回の壁レコードは、やはり現役最強?ロックバンドの貫禄を見せつけたRolling Stonesを特集してみました。
とはいっても、長い長い歴史を誇る彼等なので、とても3枚だけに絞れません。
先ずは60年代に在籍したデッカレーベルに残した作品からピックアップしてみました。
先ず玄関先です。
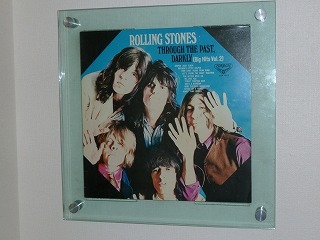
1969年発表のベストアルバム第2集、「Through the past, darkly」です。
オリジナルは8角形の変形ジャケットでして、程度の良いオリジナルはかなりの値段がついていますね。なかなか巡り合わせが悪く、未入手にて、国内盤の普通の正方形のものを飾りました。スミマセン・・・。
まあ、ベスト盤に評論云々は野暮なので、内容については無難な選曲ですね、とだけ言っておきます。
面白い、というか哀れなのは求心力を失って、ぶざまな顔をさらしても平気?なブライアンジョーンズです。
普通、いくらなんでもロックミュージシャンがブタ鼻はやらないですよね。おっさん揃いのELOだって、「Face the music」の裏ジャケットで同じようなコンセプト(硝子板に顔を押しつける)で写真を撮ってますが、笑いを取ってる人はだ~れもいません!
その数年前のアルバム「Between the buttons」でも、薄ら笑い、半開き眼のみっともない?写真をフロントカバーに使われても、文句言わない(言えなかった?)のは、仮にもリーダーを務めてきた人間と同一人物とは思えません。
やはり、相当ドラッグの影響はあったんでしょうね。
その後、追い出されるように脱退~謎の死を遂げる訳ですが、オルタモントの悲劇は、彼の怨念が起こしたものではないでしょうか?
日本人ならば、怨念を封じ込める為に社を築いていた所でしょう。
それでは壁の2枚です。

まずはロック名盤に必ず登場する大傑作のこれです。
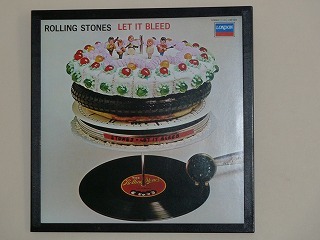
泣く子も黙る、1969年の「Let it bleed」です。
これは私もフェイヴァリットアルバムでして、何度聴いても新たな発見がある凄いアルバムです。
全ての曲が素晴らしく、完璧な仕上がりだと思います。
なんかの本で、カントリーホンクでなく、シングルでリリースされた「Honky Tonk Women」だったらもっと良かった、なんて記事がありましたが、解ってないなあ、と思います。
やはりあの流れで「Live with me」の地を這う様なベースが始まらなきゃねえ・・・・。
どの曲も好きですが、A面では冒頭のキースのギターが冴えわたる「Gimme Shelter」、ボビーキーズのサックスや、レオンラッセルのピアノの客演もカッコいい「Live with me」、そして6人目のメンバー?イアンスチュアートの転がるようなピアノが最高なタイトル曲、「Let it Bleed」。
B面では不穏なイントロから何かとんでもない世界が繰り広げられる予感かしますが、果たしてその通りの展開を見せる「Monkey Man」、そしてプロデュ-サーのJimmy Millerが意外に達者なドラムを叩く、大団円の「無情の世界」など、本当にこの時期のストーンズは凄かったですよねえ。
一応、ミックテイラーはこのアルバムから参加、という事になってはいますが、実際は「Country Honk」と「Live with me」でギターを弾いているだけでして、殆どはキースが多重録音しているんですよ。
どうしても、キースはカッティング命のリズムギタリスト、というイメージが強いんですが、どうしてどうして、素晴らしいソロも弾くんですねえ・・・。
お次はこれです。
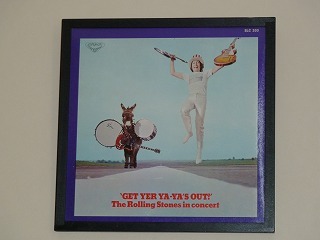
御茶目なチャーリーワッツとロバが可愛い?ライヴアルバム「Get Yer Ya-Ya's out」です。
これはミックテイラーの流麗なギターが楽しめる名ライヴアルバムですが、やはりLP一枚だと時間的な制約もあり、物足りないといえば物足りないです。
先ごろ正式にネット上にアップされた1973年のヨーロッパツアーでのライヴなんか聴くと、ぶっ飛びますね。
今のストーンズもいいですが、あの頃の演奏は荒いですが、凄まじい勢いが感じられます。正に「世界一のロックバンド」でしたねえ。
個人的には、ミックテイラー時代のストーンズは最高だと思います。
ロンウッドも気がついたら40年近く居るんですが(それも凄いことですが)、やはり彼は、ストーンズに入らないほうが良かったんではないでしょうか?
Rod Stewartとずっと組んでいて欲しかったし、「Now Look」の路線でファンキーなソロアルバムをもっと出して欲しかったなあ、と思うのは私だけでしょうか?
今月の壁レコード~お面ジャケット?特集(2014/02/17)
今年は大雪に悩まされる日が多いですが、皆様如何お過ごしでしょうか?
さて、ブログ更新は2月半ばになってしまいましたが、ジャケットは2月前半に変えております。
節分の日にニュースを見ていましたら、一畑山薬師寺の豆まきの様子が映し出され、鬼のお面の代わりにキングクリムゾンの一作目のジャケットを使ったら面白いだろうな、と思ったのがきっかけで、ジャケット一面に顔がフューチャーされたレコードを捜してみたら、結構あるんですよね。
という訳で、今回はでか顔ジャケットを3枚厳選してみました。
先ずは日本人代表で、これです。
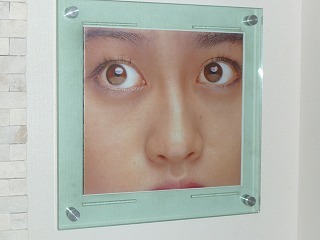
渡辺美里さんの1987年のアルバムです。
これは恐らくアップ度は古今東西のレコードジャケットの中でも断トツではないでしょうか?
眼科医の見地から見ると、結膜(白目)のマッ白さは尋常ではありません!もし修正無しだったら凄く健康な生活をしてらっしゃるんでしょうね。
お次はこの2枚。

先ずは白人代表で、フィルコリンズさん!
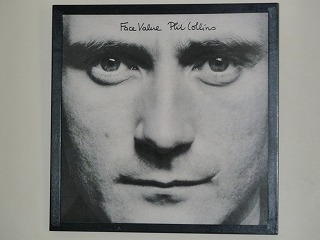
これは1980年の初ソロアルバムですが、見て下さい、この自信に溢れた精貫な顔つきを。
Peter Gabriel脱退後のGenesisを引っ張って、見事本国英国だけでなく、亜米利加をも制覇した自信と余裕が漲ってますね。
彼は相当自分の顔に自信を持っているようで、続くセカンド、サード共に御顔のドアップをジャケットにしていますね。
サードは最高傑作だと思いますが、この頃になると自分の立ち位置が分ってきたようで、ちょっと「キモい親父」っぽくにやけてるんですよね。
でも、内容は大まじめ、というのが笑えます。
この人のドラムは独特のバタバタしたフィルインが好き嫌いが分かれる所でしょうが、個人的にはタムタムの使い方は大変参考にさせて頂きましたね、昔。
そして、黒人代表はこの方。
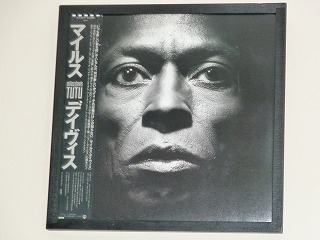
泣く子も黙る、ジャズ~ファンクの御大、Miles Davisの1986年のアルバム、「TUTU」です。
この頃の御大は前年のアルバム「Your under arrest」でマイケルジャクソンの「Human Nature」、シンディローパーの「Time after time」といったポピュラーミュージックを取り上げた事もあり、ジャズの垣根を飛び越して、コンテンポラリーな人気がありましたね。
日本でも洋楽ブームだった世相を背景に、普段音楽を聴かないような方でもかなりの知名度はありましたね。
このアルバムはマーカスミラーのプロデュ―スにて、ソリッドなファンクを演っている事もあって、ジャズマニアからはそっぽを向かれましたが、ファンク、ヒップホップ好きには歓迎されたんじゃないでしょうか?
因みに、このドアップ顔ジャケットは石岡瑛子さんのコンセプトで、彼女はこれでグラミー賞を獲っているんですね。すごいなあ!
黒人の中でも、かなりのイケ面のマイルスの御顔はやはり歳を取ってもイケてます!!
ジャズのレコードは結構、ジャズメンの顔アップ写真のジャケが多いんですが、ブルーノートのArt Brakeyの「Mornin'」とかWalter Davis Jr.の「Davis Cup」とか、結構迫力あります。
ラズウェル細木の漫画で、夜道でチンピラに絡まれている女性を助ける為に、先の2枚のジャケットを顔に当てて凄んでみせる、というのがありましたが、私も今度やってみようかな?
謹賀新年 今月の壁レコード~午(馬)特集(2014/01/11)
皆さま、明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い申し上げます。
今年は午年にて、壁レコードも馬関係にて統一しました!
先ず玄関先はこれです。
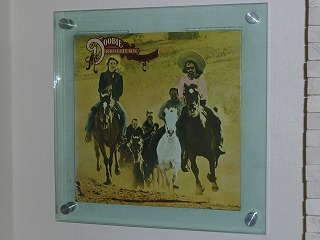
Doobie Brothersの1975年発表の快作「Stampede」です。
次作からMichael McDonaldが加入し、やや作風が変わってくるので、このアルバムが前期Doobieのピークでしょうね。
このアルバムからSteely Danにいたギター職人?Jeff Baxterを迎えており、トリプルギター編成となり、スケールアップしている姿が馬を駆る豪快なジャケット写真に垣間見れます。
この頃のライヴ素晴らしかったでしょうね。アルバムからのシングル、「君の胸に抱かれたい」はモータウンナンバーを豪快にアレンジした、如何にもTom Johnstonらしい男っぽい演奏、歌が繰り広げられますが、この曲のヴィデオクリップがまた格好いいんですよね。
流麗なギターソロを披露するJeff Baxterの不敵な?目がいいですね。因みに彼の綽名は「スカンク」でして、何でも靴を脱いだら足が相当臭かったとか・・・・・。
Tom Johnstonがイニシアチヴを握ってた前期とMichael McDonaldがフューチャーされた(リーダーはあくまでPatrick Simmonsでした)後期とどちらが好きか?というのは良くロックファンの間で話題になりますが、私はどちらも大好きですね。
ソウルミュージックに没頭していたころは、断然後期の洗練されたサウンド派でしたが、初期の荒削りな如何にもアメリカンロック!な頃もやはり素晴らしいですね。
最近、1973年頃のスタジオライヴ盤を入手して聴きまくってますが、Tomも Patも本当にギターが巧いですね。
という訳で、いずれDoobie Brothers特集もやりたいと思います!
待合い壁の2枚です。

先ずはこちら
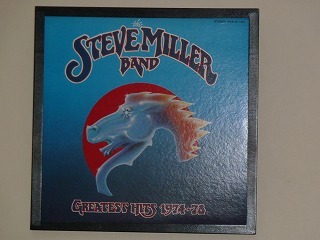
Steve Miller Band の「Greatest Hits」です。1978年の発表です。
本当は前作「Book of Dreams」の天馬のジャケットを使いたかったのですが、行方不明になってしまったので、同じく馬がフューチャーされたこちらを使いました。
Steve Millerは気まぐれというか、レコード発表のインターバルが長い事で有名?ですね。(Bostonには負けますが)
1973年の「Joker」までは比較的せっせとアルバム発表していたのですが、ジョーカーで全米ナンバー1を取ってからは、マイペースの極みになってしまいました。
でも、1976年の次作「Fly Like an Eagle」なんて、今聴いても目茶苦茶格好いいし、1982年には「Abracadabra」で久々に全米ナンバー1になりましたし、70~80年代には本当に輝いてました。
もともとはサンフランシスコで結成された渋いブルーズバンドでして、初期のメンバーには、あのBoz Scaggsもいたんですよね。
最近は何をやってらっしゃるのでしょうか?思いついたように地元のライブハウスなんかに出ているのでしょうかね?
次はこれです。
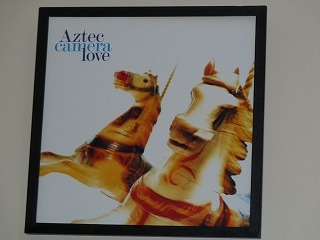
Aztec Cameraの「Love」ですが、これに関しては完全に「馬」だけで選んでます。全然聴きこんでないので、ノーコメントでお許しください。
本当は、Bob Segerの「Against the wind」あたりで攻めたかったんですが、生憎レコード棚に見当たりませんでした。確かに持ってはいるんですが・・・・。
今月の壁レコード ~ 祝!来日!!Paul McCartney特集(2013/11/28)
かなり寒くなってまいりました。どうりでもうじき師走です。
今年も気付いてみたら年末です。歳を取ると月日の流れが格段に速くなっていくのは私だけでしょうか?
さて、今月の話題は何といってもポールマッカートニーの来日につきますね。
スケジュールの都合で結局「最期」と言われたコンサートには馳せ参じる事はできませんでしたが、毎日ニュースやインターネットで情報はまめに入手してましたよ。
しかし、何で名古屋では演ってくれないんでしょうかね?
前回2002年来日時も「名古屋飛ばし」でしたので、仕事をやりくりして、大阪まで観に行ったものです。
最終新幹線に乗る為に、最後まで聴けなかったのが今でも心残りです。
ま、どこかのケーブルTVが最終公演を放映してくれる、という噂もありますので、期待する事にしましょう。
という訳で今月の壁レコードは「80年代のポールマッカートニー」でキメてみました。
玄関先はこのジャケットです。
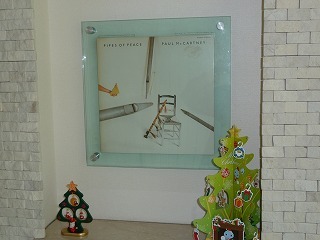
1983年の「Pipes of piece」です。
当時飛ぶ鳥を落とす勢いだったマイケルジャクソンとの共演、「Say Say Say」の大ヒットに埋もれ、他の曲はあまり評価されてませんが、秀逸なプロモクリップのおかげで、表題曲と「So Bad」は割と皆さん、聞き覚えあるんじゃないでしょうか?
ただ、その3曲以外はあまり大した事ない(失礼!)ナンバーが続き、正直今ではターンテーブルに乗ることは殆ど、まずありませんね。
「Say Say Say」も金のかかっている劇仕立てのプロモクリップなしではあまり面白い曲ではないので、今となってはあまり聴く事はないですが、「Pipes of piece」と「So Bad」はいつの時代になっても色あせない名曲だと思いますね。
お次はこの2枚です。

やはり80年代はこの一枚でしょう!1982年の傑作「Tug of War」です。
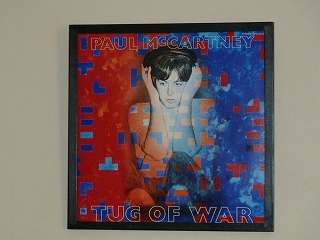
私は1981年からロックを本格的に聴きだしたので、このアルバムはリアルタイムで楽しみました。
Stevie Wonderとの共演「Ebony and Ivory」は稀代の名曲で、ピアノの鍵盤を黒人と白人に置き換え、「人類平和、世界は皆兄弟」を控えめに訴える、という内容も相まって全米ナンバー1を独走しましたね。
何故かライヴでは殆ど取り上げられなくて、今回の公演でも当然スル―されてましたね。
やはり黒人とのデュエットでないと意味がないからかなあ・・・。
だったら、ドラムのエイブラハムが歌えば可能だったんでは・・・?
最終公演のサプライズでやるのかな?なんて密かに期待してたんですが・・・。
他の曲も、4曲目のこれまたStevieとの共演「What's that you doing」以外は捨て曲無しの名盤です。
冒頭1曲目の表題曲「Tug of War」は綱引きの掛け声から静かに始まりますが、途中から力強いギターサウンドになり、感動的な展開になる名曲です。
2曲目の「Take it Away」は後述します。
3曲目の「Somebody who cares」は目立たないですが、個人的には大好きな曲です。
調子良い時のポールって、こういう地味な曲でもそれなりに仕上げてしまうんですよね。
5曲目は先の日本公演でも演奏された、ジョンレノンに捧げた「Here Today」でして、あの忌まわしい事件後、沈黙を続けていたポールが初めて公式の曲で追悼したと、当時は話題になりました。
2分程度の小曲ですが、無駄の無い起承転結のはっきりしたポールらしい佳曲です。
続いてB面ですが、個人的には、何となく「Abbey Road」のB面を彷彿とさせるんですね。
印象的な小曲が次々と飛び出してきて、最後に名曲「Ebony and Ivory」で締めくくるところなんざ、やはりプロデュ―スをGeorge Martinに依頼しただけの事はある、と思います。
評論家のセンセ―方もご指摘ですが、ポールって、何でもできちゃうので自身でプロデュ―スすると詰めが甘くなってしまうので、やはりこういう辣腕プロデューサーの存在は必要ですね。
続いてもう一枚。
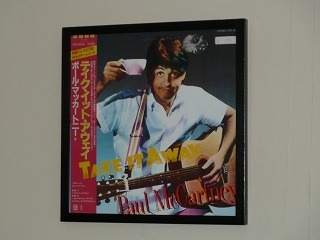
セカンドシングル、「Take it Away」の12インチ盤です。
この頃からポールは従来の7インチに加え、12インチでも沢山シングルを発表するようになり、コレクター泣かせとなっていきます。(ま、そこが集めがいがあっていいんですが・・・)
この曲はメロディーもポールらしい、わくわくするような展開の名曲ですが、Ringo StarrとSteve Gaddのツインドラム、シカゴを彷彿とさせるようなホーンセクション、愛妻Lindaや10CCのEric Stewartらの分厚いコーラス・・・と演奏面でも素晴らしい出来で、やはりGeorge Martin、良い仕事してますねえ・・・・。
さて、大好評に終わった今回の来日公演ですが、やはり・・・行きたかったなあ・・・・・・・。
もし次があるなら、呼び屋さんのキョード―さん、もしくはウド―さん、名古屋も呼んでちょーよ!!
今月の壁レコード~Stephen Bishop特集(2013/10/31)
10月も終わりになり朝夕かなり冷え込んでまいりました。
皆さま季節の変わり目には体調にご注意ください。
さて、毎年言ってますが、秋になるとセンチメンタルな音楽が恋しくなってまいります。
そういった時に欠かせないのが、所謂シンガーソングライター達のアルバム群です。
今回はナイ―ヴではかなげな作風が今の季節にジャストフィット?なスティ―ヴンビショップを特集してみました。
先ずは玄関先です。
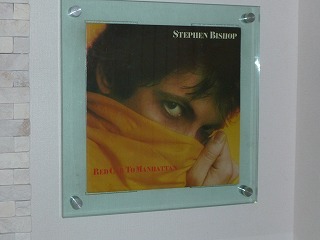
1980年発表の3作目、「Red cab to Manhattan」です。邦題は何と「哀愁マンハッタン」という時代を感じさせるものでした。
順序としては後になるのですが、「目力」ジャケットが気に入って、玄関に飾ってしまいました。
内容はワーナー移籍後という事でそこそこ話題にはなったようですが、幾つかいい曲はあるのですが、あまり評価されてないようですね。
やはり、ABCレーベルからの1枚目と2枚目の完成度には敵いません。
待合い室の2枚です。

先ずは1976年発表のデヴューアルバム、「Careless」です。
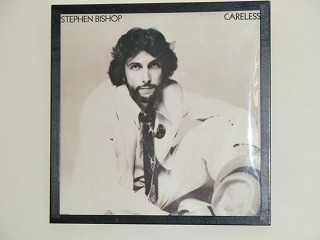
素晴らしいサポートメンバー(Larry Carlton, Lee Ritenoir, Jay Graydon, Andrew Gold, Jim Gordon, Russ Kunkel, John Guelin, Max Bennett, Victor Feldmanなどなど)の手堅い演奏。
自作で彼の曲を取り上げたArt Garfunkelは解りますが、Eric Claptonや Chaka Khanまで担ぎ出せたのは、敏腕プロデュ-サーのおかげなのか?はたまたこの人の人望でしょうか?
兎に角、デヴュー作とは思えない完成度の素晴らしいアルバムです。
殆どの曲がシングルカットできる程の素敵なメロディーが、ポンポン飛び出してきます。
A面一曲目の代表作、「On and On」は確かに素晴らしいです。
でも、彼の本質はむしろ二曲目の「Never Letting Go」に溢れているんじゃないでしょうか?
「行かないでおくれ 君に夢中なんだ 僕を捨てないで 君なしでは生きていけないんだ・・・」
何とも女々しい(女性の方、失礼!)、情けない訴えですが、このナイーヴさが彼の持ち味なんですね。
何度聴いても素晴らしい曲です。
その他の曲もいい曲ばかりです。皆さん、是非聴いてみて下さい。
お次は1978年のセカンド、「BISH]です。
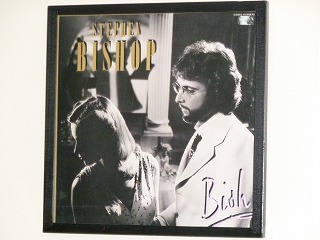
これまた前作に勝るとも劣らず、いい曲満載のグッドアルバムです。
往年のハリウッド映画のスティ―ル写真風の粋なジャケットは、文字の処理からお解りでしょう。そう、あのKOSHです。
この人は他のジャケット制作者と比べてあまり評価されてないんじゃないかな、といつも思います。
KOSHのデザインしたジャケットを集めた画集なんて出版されてたら、どんなに高くても買うんだけどなあ・・・。そんな方々も少なくないはずです。どこかの出版社さん、お願いします。
曲はやはり彼らしい、ジェントルな調べが聴かれるA面の「Losing myself in you」、「Looking for the right one」の2曲が光ってます。
その後の彼ですが、映画好きらしく、数々の映画のサウンドトラックに参加して印象的な曲を発表していましたね。
中でも、ダスティンホフマンの怪演?「Tootsie」に提供した「It might be you」はひょっとしたら彼の最高傑作ではないかと思う程、胸キュンで美しい魅惑のメロディーが聴かれます。
今月の壁レコード ~ オールマンブラザーズバンド特集(2013/09/30)
秋らしく、朝夕はかなり過ごし易くなって参りました今日この頃、皆様如何お過ごしでしょうか?
あれだけ暑く、熱帯化しちゃったんじゃないか?なんて言われてましたが、ちゃんと秋が来るんですから、日本は凄い国ですねえ・・・。
さて、秋を連想させるジャケット、何があるかなあ?と思考しますと、真っ先に思い出すのはベタな所ではシャンソンの「枯葉」なんてありますが、生憎エディットピアフのジャケットにいいものが無く、何か無いかなあ?とレコードラックを物色してたら、いいのが見つかりました!
先ごろマニア感涙のデラックス版が発売されたばかりのオールマンブラザーズバンドの名盤「Brothers and Sisters」です。
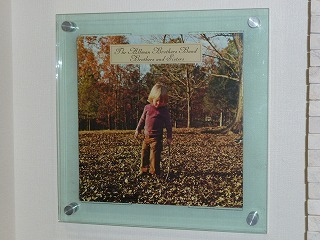
1973年に発売され、見事全米№1に輝いた素晴らしい作品です。
ジャケットは恐らく所属するキャプリコーンレーベルのホームグラウンド、ジョージア州メイコンで秋に撮影されたと思われます。
ゲートフォールド中側にはメンバーとクル―の家族集合写真が見られますが、表ジャケットの男の子(Brother)は、ドラマーのブッチトラックス(因みに私の学生時代の綽名もブッチでした)の、裏ジャケットの女の子(Sister)は、アルバム制作中にデュエインと同じようにバイク事故で惜しくも他界したべ―シスト、ベリーオークリーのお子さんだそうです。
オールマンブラザーズバンドはその名の通り、デュエインとグレッグのオールマン兄弟を軸に、後にリーダーシップを取る事になる腕利きギタリスト、ディッキーべッツ、先に紹介したベリーオ―クリー、ブッチトラックスと、もう一人の黒人ドラマー、ジェイモーの6人で確かフロリダ州のジャクソンビルで結成された、サザーンロックを代表するバンドです。
ジャクソンビルは同じくサザーンロックの雄、レ―ナ―ドスキナ―ドも結成された凄い町です。
私は留学時代、同地で開かれたシェリルクロウのコンサートを観に行った位で、あまり足を運ぶ機会はありませんでしたが、かなりでかい町です。
デュエインオールマンのギターの腕前は素晴らしく、南部のスタジオミュージシャンとして、アトランティックやスタックスのソウルアルバムに沢山演奏が残っております。(後で紹介する「アンソロジ―」に収録されてます)
ロックファンにはあのデレク&ドミノスのアルバム「レイラ」の殆どの曲でクラプトンとのツインギターが聴かれる事で知られてますよね。
セッションマンとしてのフラストレーションを解消する為に、念願のバンドを渋い喉とオルガンを披露する弟のグレッグと結成して、スタジオアルバムを2枚発表しますが、真骨頂はやはりライブ演奏だったようで、3作目にして2枚組の超名盤、「フィルモアイ―ストライブ」を発表します。
これについては後述します。
「Brothers & sisters」ですが、冒頭の2曲はまだベリーオークリーが在命中の録音ですので、あのブッといベースが聴かれますが、3曲目からは新加入のLamar Williamsの黒人ならではのファンキーなそれでいて適度に重いゴキゲンなベースが楽しめます。
でも、このアルバムを成功たらしめているのは、もう一人の新メンバー、キーボードのChuck Leavellの素晴らしい鍵盤さばきでしょうね。
近年はローリングストーンズのツアーでバンマスを立派に勤め上げている?程出世したチャックですが、このアルバムではDicky Bettsのギターと共に縦横無尽、変幻自在に弾きまくっており、何度聴いても惚れ惚れするピアノさばきです。
特に、A面最後のスローブルーズ、「Jelly,Jelly」でのピアノソロは出色の出来で、レッドガーランドのような「玉を転がすような」気持ちの良い運指が聴かれます。
この時期の彼に、フルでジャズのスタンダードをトリオで弾きまくったアルバムを作らせてあげればよかったのに・・・・。
この曲は、ブルージ―でダルなグレッグのヴォーカルとオルガンもいいし、ディッキーのギターもソロは勿論ですが、要所で渋いフレーズを入れてくるバッキングも最高です。
アルバムでは、ギターソロが延々と続いてるとこでフェードアウトしてしまうので、何でいいとこで切っちゃうんだ~とプロデュ―サーのサンドリンを恨んでましたが、今回のデラックス版で完奏版を聴いて納得。
あそこから後はテンポアップして、「Hot Atlanta」みたいな疾走感溢れる展開になっていきまして、最後は少々ダレてしまいます。
やはり、あそこでハサミを入れて大正解でしたね。やはり理由があったんですねえ。
その他の曲ですが、Dicky Bettsがイニシアティヴを執った「ランブリンマン」、「ジェシカ」「ポニーボーイ」はやはりカントリーがかっています。
「ランブリンマン」のポップさはこれまでのファンを戸惑わせるものだったかもしれませんが、ビルボードチャートを駆け上って(確か2位になったのかな?)、新しいファンも獲得したに違いありません。
私は風来坊を唄ったこの曲の歌詞が大好きで、「オイラはハイウェイを走行中のグレーハウンドのバックシートで生まれた」なんて、まずありえねえ!と思いますが、何かいいですなあ。まさにアメリカ人が好みそうですね。
アメリカ留学時代、何度かグレーハウンドバスは乗りましたが、どの路線も結構混んでた覚えがあります。
一風変わった黒人の自称ミュージシャンと隣り合わせ、自主制作CDを売りつけられたっけなあ。
B面一曲目の「サウスバウンド」はこの時期のコンサートのオープニングを飾った、各人の見せ場がフューチャーされたファンキーな名曲です。
チャックの滑らかなピアノ、放っておいたら何時間でも弾いてそうなディッキーのギターと、素晴らしいソロの応酬です。
続いて壁の2枚です。

先ずはロックライヴアルバム史上1、2を争う傑作「At Filmore East」です。
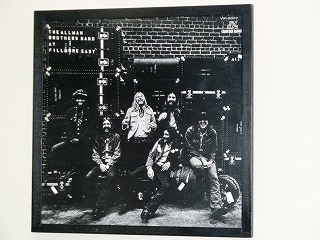
このアルバムを聴いてブルーズの世界にどっぷり漬かった方も多いのでは・・・。私もそのクチです。
まさに「スカイドッグ」の綽名の如く天にも登るようなデュエインのスライドを始め、バリバリのブルーズロックが堪能できますが、多くの方が指摘されているように、長尺ナンバーでは後期コルトレーンの如しフリージャズの影響も測り知れません。
「Hot 'Lanta」や「Whipping Post」なんか、当時この会場で、非合法な煙の中で聴いてたら最高だったんでしょうね。
ちょっとアブナイ話になってきました。
さて、個人的にはこのアルバムではスローブルース「Stormy Monday」とノリノリの「You don't love me」が特に好きですねえ。
前者は多分先にソロをとるディッキーの頑張りが素晴らしいです。粘っこくねちっこい!いいソロです。
勿論しんがりのデュエインのソロも貫禄充分です。
この人は本当にギターの神が降臨してきてたんでしょうね。
何であんなにあっけなく亡くなってしまったんでしょうか・・・。
私はフロリダ大学留学中に、何度かジョージア州に行きました。
メイコンには今は無き「キャプリコーンレーベル」の跡地というか、博物館のような所があり、そこのおじさんにデュエインとベリーオークリーのお墓の場所を聞き出し、お参りに行きました。
あと、彼等が亡くなったオートバイ事故の現場も行きました。
勿論時代が変わっている事もありますが、日本と違い道路も広いし、事故なんて起きたの?というような車通りの少ない辺鄙な場所だったのを覚えてます。
その時の写真もありますが、何せデジカメなどない90年代半ばですので、今ここにアップはできませんでした。
また機会があればお見せしたいと思ってます。
最後に、デュエイン追悼アルバムでしめたいと思います。
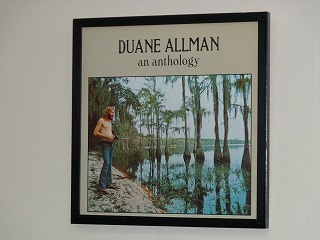
生前のセッション等を編集した「Anthology Vol.1」です。
如何にもスワンプ!とういった沼地で釣りをしている姿はやはり「南部人」だなあ、という感じですね。
余談ですが、80年代後期に「大事マンブラザーズバンド」という日本のバンドがありましたが、あれって、(オオジマンブラザーズバンド)なのか、(ダイジマンブラザーズバンド)なのか?
どっちにしろ、絶対意識してますよね!!
今月の壁レコード ~ ボサノヴァ特集(2013/08/26)
酷暑の中、如何お過ごしでしょうか?
こうも暑いと、海にでも出かけたくなりますが、芋洗い状態のビーチ、大渋滞の道中、大混雑の食糧調達・・・を想像すると途端に足が動かなくなります・・・。
やはり、冷房の利いた部屋で涼しげな音楽を聴いていた方がよいのかもしれませんね。
という訳で、ブラジルの香りを運んでくれるボサノヴァを特集してみました。
Bossa Novaとは、ポルトガル語で、「新しい感覚」とでも訳すのでしょうか?それまでのブラジルの音楽とジャズが融合したような、クールな音楽は当時一世を風靡したようです。
後述しますStan Getzを筆頭に、様々なミュージシャンがボサノヴァテイストの音源を残しています。
ただ、当時は「新し」かったボサノヴァも、時の変遷によって、唯のジャンルになってしまった部分は否めません。
昔、アメリカ留学時代の1997年に、向こうで知り合った方とブラジル旅行へ行ったのですが、生のボサノヴァを聴きまくってやるワイ!と意気込んでイパネマやレブロンのビーチをそぞろ歩いても、調子の良いサンバばっかりで、全くボサノヴァを演ってるライヴハウスなんて無かったですね。
先ずは玄関先です。
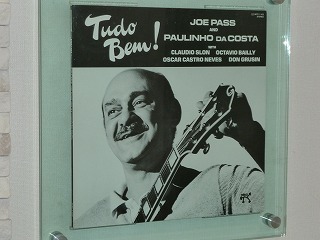
ちょっと時代は後になるのですが、贔屓のジャズギタリスト、Joe Passの傑作ボッサギターアルバム、「Tudo Bem!」です。
Tudo Bemとは、ポルトガル語で、「ご機嫌いかが?」という意味です。
冒頭から、名曲「Corcovado」がご機嫌な調子で流れてきます。もう、この時点でこのアルバムの虜になってしまいます。
私は、このアルバムは栄のジャズ喫茶「YURI」で知ったのですが、あまりの調子の良さに、リズムを取る足の振動がついついでかくなり、横にいたOL達が「すわ、地震!」と大騒ぎしていました。(脚色大)
二曲目はヒートアップした昂りを冷ますように、ジェントルなバラッドに癒されます。こういう曲でのジョーパスは本当に巧い!
私のお気に入りジャズギタリストは、彼の他にはバーニーケッセル、ケニーバレル、ハーブエリス、ラリーコリエル、ジミーレイニーなどなどですが、50、60年代の録音がもっと残っていれば、ジョーパスがトップに躍り出る事は間違いないでしょう。
三曲目は、あの「Wave」ですが、これまた凄まじくリズミックに仕上げられており、腰痛持ちの方でも、ノリノリで腰を振りそうです。
Don Grusinのたたみかけるようなピアノソロが気持ちいいです。
続いて待合壁です。

先ずはこれぞボサノヴァの金字塔ともいうべき超名盤「Getz / Gilbert」です。
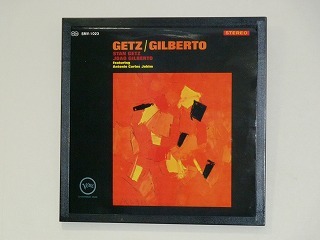
涼しげな抽象画からも内容が伺い知れますが、参加メンバーも曲目も演奏も何もかも素晴らしいの一言です。
プロデュ―サー、クリードテイラーの手腕は凄いものがありましたね。
スタンゲッツはもともとクールなテナー吹きでしたが、ボサノヴァとの相性は抜群でしたね。
加えて、ジョアン&アストラッドのジルベルト夫妻、ボサノヴァの大御所、アントニオカルロスジョビンといった大物が加わり、もの凄いアルバムが完成しました。
冒頭の「イパネマの娘」は誰もが知っている有名曲ですが、やはりこのヴァージョンが一番しっくりきますね。
呟くようなジョアンジルベルトの唄い方は後にマイケルフランクスが受け継いでますが、ポルトガル語の語感と相まって、何とも涼しげなムードを醸し出してます。
その後に続くアストラッドジルベルトの英語での唄は、必要以上にはっきりといきいきと聞こえますね。敢えて抑揚を無くしたちょっと素人っぽい唄い方は、Everything but the girlのトレ―シ―ソーンに影響を与えてそうですね。
フロリダでの留学中、暇をもてあましてバンド活動をアメリカ人達とやっていたんですが、ひょんな事から毎週火曜夜に別口でジャズセッションに参加するようになり、(シェリルクロウのデヴューアルバムみたい!)良くこの曲を演ったものです。全てが懐かしい・・・・。
アルバム通して極上のボサノヴァ名曲が続きますが、先の「イパネマの娘」と並んで有名なのは、A面最後の「ディサフィナ―ド」とB面頭の「コルコヴァド」ですよね。
共に(トム)ジョビンのペンによる名曲中の名曲ですが、これまでに幾多のアーティストがカヴァーしていますが、前者はあのジョージマイケルが90年代後期に歌ったヴァージョンが、後者はバーニーケッセルのこれまた渋いジャズギターアルバム、「Autumn Leaves」に入ってるバージョンもお勧めです。
そしてもう一枚。
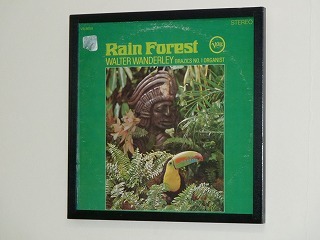
オルガン奏者ワルターワンダレイの代表作、「Rain Forest」です。
邦題は安易ですが、「サマーサンバ」・・・・。センスないなあ。
ジャケットの写真通りの熱帯雨林な?世界が展開されてます。
熱い(暑いではなく)のですが、どこかクールな矛盾した、不思議な感覚のするアルバムです。
ともすると、スーパーマーケットのBGMに陥りそうなものですが、ワルターのジャズ魂?がガチッと踏みとどまっているような感じです。
ジャズとイージーリスニングの違いはなかなか文章では説明できないのですが、やはり「ソウル~魂」を感じるか、否かですよね。
今月の壁レコード~AOR特集(昼編)(2013/07/23)
皆さま毎日暑いですね、日本は、地球は一体どうなってしまったのでしょうか?
私は45歳ですが、子供の頃は夏といってももうすこし過ごし易かった記憶があります。
今の子供たちはこんな灼熱地獄の中で部活に精を出しているんですよね。
日射病、熱中症にはホントに気をつけて頂きたいです。
さて、という訳で今回のジャケット特集は涼しげな音楽を特集してみました。
昼の海岸線をドライブするシチュエーションに最高な3枚です。
先ずはこれです。
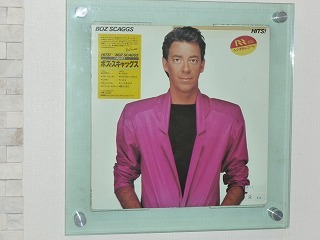
AOR四天王?の一人、Boz Scaggsの「Hits」です。
ベスト盤は本来は禁じ手なんですが、このアルバムはそんじょそこらのベスト盤とは一線を画しておりまして、ジャケット、曲順ともに練りに練り上げられてまして、オリジナルアルバムに準じられる完成度なんです。
特にA面は冒頭のロウダウンからスローダンサー、ミスサン、リドシャッフル、最後の「二人だけ」まで至福の時間が続きます。
シカゴにも同名の名曲がありましたが、ロウダウンはJeff Porcaroの叩き出す16ビートに乗って、いなせなボズの唄が聴かれます。
ご存知の方もいるでしょうが、実はこの曲って、TOTOの「Tale of the man」の間奏で聴かれる恐らくDavid Paichの編みだしたフレーズを発展させたモノなんですねえ。
ペイチはかなりボズに進言したんじゃないでしょうか?
「Silk Degrees」でのペイチの貢献度は計り知れないですし、(このセッションからTOTOが産まれたんですよね。)
3曲目の「Miss Sun」も、もともとはTOTOがレコーディングしていますからねえ。(アレンジも殆ど同じで、ヴォーカル以外はTOTOの方がカッコいい!)
数年前、TOTOがボズと共に来日した時は、めっちゃ期待したんですが、蓋を開けたら、それぞれのセットを中心に、最後に申し訳程度に共演しただけだったので、椅子を投げそうになりました。
2曲目の「スローダンサー」はJohnny Bristolばりのソウルフルな素敵な曲です。実は一番好きかも。
4曲目の「二人だけ」は未だにドラマやCMで使われるキャリアを代表する名曲、名唱ですが、原題「We're all alone」を「みんな独りぼっち」と世紀の?誤訳をしたリタクーリッジの担当者の顔が見たい!
あっ、因みにB面もサンタナのエモ―ショナルなギターが聴ける「トワイライトハイウェイ」やファンキーな「ジョジョ」は最高です。
お次はこの2枚です。

ジムメッシ―ナの傑作「Oasis」です。
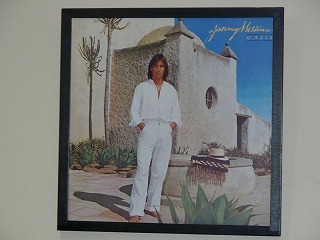
ケニーロギンスとの名コンビ(Loggins and Messinaについては、またしっかりと特集してみるつもりです。)を解消した後、第一線で活躍する元相棒を尻目に、サクッと肩肘張らない、それでいて聴きこむ度にスルメの様に味の出る名作を発表したメッシ―ナ。
ジャケットからはメキシコ~中南米辺り?のリゾートっぽい雰囲気が漂っていますが、ジムの顔つきからして、出身もそうなんだろうな、と思わせます。
A面一曲目からラテンフレーヴァ―満載のリゾートナンバーが飛び出してきて、これ聴きながら昼下がりの海沿いをドライヴすればホントに気持ち良いでしょうねえ。
二曲目はのっけからメッシ―ナの必殺パキパキテレキャスギターが炸裂する、ファンキーなノリノリなナンバーです。
途中の長~いソロがたまらないです。
そして、アドリブ誌をして、「これを聴かずしてAORを語るなかれ」と言わしめた、傑作バラッド「Seeing You」が厳かに始まります。
メッシ―ナにしては饒舌?なエモ―ショナルなヴォーカルがスリリングですが、名曲なのに意外とカヴァーされてないのは、完成度が高すぎるからでしょうか?
確かに、間奏のサックスや、エンディングで情感たっぷりに繰り広げられるギターソロはメッシ―ナらしい朴訥とした、決して饒舌ではないのですが、味のある誰にも真似できない完熟ぶりです。
そして、もう1枚です。
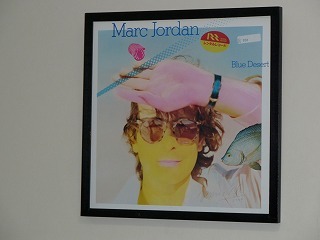
マークジョーダンの「ブルーデザート」です。
これは、ギターのジェイグレイドンを聴くアルバムと言っても過言ではありません。
冒頭の1、2曲で炸裂する伸びやかなギターソロは眩暈がする程官能的です。
これだけ弾ければ気持ちいいでしょうねえ。
Steely Danの「Peg」セッションで、並みいる強敵を退けて見事フェイゲン&ベッカーのお眼鏡にかなっただけあります。
マークジョーダンはこの前作「マネキン」があのGary Kutzのプロデュ―スなんで、やはりSteely Danづいてますね。
割と甘めな顔からは想像できない塩っぽいニヒルな歌声が完璧なAORサウンドに乗ると、何ともいえない味を醸し出します。
そんな所もドナルドフェイゲンっぽいですね。
今月の壁レコード ~ ウイングス特集(2013/06/10)
梅雨らしくない梅雨の真っただ中、皆様如何お過ごしでしょうか?
レコード自体は交換してはいたんですが、なかなかブログの更新ができませんでして、申し訳ありませんでした。
今回は先日リマスター発売されたライブアルバムが話題騒然のPaul McCartney&Wingsを特集してみました。
先ずは玄関先です。
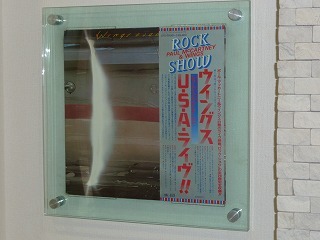
1976年に発表された前年のUSツアーの実況録音盤、「Wings Over America」です。邦題は「ウイングスUSAライブ」でした。
ツアー専用機?の格納庫が少しずつ開いていく様子を捉えたヒプノシスデザインのカヴァーですが、インナースリーヴ3枚裏表に渡って表現されている割には、面白くないんですよね。
ジャケットも3枚組なのに、ゲートフォールド二つ折りにて、ポスターがついてはいますが、何か予算ケチってるなあ?と最初は思ってました。
内容は、全盛期のポールのライヴなんで、悪いわけがないです。
冒頭の「Venus & Mars~Rockshow~Jet」のメドレーなんて、特にジェットの始まるとこなんざ、背筋がゾクゾクっとしてきます。
そもそも後期ビートルズでは叶わなかったコンサートツアーをしたいが為に結成したと言われる「Wings」ですから、ポールも唄にベースにピアノにギターに、八面六臂の活躍振りです。
勿論、リンダさんも頑張ってます。キーボードの腕は??ですが、バックコーラスはなかなか決まってますよね。
脇を固める相棒デ二―レイン、ジミーマッカロクも頑張ってます。
ジョーイングリッシュのドラムは個人的には・・・・・・。
今回、映像版「ロックショウ」もリマスターされ発売されましたね。
購入したものの未見ですが、「ベストヒットUSA」で数曲見ましたが、かなり色調が明るくなってますね。
私の持ってるVHSカセットでは真っ暗ですからね。
お次は待合室壁の2枚です。

先ずはウイングスとしての最高傑作、1975年の「Venus and Mars」です。後述しますが、ニューオーリンズで録音されております。
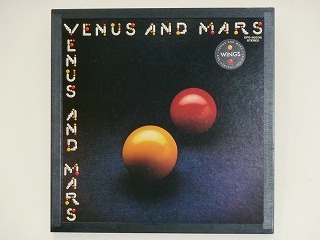
二つの球を金星と火星に例え、接写した写真はリンダさんが撮影したもので、同じようなモチーフは、ポールの最初のソロアルバム「McCartney」でも見られる手法です。
ジャケットのコンセプトは勿論ヒプノシスで、特徴あるレタリング~グラフィックはジョージハ―デイが腕をふるってます。
ゲートフォールド見開きの美しい壮大な写真はカリフォルニア州の何処かでヒプノシスによって撮影されてますが、デ二―レインが独りぽつねんと写っているのは御愛嬌ですね。
これまでのレコードセールの好調さから、会社から予算をふんだんにせびったとみえ、このレコードはおまけが充実しています。
ポスター2枚、ステッカー2枚、特製インナースリーヴ、特製レーベル。
何か、ピンクフロイドの「狂気」を彷彿させますね。
EMI社は太っ腹でしたね。
レコードA面は捨て曲無しの大傑作でして、冒頭の「Venus and Mars~RockShow」は勿論ですが、続く哀愁溢れるポールの唄が最高な「Love in song」、ビートルズ時代の「Honey Pie」にも通ずるボードビル調の「You gave me an answer」、賑やかな「磁石屋とチタン男」、ハードな「Letting Go」と、流れるような展開です。
一方、B面はデ二―とジミーにリードヴォーカルを任した曲もあり、あまり統一感がありません。
全米№1シングル「あの娘におせっかい」も、何か浮いて聞こえるんですよね。
そういえば、この曲の冒頭の多分ポールが喋ってるニューオーリンズ訛りのトークは、アラントウ―サンを真似てるんでしょうね。
この時期、1974年頃はアラントウ―サンが持て囃されていた時期でして、イギリスから幾多のアーティストがニューオーリンズ詣でをしたものでした。
特に、R&B系激渋シンガー3人衆?ロバートパーマー、フランキーミラー、ジェスローデンの御三方がそれぞれこの時期に録音した作品は、どれもが私に愛聴盤であります!(機会があれば、この3人を特集してみたいのです。)
さて、本来なら続く3枚目はこのツアーの直前に発表され、「心のラヴソング」の大ヒットを生んだ、(あと個人的に大好きな「Let 'em in」もいいい!)「Speed of sound」を持ってくるべきなんでしょうが、ジャケットの絵面がちょっとシンプル過ぎてつまらないので、これにしました。
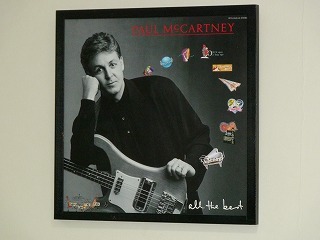
禁じ手ですが、ベストアルバム「all the best!」です。
それまでに出ていたベスト盤「Wings Greatest」はジャケットはつまらないんですが、シングルでしか聴けなかった作品を沢山収録してたんで、結構好きでした。
それに引き換え「All the best」は、ええっ、これがベスト盤に入っちゃうの~?という、編集の甘さはあるものの、まあ、多くのリスナーが納得する妥当なベスト盤です。
「Goodnight Tonight」が収録されてるのは個人的には非常に嬉しいです。
稀代の名曲「With a little luck」は、シングルヴァージョンでなくて、フルで収録して欲しかったです。(あの冗長な?間奏がよいのです)
「We all stand together」なんて入れるんなら、「So Bad」を入れて欲しかったなあ・・・・・。
しかし、こうしてシングルに切られた各曲を聴いてると、ポールの作曲能力は凄かったなあ、と改めて思い知らされます。
まあ、ポールはセルフプロデュ―スだと詰めの甘さが露呈してしまうので、こういう寄せ集めの方が良いのかも・・・・・。
その点、かのGerorge Martinが制作にあたった82年の「Tug of war」は完璧でしたよね。
今月の壁レコード ~ バートバカラック特集(2013/04/30)
いよいよ春到来ですが、朝晩は割と冷えますねえ。
世間さまは大型連休のようですが、当院はカレンダー通りでございまして、皆様が羨ましいです。
さて、暖かくなってくると、ハッピーな音楽が聴きたくなってきますね。
先日、無性にカーペンターズが聴きたくなり、いろいろ聴きましたが、やはり初期の如何にもA&Mカラーの出てた頃は何を聴いてもいいですねえ。
3作目に入ってる「バカラックメドレー」を聴いて、何て素晴らしいメロディーなんだろうと再認識しましたが、やはりバカラックの創りだす音楽は普遍的な素晴らしさがありますねえ。
という訳で、今回はバカラックの名作の数々をご紹介したいと思います。
先ずは玄関先です。
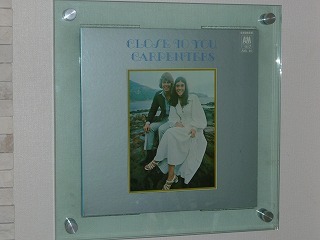
Carpenters / Close to youです。1970年の発表で彼等のセカンドアルバムで、邦題は「遥かなる影」といった、どこぞのプログレバンドみたいなシュールなものでした。
このアルバムには、「We've only just begun」、「(They long to be) close to you」といった彼等の二大代表傑作が収められています。
前者は結婚式のド定番ソングで、恥ずかしながら私も自身の式に使わせて頂きました(汗)。
もともとは銀行のCMソングだったそうで、リチャードカーペンターの選曲、編曲センスが光る大傑作ですね。
そして、後者は誰もが認める彼等の最高傑作でして、これは今回の主役、バートバカラック節が炸裂する超名曲です。
何気ないようで、計算されたピアノ、要所でアクセントをつけるドラム(これはやはりハルブレインなんでしょうね。PVではカレンが叩いてますが・・・。)、間奏の哀愁あるトランペット、すべてが素晴らしいです。
また、よく言われている事ですが、カレンの歌い方って、本当に一つ一つの単語を大切にはっきり発音していますよね。
意味は瞬時には解らなくても、単語自体はしっかりと聴きとれますよね。
次に待合壁です。

名画「明日に向かって撃て!」のサウンドトラックです。
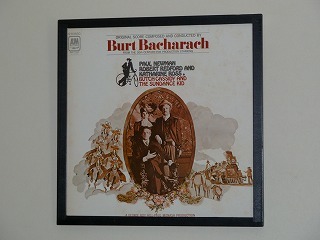
バートバカラックの最高傑作の一つ、「雨に濡れても」はBJトーマスの唄も相まって最高です。
映画もポールニューマン、ロバートレッドフォード、キャサリンロスと最高の布陣でした。
同じ監督(ジョージロイヒル)、ニューマンとレッドフォードのコンビでの1973年の「Sting」も素晴らしかったですね。
そして、時代は80年代に飛びますが、これまたキャリアを代表する名曲となった「Best that you can do」を含む映画「ミスターアーサー」のサントラです。
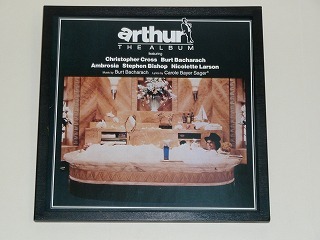
クリストファークロスのハイトーンボイスは当時人気絶頂でしたね。
フラミンゴのイメージで売ってましたが、ファーストアルバムは大傑作でして、今でもよく聴くアルバムです。
今月の壁レコード ~ デビッドボウイ特集(2013/03/27)
日に日に春めいて参りました今日この頃、皆さま如何お過ごしでしょうか?
花粉症に泣いている方々も多いと思います。私もその一人です。
完全に治す事は困難ですが、対症療法として少しでも症状を和らげる事は可能ですので、是非ご相談下さい。
さて、今回のレコード紹介は、10年振りの新作が話題のデビッドボウイを特集してみました。
正直ここ数作は凡作?が続いたボウイ様ですが、今回は気合が入っているようで、各種音楽雑誌がこぞって表紙に据えて特集を組んでいますね。
何でもあの70年代後半のブライアンイーノとの「ベルリン3部作」の頃を彷彿とさせるそうです。これは聴いてみたくなりますよね!
(実はまだ聴いてないんです、スミマセン・・・。)
という訳で、今回の3枚はその「ベルリン3部作」です。
先ずは玄関先です。
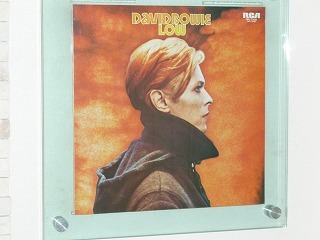
1977年に発表され最高傑作の一つに挙げられる「Low」です。
後にニックロウが、「Bowie」とパロってEPレコードを出しましたね。
流石パブロックの重鎮、やることがニクイですねえ。
内容的には、イーノの影響を受けたシュールでありつつもポップなA面とシンセサイザーを全面に出した重く陰鬱なB面と、表裏で全く変わった音楽を追求しています。
これはLPで聴かなきゃ駄目ですね。CDではわびさびも吹き飛んでしまいます!
A面ではNHK衛星放送の映画番組のオープニングにも使われた「Speed of life」、91年再発プロジェクトの際キャッチフレーズとして使われた?「Sound and vision」、B面ではコンサートのオープニングでギタリストのカルロスアロマ―が指揮している姿が印象的な「Warszawa」がお気に入りです。ベタでごめんなさい。
お次はこの2枚です。

これも1977年発表の「Heroes」です。邦題は「英雄夢語り」でした。
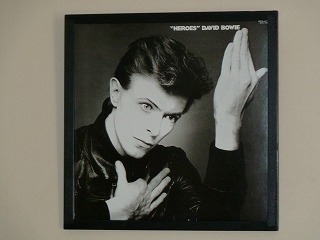
カメラマン、鋤田正義氏の撮影による素晴らしいポートレイトがジャケットを飾るこれまた傑作ですが、ロウにしろ、これにしろ、裏ジャケットはクレジットだけなんですよね。
これなんて、他にフォトセッションで撮られた良いカットが沢山あるのに、(日本盤シングル、ビーマイワイフに使われてるのは特に秀逸!)何で使わなかったんですかね??
A面は結構エグい、メタリック調の曲が目立ち非常にカッコいいです。
冒頭の「Beauty and beast」で聴かれる(多分)ロバートフリップのギターは鳥肌ものです。
タイトルトラックで70年代後期を代表する、とされる「Heroes」ですが、NHKヤングミュージックショーでは伸びやかなAdrian Brewのギターが良かったですね。
一方、B面ですが、クラフトワークは割と好きなんですが、ちょっとついていけないですねえ。失礼ながら、ナイトキャップとしてはいいかもしれません・・・・・。
そして、個人的には一番聴いた回数の多いアルバム、「Lodger」です。
1979年の発表で、邦題はボウイ自ら指名してきた「間借人」でした。
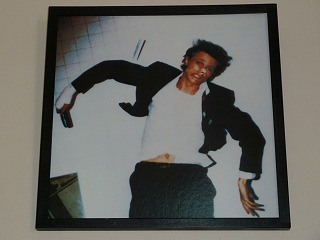
鼻がひしゃげた事故現場写真みたいなヘンなジャケットでして、見開くと何だか意味深な写真、イラストが載っています。
あまりこの事について言及される記事はないので、真意が解りかねますが、「レコードコレクターズ」誌今月号のボウイ特集で、興味深い考察がされており、カメレオンの様に、ファッションや音楽スタイルを変える移り気な自分自身を「間借り人」と表現しているらしいです。
内容はその通りで穏やかな「Fantastic Voyage」「Move on」、エスニックな「African night flight」「Yassassin」、如何にもボウイ流ロックの「Look back in anger」「Red Sails」などなど、雑多な曲調ですが、どれもが魅力的で、気付くと全編聴いてしまっています。
演奏陣も、ノリノリでして、B面3曲目の「Boys keep swinging」ではメンバーが楽器の交代してるんですよねえ。ギターのカルロスアロマ―がドラムを叩いて、ドラムのデニスデイビスがベースを弾いたり・・・それでもお遊びではなく、しっかりとしたサウンドになっているのは勢いなんでしょうね。
という訳で、ベルリン3部作、ご紹介しました。
この後、若干同じ路線の「Scary Monsters」を1980年に発表した後、1983年にあの「Let's Dance」を発表し、一大ブレークする訳ですが、あのアルバムはナイルロジャースの色が出すぎで、今では中古レコード屋の100円コーナーに押し込まれてしまってますね。
個人的にはTony Thompsonのドラムが好きなのでナイルロジャース関連作は嫌いじゃないですがね。
因みに全時代を通して好きなアルバムを挙げると・・・
*Hunky Dory
*Alladdin Sane
*Pin ups
*Lodger
ですかね・・・・・。
それではごきげんよう。
今月の壁レコードジャケット ~ パブロック特集!(2013/02/21)
まだまだ寒い日々が続きます。一年で最も寒い時期とはいえ、辛すぎます。
おかげで?ウチの副院長(小生の親父)が、体調をくずしてしまい、長期療養中であります。
幸い、かなり良くなってきましたが、暫くは様子をみて医院での仕事は控えてもらおうと思っております。
そういう事もあり、ここ最近忙しくてブログの更新もままならない状況でした。申し訳ありませんでした。
ジャケット自体はかなり前から変えてはいたんですが・・・・・。
さて、今回はちょっと渋い所で、パブロックのアーティストを特集してみました。
最近ひょんな事から、昔買ったStiff Recordのボックスを聴きまくっており、やはりあの時代のイギリスロックは素晴らしかったなあ、と独り再評価?している次第であります。
パブロックとは普通のロックからパンクロックに至るまでの過渡期的なモノ、とする向きもあるようですが、うまく定義づけられませんが、パブロック!といえばその筋の御仁にはニンマリされる、通をうならせる渋い音楽であることは間違いありません。
イギリスの庶民の交流場として欠かせないPub、私も学生時代英国放浪の旅をした時に、毎晩あちこちのパブに入り浸ってましたが、やはり「町の社交場」なんで、ロンドンはともかく、地方都市のパブでは変な東洋人、的な数奇な眼で見られてましたね。
そんなパブでは良く、バンド演奏が入りますが、大体皆R&Bをベースにした肩肘ばらない酒のすすむ?渋いロックを演奏していました。
まさにそれこそがパブロックの定義だと思います。
では私のお気に入りのアルバムをご紹介します。
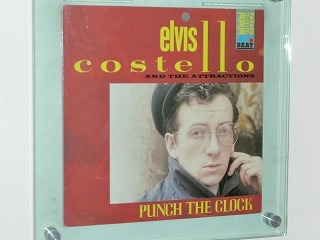
Elvis Costelloの個人的には最高傑作、83年の「Punch the clock」です。
厳密にはこの時期のコステロはもはやパブロックの範疇を通り越して、ビッグネームになっており、このアルバムも確か全英№1になっているんですね。
でも、やはりスティッフからレコードを出してた初期のコステロは如何にもパブロックでしたよねえ・・・。
パンクの範疇にも入れられる事もありますが、何かちょっと違うんじゃないかな、と思います。
このレコードはほぼリアルタイムで聴いたのですが、金太郎飴のように次から次へと出てくる名曲の数々にノックアウトされましたねえ。
特にA面は全ての曲がシングルカットできる程、素晴らしい出来です。
特に好きなのが5曲目の「Love went mud」でして、小気味良いSteve Neiveの鍵盤さばきは素晴らしいです。
そして、A面最後の「Shipbuilding」ですが、Robert Wyattのバージョンもいいですが、コステロ版もいい味を出しております。
特に、Chet Bakerのトランペットは哀愁味溢れる素晴らしい効果を出しており、80年代のベストプレイの一つに挙げられると思います。
当時私は高校一年でして、ジャズには門外漢だったのですが、インサートにコステロよりもでかい顔で写ってる彼に非常に興味を持ちました。
その後、「Chet Baker Sings」を聴いて一挙に彼の虜になり、いろいろ聴きあさりました。またChetについては書かせて頂きたいと思います。
さあ、B面に移りましょう。
A面に比べると、ややキャッチ―なメロディーが少ないんですが、しんがりに凄い曲が登場します!
「The world and his wife」、邦題は何と!「コステロ音頭」!!
何じゃそりゃ!と思うでしょうが、聴いてみれば納得納得の名邦題です。
ラッパのリフがまさに「音頭」なんですよ。眼を閉じて聴いていると、ドラえもんとかオバQが法被を着て踊ってる姿が浮かんできます。
歌詞の事は全くすっ飛ばして、曲調だけで邦題を決めてしまうなんて当時の担当さん、粋だなあ。
フランクザッパの「〇△□」なんてハチャメチャなのもありましたが、昔の洋楽担当ディレクターの権限は凄かったんですねえ。
お次の2枚です。

この2枚はまさにパブロックの超名盤!これを聴かなきゃ始まらない!的なレコードです。
先ずはIan Duryの最高傑作「New boots and panties」です。
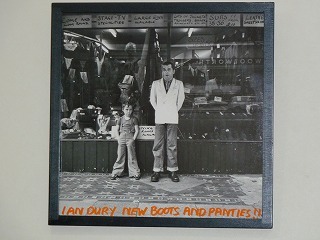
何ともいかがわしいというか、下世話なジャケットですが、中身もやはり相当にぶっ飛んでる愛すべきアルバムです。
Nick Loweと Elvis Costelloという二代看板に去られたStiff Recordを救った?のはやはり彼でしょう。まさにレーベルを代表するアーティストでしたね。
パブロックの連中は後述のDr.FeelgoodのようなR&Rをベースとしたバンドが多いのですが、彼とバックバンドのBlockheadsはファンクを取り入れた黒っぽいサウンド創りがいかしてましたね。
バンマスのChaz Junkelのセンスもあるのでしょうね。彼が脱退してからは少し雰囲気が変わってしまいますから・・・。
このレコードも全曲捨て曲なしの文句なしの名盤です。是非聴いてみて下さい。人生変わりますよ!?
そして、パブロックといえばこのバンド、ドクターフィールグッドです。
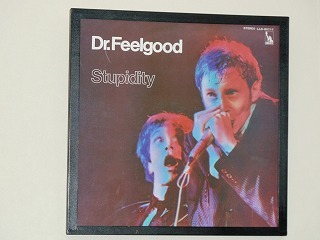
3枚目の傑作ライブアルバム「Stupidity」です。邦題は「殺人病棟」!
何とまあ、恐ろしい病院だこと。大体、前作の邦題も「不正療法」だったし、いくらバンド名にドクターがついてるからって、ちとやりすぎなんじゃないの、当時の担当者さん!
気を取り直してまいりましょう。
このバンドはリーブリローの塩辛い?ダミ声ボーカル(AC/DCのボンスコットもそうでした)とハーモニカ、ウィルコジョンソンのマシンガンギター(ソロを派手に取るんじゃなくて、ひたすらコードを掻き毟る)の二代看板が売りのシンプルなロックンロールバンドでした。
特にWilko Johnsonの人気は日本でも絶大でして、今でもライブをやればソールドアウトでしょうね。
彼の逸話にまさにパブロックの本質を代弁している名言がありますので、それを引用させて終わりとさせて頂きます。
当時パブシーンで人気上昇中の彼等のステージを見に、とあるパブにやってきたスパークスという人気バンドのマネージャーがウィルコを引き抜こうとしてこう言います。
「君はどうしたいんだ?(有名バンドに入って)プロフェッショナルなミュージシャンになりたいのか?それともあんな(パブに入り浸っているようなくだらない)奴らと一緒に無駄に時間を過ごしていたいのか?」
それを聞いてウィルコジョンソンが言った言葉です。
「あんな奴らと時間を無駄に過ごしていたいんです!」
あけましておめでとうございます。今月の壁レコ ~ 蛇特集!(2013/01/12)
遅くなりましたが、皆様、明けましておめでとうございます。
今年もスタッフ一同、頑張ってまいりますので宜しくお願いします。
さて、恒例の干支特集ですが、今回は巳年なので、蛇をモチーフとしたジャケットを特集しました。
先ずは玄関先です。
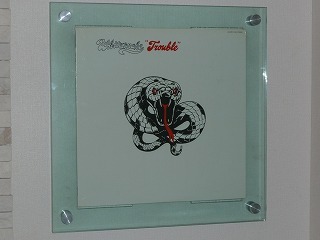
まさに白蛇!Whitesnakeの1作目「Trouble」です。
David CoverdaleがDeep Purple解散後、2枚のソロアルバムを経て、有能なメンバー(ギターにはBernie MarsdenとMicky Moodyという渋い二人を揃え、キーボードには何と!Purpleのリーダーだった惜しくも昨年鬼籍に入ったJohn Lordを引っ張りこみました。ベースも名手Neil Murrayでした。)と共に結成した、ブルージーなハードロックバンドWhitesnakeですが、私がロックを聴き始めた80年代初期は非常に人気があり、よく聴いたものです。
特に、ドラムがあのIan Paiceにチェンジした「Ready & Willing」からは疑似パープルみたいな感じがして、ハードロックの様式美を求めるファンからは絶大な人気を得ました。
名曲「Fool for your loving」は昔やってたバンドでカヴァーしましたねえ。
お次はこの2枚です。

両方とも、蛇顔のアップに赤い背景という点は共通してます。
まずはBlackhootです。
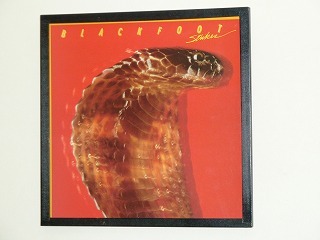
このバンドはアメリカ南部出身というので、サザンロックみたいな感じかと思いましたが、割とストレートなハードロックでしたね。
あまり聴きこんでおりませんので、詳細はカットさせて頂きます。
そして、ステージでも蛇を首に絡ませてたという、まさにショックロックのAlice Cooper初期の傑作「Killer」です。
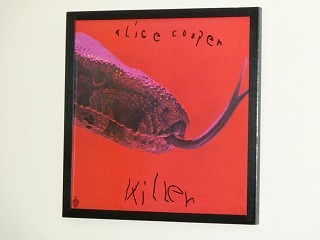
70年代前半の彼等の人気は絶大なものがあり、出すアルバムは皆チャートの上位に君臨していました。Billion Dollar Babiesのように全米№1になったものもあります。
何しろ売れに売れたようで、所属レコード会社のワーナーも太っ腹でして、変形ジャケットやポスター類のおまけの大判振る舞い!
コレクターにとっては集めがいのある作品ばかりで嬉しいバンドでした。
70年代後期から失速しますが、80年代後期にLAメタルブームの余波をかって奇跡的?に復活したのは嬉しかったです。
日本では蛇はけっこう神聖なものとして崇められてますが、欧米ではどうでしょうか?
今回のジャケットでもそうですが、凶暴でおどろおどろしいもの、気をつけなくてはいけないもの、として負のイメージが強いように思いますが、如何でしょうか?
いろいろ捜しましたが、あまり可愛らしい蛇のイラストってないんですよね。
同じハ虫類でもワニなら、あったりするんですが・・・。(Hampton Hawesのコンテンポラリーから出てるトリオ第3集で、あの名古屋のジャズ喫茶「Yuri」の看板にも使われてます。)
今月の壁レコード~Paul Simon特集(2012/12/03)
師走に入り、流石に寒くなってまいりました。
皆様、お忙しい事とは思いますが、体調管理、大事ですよ!
さて、先日録り溜めたDVDを整理していましたら、衛星放送で放映されてたアメリカの「Saturday Night Live」がまとまって出てきました。
今でも確かNBCで放映されている筈ですが、今はmusical guestはどんなアーティストが出ているんでしょうか?
この番組の売りは、毎回キラ星の如く素晴らしいミュージシャンが惜しげもなく?生演奏を2~3曲披露してくれる事でして、むか~しNHK衛星でも何度か特集され、必死で衛星システム持っている知り合いに頼み録画させてもらったものです。
1975年のスタート当初は、如何にもニューヨーク!という雰囲気が漂ってまして、(何しろ、オープニングは無名時代のChevy Chaseが寸劇の後に、「Live from New York, It's a Saturday Night!」とキメるものでした。)今見ても大人の番組だなあ、という感じがします。
そのSNLに何度も登場し、準レギュラー的な存在感を示していたのが、あのPaul Simonです。
放映第二回目では番組ホストとして、唄は勿論のこと、司会、進行、コントまでやってのけます。
しかも、Art Garfunkelを引っ張りだしてきて「ボクサー」「スカボローフェア」をハモッてくれるんですよ!
丁度限定復帰?シングル「My little town」を出した頃だったから、あまりサプライズは無かったかもしれませんが、確か82年まで共演ライブはなかったから、貴重な映像ですけどね・・・。
という訳で、今回の壁ジャケットはPaul Simonを特集してみました。
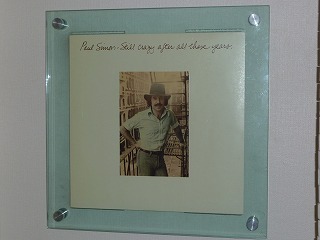
1975年の傑作「Still crazy after all these years」です。
邦題は「時の流れに」でした。
ガーファンクルとのコンビ解消以来、ポールサイモンはどちらかといえば、フォークやロックなどの白人音楽以外の音楽、例えばレゲエ(当時はレガエ)や、リズム&ブルース、ニューオーリンズジャズ、第3世界の民族音楽など、自らの引き出しを広げて雑多なノンジャンル音楽を展開していたように思います。
そんな彼が離婚を機に(多分)、ニューヨークで孤独感に浸りながら辣腕ミュージシャンと創り上げた傑作だと思います。
勿論、前作「ひとりごと」でもみられたマッスルショールズ録音のものもありますが、全体に流れる寂寥感、夜のしじまに、といった雰囲気は紐育を強く感じさせるものです。
冒頭のタイトル曲のオープニングの印象深いエレクトリックピアノ、てっきりRichard Teeだと思ってましたが、実はBarry Beckettなんですねえ。
他のミュージシャンも、スタッフ関連かと思いきやマッスルショールズリズムセクションなんですね。
間奏のMichael Breckerのサックスソロも素敵ですが、SNLでのDavid Sanbornのソロも負けず劣らずでしたね。
心地よいエレクトリックピアノの余韻を引きずりつつ低いピアノの音で始まる2曲目の「My little town」ですが、これは先述したように久々のガーファンクルとの公式録音でして、同時期に発表されたガーファンクルのソロアルバムにも収録されています。
でも、やっぱりサイモンのアルバムに入ってた方がしっくりきますね。曲順もここしかありえない!って感じがします。
これもマッスルショールズリズムセクションがバックですが、こういった曲での彼等は水を得た魚のようにいきいきとしたビートを叩き出しています。特にDavid HoodとRoger Hawkinsのリズム隊が素晴らしい!
3曲目の「I do it for your love」こそ、このアルバムでサイモンが最も言いたかった内容ではないでしょうか?CDの詳しい解説を読んで納得しましたが、ペギーとの離婚はかなりこたえたみたいですね。
もの哀しい旋律もいっそう寂寥感に拍車をかけています。
4曲目の「50 ways to leave your lover」は、Steve Gaddが練習中に何気なく叩いていたリズムパターンを元に創られた曲で、シンプルな作風ながら全米一位に輝いています。
このドラムパターン、簡単なようですが、なかなかあの味は出せません。
やはりガッドは凄い!
ビルボード名古屋で彼のドラミングを真近に見る機会がありましたが、ジョンボ―ナムよろしく4sticksで叩きまくる勇姿に圧倒された覚えがあります。
A面最後はトゥーツシールマンスの職人芸ハーモニカをフューチャーした「Night Game」です。
これこそnight musicといいますか、昔これを聴いてから寝る習慣になっていた時期がありました。
曲調、演奏共に何となく冬の凍てついた紐育を彷彿とさせるものがあります。今の時期にピッタリです。
B面はA面に比べるとあまり聴きこんでないのですが、一曲目の「Gone at last」は当時売り出し中の才女、Phoebe Snowが客演しており、いい雰囲気のデュエットになっております。
シェルターレーベルから出した傑作デヴューアルバムに続いて、コロンビアに移籍してPhil Ramoneのプロデュースにて発表した彼女のセカンドアルバムはジャケットといい、参加ミュージシャンといい、曲調といい、「時の流れに」と兄弟アルバムのように似ています。
これも傑作なので是非未聴の方は聞いてみて下さい。
このアルバムでグラミー受賞も成し遂げたPaul Simonですが、この後、創作意欲が低下したのか、ベスト盤や、映画出演とそのサウンドトラックの発表はありましたが、純粋な新作集は1982年まで発表されませんでした。
ただ、TV出演などは盛んだったようで、SNLにも何度か登場し、あのGeorge Harrisonと即席デュオを組んだり、(これは素晴らしかった!)エンターテインメント界での交遊を通じてか、女優キャリーフィッシャー(スターウォーズのレイア役で有名)と再婚したり、話題には事欠かなかったですね。
1986年には問題作「Graceland」を発表し、またまたグラミー賞を獲得しますが、この後はチャート的にはともかく、音楽面では新しいヒットを出せないでいるようです。
私も、新作はなるべく追っかけてはいたんですが、あまり印象に残った作品は無いです・・・。
という訳で、過去の作品にバックしてみましょう。
待合壁の2枚です。

世評的には彼の最高傑作とされる、1973年の「ひとりごと」です。
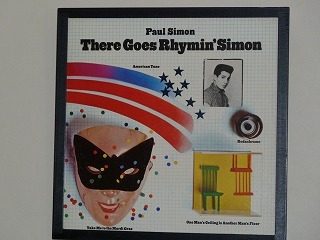
原題は「There goes rhymin' Simon」です。
仕事も家庭も絶頂?期の作品なので悪い訳がありませんが、これほど多彩な音楽性を大衆性を損なわずに表現できたアルバムもそうはないでしょう。
冒頭のマッスルショールズ録音の躍動的な「Kodachrome」から、一転してアンニュイなムード漂う「Tenderness」が始まります。ゴスペルライクなコーラスをフューチャーした佳曲で、個人的にはこのアルバムの白眉です。
3曲目はニューオーリンズの情景漂う「Take me to the Mardi Gras」です。留学時代にマルディグラ祭を観に行った事がありますが、ちょっと変わった(ここでは書けない)奇習?の事もあり、今でも忘れられません。
4曲目は名曲「Something so right」です。後の「時の流れに」へ繋がる都会的なサウンドが聴かれます。良い曲ですよね。
B面は一曲目の「American' tune」と最後の「Loves me like a rock」が群を抜いてます。
前者は非常に評価が高く、アメリカの第二の国歌だ、なんて声も上がったほどですが、個人的にはあまりピンときません。
後者は解説の小倉エージさん曰く「悪乗り」と評される程、シニカルな彼には珍しい程の明るい(逆ハイ?)熱唱が聴かれます。
これもSNLでゴスペルグループをバックにアツ~く歌われてました。
もう一枚は何にしようかと悩んだのですが、やはりこれにしました。
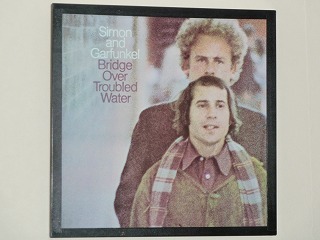
Simon & Garfunkelとしての最終作「明日に架ける橋」です。
1970年の年間チャートをシングル、アルバム両部門で制覇した名盤です。
ラリーネクテルのピアノが印象的な、いかにもガーファンクルが鼻の穴を拡げて(失礼!)熱唱してそうな表題曲も素晴らしいですが、民族音楽好きのポールらしい「コンドルは飛んで行く」や、シンプルなリズムに猥褻な歌詞をのっけた「セシリア」、S&Gとしての最高傑作の一つ、サイモンらしいシニカルな歌詞が光る「ボクサー」など名曲満載のアルバムです。
数年前、S&Gとして来日した際には名古屋ドームまで観に行きましたが、やはり「明日に架ける橋」は腰の重い中高年をも総立ちにさせるパワーがありましたね。
個人的にはサイモンの「時の流れに」が一番嬉しかったですねえ。アレンジもキーも殆ど変えてなかった所も良かったです。
今月(先月)の壁レコード ~ Bob Dylan特集(2012/11/05)
11月になり、流石に肌寒く感じられる今日この頃ですが、皆様如何お過ごしでしょうか?
遅々として更新されないこのブログですが、あまりにも趣味に走りすぎてます故、先月終わりから「院長のひとこと」として、医療関係の情報発信も始めさせて頂いております。
トップページからお入りくださいね。
さて、今回のレコードジャケットは新作も好評なBob Dylanを特集してみました。
先ずは玄関先です。
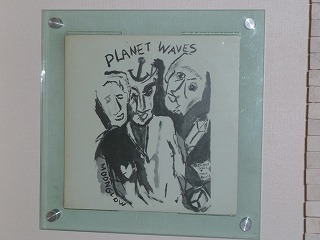
1974年発表で全米チャート№1にも輝いたThe Bandとの共演アルバム「Planet Waves」です。
この味のある、へたうま?イラストも彼の筆によるものです。
私はこのアルバムが大好きで、特にA面は次から次へと名演のオンパレードで針を上げる暇もありません。
交通事故から復帰して初めての全米ツアー目前という事もあり、ディランの張り切った唄とハーモニカも最高ですが、油の乗りきったいぶし銀の演奏を聴かせるザバンドの面々も素晴らしいです。
特にRobbie RobertsonのギターとRick Dankoのベースが絶好調で、これぞ唄伴!といった名演を聴かせてくれるんです。
3曲目の「タフママ」、4曲目の「ヘイゼル」、5曲目の「君の何かが」の3連発はホント心に染みてきますねえ。
お次は待合室壁です。

これぞディランの最高傑作「追憶のハイウェイ61」です。
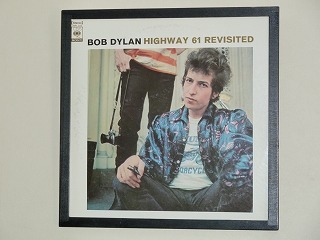
60年代後期のアメリカを代表する名曲「Like a Rolling stone」から始まり、最後の「Desolation Row」まで、神がかった?名曲、名演が続きます。
まさにマスターピース!時代を超えた名盤です。
個人的にはA面最後の「やせっぽちのバラッド」がお気に入りで、「Do you? Mister Jones」のキメを何とは無しに呟いている事がよくあります!?
これのモノラルのUSオリジナル盤が欲しいんですが、なかなかお目にかかれませんね。
次は本来なら「Blonde on Blonde」とくるべきでしょうし、実際そうしてみたんですが、何かベタすぎるので、敢えてこれをもってきました。

1970年発表の「Self Portrait」です。調べてみたら、米キャッシュボックス誌でディラン初の№1アルバムとなったそうです。意外ですね。
この子供が書いたような絵も彼自身の筆によるものであり、強烈なインパクトがあります。
横に「おとうさん」と書いてあっても違和感ない・・・・。
たまに患者様が「お子さん絵がお上手ですね。」・・・・なんて言う訳ないですよ!
内容はまさに寄せ集めであり、中村とうようサン曰く「オレハタダノぽっぷしんがーナノダ」という主張の元に、歌手としての表現を全面に出した作品集です。私は数回聴いただけですので、あまりこれを評論する資格はありません。
今月の壁レコード ~ キングクリムゾン特集!(2012/09/29)
朝晩はかなり過ごし易くなってきて、ようやく秋らしくなりましたね。
皆さん如何お過ごしでしょうか?
先日いきつけの中古レコード屋さんで、あの「クリムゾンキングの宮殿」のイギリスオリジナル盤(マニアの為に記しますが、マトリックスはそれぞれ”3”なので、それほど自慢できないのですが・・・)を入手する事ができまして、改めて聴きこんでみると、その素晴らしさに圧倒されっぱなしです。
という訳で、今回のジャケットはKING CRIMSONで特集してみました。
まずは玄関先ですが、「宮殿」は待合室でじっくり?観賞して頂きたい事もあり、後回しにしまして、1973年発表の「太陽と戦慄」を飾りました。

これは、リーダーのRobert Frippが当時心酔していた白魔術師Walli Elmlarkに影響されて、メカニカルなインプロビセイション主体な音楽を創る、という名目で結成した「第二期」キングクリムゾンの第一作です。
原題の「Lark's tongues in aspic」の解釈はいろいろ書かれてますが、白魔術師Elmlarkからきている、という説を私も信じます。
白魔術とは、別名錬金術ともいいますが、その内容は「黒から純粋の色である白へ辿り着く事を目的としているが、その探求の究極の結果に赤がある」という事らしいです。
後に「Red」というアルバムを出す事になるのは、「やり尽くした」事の表れでしょうか?
イラストは太陽と月の不気味なイラストでして、夜誰もいない部屋でこれを見ながら重厚な音を聴いているとうすら寒くなってきます。
次は待合室壁です。

「宮殿」は最後にさせて頂き、左側、ちょっとビートルズの「With the Beatles」を意識した?と思われる第二期の最終作「Red」です。
(ライブ盤の「USA」は蛇足と思うのです。契約上の最終作であり、フリップは不本意だったと思われます。)
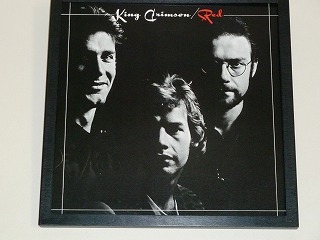
これは何というか、プログレというよりへヴィメタルと言った方が良いかも知れません。それ位ソリッドでカッコいいリフが続出です。
さっき、「With the Beatles」みたい、といいましたが、A3「再び赤い悪夢」がいきなりバッサリと終わるとこなんか、「Abbey Road」のA面最後の「I want you」と酷似してます。
考えてみれば、両方とも、これで解散するんだ!という意気込み?で創られたという点も共通してます。
そして、いよいよこれです。
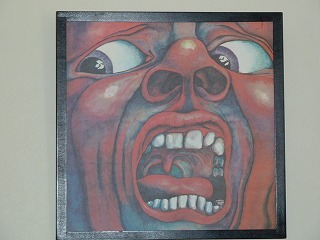
1969年10月に発表され、音楽関係者に絶賛され、あの「Abbey road」をチャートから引きずりおろした?と言われてる位一般受けもした、ロックの範疇を飛び越え、20世紀音楽の至高の一枚であります!
このアルバムを時代を超えた名盤たらしめているのは、ひとえにメンバーの組み合わせの妙に尽きると思います。
勿論、最終的にはリーダーのRobert Frippのコントロール下によるものでしょうが、美しく朗々としたGreg Lakeのヴォーカル、ジャズに影響された繊細で驚嘆すべき細かいスティックワークのMichael Gilesのドラム、
(この人は私のフェイヴァリットドラマーの一人です。)
バンドにクラシカルなエッセンスを注入したマルチミュージシャンのIan McDonald、幻想的かつ思慮深い歌詞を提供したPete Sinfield
この5人の誰が欠けても、この類い稀なるサウンドは生まれなかったと思います。
中でも、Ian McDonaldの存在感は絶大なものがあったでしょう。
第一期クリムゾンの前身、Giles,Giles&Frippとは全然スケール感が違います。
「風に語りて」、「エピタフ」の抒情性は彼なしでは成り立たなかったと思います。
クリムゾン脱退後、Michael Gilesとコンビを組んで創った「McDonald and Giles」は「風に語りて」を拡大希釈したような、牧歌的なヒューマンなサウンドで、クリムゾンを過度に期待して聴くと肩透かしを喰わされますが、これはこれでなかなか良い作品です。
その後、1977年に、後期Spooky Toothの影のリーダー、Mick Jonesと組んだ「Foreigner」で第一線にカムバックしましたが、徐々にポップ化するサウンドに耐え切れなくなったのか、3作目で脱退してしまいます。
先日BSテレビでやってる「Songs to soul」で元気そうな姿が見れましたが、唯の爺さんになってしまってました。
今月の壁ジャケット ~ 水!!(2012/08/31)
8月も終わりだというのに、まだまだ日中は暑いですね。
そんなこんなで、今回の壁ジャケットは「水」をフューチャーしてみました。暑気払いに如何でしょうか?
先ずは玄関先です。
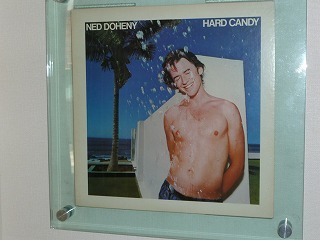
Ned Doheney1976年の名盤「Hard Candy」です。
思いっきりシャワーを浴びて(浴びさせられて?)いるNedがキュート?なジャケットですね。
たるんだお腹が育ちの良さを醸し出していますが、彼はLAの資産家Doheney家の御曹司だそうです。
LAをドライブした時、交差点に「Doheny St.」と標識があるのを発見してなるほど、と一人悦に入ってました。
アサイラムからのデヴュー作もなかなか聴かせますが、このコロンビア盤はSteve Cropperのプロデュースとは思えない程、洗練された素晴らしいサウンドを聴かせてくれます。
特にA面は全く無駄のない完璧な流れでして、曲、ネッドの唄、バックのサウンド、構成とも最高です。
彼方から聞こえてくるミステリアスなイントロから始まる1曲目、EaglesのGlenn Freyと Don Henleyが魅惑的なコーラスをつける2曲目、ブラスを効果的に使った3曲目に続いて、稀代の名曲といえる4曲目は涙なしには聴けません。
B面も最後の「Varentine」は哀しげな旋律が「夏の終わり」を彷彿させて、この時期にピッタリです。
続いて待合室の壁です。

この2枚は何か雰囲気が共通してますね。
先ずはNirvanaの時代を変えた?一枚「Nevermind」です。
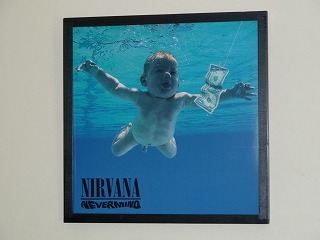
これは、何というか、ブラックジョークの極致、といった感じですね。
でも面白い!!
次はArgentの「In Deep」です。
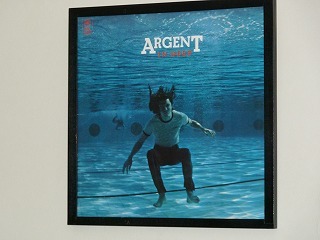
これはあのヒプノシス作なんですが、何か間が抜けた感じがいいですね。
今月(先月?)の壁レコード ~ スタイルカウンシル特集(2012/08/02)
酷暑の中、皆様いかがお過ごしでしょうか?
熱中症にはくれぐれもお気をつけくださいね。
さて、ロンドンオリンピック真っただ中ですが、開会式でのポールマッカートニー、貫禄でしたね。
やはり、誰もが認める英国を代表する存在なんですね。
ただ、私的にはもっとも英国、イングランドを連想させるアーティストとしては、ポールウェラーなんですね。
という訳で、今回の壁レコードは、彼が結成したStyle Councilを特集してみました。
先ずは玄関先です。

1984年の1stアルバム「Cafe Bleu」です。
これは高校1年の時に出たんですが、テープに落として登下校時にウォークマンで聞きまくりましたね。
まだ田舎のガキんちょにとっては、お洒落でジャジーなサウンドが未だ見ぬ都会生活への憧れを増幅させ、たまりませんでした。
当時流行してた「カフェバー」なんかでよくかかってたらしいですが、深夜テレビで「ガルボクラブ」「ラテンクオーター」などの名古屋のお店のCMを見ては「早く大学生になりたい!」などと妖怪人間みたいな呻きを発していた事を思い出します。
肝心の中身ですが、Mick Talbotの粋なピアノで始まり、これまたいなせなPaul Wellerの張りのある唄と、意外に巧みなジャジーなギタープレイが光る冒頭の2曲で早くもノックダウンされます。
続く3曲目と4曲目はインストですが、やはりジャム時代にはなかった余裕が感じられます。後者のポールのギターは素晴らしい!
そして、Everything but the girlの二人をゲストに迎えた名曲「The Paris Match」です。
ポールの唄バージョンもいいですが、Tracy Thornの物憂げでアンニュイな唄は仏映画「死刑台のエレベーター」で恋人に待ちぼうけされ(実際はエレベーターに閉じ込められてたんですが)、パリの街を彷徨うジャンヌモローを彷彿とさせ、素晴らしい出来です。
そしてA面のハイライト、ポールの名唱が聞かれる「My ever changing moods」です。
ジャズボッサ調のアップテンポヴァージョンもカッコいいですが、ミックのピアノ伴奏のみで朗々と歌われるこちらの方が、歌詞の重みと相まって、ズシリと心に入ってきます。
最後のインストはちょっと冗長な感じにて、B面にうつります。
1曲目と2曲目は今聞くとちょっとしんどい、時代を感じさせるアレンジですね。(昔から早送りしてました・・・すみません!!)
3曲目からは名曲揃いです。
美しい旋律とミックタルボットの可愛らしい?ハモリも聞ける「You are the best thing」、スタッフスミスみたいな子粋なフィドルが楽しい「Here's one that got away」、DC Leeも大活躍の「Headstart for happiness」、タルボットのJimmy Smithばりのオルガンも聞かれる「Council meetin'」と針を上げる暇もありません。
ジャケットですが、これは文字通りパリのカフェをイメージしてるんでしょうが、力関係を表した?と言われるポールとミックの写真比率が面白いですね。
後にミックのドアップ写真の12インチシングルを出したのは、この時のフォローだったのでしょうか?
次に待合室です。

御次は翌1985年に出された最高傑作「Our favorite shop」です。
これは高校2年の夏に日本で出され、当然のように聞きまくりました。
この頃の彼等は本当に人気ありましたよね。
あの「Live Aid」もこの年の夏でして、徹夜してビデオに収めたものです。よく言われてるように、日本のテレビ局の音楽への愛情の感じられない放映スタイルには憤りを感じましたね。観ていた方、皆同じ思いだったのではないでしょうか?
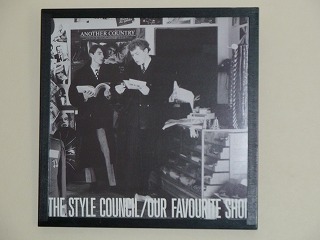
このLPはホント捨て曲が無く、素晴らしい演奏と唄がつまった名盤です。
一作目よりアレンジが練られて音の厚みが増した分、演奏から解放されて?ポールも歌うことに集中している感じです。
個人的に好きな流れは、A面2曲目から3曲目。もろボサノバの「All gone away」から間髪なくSteve Whiteのスネアで始まる「Come to Milton Keynes」はヘンテコなPVも最高でした。
B面も3曲目の「Lodgers」から4曲目の「Luck」と超名曲のダブルパンチはいつもヤラレます。
この頃はDC Leeと結婚してたんでしたっけ?息もぴったりです。
あと、フルートが効果的に使われてるボサノバチックな「Everything to lose」も、キャッチ―なシングル曲「Shout to the top」も、当時は訳も解らず聴いてた、政治的なリリックの「Walls come tumbling down」も素晴らしいとしかいいようがありません。
後期ジャム時代からこの頃までのPaul Wellerの創作能力は神ががっていましたね。
残念な事に、この後からだんだん作品の質も、演奏も時代とそりが合わなくなったのか?低迷していく事になります。
でも、本当に80年代初頭の彼は輝いていました。
シングル、12インチ、LPと様々な形態で出された作品群は、センスの良いジャケットと相まってイギリスオリジナル盤は中古市場でも大人気です。
最後に、そんな彼のセンスの良さが滲み出ているジャケットを紹介しましょう。
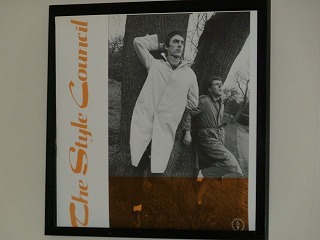
初期のシングル「Money go-round」の12インチシングルです。
これはメリーゴーランドをもじったんでしょうね。
曲は時代を感じさせる、やや硬い一本調子の白人ファンクですが、ジャケットのビジュアル、いかしてますね。
何気ないショットなんですが、色合いとバンド名のロゴの処理が絶妙ですね。
ジャムの頃からそうでしたが、ジャケットのセンスは超一級です。
また機会があれば、ジャムについても書きたいですね。
今回もお付き合い有難うございました。
まだまだオリンピックは続きます。
個人的にはBGMはStyle councilの「Long hot summer」をかけて欲しいんですが、まだ聞いたことありませんね。
気だるい夏のロンドンの雰囲気ばりばりだと思うんですがねえ。
1991年の夏に、英国(イングランド、ウェールズ、スコットランド)を放浪しましたが、ロンドンにいる時はいつも「Long hot summer」を聴いてた覚えがあります。
夕暮れのビッグベンに似合うんですよねえ。
今月の壁レコード ~ 10CC特集(2012/06/08)
6月になって流石にじめじめしてきました。
6月に生まれた私ですが、梅雨は湿気が増えてモノの保管には最悪な時期です。早くカラッとして欲しいものですが、今年は梅雨入りが遅そうですね。
さて、今回のジャケットは職人的(曲者?)音楽集団、10CCを特集してみました。
彼等はやはりオリジナルメンバーの4人の頃が最高ですね。
そもそもバンド名の由来も、大人4人の一回射精分の精液の総量、という訳なんで。
Eric StewartとGraham Gouldmanのポップ組?とKevin GodleyとLol Cremeの実験組?のバランスは素晴らしいものがありました。
Godley&Cremeは映像作家としても、数々の素晴らしい自身や他アーティストのヴィデオクリップで大成功しますね。
初期はビートルズの影響大のオールドタイムなポップロック、という感じでしたが、徐々に独自性を発揮していった頃の三部作を紹介します。
まずは玄関先です。
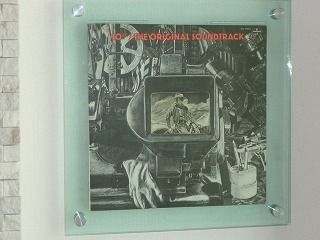
75年の出世作にして最高傑作、「Original sound track」です。
一般的には2曲目の素晴らしいラブソング「I'm not in love」が有名ですが、他にもG&Cの良い所が出た一曲目の「Une nuit a Paris」も個人的には大好きです。
架空の映画のサントラ、といった趣のジャケットも味があります。
因みに今回の3枚は全てあの、ヒプノシスがデザインしてます。
待合の2枚です。

まずは76年のオリジナルメンバーでの最終作、「How dare you!」です。
邦題の「びっくり電話」の方がおなじみですかね?しかし、よくこんな邦題を思いついたものだ、という感じですね。解説を書いている今野雄二さんのアイデアかな?
あのBryan Ferryをして「Tokyo Jo」と言わしめたハイセンスな今野さんなら納得ですが、意外と担当ディレクターだったりして・・・。
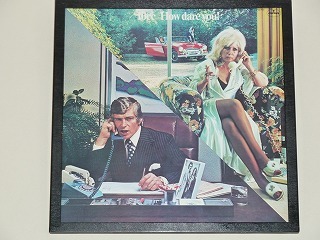
これは電話をテーマとしたこれまたヒプノシスの大作で、見開き写真での電話づくし?には唸らされます。
まだ携帯の無い頃ですが、今の「一人一台電話時代」を先取りしています!?
内容的には、これで袖を分かつのも当然?という感じで、両ペアの作風がバラバラです。
前作ではバランスが取れてたんですが、今作では駄目ですね。
E&Gペアの「I'm Mandy fly me」、「Arts for art's sake」は最高です。
そして、個人的には一番好きな77年の「Deceptive Bends」です。
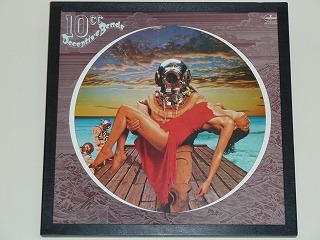
実験的な二人が脱退した為、これまでもステージを共にしてきたドラマーのPaul Burgesと3人で創り上げたレコードですが、物凄くポップで濃密な捨て曲の全くない傑作です!
先ず、冒頭の「Goodmorning Judge」で軽くジャブを食らった後すぐに、稀代の名曲「Things we do for love ~ 愛ゆえに」が飛び込んできます。
「I'm not in love」にも劣らない、Eric Stewart節満載の傑作です。
よくBGMで使われてますので、皆さん聞き覚えあるかと思います。
3曲目はGrahamをフューチャーした結婚相談所に通うしょぼくれ?男の唄ですが、これまた彼らしい、ほんわかした味の良い曲なんです。
4曲目の「People in love」も2曲目と同じ流れの恋人達を唄ったEricの佳曲です。
A面最後の「Modern man blues」では、前半は重くダルな雰囲気ですが、「Hey!」というEric?の掛け声と共に始まる後半はふっきれたような、半ばヤケクソ気味な、はっちゃけぶりが楽しいです。
Ericのギターもなかなか聴かせてくれます。
B面に移って、一曲目「Honeymoon with B troop」は、Grahamがリードを執る、摩訶不思議なロックですが、途中ビートルズっぽいブリッジを挿入する辺りは流石やなって思ってしまいます。
2曲目はJoe Pass辺りのジャズギターっぽい雰囲気を狙った小品ですが、音楽用語を駄洒落風に紡いでいく歌詞(フラット、C、メジャー、G等など)といい、子粋なEric Stewartのヴォーカルといい、シャンソンっぽいアンニュイな感じを醸し出しており、これまた絶品です。
次の「You've got a cold」ですが、カッコいいリフと炸裂するツインギターソロの応酬はその辺のハードロックバンド顔負けですが、歌っている内容は「君は風邪ひいたね」なんてバカバカしいもので、マジで演っているとは思えず、当時隆盛を極めていたKiss、Aerosmithなどをからかっていたんでしょうか??
そしてフィナーレを飾るのは大作「Feel the Benefit」です。
パート1~3まであるこの曲は、ライヴ映えする素晴らしい構成と演奏ですが、けしからん事に最初にCD化された際に、無理やり「オリジナルサウンドトラック」と2イン1したものですから、削られてしまっていました!
当時レンタルしてテープに落としたんですが、後に中古レコード屋でアナログをゲットし、無事に編集しました!(しかし音圧が違い、かなり違和感ありましたが・・・)
泉水扶をモチーフとしたこれまたヒプノシスのジャケットですが、裏ジャケットで、潜水帽?を脱ぎかけている男が写ってますが、これ、誰だと思います??
実はドラマーのPaul Burgesなんです!来日時にじかに彼に聞いて確認したので間違いありません、(Grahamもそう言ってました!)
ところで、邦題は安直に「愛ゆえに」なので、原題のニュアンスが全然分かりません。
Bendsは「潜水病」なので、「みせかけの、偽りの潜水病」ということでしょうか?ジャケットからするとそんな感じですが、こういう解釈はどうでしょうか?
4人組から二人になって最初のアルバムだから、批評家は我々がアップアップしてるだろうと思ってやがるだろうな?ええそうなんですよ、あの二人が居ないと大変で大変で・・・。(本当はへっちゃらなんだけど)
「Deceptive Bends」について言及している文章が(私の知る限り)皆無なので、間違っていたら誰か教えて頂けますでしょうか?
1994年にEricとGrahamが揃ったラインナップで来日公演を行いましたが、この時のライヴは最高でした。名古屋公演はクラブクアトロという、小さなハコでしたのでこれまた最高でした。
同時期に来日したSqueeze(ドラマーがあのPete Thomasだった!!)と並んで強烈に脳裏に残っています。
生涯観たライヴ10傑に入ってます!
たま~にGraham GouldmanがPaul BurgesやRick Fennらを連れてブルーノートなどで演奏しに来ますが、やはりEric Stewartがいなきゃね・・・・。
一時期Paul McCartneyがデ二―レイン的な存在を求めてEricとつるんでたのは嬉しかったですが、一曲でもいいから、名曲を生み出して欲しかったですね。
あと、Paulのプロモクリップ「So Bad」で准レギュラー的扱いを受けていたのは嬉しかったですね。
最後の方で、ポールとリンダとリンゴスターと背中越しに丸く並んで上から撮られた、多分にEP盤「Yesterday」のジャケットを意識して撮られた画はファンなら分ると思いますが、涙ちょちょ切れました。
話がとりとめもつかなくなってきました。
そろそろオリジナルメンバーで再結成してくれませんかねえ。
今(先?)月の壁レコード ~ ビルエヴァンス特集(2012/05/09)
すっかり春めいて、時には暑い位になってきた今日この頃、皆様如何お過ごしでしょうか?
うっかりしていて、先月のブログ更新を怠ってしまいました。
レコードの交換はちゃんとしていたんですが・・・。
先月はBill Evansの諸作を特集してみました。
抒情性のある、如何にも白人的なピアノを弾く彼は日本で最も人気あるピアニスト、と言ってもよいと思います。
先ずは玄関先です。
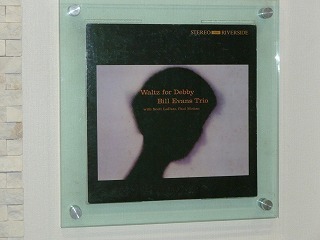
代表作、「Waltz for Debby」です。
A面冒頭から、ライヴハウスでの客のざわめきやグラスのぶつかる音が聞かれ、目を閉じるとまるで自分もその場にいるかのような感があります。
My foolish heart~Waltz for Debbyとつながる流れは素晴らしいです。
壁の2枚です。

先ずは名盤「Portrait in Jazz」です。
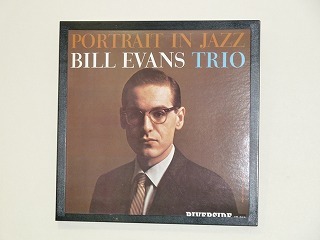
これこそエヴァンスの真骨頂といいますか、神経質そうな?ジャケットの
顔つきそのままの?音がA面一曲目から聴かれます。
その次の「枯葉」もちょっと普通のスタンダード的な解釈ではないですよね。アバンギャルドではありませんが、何か緊張感漂う感じです。
そういう、甘アマではないところも、人気がある所以かもしれません。
次は70年代に発表したこれです。
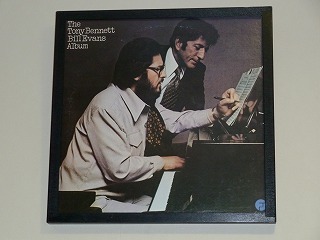
御大Tony Bennetとのデュオアルバムです。
これは、今は無き栄にあったジャズ喫茶「The Cat」で知ったのですが、冒頭からTonyの張りのある歌声にひきこまれましたね。
夢中で聴いていました。
今でも、よくターンテーブルに乗るアルバムです。
続編も出ていますが、やはりこっちの方が世界観が違います。
素晴らしいアルバムです。
今月の壁レコード ~ ブルーノート特集(2012/03/27)
三月も終わりに近づき、徐々に春めいてきましたが、まだまだ朝晩の冷え込みは続く今日この頃ですが、皆様如何お過ごしでしょうか?
前回のジャズヴォーカル特集は割と好評でしたので、今回もジャズでいこうと思います。
先ずはベタで申し訳ありませんが、Blue Noteレーベル、その中でも特に人気ある3枚をセレクトしてみました。
ジャズも永年聴いていると、どうしてもマニアックなレコードを有難がるようになり、このような名盤は逆に敬遠しがちになってしまいますが、改めて聴いてみると、やはり名盤には名盤たる所以がありますね。
玄関先です。
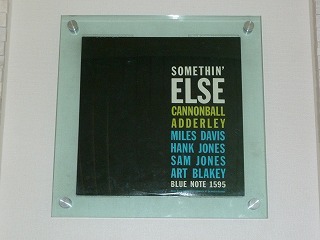
Cannonball Adderley名義のSomethin' Elseです。
ブルーノートを、いや、モダンジャズを代表する一枚です。
Reid Milesデザインのシンプルなグラフィックジャケットですが、何でもないような文字の配置や色使いが絶妙で観る者を飽きさせません。
ユニクロさんが、昨年ブルーノートのジャケットデザインのTシャツを何枚か発売しましたが、やはり一番人気はこれでしたね。
私も買いましたが、もったいなくてまだ着てません。
内容は語り尽くされてきた感がありますが、冒頭の「枯葉」は哀愁感あるマイルスのミュートトランペットが素晴らしいです。
個人的には、B面のタイトル曲が勇ましい感じで好きです。
待合壁です。

先ずはJohn Coltrane BNでの唯一のリーダー作、「Blue Train」です。
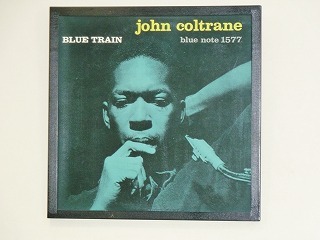
鉄道マニアが勘違いしそうですが、「はやぶさ」とか「さくら」なんて曲はありません。
硬派なジャズ喫茶に映えそうなハードバップです。
私はコルトレーンに関してはあまりよい聴き手ではなく、マニアが腕組して瞑想に耽る?後期インパルスはどうも苦手です。
初期のプレステッジでの諸作や、インパルスでも「Ballad」や「with Duke Ellington」などの方がターンテーブルに乗る回数は多いですね。
このLPでも、実は一番好きなのはB面2曲目のバラッド「I'm old fashioned」だったりします。
年をとってくると、スタンダードのバラッドがより心に染みてきますね。
日和った、という事なんでしょうね。
次はこれです。
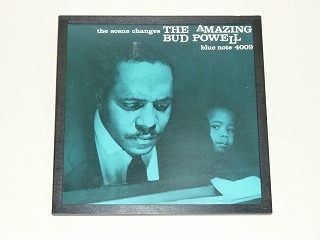
名曲「クレオパトラの夢」を擁するBud Powell後期の名(迷?)作です。
この頃のパウエルは麻薬の影響で、神経症状も患っていたらしく、運指はスムーズでなく、所々怪しい部分があります。
でも、それも許せてしまうくらい、全盛期の彼は凄かったみたいですね。
ルースト盤の邦題「バドパウエルの芸術」での、鬼気迫る指使いとは雲泥の差ですが、やはり枯れても天才、凡百のピアニストが束になっても敵わない”somethin' else”が彼にはあります。
そんなおやじを心配そうに見つめている息子を撮ったフランシスウルフの写真を絶妙にトリミングしたリードマイルスも流石です。
BNにはまだまだ素晴らしいジャケットデザインが沢山ありますよね。
また機会があればご紹介させて頂きたく思います。
今月の壁レコード ~ ジャズヴォーカル特集(2012/02/28)
まだまだ春は遠し・・という感じですが、皆様如何お過ごしでしょうか?
寒い時は、粋なジャズヴォーカルでも聴きながら温かいコーヒーでも如何でしょうか?
時間があれば、ジャズ喫茶で本でも読みながら、時にブラインドなどやったりしてのんびりしたいですんですけどね。
学生時代は名古屋の今は無き「The Cat」や、今でもたまに行きますが、「Yuri」に良く行ったものです。それこそコーヒー一杯で数時間粘って次にかかるアルバムを心待ちにしていたものです。
むか~し、岡崎にもジャズ喫茶があったのですが、今はたぶん無いでしょうね。誰か創ってくれませんかね?
もう少しいろいろな意味で余裕があれば、私が開くのですが・・・。
では、玄関先です。
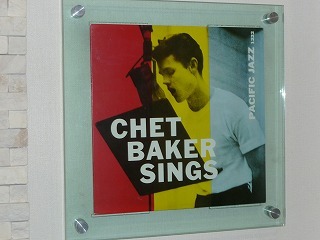
Chet Bakerの名盤、「Chet Baker sings」です。
オリジナルは10インチレコードですが、なかなか状態の良いものに巡り合ってないので、LPでご勘弁を。
彼のヴォーカルは逞しい?トランペットの音とは対称的に、中性的になよっとしてますね。
口の悪い御仁は「ナメクジ」などど揶揄しますが、私的にはアンニュイな感じがたまらなく好きですけどね。
ただ、このパシフィック期よりも、麻薬でボロボロになった後、カムバックしてからの方が辛酸を舐めた分だけ、凄みが増して更に好きです。
70年代後期のSteeplechaseや、80年代のCriss Crossといったマイナーレーベルに膨大な作品を残してますが、ボーカルの入った盤はいずれも外れなしです。
特に、Pau Breyのピアノとのデュオアルバム「Diane」は最高ですね。
若い頃、彼の刹那的な生き様に憧れ、自伝映画「Let's Get Lost」を貪るように観てた時期がありますが、やはり凡人の私には到底真似できませんでした。
続いて待合室の壁です。

先ずは、こちらです。
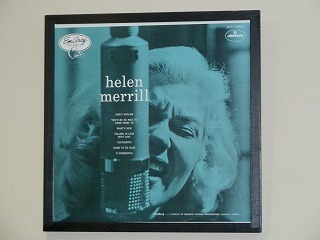
Helen Merrillの名盤です。
Clifford Brownの名演やQuincy Jonesの名アレンジもあり、女性ジャズボーカルの金字塔、といえる素晴らしいアルバムです。
ジャズビギナーに聴かせるならこれ!ってな感じで様々なガイド本に登場しますが、事実、私も中学の時にこれを聴いてジャズヴォーカルの深みにハマっていきました。
全編素晴らしいのですが、私は「恋に恋して」が一番好きですねえ。
何か、ニューヨークの雑踏を歩いているイメージが湧いてきます。
深夜の人気のない寒い路地~道路脇からスチームの蒸気がボワ~っと上がっている~を恋人と二人で酔っ払いながら歩いている、そんな感じです。
例えるなら、Bob Dylanのフリーホイーリンのジャケットをそのまま夜にした感じかな?
もう一枚は私のフェイバリットフィメールシンガー、Anita O'dayです。
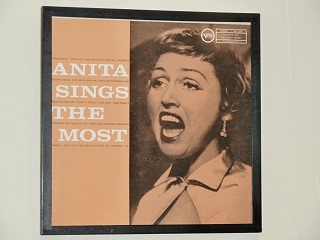
名盤「Anita sings the most」です。
歯医者さんの看板に使えそうな位、大口を開けているのは御愛嬌。
彼女ほど鉄火肌~姉御的な唄を聴かせてくれる白人女性シンガーはいないと思います。
なかなかの美人だし、意外にグラマラスですし、ノーマングランツが気に入ってVerveに沢山吹き込ませたのも当然です。
私は殆ど持ってますが、どれも良い唄が沢山つまってます。
特にこのアルバムは、歌伴がOscar Peterson Trioですから、尚更です。
冒頭の「スワンダフル~誰も奪えぬこの思い」は素晴らしいし、次の「テンダリー」も最高!
てな具合で、本当に素晴らしいアルバムです。
皆さん、是非聴いてみて下さいね。
今月の壁レコード ~ ドラゴン特集!(2012/01/16)
あけましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い申し上げます。
今年は辰年、という事で、今月のレコードジャケットは「竜~ドラゴン」で攻めてみました。
先ずは玄関先です。
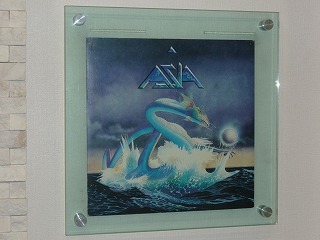
プログレのつわもの達が集まったスーパーバンド、エイジアの1stアルバムです。
1982年の発売時、私は中2でした。
雑誌に「クリムゾン、イエス、ELPのメンバーらで結成されたスーパーグループ!」なんて大々的に宣伝されていた事もあり、予約して買った覚えがあります。
当時はプログレ四天王は、「宮殿」「こわれもの」「タルカス」「狂気」位しか聴いてませんでしたが、カッコよく、しかもメロディアスな展開に痺れまくり、ホント聴きまくりました。
久々に聴いてみても、やはり素晴らしく特に冒頭2曲の完成度は圧倒的です。また、PVもなかなか良かったですね。確かGodley&Cremeが監督してましたね。
余りにも売れた為、よく「産業ロック」と揶揄されますが、売れるのはそれだけの出来栄えという事ですよね。
TOTO、Journey、Foreigner、Boston、Styxなど、80年代初期に人気のあったバンドは今では中古レコード屋で一枚100円で叩き売り状態ですが、私にとってはあの頃の情熱を取り戻させてくれる、かけがえのないバンドです。
この後、セカンドまでは割と頑張ってたのですが、John WettonがGreg Lakeに変わったりして徐々にパワーが衰えていき、自然消滅的になってしまったのですが、数年前、再結成して日本にも来てくれましたね。(私は行きませんでしたが・・・。Heat of the momentでは大合唱だったのでしょうか?)
因みにドラゴンの画を描いたのは、あのRoger Dean画伯です。
この辺も、Yes繋がり、という感じですね。
壁の2枚です。

ますは、Jefferson Starship1976年の「Spitfire」です。
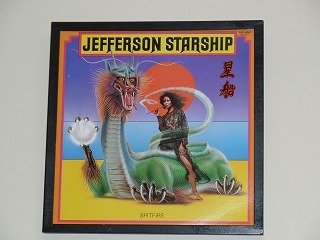
オリエンタルテイスト溢れたジャケットは、長岡秀星氏によるものです。
彼は、この他にもEW&Fの一連の作品や、CarpentersのNow & Thenなどで洋楽ファンには有名ですね。
Jeffersonも、リーダーのPaul Kantnerと歌姫Grace Slickとの間の娘に「China」と名付けているあたり、東洋に興味があるんでしょうね。
因みに、AirplaneからStarshipへとパワーアップしてからの第一作、「Dragonfly」にも、Ride the tigerというカッコいい曲がありますが、歌詞にもOriental manなんて出てくるし、Papa john creach(関係ありませんが、いつもこの名前を聞くとマドンナのあの曲を思い出してしまいます。パパ、どん、プリーチ!)の弾くエレクトリックヴァイオリンも、どことなく中国っぽいんですよね。
私は、このバンドは3人ヴォーカルのこの頃が一番良かったと思います。特に前作「Red Octopus」は最高ですね。貫禄のついた姉御Grace Slickは勿論ですが、復帰したMarty Balinも「Miracles」で一世一代?の名唱を聴かせてくれます。まさにミラクル!
演奏陣も素晴らしく、マルチプレーヤーのPete Sears、伸びのあるギターが最高なCraig Chaquicoのお二方は、1986年にスターシップとして来日した時にも、やはり巧かった!Grace Slickもすごく綺麗でびっくりしました。Mickey Thomasはやっぱヒゲがあった方がいいです、個人的には。
続いてこれです。
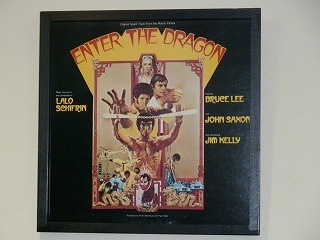
映画、「Enter the Dragon」のサントラです。
今回、しげしげとジャケットを見てて気付いたんですが、音楽はあの、ラロシフリンが担当してたんですね。
私はあまりブルースリーに思い入れは無いので、あれこれ蘊蓄は書けませんが、74年頃は本当にカンフーブームだったんですよね。
カールダグラス(カークではありませんよ!)の「吼えろカンフー」なんて、ブームにあやかった№1ヒットも生まれましたね。
漫画「魔太郎がくる!」で、人気のドラゴンジャケットを不良に奪われた魔太郎がとんでもない仕返ししてる話もありましたねえ。
ここでおまけです。
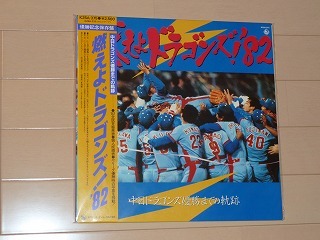
中日ドラゴンズ1982年優勝時の記録レコードです。
DVDなんてないし、ヴィデオだって高かった当時は、レコードでファンは記憶に留めていたのです。
今でもしっかり覚えてるのは、巨人との終盤デットヒートを繰り広げてる時ですね。
江川投手から9回に3点もぎ取った時の連打の嵐には泣いて喜んだ覚えがあります。
今の貧打線とは比べ物にならない、まさに「恐竜打線」でした。
今年は往年の強打を蘇らせて、面白い試合を見せて頂きたいです。
Merry Christmas!(2011/12/24)
寒いさむいクリスマスになりそうな今年ですが、皆様如何お過ごしでしょうか?
今、まさに24日で、遅い更新になってしまい申し訳ありません。
今回のジャケットは当然クリスマスものなんですが、なかなかいいものが無くて、結局昨年と同じモノになってしまいました。
よって、今回は画像添付はありません。すみません。
今年を振り返ってみますと、やはり3月の震災の爪痕は大きかったですね。未だに仮設住宅や各地への避難を余儀なくされている方々の心労は計り知れないものがあるでしょう。
家族、友人を亡くされた方々、本当に辛い事と思います。
私も今年は個人的には大変辛い思いをしたのですが、何故神様はこんなに不公平なんでしょうね。
心境的には「Let it be」なんでしょうが、なかなかそこまで達観するのは「Long and winding road」でしょうね。
来年は坂本九さんの「スキヤキ」をテーマソングに、「上を向いて」生きていきたいです。
皆様、来年も宜しくお願い申し上げます。
今月の壁レコード ~ ジェントルサウンド特集(2011/11/20)
秋も深まり、日に日に冬に近付いている今日この頃、皆様如何お過ごしでしょうか?
これから寒くなってくると、暖かい音楽が欲しくなってきますね。
外は寒くても、心が癒されれば暖かく感じられますよね。
という訳で、今回のレコードジャケットは大人の為のジェントルでハートウォーミングな音楽を特集してみました。
先ずは玄関先です。

Michael Franksの1977年の名盤、「Sleeping Gypsy」です。
神秘的なジャケットはブラジルの熱帯雨林をイメージしていると思われる淡い光群と蛾(蝶?)の幻想的なイラスト(写真?)です。
私はアメリカ留学時代、機会がありブラジル旅行をしたんですが、イグアスの滝を観に行った時、生い茂る熱帯雨林を散策し、木々の隙間から空を見上げた時に同じ様な光景を目の当たりにし、これだったのか~と妙に感動した覚えがあります。
初めてこのアルバムを聴いたのは高校一年の時でしたが、針を落とした瞬間から拡がる幻想的なサウンドにノックアウトされ、勉強そっちのけで暫く聴いていましたね。
ブラジル(ボサノヴァ)に強く影響を受けたと言われるマイケルフランクスのサウンド、確かに朴訥とした唄はジョアンジルベルトを彷彿させます。
レコードの解説で、「彼は歌っているが、決して歌手ではない」という記載がありますが、言われてみればそんな感じもします。
「唄+伴奏」ではなく、声がでしゃばらなくて、それ自体が一つの楽器の様に全体に溶け込んでいる、といった感じです。
アルジャロウやボビーマクファーリンの様な技巧的な、非人間的?な感じではなく、もっとヒューマンでジェントルですが・・・。
バックのメンツも素晴らしく、Larry Carlton, Joe Sample, Wilton FelderのCrusaders一派、Joni MitchellのパートナーだったJohn Guerlain、ホーン陣はMichael Brecker, David Sanbornなど目のくらむような豪華さ。
制作陣もTommy LiPuma、Al Schmidtと最高の布陣です。
内容も全て素晴らしいのですが、特にA面一曲目の「淑女の想い」はカールトンの浮遊感のあるギターが素晴らしい名曲です。
日本ではアントニオカルロスジョビンを唄った「アントニオの唄」が特に人気ありますが、他にも良い曲沢山なので、是非LPを通して聴いてみて下さい。
壁の二枚です。
先ず、Joni Mitchellの1974年の傑作「Court and Spark」です。
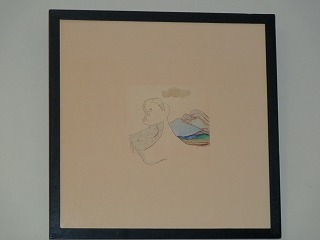
ジャケットの絵はジョニ自身の手によるものです。
彼女の絵の才能は並々ならぬもので、自身のレコードジャケットを沢山描いていますが、割としっかり描きこんだものが多いので、このようなシンプルなイラストは珍しいですかね?
参加メンバー的には結構先のマイケルフランクスと重複するんですが、クルセイダーズの3人、特にラリーカールトンのギターは重要な役割を果たしてますよね。
あのプリンスも好きな「Help Me」、アサイラムレコードのオーナー、David Geffinをモチーフとした「Freeman in Paris」は彼のギターでなければ、随分印象が変わってくると思います。細かなバッキングにもセンスが感じられるんですね。
ギター繋がりで言えば、B面の「陽気な泥棒」ではあのThe BandのRobbie Robertsonの例の個性的なパキパキギターが楽しめます。
本当に彼のギターってワン&オンリーですよね。
他の曲はピアノとアコースティックギターを主体としたしっとりとしたものが多く、解説で小倉エージさんが絶賛するほど全体がファンキーなものではありません。
彼女はこの後もフュージョン路線を突き走り、ジャコパスやパットメセニーらフュージョン界のトッププレーヤー達と共演します。
「Shadows and Light」の映像も素晴らしいですが、個人的には「The last waltz」で、The Bandをバックに「コヨーテ」を唄った時の映像が大好きですね。
続いてキャロルキング1975年の名盤「Wrap around Joy」です。
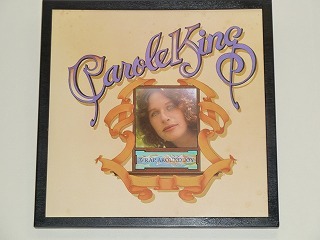
大ヒットした「つづれおり」には敵いませんが、このアルバムも全米№1になっているんですよ。
あまりにもシンガーソングライター然とした「つづれおり」よりも歌詞を他者に委ねた今作の方が、元々ブリルビルディングのソングライターだった彼女らしい、ともいえます。
「つづれおり」の様な超名曲の目白押し!というのとは違いますが、このアルバムも良い曲がたっぷり詰まってます。
日本盤ライナーにもありますが、「聴いていて楽しくなってくる」アルバムなんです。
愛娘達をコーラスに使った穏やかなA-1に始まり、男女の心情の機微を唄った、ほろりとくるA-2、トムスコットのサックスをフューチャーしたシングルヒットA-3、楽しげなタイトル曲B-1、美しいメロディラインのB-2、当時の夫君チャールズラーキーのベースがカッコいいB-3などが特にお気に入りですが、全曲捨て曲なしの名盤です。
昨年James Taylorと共に来日し大好評だったコンサート、名古屋はとばされましたので観に行けれなかったのですが、バックバンドはあのSectionだったそうで、素晴らしかったようですね。観に行けた方が羨ましいです。
今回紹介した3枚のアルバム、いずれも黄色~ベージュっぽい色合いですね。
参加ミュージシャンも近いものがあり、聴いていると心が癒される、という点で共通してます。
本当はもう一枚、Joan Baezの「Diamonds and Rust」も同系統のアルバムとして紹介したかったのです。
Larry Carlton、Joe Sampleがここでも良い仕事をしています。
Bob Dylanの「Simple twist of fate」では、掟破りの?Dylanの物真似まで披露してくれますよ。
これも良い曲満載の良作なので、是非聴いてみてくださいね。
それではまた来月!
祝!リマスター!! ~ ピンクフロイド特集(2011/10/17)
10月も半ばを過ぎ、かなり過ごし易くなってきた今日この頃、皆様如何お過ごしでしょうか?
秋は一年のうちで最も芸術的な雰囲気が感じられる季節ですね。秋の夜長にはプログレッシブロックが似合いますね!?
という訳で、今月の壁レコードは先日リマスターCDが大々的に発表されたプログレの雄、Pink Floydを特集してみました。
先ずは玄関先から・・・
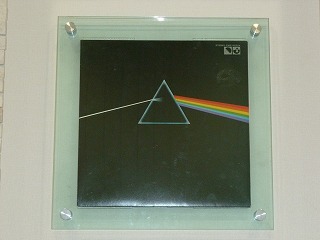
1973年の超名盤「狂気」です。
原題の「The Dark Side of the Moon」も、神秘的で、語感もいい素晴らしい題ですが、邦題のインパクトには負けますね。
当時の東芝レコードさんは秀逸な邦題が多かったですね。
ビートルズ関連で大儲け?したおかげでロック部門への潤沢な経費があったんでしょう。
70年代の東芝のロックレコードは帯、解説書、ポスターなど、コレクター心をくすぐる豪華仕様でした。
あと、73年頃まで存在した「赤盤」は何というか、愛おしくなってきますね。同じレコードでも、赤盤というだけで中古値段が倍増するとこなんぞ、東芝さんの先見の明というか、マニア心を良く分かっていたんだな?と思います。
脱線してしまいました。
内容はといいますと、このアルバムが全世界で飛ぶように売れた、というのはやはり他のプログレバンドとは一線を画する「解り易さ」言い換えれば、「曲の良さ」にあったのではないでしょうか?
技法に走り、難解なアルバムが多い中、安心して聴けるボーカルとサウンド、時折飛び出して来る効果音(心拍、笑い声、足音、宇宙船の様な音、時計、レジスター・・・)と、誰でも一度聴いたら最後まで引き込まれてしまう凝った音創りが、爆発的なセールを生んだのでしょう。
ロック好きには要所で炸裂するデヴィッドギルモアの鋭角的なギターがたまりませんね!
1988年に名古屋公演を観に行きましたが、やはりギルモアのギターは凄かったです。
あと、ヒプノシスの手がけたプリズム反射のジャケットも特筆ものです。
このジャケットしかあり得ない!という程内容とマッチしているのは流石ですね。
壁の二枚です。

先ずは1975年の「炎~あなたがここにいてほしい」です。
原題は「Wish you were here」です。
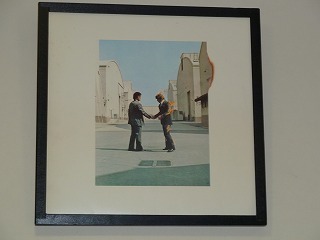
これもヒプノシスのインパクトあるジャケットです。
表ジャケットは「火」、裏ジャケットは「砂」、インナースリーヴ表は「風」、裏は「水」をモチーフに、それぞれに(存在しない人間)が写っている、という何とも不気味なジャケットです。
おそらく、原題からイメージしたんでしょうが、ヒプノシスらしい、凝ったジャケットです。因みに、初回盤は黒いビニールシュリンクがかかって売られていました。
多くのフロイドファンがファイヴァリットに挙げるこのアルバム、確かに前作「狂気」と比べると、より「フロイドらしい」、感じがしますね。
リスナーを突き放すような?冷たい感じは彼らの真骨頂と思います。
A面一曲目の「狂ったダイヤモンド」は発狂してグループを去ったシドバレットへのレクイエムですが、情念のギルモアのギターがたまりません。
よくコンサートのオープニングに使われ、88年の日本公演でも、リックライトの透明感のあるシンセサイザーの音が流れてきた時は興奮しましたね。
次の「ようこそマシーンへ」、B面一曲目の「葉巻はいかが」と緊張感のある曲が続きますが、B面2曲目、タイトルトラックの「あなたがここにいてほしい」はほっとする佳曲です。
歌詞からすると、シドバレットの事を唄っているのでしょうか。
初期のサイケデリック期を支えた彼が、発狂せずにリーダーとして留まっていたら、彼等はどんなバンドになっていたのでしょうか?
かなりポップなお洒落なバンドになっていたかもしれません。
少なくともプログレ四天王には選ばれなかったでしょうね。
壁のもう一枚です。
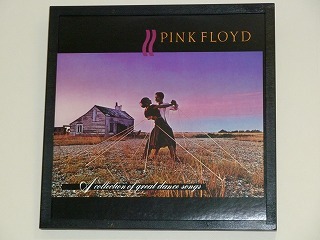
1982年に発売された編集盤「時空の舞踏」です。
原題は「A collection of great dance songs」と、彼等らしい、人を喰ったものです。
彼等の曲が、ダンスミュージックな訳ありません。踊りのBGMとして使われる事もないでしょう。
そういう皮肉が、「ピアノ線で固定されたダンスカップル=踊れっこない!!」として表現されてるんでしょうね。
一見ヒプノシスっぽいセンスですが、クレジットには彼等の名前はありません。それっぽく他者がデザインしたんでしょう。
確かに、文字の処理やインナースリーブなどはちょっと詰めが甘いですかね?
内容的には特記すべき事はない、唯の「寄せ集め」です。
それでも、割と売れてしまう所が流石です。
今回は書きませんでしたが、彼らにはもう一作「The Wall」という代表作があります。
ジャケットは白いレンガの壁をモチーフしているので、ほぼ真っ白ですので、流石に壁には飾れませんでした。
いずれビートルズの「ホワイトアルバム」を飾る時が来たら、一緒に飾ろうかな??
もう一枚はSantanaの「Welcome」か、James Taylorの「Greatest Hits」か?
今月のレコードジャケット ~ 夏の終わり(2011/09/21)
皆様、如何お過ごしでしょうか?
今日(9月21日)は台風の真っただ中なんですが、ジャケットを飾ったのは少し前なので、こんなタイトルになってしまいました。
先週までは真夏日が続いて日本はどうなっちゃったのか?と言ってたのでまだ海系のジャケットでいいかな?と思ったんですよ。
この台風で秋になっていくんでしょうかね?
今回のテーマは「晩夏の浜辺」です。
夏の終わりの海岸って、何か哀愁が漂いロマンティックですよね。
白いジャケットで靴を脱いで裸足でそぞろ歩く・・・といった光景が浮かんできます。(正に後述するジェームステイラーのジャケットそのままですね!)
先ずは玄関先ですが、クリスレアの「On the Beach」です。

ジャケットの写真自体は夏!という感じもしますが、これは表題曲の雰囲気で選びました。
86年に一世を風靡した?哀愁味あふれる名曲です。
確か車のCMにも使われてたので、ご存知の方も多いでしょう。
クリスレアは初期のトムウェイツみたいな渋い声のミュージシャンで、良作を沢山発表してます。
どちらかといえば知る人ぞ知る、という存在でしたが、この名曲で一気にブレイクしました。ただ、その後も地に足の付いた地道な活動をしていったのは流石ですね。
壁の2枚です。

先ずはまさに夏の終わり、という感じのNeil Young1973年の「On the Beach」です。

多作な二ールさんですが、このアルバムは評価ほんとに低く、CD化も永年されませんでした。
確かに、あまり心に残る曲はなく、散漫な印象はありますね。
ジャケットは内側まで絵がプリントしてあり、手間暇がかかっているんですけどね。
まあ、二ールさんについてはまたゆっくり書きたいと思ってます。
最後はJames Taylor 1975年の名盤「Gorilla」です。
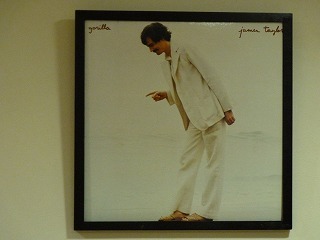
これはまず、秋~冬と思われますが、海岸沿いを白いスーツと裸足で歩いているんですね。これこれ!まさにこのシチュエーションですよ!!
映画の一場面みたいですね。
中身の素晴らしさと相まって、最高のアルバムです。
残暑御見舞申し上げます~今月のレコジャケ:Beach Boys(2011/08/16)
残暑お見舞い申し上げます。
皆様、毎日暑いですね。
心配されていた電力供給停止ですが、今のところ、何とかなっていますね。
皆様の節電効果の賜物だと思います。中部電力さんにも感謝感謝。
さて、今月のレコードジャケットは夏らしく、Beach Boysでいってみました。
オリジナルメンバーはマイクラブだけになってしまったようですが、未だに現役で活動しているのは、シカゴと並んでアメリカの誇りでしょうね。
一般的には「ビーチボーイズ=夏、サーフィン」といったイメージなんでしょうね。
確かに沢山出されている編集物のジャケットは大抵「サーフィン、海、女の娘」といったイメージですよね。
低迷していた70年代前半リプリーズ時代も、オリジナルアルバムは売れなかったようですが、キャピトルがやっつけ仕事?で適当なジャケットで出したヒット曲集「Endless Summer」は確か全米№1になりましたものね。大衆が求めているものは過去のヒット曲なんですね。
その事に気付いた?彼等はライブ活動に精を出すことになります。
73年の「In Concert」はブライアンは不在ですが、サポートメンバーを加えてなかなかの好演を繰り広げており、見開きジャケットの内側の魅力的な写真と相まってとっても楽しめます。
その後、ブライアンが奇跡的に?復活したり、グループ唯一のサーファー、デニスが他界したりと紆余曲折ありましたが、80年代後半には映画「カクテル」の挿入歌「ココモ」で久々の全米№1ヒットを放ち、まさかのブライアンのソロアルバムも出て、日本音楽業界の折からの「ペットサウンズ」「スマイル」再評価の波もあり、かなり盛り上がってたのを覚えてます。
先ずは玄関先です。
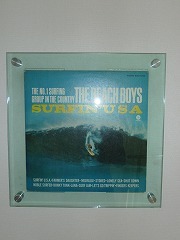
1963年のセカンド「Surfin' USA」です。
如何にも60年代的な感じですね。曲もサーフィン関係が多いですかね。
昔、サビの部分を「いっさい、がっさい、USA」と遊びで唄っていたのが懐かしい。
壁の2枚です。

これも1963年のサードアルバム「Surfer Girl」です。
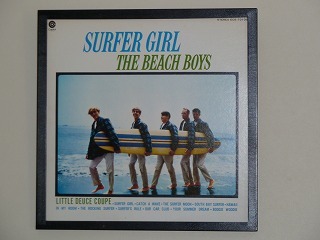
永遠の名曲「Surfer Girl」だけでなく、後のペットサウンズに繋がる世界観が歌われる「In my room」も入っており、美しいアルバムです。
この後は全盛期に突入し、「I get around」、「All Summer long」、「Girl on the beach」、「Fun,fun,fun」、「Wendy」、「Don't worry baby」、「Please let me wonder」、「California girls」、「Let him run wild」、「Barbara Ann~これのThe Whoバージョンは最高です」などなど、名曲揃いに頭がくらくらしてきます。
当時ビートルズに対抗できる唯一のアメリカンバンドと称されたのも当然ですね。
唯、当時の彼等はLPとしてはシングルの寄せ集め的な所があり、完成度は低かったように思います。
ブライアンがビートルズの「Rubber Soul」を聴き、ショックを受けて「作品」として統一感を出そうとして独り努力して創り上げた傑作が「Pet Sounds」です。
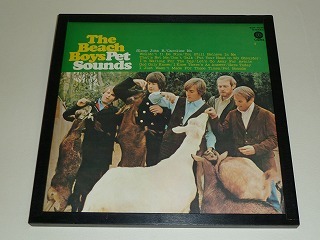
1966年に発表されたこの作品はほぼブライアンのソロアルバムといってもよいでしょう。勿論メンバーもコーラスで参加していますが。
A面頭の「素敵じゃないか」から「少しの間」まで、最高の流れです。
最後の「スループジョンB」は録音も前年のものだし、楽天的な曲調も相まって、あまりこのアルバムに調和してないですよね。いつも飛ばして聴いてしまいます。(すみません!)
B面もPaul McCartney絶賛の「神のみぞ知る」、ブライアンのいじけぶりが愛おしい「駄目な僕」、美しすぎて涙ちょちょ切れる「キャロラインノー」と、素晴らしい作品が続きます。
こんなに素晴らしく、現在では「最高傑作」と絶賛されている「Pet Sounds」ですが、リリース当初は売れず、メンバーやマスコミにも酷評されたそうです。マイクラブなど、「こんなもの誰が聴くんだ?犬か??」という様な酷い事を言ったそうですね。
わからないものですね。
おかげでブライアンのプライドはずたずたに引き裂かれ、後の狂気に繋がっていくのです。
しかし、「駄目な僕」で露呈したように、このアルバムが「今の時代とずれて産まれた」事にブライアン自身も気付いていたふしがあります。よく言われてますが、このアルバムは時代を超越しているんですね。
大抵のアルバムは時代とリンクしており、聴いた時に、(後追いでも)その時代背景が感じられてくるものなんですが、ペットサウンズは何かそういうのが無いんですよね。
今の色々な音楽が氾濫した(出尽くしてしまった??)時代の耳で聞いてもそう感じるのだから、60年代のアメリカでは皆が??となってしまったのも無理がありません。
でも、再評価されて本当に良かった、というか、良い仕事は報われるんですね!
私ももっともっと頑張ります!!
P.S.年内にあの「スマイル」のブライアン制作のもとでの正式リリースが実現しそう、というニュースを聞きました。
本当なら「素敵じゃないか」。
本編では触れませんでしたが、個人的には「All Summer long」と「Today」がLPとしては好きですね。
曲としては「Good Vibration」、「Darlin'」、「Sail on Sailor」や渋い所で「Let's put our heart's together」が後期では好きですねえ。
今月のレコードジャケット~シカゴ特集(2011/06/23)
梅雨もそろそろ明けて暑くなってきた今日この頃、皆様如何お過ごしでしょうか?
今年はエアコンもあまり低温度では使えないので、どんな状況になるのやら今から戦々恐々しています。
待合室のエアコンの温度もあまり高めでは皆様の健康を損ねる事になります。かといってあまりガンガン冷やしては、世間に後ろ指を指されてしまいますので、その辺のバランスが問題ですね。
さて、先月予告?した通り、今月の壁レコードはシカゴを特集してみました。
折しもつい先日ライノから全盛期1975年のライヴ盤が奇跡的にリリースされたばかりです。
私は待ちきれなくてアメリカから取り寄せましたが、素晴らしい内容で毎日聴きまくってます。いやあ、テリーキャスのギターは最高ですね。
シカゴのアートワークは「Ⅱ」で初採用された例のロゴマークを、毎回色々なパターンでデザインする、というものですが、傑作揃いのコロンビア時代からこの3枚を飾ってみました。
先ずは玄関先です。

1975年の「Ⅷ」です。因みに邦題は「未だ見ぬ亜米利加」です。
シカゴはイリノイ州の州都ですが、ジャケットに見られる鳥はカージナルで、イリノイ州の州鳥だそうです。
オリジナル盤にはこのデザインのアイロンステッカーが付いていました。
あとこの後シリーズ化する、あのブルーノートの諸作をデザインしたリードマイルス作の(警官との追っかけっこ)ポスターも付いており、コロンビアさん、太っ腹でしたね。
内容は円熟味溢れる落ち着いた雰囲気で、当然のように全米LPチャートNo.1を獲得。結局「Ⅴ」から「Ⅸ」まで5作連続でLPチャートの一位に送り込んだのですから、この頃の勢いは凄かったですね。
この頃になると初期の政治的メッセージは影を潜めて、割と普遍的な事を唄うようになってきてますが、ロバートラム作の「Harry Truman」は久々に「アメリカ」を唄った曲です。
「ニクソンが失脚してフォードに代わっても何も変わらない、ハリー、今こそ貴方の力が必要だ。」72年のマクガヴァン候補惨敗のショックがまだ尾を引いているかのような内容ですが、ユーモラスな曲調の為かあまり深刻な感じはしません。
B面最後のJ.Pankow作の「Old Days」は確かチャートの5位まであがった未だにステージでも取り上げられる名曲です。でも唄ったP.Ceteraは歌詞があまり好きじゃなかったような事を言ってましたね。
待合壁の2枚です。

まずは1972年の「Ⅴ」です。
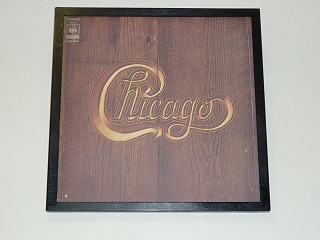
木彫りのレリーフをデザインしたもので、これ、本当に彫って創ったんですかね?
このLPで初の全米No.1を獲得します。
まだシカゴが政治的メッセージをばりばり発してた頃の作品で、やはり活きがいいですね。「Dialogue」なんて最高ですよね。
特筆すべきはB面2曲目のロバートラムの最高傑作、「Saturday in the park」でしょう。当時キャロルキング風のピアノ弾き語りアルバムを制作していた?ことがうかがわれるピアノのイントロに導かれ、如何にもシカゴ風の音楽が展開していきます。
ボビー(ロバートの愛称)のピアノが堪能できる作品といえば、勿論ファーストの「一体現実を把握している者はいるのだろうか?」のフリーフォームイントロですが、ちょっと前衛的なので、私的には「Ⅵ」の一曲目「お気に召すまま」を大推薦します。
これは完全にボビーのピアノ弾き語り作品であり、恐らくボツになった初ソロアルバムからのものでしょうね。
その後74年に「Skinny Boy~華麗なるロバート」を発表しますが、時代が時代だけにかなりクロスオーヴァー的な音作りが目立ちました。(これはこれで格好いいのですが・・・。)
もし可能なら、ライノさんボビーにお願いして72年に制作してた音源発表してくれないかなあ?と切に願います。
壁のもう一枚です。
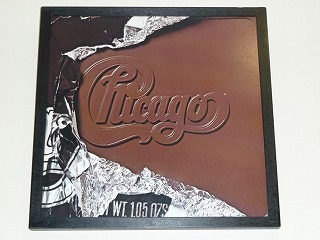
1976年の「Ⅹ」です。邦題は何故か「カリブの旋風」でした。
このチョコレート、商品化されたら箱買いモンですよね。
この魅力的なジャケットは、確かその年のグラミー最優秀デザインに選ばれたんじゃなかったですかね。
これはメンバーほぼ全員が民主主義的に作品を持ち寄った、「ポップ化した」シカゴの最高傑作と思いますが、他に強力アルバムが出揃っていた時代でしたので、最高位は残念乍3位止まりでした。
しかし、本当に捨て曲の無い、恐ろしく密度の濃いアルバムです。
テリーキャスはど頭のロックンロールとしんがりのバラードでその存在感を示し、ボビーはカリブ調の「雨の日のニューヨーク」などでその先進性を披露。ピーターは賛否両論の甘甘名曲「愛ある別れ」で初のシングルNo.1をグループにもたらしました。
ホーンの二人も、それぞれ自作曲では何と、リードヴォーカルまで披露しています!!特にLeeの「 Together Again」は素晴らしい曲です。
シカゴは本当に好きなグループなんですが、実を言うとテリーキャス時代が好きなんですね。まあ、ドニ―デイカスまでは(つまり13まで)何とか許せるんですが、14からは作品の質も落ちてきてるし、正直殆ど聴いてません。
とはいっても私にシカゴの素晴らしさを教えてくれたのは82年のあの、「素直になれなくて」なんですけどね。
当時中学2年生でして、本当にあのメロディには心を奪われました。早速レンタル屋さんに行って、シカゴのベストアルバムを借りてから一挙に彼等の素晴らしさにハマってしまい、今日に至ります。
いつも思うのは、あの時テリーのピストルが暴発しなかったらどうなっていたのだろうか?という事です。もっともっとシカゴの黄金時代は続いていたでしょう。彼のソロアルバムも聴いてみたかったです。
タイムマシーンがあればなあ。
今月の壁レコード~リンダロンシュタット特集(2011/05/23)
五月に入り、かなり過ごし易くなってまいりました。
皆様、如何お過ごしでしょうか?
今月の壁レコは、ウエストコーストの歌姫、Linda Ronstadtを特集してみました。
Eaglesの結成にも一役買った(彼女のバックバンドがEaglesに発展した?)とされ、その彼等をして「Witchy woman」と言わしめた彼女ですが、すごい美人という訳では(失礼!)ないんですが、愛嬌のあるチャーミングな容姿で、全盛期には数々の浮名を流したようです。
有名な所ではイーグルスとも関係の深いJ.D.Souther、当時のカリフォルニア州知事ジェリーブラウンなど。またMick Jaggerも噂されましたが、これはストーンズの「ダイスをころがせ」をカバーした際の話題作りだったような感があります。
では玄関先から・・・
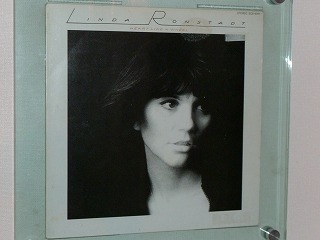
出世作、1975年の「Heart like a wheel」です。
このアルバムよりPeter Asherが全面プロデュースするようになり、全盛時代へと突入していきます。
彼女のような自作曲を書かない「シンガー」のアルバムには、辣腕プロデューサーが必要ですが、本当にPeter Asherはいい仕事をしてます。
A面一曲目の「悪い貴方」は初の全米No.1ヒットで、先述のJ.D.Southerの事を歌った曲と言われてますが、自作ではないんですよね。
Paul Anka作の2曲目「もうおしまい」は曲の良さもありますが、抑制の利いた優しい唄い方が最高です。
3曲目は例のJ.D.Southerの曲で、何とハモリまでつけています!当時の二人の関係が垣間見られるようですね。
J.D.Southerはハモリの名手で、他にもJames Taylorの「想い出の街」でも惚れ惚れするようなハーモニーを聴かせてくれます。
4曲目、5曲目も素晴らしいボーカルが堪能できます。5曲目、タイトルトラックの哀愁感は堪りません。
B面もEverly Brothersの「いつになったら愛されるのかしら」、Lowell Georgeの「ウイリン」など選曲の良さが光ります。
全曲捨て曲がなく、初期のカントリー風味とLAサウンドが調和した名盤ですね。
彼女はこの後もPeter Asherのプロデュースの下、良作をコンスタントに発表し、70年代後半に絶頂期を迎え「ミスアメリカ」の称号を得るようにまでなります。
ジャケットも、KOSHが手がけるようになり、洗練されていきます。
KOSHの特徴はアメリカンノスタルジック調のレタリングにありますが、Lindaの一連の作品は非常に統一感があって好きです。
壁の二枚です。

先ずは個人的には一番好きな82年の「Get Closer」です。
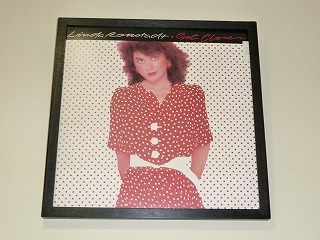
水玉模様をあしらったKoshのセンス溢れるジャケットです。
これ、ゲートフォールドで出して欲しかったですね。何でシングルジャケットなんだろう、と当時思いました。
単に予算の都合だったのか?それともこれが「粋」なのか??
内容は盛り沢山でして、A面一曲目のタイトル曲は、当時のLAロック的なサウンドに乗ってシャウトする、前作「Mad Love」を踏襲した感じの佳曲です。
2曲目のJim Webb作の「月はいじわる」はJoe Cockerのバージョンにも負けず劣らずの名唱です。本当に彼女って歌が巧いなあと思います。
3曲目の「さよならのページ」はアルバムのベストトラックと思います。
ラスカンケルのドラムが最高で、派手なオカズはありませんが、歌伴としての役割を知り尽くしたそのプレイはもっと評価されて欲しいです。
5曲目の「people gonna talk」もニューオーリンズっぽく決めてて最高な一曲です。サックスと張り合うリンダのパンチある歌声も素晴らしい。
B面は大ロックンロール大会?で非常に小気味良い演奏、歌が楽しめますが、5曲目でまたまたJ.D.Southerが登場します。リンダさん、本当に好きなんですね。
最後はドリーパートン、エミルーハリスと組んだトリオ曲です。
この数年後、3人名義のフルアルバム「Trio」がリリースされますが、3人とも綺麗で、歌も巧く、最高なアルバムでした。
彼女はその後、1983年に永年の夢であったジャズスタンダードアルバム「What's new」をリリースします。
何とネルソンリドルに歌伴を依頼するという徹底ぶりで、大成功をおさめました。
その勢いをかって出された第二弾「Lush Life」がこれです。
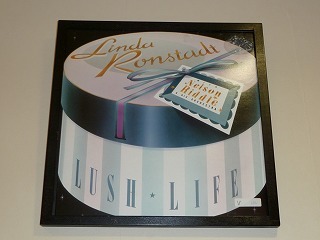
如何にもあの時代を彷彿とさせるジャケットはKOSHの最高傑作ではないでしょうか?
これ、衣装ケースの箱を開ける(ジャケットを上にずらす)とリンダさんが出てきます!

裏ジャケットも古き良き時代のアメリカって感じがしてうっとりします。
リアルタイムを知っている訳でありませんが、素晴らしい時代だったんでしょうね。
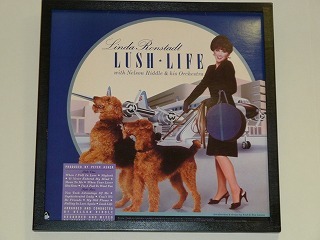
曲目は誰もが知っている有名曲から、通好みまで様々ですが、発表当時の評価は「唄が一本調子」とか、あまり良くなかったように記憶してます。
しかし、セールスは好調で、この後もう一枚ネルソンリドルとの共演作を発表します。
欧米の歌手たちは「成功の証」として、クリスマスアルバムとスタンダードアルバムを発表したくなるみたいです。
あのRod StewartやRobert Palmerもスタンダードアルバムを発表しましたもんね・・・。
さて、数多くの作品を発表しているLinda Ronstadtですが、入門編として先ずお勧めしたいのは、禁じ手かもしれませんが、「Greatest Hits Vol.1&2」です。
しかし、このベスト盤はよくある、ただ年代順にヒット曲を並べただけ、というお手軽ベストとは一線を画したもので、ジャケットのアートワーク(写真アルバムを模したもの~勿論KOSHデザイン)や、選曲、曲順まで配慮したオリジナルアルバムとカウントしてもいいような愛情のこもった仕上がりです。
中学生の時、この2枚を90分テープの両面にダビングし、カセットケースに「FM fan」から切り取った写真を入れ、むさぼるように聴いていました。「未だ見ぬ亜米利加」を夢見て・・・・・
(最後、シカゴⅧの当時の邦題みたいになっちゃいましたね。何を隠そう、私はコロンビア時代のシカゴはBeatlesに次ぐフェイバリットグループなのです。またそのうちシカゴへの想いも語りたいですね。)
今月のレコードジャケット~Jackson Browne(2011/04/11)
このたびの震災の被害を受けた方々に心よりお見舞い申し上げます。
何も悪い事などしていないのに、突然幸せな生活を目茶苦茶に破壊されるなんて、何と理不尽な事でしょう・・・。
私も最近、人生観が変わる位の辛く悲しい出来事がありましたが、被災地の方々を思えば、へこたれてはいられない!と自分を鼓舞しています。
4月に入り、徐々に暖かくなってまいりました。
今月のレコードジャケットは前回のEagles繋がりでJackson Browneを特集してみました。
先ずは玄関先には「Runnig on Empty」です。
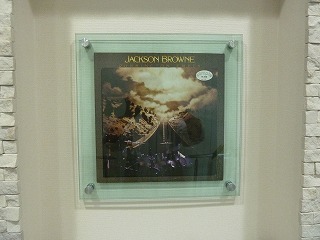
表題曲は彼の代表曲の一つで、コンサートでも大盛り上がりの曲です。
昔、80年代後半彼のコンサートに行きましたが、確かアンコールでこの曲を演る時に、「皆もっと前においでよ!」と彼が言った途端、私を含むアリーナの客がステージ前に押し寄せ、物凄い一体感となった事は忘れられません。
この曲は映画「フォレストガンプ」でも効果的に使われてましたね。
B面最後の「Stay」はフィナーレに相応しい感動の名演です。
Rosemary Butlerのパンチのある歌声、意外に御茶目なDavid Lindleyと役者が揃ってます!
その昔、サザンの桑田さんが「嘉門雄三」名義で出した洋楽カバーアルバムでもこの曲を実に楽しそうに演奏してましたね。
壁の2枚です。

先ずは初期の傑作「Late for the sky」
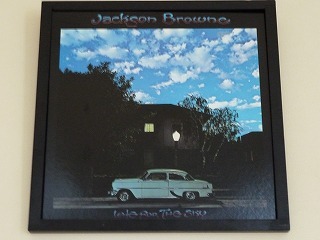
マグリットのパロディのような面白いジャケットですね。
表題曲から「Fountain of sorrow」へと続くA面の流れは美しいです。
後の社会派シンガーへの萌芽が感じられる「Before the deluge」も聴きものです。
そして個人的には一番好きな「The Pretender」です。
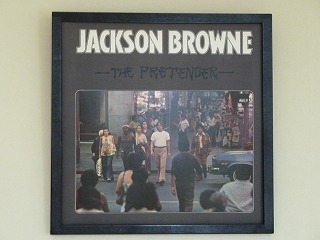
このアルバムは深い哀しみに包まれているような感じがします。
完成直前に当時の奥方が自殺を図り、亡くなったのです。
裏ジャケットに写っている幼子を残して・・・・。
そういった背景を知っているから余計にそう感じるのでしょうが、このレコードを聴いていると無性に泣けてきます。
A面最後に、まさに「溢れ出る涙」という曲があります。
逝ってしまった妻への想いを切なげに、しかし力強く唄った名曲です。
後に「MUSE~No Nukes」で深く関係する(この事についてはまた書きます)Orleans の John Hallのギターソロも最高ですが、特筆すべきはBonnie RaittとRosemary Butlerの素晴らしいバックコーラスでしょう。
サビの所でJacksonに絡む二人の強力な歌声はもはやバックの域を超えて、トリプルリードみたいな感じです。(CSNみたい?)
特に最後の方で、女性二人だけになる所は何度聴いても鳥肌が立ちます。
他の曲も、Little FeatのLowell Georgeのスライドをフューチャーした「Your bright baby blues」、Don HenleyとGlenn Freyのコーラスが光る「The Only Child」、宗教的で敬虔なサウンド、歌詞の聞かれる「Sleep's dark and silent gate」、昨年の来日公演でも印象的だった、深いテーマの「The Pretender」と聴きごたえのある曲が目白押しです。
正にスピーカーと対峙して、歌詞カードを読みながら拝聴する、そういった類の音楽です。(しかし、最近なかなか時間が取れず、ipodで聴いています・・・偉そうな事言ってすみません。)
彼はこの後、スリーマイル島原発事故に触発され、先ほど言及した「MUSE」を主宰し、反原発運動など、様々な社会的活動を展開していくようになりますが、コンスタントに「音楽的」な作品も発表しているのは流石ですね。
また機会があれば、MUSEの事も書きたいと思います。
しかし、Jackson Browneは今回の福島原発事故に関してどんな思いなんでしょうね?
機会があれば誰かインタビューして頂きたいですね。
今月の壁レコード~祝来日!イーグルス特集(2011/03/08)
徐々に暖かくなってきた今日この頃ですが、皆様如何お過ごしでしょうか?
今月のジャケットは久し振りに来日を果たしたイーグルスを特集してみました。
3月3日には名古屋公演もありましたね。私は残念ながら諸事情で行けませんでしたが、観に行かれた方も多かったのではないでしょうか?
Eaglesは70年代アメリカンロックを代表するロックグループで、Doobie Brothersと並んで最も成功したアメリカンバンドではないでしょうか?私は高校生の頃非常に影響を受け、本気でアメリカに永住しようと思った程です(笑)。
先ず玄関先は代表作の「Hotel California」です。

LAに実在するビバリーヒルズホテルを使ったKOSHデザインの素晴らしいジャケットです。
KOSHはアメリカンノスタルジック調な作風で有名ですが、もともとはイギリスで活動しており、意外な所では、あのBeatles の「 Let It Be」も彼のデザインです。
表題曲については、語り尽くされた感があり、敢えて多くを言及しませんが、やはりこの曲のギターはDon FelderとJoe Walshのツインで聴きたいですねえ。
続く「New kid in town」もいい曲ですね。J.D.Southerも加わった一糸乱れぬハーモニーも素晴らしい。
よくこの曲はホール&オーツの事を歌った、という記事を読みますが、歌詞を読んでもピンとこないんですが、本当なんですかね?
「Life in the fast lane」「Wasted Time」と続くA面は完璧。
B面はややテンションが落ちますが、顔に似合わず?ロマンチックな面が伺われるJoe Walshの「お前を夢見て」、哀愁味溢れるRandy Meisnerの「素晴らしい愛をもう一度」はなかなかの佳曲です。
壁の2枚です。

先ずはセカンドの「ならず者」
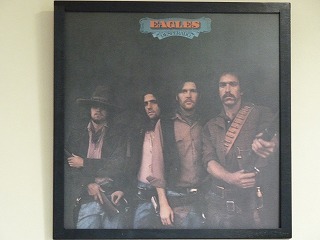
Henry diltzの渋い写真を使ったジャケットです。
西部のならず者を描いたトータルアルバムですが、やはりA面の3曲、
「Doolin-Dalton」「Tequila Sunrise」「Desperado」は素晴らしい出来栄えですね。やはり名曲です!
そして彼らの出世作、「呪われた夜」です。

個人的には表題曲は彼等の最高傑作ではないかと思います。
Don Henleyの艶めかしい唄も勿論ですが、スリリングなDon Felderのギターソロ!最高です。
これ程までにセンス良く無駄のないソロは、他にはSteely Danの「Peg」に於けるJay Graydonのそれ以外思い当たりません、というのはちと褒めすぎですかね?
次の「Too Many Hands」もギターが活躍するハードな曲です。
B面の「Visions」もDon Felderをフューチャーした疾走感溢れる佳曲で、(当時ソロで活動してましたが)Joe Walshっぽい感じが格好いいです。
B面最後はこのアルバムでグループを去るBernie Leadonの「安らぎによせて」ですが、これまた泣ける良い曲なんです。まさに「置き土産」ですね。
彼等はこのアルバムで名実共に№1アメリカンバンドとなります。
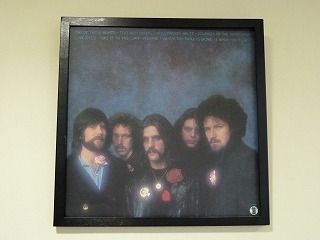
裏ジャケットのノーマンシーフ撮影のポートレイトは当時飛ぶ鳥を落とす勢いだった彼等の自信漲るいかした一枚です。
特に、今では人のよいおっさん?になってしまいましたがGlenn Freyの凄みある表情には男の私でもドキッとしてしまいます。
最後にもう少し。今回は載せませんでしたが、私の一番好きなアルバムは
「On the Border」です。ジャケットはイマイチですが、内容の充実度は他を軽く凌駕します。
特に脇役?の二人、Bernie Leadonの「My Man」とRandy Meisnerの
「Is it true?」は最高ですよ。
前者はグラムパーソンズの事を歌っており、美しい旋律と優しいボーカルが印象的です。
Meisner節の聞かれる後者は、Glenn Freyの弾くスライドギターがいい感じです。
あと、特筆すべきはTom Waitsの名曲「'Ol 55」のカバーです。
GlennとDonによって交互に歌われる抒情的な名曲ですが、独特の世界観を持つオリジナルには敵わないかもしれませんが、如何にもアメリカ的なアレンジは個人的にはアルバムのベストトラックに推す出来栄えです。
いつもこの曲を聴くと留学時代テキサスのインターステートを明け方に走った思い出が蘇ってきます。所謂dawnの雰囲気に合うんですよね。
以上、長々とお付き合い頂き有難うございました。
やはりイーグルスいいですねえ。
今月のレコードジャケット~寒いですね(2011/02/03)
毎日寒い日々が続いておりますが、皆様風邪などひかれてないでしょうか?
先月16~17日の大雪はびっくりでしたね。岡崎であんなに積もったのは久しぶりでした。
という訳で、今回のジャケットは「寒そうな」やつをチョイスしてみました!

まず玄関先はジョニミッチェルの1976年の傑作「逃避行」です。
ノーマンシーフ撮影の素晴らしい写真に圧倒されます。まさに寒そう!(余談ですが、彼の手がけるポートレイトは本当にアーティストの本質を浮かび上がらせていて素晴らしいです。)
内容もジャコパストリアスのベースが強調され、ジャケットさながらに透明感~寂寥感のある独特の音像が記されております。
このレコードのオリジナルライナーノーツは湯川れい子さんの傑作の一つですので、是非読んでみてください。
壁の二枚です。

まずはウイーザーのピンカートンです。
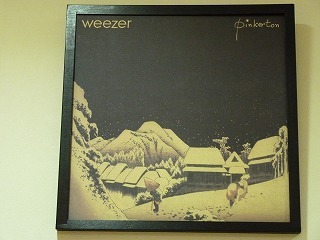
歌川(安藤)広重の東海道五十三次の中の「蒲原」を使ってます。
パワーポップのバンドが何故浮世絵を使ったのか定かではありません。内容も特に日本を意識した訳ではなさそうです。
でも、昔の人はダウンジャケットもないし、あんな寒い格好で雪道を歩いたんですねえ。
御次はスーパートランプの「蒼い序曲」です。
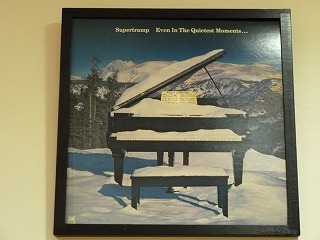
雪山に何故かグランドピアノが佇んでおります。一体誰が運んできたのでしょうか?
因みにこのジャケットは内側も青色に塗られてるんです。凝ってます!
本日は節分です。これからは徐々に暖かくなっていくんですかね?
皆様、インフルエンザには気をつけましょう!
新年のご挨拶 ~ 今月のジャケット(2011/01/04)
明けましておめでとうございます。
本年も「誠実な対応、分かりやすい説明」をモットーに、皆様のお役に少しでも立ちたいとスタッフ一同、頑張ってまいりますので宜しくお願い申し上げます。
今年最初のレコードジャケット掲示ですが、やはり兎年という事で、ウサギさんのジャケットを探したのですが、あまりウサギをモチーフとしたものはなく、2枚しか見つかりませんでした。
そこで、玄関先には少しでもお正月っぽい感じのするものを苦肉の策でチョイスしました。
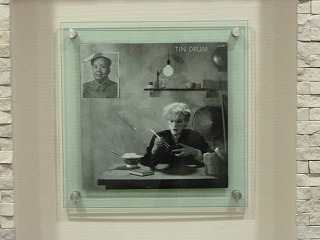
Japan のTin Drum(ブリキの太鼓)です。
どちらかというと、中国をイメージしてますが、何となくこの時期に合っているような気がしますので、チョイスしてみました。
勿論、メンバーはYMOとの交流もあり、日本についてはきちんと理解していた筈なので、所謂「西洋人からみた間違った日本のイメージ」ではありませんよ!
アルバムに「広東」とか「Visions of China」なんて曲が入ってるので中国っぽくしたんでしょうね。
でも、タイトルの「Tin Drum」は戦前ドイツ文学なんですよね。未読なのではっきり言えませんが、この時期の何か達観したかのようなデビッドシルビアンの声に合っているのかもしれません。
待合壁の2枚です。

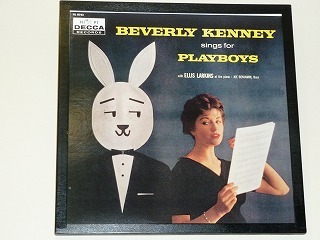
これはビバリーケニーのジャズボーカルアルバムです。
唄伴がエリスラーキンスなので、粋なアルバムに仕上がっています。
欧米では雑誌の影響でウサギはプレイボーイの象徴となってますね。
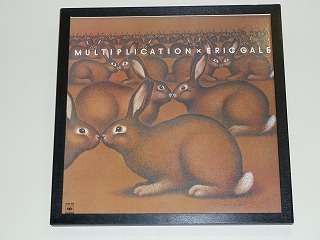
これは名スタジオミュージシャン、またはスタッフのメンバーとしても有名なエリックゲイルのリーダー作です。
「うさぎアルバム」としては最も有名な一枚ではないでしょうか?
以前「アート特集」でも紹介しましたが、院内にはキースへリングの例のプレイボーイ兎をモチーフとしたリトグラフも飾ってあります。
童話「兎と亀」やバックスバニーなど、どうもウサギはおっちょこちょい的なイメージで描かれているようですが、昔飼っていたこともあり、やはり愛らしい、癒しの動物だと思います。
当院もそんな皆様に愛される存在になりたいと切に願っております。
どうか今年も宜しくお願い申し上げます。
クリスマス!(2010/12/18)
あと数日でクリスマスですね。
院内もクリスマスっぽくしてみました。

まずは玄関入口通路にツリーを飾ってます。

受付の台には、スノーマンの動く置物です。お子さんに大人気です。
レコードジャケットも勿論用意してございます。
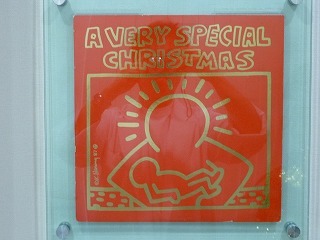
入口にはキースへリングのイラストで有名なオムニバス盤です。
ロック~ソウル~ポップスの大御所揃い踏みの豪華企画でしたね。
待合壁には、可愛らしくDisneyもので・・・

共にアメリカで出された子供向けレコードですが、さすがDisney、手を抜きません。素晴らしいジャケットです。
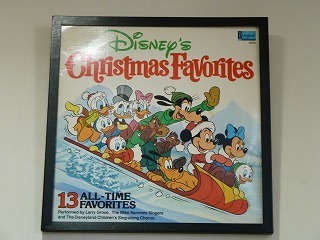
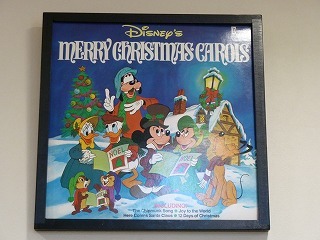
何歳になっても何故かこれらのキャラクターを見ると和んでしまいます。
ワーナーのルーニーチューンズとかトムとジェリーなどあの時代のアメリカが創り出した文化は偉大ですねえ。
今月の壁レコード~ジョンレノン(2010/12/06)
今月前半の壁レコードは生誕70周年、没後30周年で盛り上がってる?ジョンレノンで揃えてみました。
毎年、命日の12月8日近辺はジョンレノン特集してはいますが、今年はメモリアルイヤーという事で・・・。

玄関先は邦題「ジョンの魂」です。穏やかなイメージのジャケットとは裏腹な激しいジョンの魂の叫び。個人的には2曲目の「しっかり、ジョン」が大好きですね。
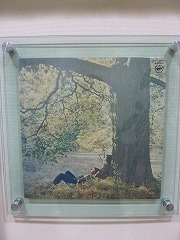
待合壁の2枚は

ビジュアル的な側面で選んでおり、内容的には??というものですが、お許しください。
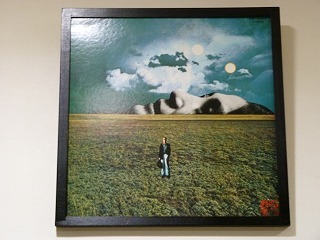
ヨーコさんの大胆な構図とちっぽけなジョンに当時の二人の関係が垣間見れるようです。
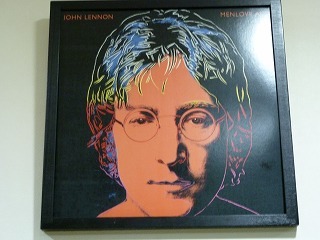
これは死後に出された編集物ですが、Andy Warholの作品を使ってる点では評価されると思います。
ジョンレノンは素晴らしい音楽家でありましたが、やはり「only human」であり、必要以上に聖人化されなくてもいいような気がします。どうも「愛と平和の伝道師」みたいな持ち上げられ方をされてると違和感を覚えてしまうのは私だけでしょうか?
芸術の秋~アート特集(2010/11/23)
もう師走も近づいて参りましたが、「芸術の秋」という事で、久々に中待合室の絵画をリニューアルしてみました。

これはサンデーモーニング(Andy Warhol)の「フラワー」です。
最初はちょっと医院には派手かなあ?と思いましたが、なかなか存在感があり、観てると元気になります。ヒーリング効果もあるのかもしれません??

次は私の大好きなキースへリングです。

来年の干支に因んで、ウサギさんです。
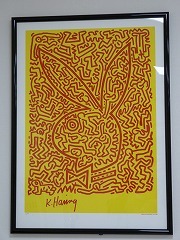
そして前のモダンアートとは少し時代が違ってきますが、皆さんに人気のシャガールです。

これは有名な絵で美術の教科書なんかでお見かけした事があると思います。なかなかインパクトある絵ですね。

以上、御紹介させて頂きました。
良い絵は心を和ませてくれますよね。すこしでも居心地の良い待合室になるように日々努力していきたいと思っています。
今月の壁レコード~エルトンジョン(2010/11/19)
皆様おまたせしました!
ようやくPC環境が整い、ブログ更新する事ができました。
アナログ人間の私にとっては大変な作業ですが、できるだけ更新していきたいと思っております。
当院では毎回テーマに沿って玄関先と待合室壁にLPレコードジャケットを飾っています。
先月のビリージョエルに続き、同じピアノマン繋がりで今回はエルトンジョンをピックアップしました。
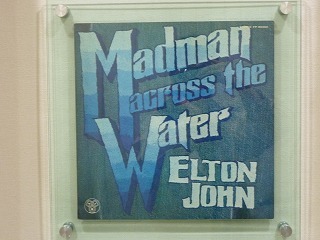
玄関先はまだ吟遊詩人的なイメージの残る時期の「Madman across the water」です。
この頃の彼はまだ青臭い感じがしていいですね。Tiny Dancerは名曲です!

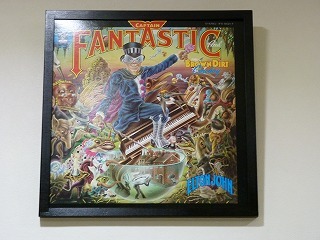
これは1975年の作品ですが、コンセプトアルバムで、これまでの総決算?といったゴージャスな内容で、他のオリジナルアルバム群とは比較できない素晴らしいものです。
中学2年の時に貸しレコード屋で借りて夢中で聴きまくりました。
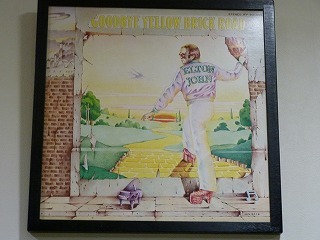
これも傑作で1973年の作品です。
ただ、2枚組の為か、作品にばらつきがあり私的には世間の評価ほど聴く回数は多くありません。
唯、A面の流れは最高ですね。
以上、簡単なコメントをつけさせて頂きました。エルトンファンの方、お手柔らかに!?
HPリニューアルの御挨拶(2010/10/05)

桐渕眼科のホームページが新しくなりました。
これまで以上に分かりやすく楽しめる内容になったと自負しております。
医院や医師の紹介は勿論のこと、医院の歴史やスタッフの写真もアップしました。
御好評頂いている玄関、待合壁に飾ってあるレコードの説明はブログにて行って参ります。
今後とも宜しくお願い致します。